【中学3年生の夏休み】受験生の勉強時間はどれくらい?目安と効率アップ法
公開日:2025年7月9日
更新日:2025年7月9日
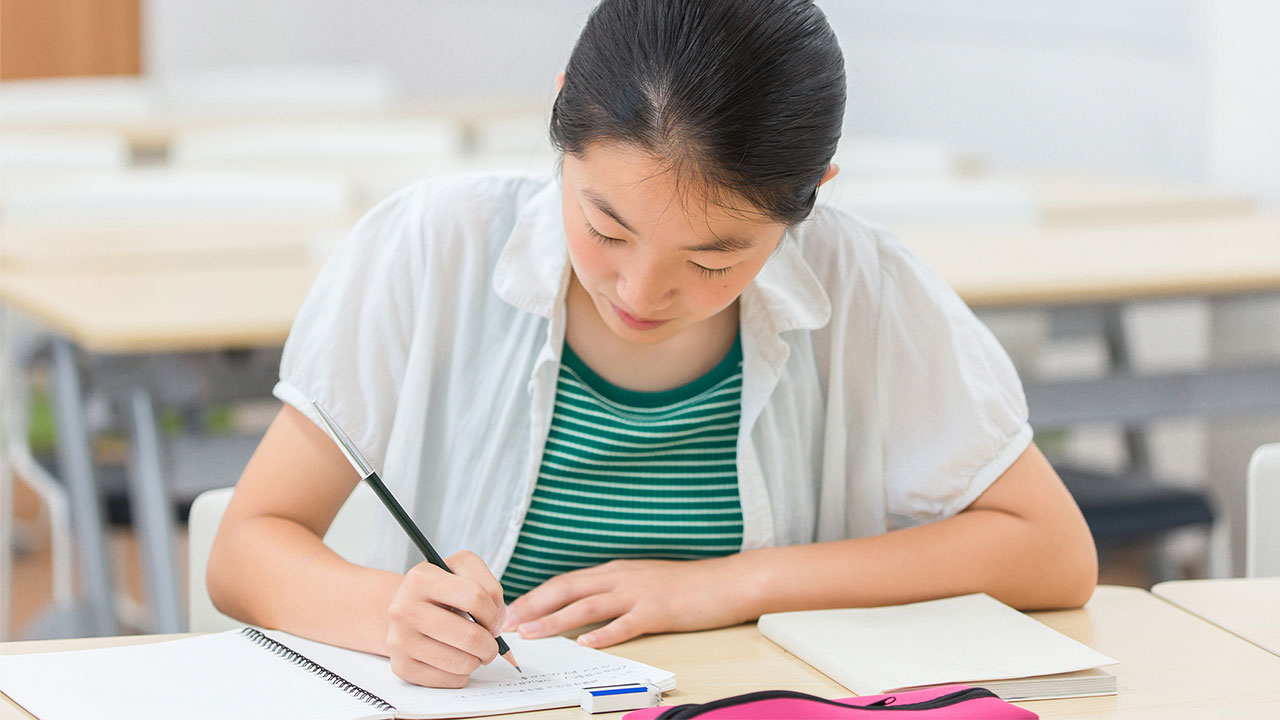
中3の夏休みは、高校受験に向けて最も大切な期間です。
このコラムでは、夏休みに確保したい勉強時間の目安や、効率よく勉強時間を確保するコツ、やるべき学習内容、やってはいけないNG勉強法まで詳しく解説します。
限られた夏休みを合格につなげるために、ぜひ参考にしてください!
中学最後の夏休みはどれくらい勉強すればいい?|時間の目安を知ろう
中学3年生にとって、夏休みは高校受験に向けた“勝負の40日間”です。この時期にどれだけ勉強に集中できるかで、秋以降の仕上がりが大きく変わってきます。
とは言え、「どのくらい勉強すればいいのか」「どんな時間の使い方をすればいいのか」と不安になる方も多いでしょう。ここでは、夏休みに目指したい勉強時間の目安と、時間配分の工夫について詳しく解説します。
1. 目標は40日で200〜300時間|1日5〜8時間が基本
高校受験を控える中学3年生にとって、夏休みの勉強時間の目安は40日間でおよそ200〜300時間とされています。これは、1日あたりに換算すると5〜8時間程度の勉強が必要になる計算です。
とは言え、最初から8時間も集中して取り組むのは難しいので、夏休みの前半は1日5時間程度から始め、徐々に時間を増やしていく方法が現実的でしょう。
朝の時間をうまく活用し、日中の生活リズムを整えることで、秋以降の学習習慣にもつながります。
高校受験の勉強時間の目安についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高校受験に必要な勉強時間とは?|偏差値50〜70・時期・学年別に解説」
2. 志望校のレベルに合わせて調整しよう
必要な勉強時間は、志望校のレベルや現在の学力によっても異なります。
例えば、偏差値の高い公立・私立高校を目指す場合は、夏休み中に300時間以上の学習が目安となるでしょう。
一方で、基礎学力の定着を重視する段階であれば、200時間前後でも十分効果的な夏になります。
重要なのは、「時間をかけること」そのものではなく、自分に必要な勉強に、しっかり時間を使うことです。現時点での弱点や志望校とのギャップをふまえて、無理のない計画を立てるようにしましょう。
効果的な勉強計画の立て方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「効果的な勉強計画の立て方|計画倒れしないためのコツもご紹介!」
3. 午前・午後・夜でメリハリある時間割を意識しよう
1日の勉強をただ「◯時間やるか」だけではなく、時間帯ごとに内容を区切ることで、集中力を保ちやすくなります。
例えば、午前中は暗記系や計算など集中力が必要な科目、午後は演習・問題集中心の時間、夜は復習や見直し・間違い直しなど、役割を分けるのが効果的です。
また、適度な休憩を取り入れることも重要です。一般的に、人の集中力は40〜50分程度が限界と言われています。無理に詰め込まず、「短時間集中×こまめな休憩」のリズムを意識することで、効率的な勉強時間を確保することができます。
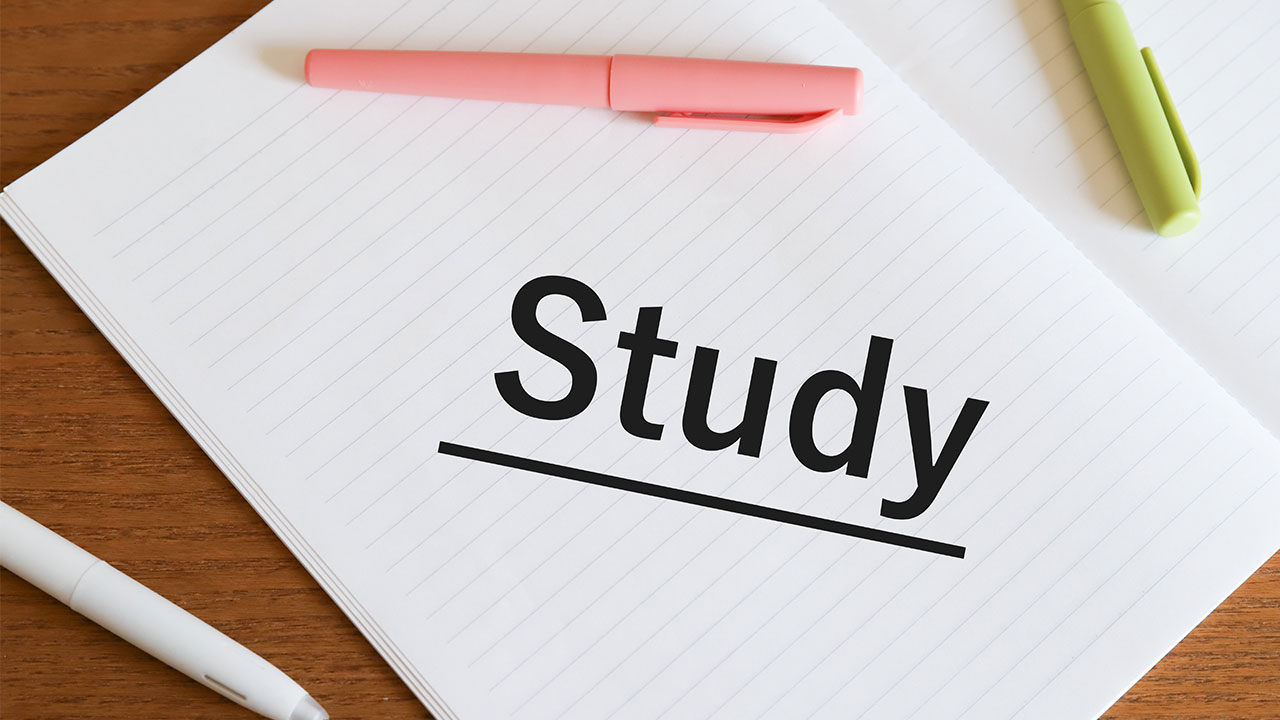
勉強時間をしっかり確保するための5つの工夫
いくら「夏休みは1日○時間勉強しよう」と決めても、なかなか計画通りにいかないのが現実です。ついスマホに手が伸びたり、時間があると思って後回しにしたり…。
大事なのは、やる気に頼るのではなく「勉強が続けられる環境と習慣」を先に作ってしまうことです。
ここでは、夏休みの勉強時間を確実に確保するための具体的な工夫を5つご紹介します。
1. スマホやゲームとの距離を見直そう
集中力の最大の敵は、スマホやゲームの誘惑でしょう。「少しだけ見るつもりが、いつの間にか30分以上経っていた…」という経験は、多くの人にあるのではないでしょうか?
対策としては、勉強中はスマホを別の部屋に置く、通知をオフにする、保護者に預けるなど、物理的に距離を取るのが効果的です。
ゲームについても「勉強が終わった後のごほうびタイム」として1日○分だけと時間を決めて遊ぶ習慣にすると、勉強のメリハリがつきやすくなります。
2. 午前中に集中できる環境を作ろう
午前中は、脳が最も活発に働きやすいゴールデンタイムです。この時間をどう活用できるかで、1日の学習効率に大きな差が出ます。
まずは、朝食を食べたら机に向かう習慣をつけましょう。机の上はスッキリ整理し、必要な教材だけを出しておくことで気が散りにくくなります。
また、自宅では集中しにくい場合は、図書館や地域の自習室など環境を変えるのも有効です。
場所を工夫するだけで、気持ちが切り替わり、集中力が高まりやすくなります。
午前中を有効活用するメリットについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「早起きは“勉強効率”の最強習慣!|集中力も成績も変わる朝学のメリット」
3. 1日の予定は朝イチに決めるクセをつけよう
「今日は何からやろうかな…」と迷っている時間も、実は貴重な学習時間を削ってしまいます。朝のうちにその日の勉強メニューや時間配分を決めておくことで、行動に迷いがなくなり、勉強にすぐ取りかかれるようになります。
専用のノートやToDoリストを作って、「午前は英語と理科」「午後は数学の問題演習」「夜は間違い直し」など、ざっくりした計画でも構いません。予め予定を立てることで、迷いが減り、勉強のリズムが自然と身につくようになります。
4. 50分集中+10分休憩でリズムを作ろう
長時間ダラダラと勉強を続けるよりも、短時間に集中して取り組むほうが記憶の定着率も高く、疲れにくいとされています。
おすすめは、「50分勉強+10分休憩」のセットでリズムを作る方法です。
キッチンタイマーやスマートフォンのタイマー機能を活用して時間を区切れば、メリハリが生まれ、集中しやすくなります。
休憩時間にはスマホを見ず、軽いストレッチや水分補給など、身体をリラックスさせる行動を取り入れることで、次の学習への切り替えがスムーズになります。
勉強に集中する方法についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「勉強に集中する方法とは?|オススメ9つの方法をご紹介!」
5. 夜ふかしはNG!早寝早起きが勉強効率を上げる
夏休みは夜ふかしになりやすい時期ですが、生活リズムが乱れると昼間の集中力が低下し、学習効率が大きく下がってしまいます。
特に、夜遅くまで起きていると朝の起床が遅れ、午前中の”集中できるゴールデンタイム”を逃してしまうことにもつながります。
理想的な睡眠習慣としては、夜22時〜23時には就寝し、朝7時ごろに起床することです。
十分な睡眠は、記憶の定着や脳の回復にとって非常に重要で、翌日の勉強にも良い影響を与えます。

志望校合格につながる夏休みの学習計画の立て方
夏休みは時間がたっぷりあるように見えて、実はあっという間に終わってしまいます。ただ毎日勉強するだけでは、思うように成果は出ません。「何を、いつ、どうやって進めるか」を明確にしておくことで、勉強の効率もグッと上がります。
ここでは、夏の学習計画を立てるうえで押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
1. 前半は基礎の総復習、後半は応用・過去問へ
夏休みの勉強は、前半と後半で学習内容にメリハリをつけることが重要です。
前半(7月下旬〜お盆前)
中1・中2の基礎範囲や苦手単元の総復習に集中しましょう。
基礎が固まっていない状態で応用に進んでも、得点にはつながりにくいため、土台作りを徹底することが先決です。
後半(お盆明け〜8月末)
基礎を活かして応用問題や過去問に取り組む時期です。
志望校の出題傾向を意識しながら、問題演習と間違い直しを繰り返すことで、実戦力が鍛えられていきます。
2. 苦手単元をリスト化し、計画的に克服しよう
夏休み中にどれだけ苦手を克服できるかが、秋以降の成績の伸びに大きく影響します。
まずは、「何ができていないか」「どの単元に不安があるか」を具体的に洗い出し、リスト化することから始めましょう。
例えば、「英語の長文読解」「数学の関数」「理科の電流」など、教科と単元をセットで書き出しておくと、優先順位が明確になります。
その上で、1日1単元ずつ取り組めるようなスケジュールを立てることで、無理なく確実に克服を進められます。
3. 毎週、達成できた内容を振り返ってみよう
勉強計画は立てるだけで満足してしまいがちですが、実際に振り返って確認することが学習の質を高めます。ですから、週に一度は、「今週やった内容」「できたこと・できなかったこと」「来週に回すべきこと」などを簡単にメモする時間をとりましょう。
このふり返りを習慣化すると、自分の勉強の進み具合やクセが見えてくるため、やみくもに焦らずに計画的に進められるようになり、結果的に達成感を積み重ね、モチベーションの維持にもつながります。
モチベーション維持についてもっと知りたい方はこちら
⇒「勉強のモチベーションを上げる方法|テクニックを使ってやる気UP!」
4. 計画が崩れても立て直せばOK|柔軟さも大事
どれだけ綿密な計画を立てても、体調不良や急な予定などで予定通り進まない日もあります。
そんな時に「もうダメだ…」とあきらめてしまうのではなく、ズレた分は翌日以降に少しずつ巻き返すくらいの気持ちで大丈夫です。
勉強は「毎日完璧にやること」ではなく、「続けていくこと」が一番大事です。
崩れた計画を調整しながらでも前に進めるよう、週ごとに見直す柔軟さを忘れずに持っておきましょう。

夏の勉強内容が合否を左右する!|タイプ別やるべきこと
勉強時間をしっかり確保できたとしても、「何を勉強するか」を間違えてしまっては、効果は半減してしまいます。
夏の勉強は、自分の現在地や課題に合わせて「やるべき内容」を明確にすることが大切です。このセクションでは、受験生によくある4つのタイプに分けて、それぞれが夏に取り組むべき学習内容をご紹介します。
1. 【基礎が不安な人】中1・2年の重要単元を総復習しよう
模試や定期テストで平均点に届かないことが多い人、復習すると「あれ、ここって何だっけ?」となることが多い人は、基礎固めを最優先にしましょう。
特に数学や英語は、中1・中2の内容がしっかり理解できていないと中3の応用問題に対応できません。
夏休みでは、学校のワークや教科書を使って、1・2年の総復習を一通り終わらせることを目標にしましょう。
基礎をやり直すのは決して遠回りではなく、「今やることこそが合格への最短ルート」です。
2. 【苦手科目がある人】得点源に変えるチャンスにしよう
「どうしても苦手な科目がある」という人にとって、夏休みは克服の絶好の機会です。
普段よりもまとまった時間を取れる夏だからこそ、苦手科目に集中的に取り組める時間的余裕があります。
例えば、理科が苦手なら「電流」「化学変化」など分野ごとに整理し直すことで理解が深まりやすくなります。英語の文法に不安がある場合は、基本ルールを確認しながら問題演習に進むのが効果的です。
重要なのは、「何がわかっていないのか」を明確にして、順を追ってつぶしていくこと。
1科目でも得点源が増えれば、全体の得点力も上がり、大きな自信につながります。
3. 【内申対策も必要な人】提出物・復習プリントも計画的に
高校受験では、試験当日の得点だけでなく「内申点(調査書)」が合否に大きく関わります。
特に公立高校の選抜では、内申点と学力検査の比率が5:5〜3:7の地域が多く、提出物や課題の完成度が評価対象となるケースも少なくありません。
夏休みの提出物や課題は、「最後にまとめてやる」ではなく、夏の前半からコツコツ進めることが重要です。また、復習プリントや課題テストの範囲も早めに着手し、丁寧に取り組みましょう。
見た目の丁寧さや解答の工夫も評価につながるため、手を抜かずに仕上げることが内申アップのカギです。
調査書(内申書)についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「調査書(内申書)について徹底解説!|高校受験に向けて正しく理解しましょう!」
4. 【応用力をつけたい人】公立入試の過去問にチャレンジしよう
基礎がある程度身についている人は、夏休みの後半から「応用力」を鍛える段階に入りましょう。おすすめは、志望校や他県の公立高校の過去問にチャレンジすることです。
最初は難しく感じても、解けなかった問題を丁寧に見直すことで、自分に足りない力がはっきりと見えてきます。
また、出題形式や時間配分にも慣れておくことで、入試本番での対応力が格段に上がります。「解く→見直す→解き直す」のサイクルを繰り返すことで、得点力が大きく伸びていきます。
高校受験についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高校受験の過去問はいつから始めるべき? 学力別・志望校別にベストな時期を解説!」
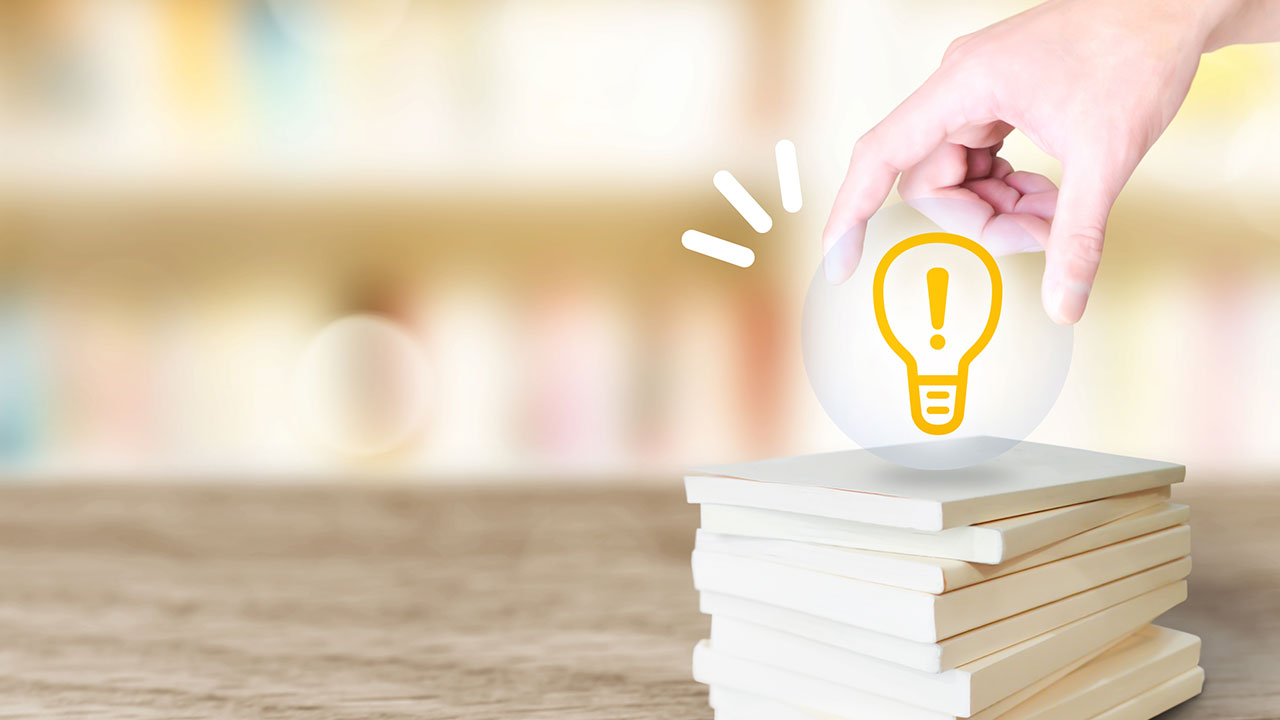
夏にやりがちなNG勉強法に注意
せっかく夏休みにたくさん勉強時間を確保しても、「やり方」を間違えてしまうと、思ったような成果が出ないことがあります。特に夏は時間があるぶん、油断や自己流に陥りやすい時期でもあります。
このセクションでは、受験生がやりがちなNGパターンを紹介しながら、気をつけたいポイントを解説します。
1. 解きっぱなしで復習しないのは効果半減
問題集を「とにかくたくさん解く」ことに満足して、間違えた問題を見直さずに終わらせてしまうのは、非常にもったいない勉強法です。間違いの原因を放置したままでは、同じような問題でまたつまずいてしまいます。
解いた後は、必ず間違えた問題の解説をしっかり読んで、「なぜ間違えたのか」「次にどうすればいいのか」を自分の言葉で整理しておきましょう。
解き直しノートを作って、何度も復習するのも効果的です。
2. 苦手を後回しにして得意ばかりやらないように
得意な教科は取りかかりやすいため、つい繰り返してしまいがちですが、苦手科目を放置していては全体の得点力は頭打ちになります。特に高校入試では「1教科の大きな失点」が合否に直結することもあるため、弱点の克服は避けて通れません。
夏のうちに「どこが理解できていないのか」を細かく分析し、計画的に対策に取り組む時間を設けましょう。
「1日10分だけ苦手科目に取り組む」といった小さな習慣でも、積み重なれば大きな自信と得点につながります。
3. 夜型になって昼に眠くなる生活は避けよう
夏休みは夜更かしや朝寝坊の習慣がつきやすく、生活リズムが乱れると昼間の集中力が低下し、勉強の効率も著しく落ちてしまいます。
特に、高校入試本番は朝9時前後から始まることが多いため、夏のうちから“朝型生活”に慣れておくことが非常に重要です。
朝にしっかり起きて、日中の頭が冴えている時間に学習を集中させることで、パフォーマンスは大きく向上します。 生活リズムを整えることも、受験勉強の一部と考えましょう。
4. 「勉強してる風」だけにならないようにチェックしよう
長時間机に向かっているだけで満足し、「ノートをきれいにまとめて終わり」などの「勉強している風」になっていないか、自分で見直す視点が重要です。
大切なのは、「どれくらいやったか」ではなく、「何を理解し、何ができるようになったか」です。学習の“質”を意識することで、勉強の効果は大きく変わります。
また、保護者や先生に「今日はこれをやって、こうだった」と説明する習慣を持つだけでも、自分の理解を客観視するきっかけになります。
アウトプットすることで、本当に身についているかどうかを確認しやすくなります。

まとめ
中学3年生の夏休みは、高校受験に向けた土台を築く大切な期間です。
目安となる勉強時間を意識しながら、自分に合った計画と学習内容で取り組めば、確かな成果につながります。
毎日の積み重ねを大切にし、悔いのない夏にしていきましょう。
家庭教師のマスターでは、高校受験を控える中学3年生の学習サポートを行っています。ご興味のある方は、気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【高校受験コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
高校受験はいつ?|【令和7年度】関東・関西の試験日程、願書締切日
-
高校受験の勉強法とは?|科目別・時期別に詳しく解説!
-
【高校受験】効率の良い受験対策・受験勉強の方法をご紹介します!
-
高校受験の勉強って何からすればいい?|中学生の為の受験勉強ガイド
-
高校受験はいつから間に合う?|始める時期と準備について
-
内申点は高校受験に関係ない?|合否への影響度について解説!
-
高校の選び方・決め方9つのポイント|失敗しない志望校の選び方
-
高校の推薦入試で落ちる理由とは?|その原因と対策を徹底解説!
-
高校受験の内申点とは?|内申書(調査書)・内申点の基礎知識ガイド
-
高校の推薦入試対策ガイド|ここだけは知っておきたいポイント























