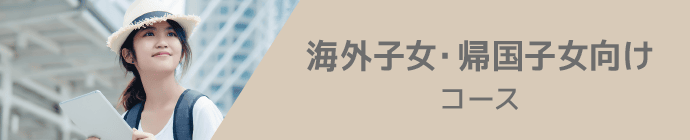不登校の出席扱いに?|オンライン授業で学校を出席扱いにする方法を解説
公開日:2025年10月7日
更新日:2025年10月7日
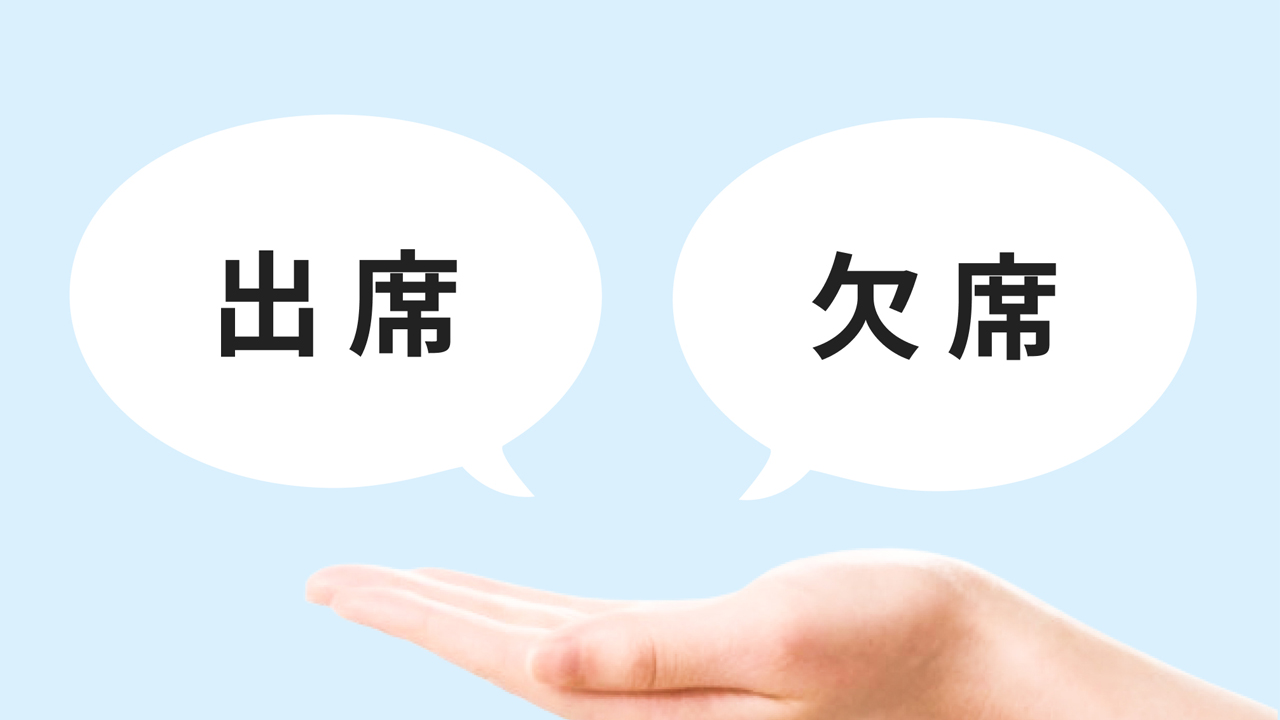
このコラムでは「不登校でもオンライン授業で出席扱いになるのか?」という疑問にお答えします。文科省が示すルール、必要な条件と注意点をわかりやすく解説。さらに実際の家庭の事例や、保護者ができるサポート方法も紹介します。
不登校のお子さんの出席や学びに悩む方に役立つ内容です。
不登校の子がオンライン授業で“出席扱い”になるってホント?
近年、不登校の子どもが増える中で、「自宅でオンライン授業を受けても出席扱いになるのか?」という疑問を持つ保護者は少なくありません。
実は文部科学省は一定の条件を満たすことで、オンラインでの学びを出席と認める制度を整えています。ただし、学校や校長の判断によって対応が分かれるのが現状です。
ここでは、制度のルールや実際のケース、そして普及が進みにくい理由まで詳しく見ていきましょう。
1. 文科省が示す出席扱い制度のルール
文科省は「出席扱いに関するガイドライン」を出しており、自宅学習やICTを活用した学習でも一定の条件を満たせば出席として認められるとしています。
具体的には、学校側が内容や進捗を把握できること、学習の成果を確認できること、そして学校と家庭の間で連携が取れていることが求められます。
単に「家で勉強しているから出席扱い」というわけではなく、学校が学習を管理・評価できる仕組みがあるかどうかがポイントです。
参照:文部科学省「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指 導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」
2. 校長の裁量で認められる仕組み
出席扱いになるかどうかは、最終的に校長の裁量によって決まります。
文科省のルールはあくまで「基準」であり、実際に承認するかどうかは学校ごとに判断が異なります。そのため、同じ条件で学習していても、ある学校では出席扱いになる一方、別の学校では認められないケースもあります。
大切なのは、保護者が担任や学校長と丁寧に相談することです。
3. 実際に出席扱いが認められたケースとそうでないケース
例えば、オンライン授業を毎日受け、学習記録やレポートを提出していた生徒が出席扱いとして認められた事例があります。学校と家庭が頻繁に連絡を取り合い、学習の進捗を確認できたことが評価されました。
一方で、同じようにオンラインで学んでいても、授業の内容を学校側が確認できなかったり、提出物が不十分だった場合には、出席扱いと認められなかった例もあります。
つまり「ただ受けている」だけでは不十分で、学習の証拠や学校との連携がなければ制度を活かしきれないのです。
4. 普及が進みにくい理由
出席扱い制度は存在しているにもかかわらず、全国的に広がりにくいのはなぜでしょうか。理由の一つは、学校側の負担です。
学習内容の確認や成果の評価を教員が追加で行う必要があり、現場にとっては大きな負担になります。
また、ICT環境が整っている家庭とそうでない家庭で差が出る「ICT格差」も大きな課題です。
さらに、制度自体が十分に周知されていないため、学校や保護者が利用をためらうケースもあります。結果として、制度はあるのに実際には活用が進まない状況が続いているのです。

不登校とオンライン授業の関係|なぜ今注目されているのか
不登校の子どもの数は年々増加しており、文部科学省の統計でも過去最多を更新しています。学校に行けなくても学びを継続できるようにするため、ICT教育やオンライン授業の導入が注目されています。
ここでは、制度が注目される背景と、他の学びの場との違いを解説します。
1. 不登校の児童生徒数は過去最多
令和5年度の調査によると、小・中学校における不登校児童生徒数は 約34万6,482人で、前年から 47,434人(15.9%)増加し、11年連続の増加で過去最多を更新しました。
また、高等学校でも 約6万8,770人と過去最多であり、前年度に比べ 8,195人(13.5%)増加しています。
参照:文部科学省「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」
2. 「学びを止めない」ために広がるICT教育
不登校の子どもにとって最大の課題は、学習の遅れです。授業に出られないことで、学習内容の積み残しが増えてしまいます。
そこで注目されているのが、ICTを活用したオンライン授業です。タブレットやパソコンを通じて、自宅にいながら授業を受けられる仕組みは、子どもが学校に戻れなくても「学びを止めない」手段となります。
国としてもICT教育の推進を掲げ、学習機会の確保を強化しています。
参照:文部科学省「やむを得ず学校に登校できない児童生徒等へのICTを活用した学習指導等について」
3. フリースクールや適応指導教室との違い
不登校の子どもの学びの場としては、フリースクールや適応指導教室もよく利用されます。
これらは子どもに安心できる居場所を提供する点で大きな役割を果たしていますが、学校によっては出席扱いと認められないこともあります。
一方で、オンライン授業は学校と直接つながって行う学習であるため、制度上出席扱いにできる可能性が高いという特徴があります。つまり、学びの場としての性格が似ていても、制度上の扱いには大きな違いがあるのです。
フリースクールについてもっと知りたい方はこちら
⇒「フリースクールの5つのタイプと子どもに合った選び方」
4. 教室に戻れない子にとっての“安心できる居場所”
不登校の子どもにとって、教室は必ずしも安心できる場所ではありません。
その一方で、自宅で受けられるオンライン授業であれば、子どもが安心して学習することが可能です。
また、画面越しであっても先生とつながれることで、子どもは「自分は学校から取り残されていない」と感じることができます。
このように、安心感のある学習環境を持つことは、再び学校に行けるようになるためのキッカケにもなるでしょう。
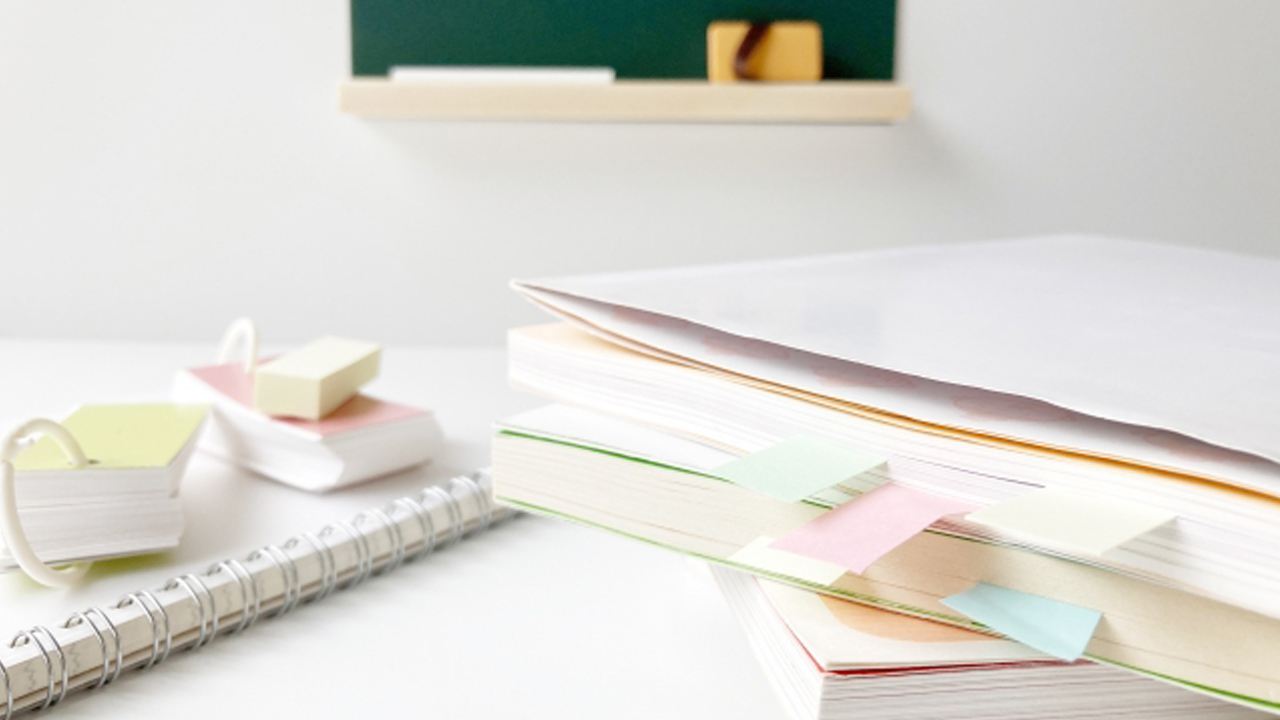
オンライン授業で出席扱いにするための具体的な条件と注意点
オンライン授業を出席扱いにするには、単に「オンラインで授業を受けている」だけでは不十分です。文部科学省の制度に基づき、学校との連携や学習の証明が必要になります。
ここでは実際に出席扱いを認めてもらうために押さえておきたい条件と、注意すべきポイントを整理します。
1. 学校との相談と連携が必須になる
出席扱いは最終的に校長の裁量で判断されます。そのため、オンライン授業を利用する際には、必ず学校側に事前相談を行い、ルールや出席扱いになる条件を確認しておく必要があります。
担任や学校長と話し合いを重ねて、どの範囲を出席として認めてもらえるのかを明確にすることが重要です。相談が不十分だと、せっかく取り組んでも出席が認められない可能性があります。
2. 学習記録やレポート提出
上記にもあるように、オンライン授業を受けているだけでは「出席した」とはみなされません。必要なのは、学習記録や成果物の提出です。
例えば、授業後に指定されたレポートやワークシートを提出したり、学習アプリの履歴を学校に共有したりすることで、学習の実態を証明できることで出席につながります。学校側はこの記録をもとに「学習の進捗」を判断するため、日々の積み重ねが非常に重要です。
3. 対面指導や登校日を組み合わせる必要性
オンラインだけで学習を完結させるのではなく、場合によっては対面での指導や登校日を組み合わせることも求められます。
例えば、定期的に学校へ登校して先生と面談を行ったり、補習授業を受けたりすることで、学校側も出席扱いを認めやすくなります。つまり「完全オンライン」ではなく、学校とつながりを保つ工夫が大切です。
4. ICT環境や家庭のサポート体制の重要性
オンライン授業を受けるためには、安定した通信環境や端末の準備が不可欠です。環境が整っていないと接続トラブルが起こり、オンライン授業に支障が出ます。
また、家庭側でのサポートも重要です。子どもがきちんと授業を受けられるように、保護者がスケジュールを確認したり、必要に応じて声をかけたりすることが求められます。
つまり、家庭の協力がなければ、制度を最大限に活かすことは難しいのです。

不登校の子がオンライン授業を受けるメリットとデメリット
オンライン授業は、不登校の子どもにとって「学校以外の学びの場」として注目されています。
ただし、メリットがある一方で、課題やデメリットも存在します。ここでは、実際に利用する際に保護者が知っておきたい利点と注意点を整理し、最後に利用した家庭の声を紹介します。
メリット①|自宅で安心・自分のペースで学べる
不登校の子にとって、学校という場そのものが不安や緊張の原因になることがあります。
オンライン授業なら、慣れた自宅で落ち着いて学べるため、心の負担が軽減されやすいのが大きな魅力です。
また、授業の進め方も柔軟で、自分のペースに合わせて学習を進められることが可能です。例えば、登校すると体調を崩してしまう子も、自宅なら午前中だけ受ける、短時間だけ参加する、といった形で「できる範囲」で学びを続けられます。
こうした安心感は、学習習慣を取り戻す第一歩となるケースも多いです。
メリット②|繰り返し学習で理解が深まる
教室の授業では「聞き逃したらそのまま」ということもありますが、オンライン授業では録画や教材の繰り返し視聴が可能です。
理解できなかった部分を何度も見直せるのは、不登校で授業に遅れがちな子にとって大きなメリットとなります。特に算数や数学のように積み上げが必要な教科では、「わからないところを振り返って確認できる」ことが学習の定着に直結します。また、復習の機会が増えることで、基礎学力の底上げや自信の回復につながりやすいという利点もあります。
デメリット①|交流不足による孤立感
一方で、オンライン授業には人との交流が少ないという欠点があります。
教室であれば友達との雑談や先生とのちょっとしたやり取りから刺激を受けられますが、画面越しの学習ではそのような体験が得にくいのです。そのため「学習はできるけれど、人とのつながりが薄れて孤独を感じる」という声も少なくありません。
特に長期間オンラインに依存すると、社会性を育む機会が不足し、孤立感や閉塞感を強めてしまうリスクがあります。
デメリット②|質問のしづらさや集中力の課題
オンライン授業では、先生にすぐ質問できない不便さがあります。
チャット機能やメールで質問できる場合もありますが、その場でやり取りできる対面授業に比べると理解が深まりにくいことがあります。
また、自宅での学習は集中を妨げる要素も多く、家族の生活音やスマホなどの誘惑によって注意が散漫になりがちです。特に集中力が続きにくい子どもは、学習効率が下がるリスクがあるため、保護者が環境づくりをサポートする必要があります。
実際に利用した家庭の声
ある中学生の家庭では、長期間学校に通えない時期が続いたものの、オンライン授業を毎日受けることで学習の遅れを最小限にできたそうです。
保護者は「録画授業を何度も見直せたので、子どもが『やっと分かった』と笑顔を見せたのが印象的でした」と振り返っています。
学習を続けられたことが子どもの自信回復につながり、少しずつ前向きな姿勢が戻ってきたとのことです。
一方で、別の家庭では「オンライン授業だけだと友達や先生との関わりがほとんどなく、子どもが孤独感を訴えるようになった」と話しています。
そのため、授業だけでなく、家庭内で一緒に学んだ内容を振り返ったり、家庭教師や地域の居場所を組み合わせたりするなど、人とのつながりを補う工夫が必要だと実感したといいます。

家庭でできるオンライン授業のサポート方法
オンライン授業は制度として利用できても、子どもが実際に学び続けられるかどうかは家庭での支え方に大きく左右されます。特に不登校の子どもは、学習意欲よりも「安心して過ごせるかどうか」が優先されることが多いため、保護者がどう寄り添うかがポイントです。
ここでは、家庭でできる具体的なサポートの工夫を詳しく見ていきましょう。
1. 子どもの気持ちを尊重し、無理に押しつけない
オンライン授業は、学校に行けない子どもにとって学びを取り戻す手段の一つですが、同時に新たな負担にもなり得ます。
「せっかく家で授業が受けられるのに、なんで参加しないの?」という思いを保護者が口にしてしまうと、子どもは強いプレッシャーを感じてしまいます。
大切なのは、子どものペースに合わせて「今日は5分だけでも参加できたね」と小さな一歩を認めてあげることです。こうした積み重ねが、やがて自信や前向きな気持ちにつながります。
2. 授業の振り返りを親子で一緒にする工夫
オンライン授業は受けて終わりにしがちですが、学びを定着させるためには振り返りの習慣が欠かせません。
例えば、授業後に「今日の授業で面白かったことは何?」と問いかけるだけでも、学習内容を言葉にして整理できます。難しかった部分を一緒に見直したり、子どもが理解できたところを褒めてあげたりすると、自己肯定感の回復にもつながります。
短い会話でも「学びを共有する」姿勢が、子どもの安心感を育てるのです。
3. 学校や先生との情報共有をこまめに行う
オンライン授業を出席扱いにするためには、学校との連携が何より重要です。
受講状況や子どもの様子をこまめに先生に伝えることで、学校側も状況を正しく把握できます。例えば、授業中に集中が途切れやすいことや、課題の提出が難しいタイミングがあるといった情報を共有するだけで、先生のサポートの仕方が変わります。
結果として、出席扱いの判断や学習支援がスムーズになり、子どもにとっても無理のない形で制度を利用できるようになります。
4. 家庭教師や外部サポートを組み合わせて理解を深める
オンライン授業は「理解を広げる場」にはなりますが、個別の疑問を解決するには限界があります。
そこで活用したいのが家庭教師や外部サポートです。先生に直接質問できないもどかしさを、第三者の存在が補ってくれます。また、外部の学習支援者が入ることで、保護者以外の大人と安心して関わる機会も増えます。
これにより、子どもは「自分を理解してくれる大人がいる」という実感を持てるようになり、孤立感の軽減にもつながります。
おすすめのオンライン家庭教師についてもっと知りたい方はこちら
⇒「おすすめのオンライン家庭教師とは?|探し方のコツを紹介します!」
5. 「安心して学べる環境づくり」が第一歩になる
最後に欠かせないのが、物理的・心理的な学習環境の整備です。
静かな部屋や安定した通信環境を用意することはもちろんですが、それ以上に「勉強してもしなくても、ここにいて大丈夫」と感じられる雰囲気づくりが大切です。
保護者がそっと同じ部屋にいるだけで安心できる子もいれば、時々声をかけてもらえることで集中できる子もいます。こうした家庭での工夫が、在宅での学習を支える土台となり、子どもが自分らしく学び続けられる環境につながります。

まとめ
不登校の子どもがオンライン授業を活用することで、学習を続けながら出席扱いとなる可能性が広がっています。ただし制度を利用するには、学校との連携や家庭での支えが欠かせません。
大切なのは「出席を増やすこと」だけでなく、子どもが安心して学べる環境を整えることです。
オンライン授業をきっかけに、学びの自信や将来への一歩を取り戻せるよう、家庭と学校が協力して支えていきましょう。
家庭教師のマスターでは、不登校のお子さんへの学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【不登校コース】について
オンライン家庭教師のマスターについて
オンライン家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 学校の授業や教科書・ワークのサポート
- 定期テストのサポート
- 中学・高校・大学受験のサポート
- 進学塾の補習
- 不登校のお子さんのサポート
- 発達障害のお子さんのサポート
- 小論文や作文のサポート
- 英検・漢検・TOEIC対策のサポート
など、ご家庭のニーズに沿った内容を指導しています。
ご家庭にある問題集やプリントで、生徒さんが教えてほしい問題や分からない分野を教えます。
料金について
「家庭教師は料金が高い」といったイメージを持つ方は多いのではないでしょうか?
オンライン家庭教師のマスターは、多くのオンライン家庭教師会社よりも低料金で指導を受けることができるので、是非、他社料金と比較してみてください!
また、2人同時指導のお得なプランもご提供しています。
- 中学1〜2年生:9,200円~/月
- 中学3年生:9,750円~/月
- 小学1~3年生:7,950円~/月
- 小学4~6年生:8,500円~/月
- 中学受験:11,700円~/月
- 高校生:11,640円~/月
- 2人同時指導(ペアレッスン):3,990円~/月
兄弟姉妹やお友達と一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、お得な料金でオンライン家庭教師の指導が受けられます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
また、オンライン家庭教師のマスターは、業界最大級の登録家庭教師の中から厳選された教師を選抜しています。お住まいの地域にかかわらず、低料金で高品質の指導を受けることができます。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学・地学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目全ての指導が可能です。
また、定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
オンライン家庭教師のマスターでは、お子さんの目的に合わせた様々なコースをご用意しています。
さらに、お子さんの学力・進路・現在の状況などに合わせて、一人ひとりに合わせたオーダーメイドのカリキュラムを組み、指導を行います。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たちオンライン家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
オンライン家庭教師のマスターでは、実際に担当する家庭教師による無料体験レッスンを行っています。
・オンラインでの指導はどんな感じか?
・先生の教え方は分かりやすいか?
・先生の人柄や子どもの相性は合っているか?
などを是非体験してみてください!
ご興味のある方は、下記より気軽にお問合せください。
関連する記事
-
子どもが不登校になる原因と親の対応方法とは?
-
小学生が不登校になる主な原因と親がすべきサポート
-
中学生が不登校になる原因と親がすべき対応策
-
「学校に行きたくない」と子どもが言った時の理由や対応方法について
-
子どもが学校を休む理由とは?|理由がわからない場合の対処法も解説
-
不登校の小学生の家での過ごし方|昼間は何をさせる?
-
不登校の中学生は何をするの?|昼間の過ごし方や家でやること
-
子供が不登校になるのは母親が原因?|育て方の影響やサポート法について
-
不登校は単なる甘え??|不登校と甘えの関連性を考える
-
いじめによる不登校について|親のサポート方法や相談窓口もご紹介
-
保健室登校とは?|不登校から教室復帰するまでの流れを解説