中学生の評定平均の出し方|高校受験に必要な内申点の計算方法と成績アップのコツ
公開日:2025年8月4日
更新日:2025年8月4日

中学生にとって「評定平均」は高校受験にも関わる大事な数字です。このコラムでは、通知表を使った評定平均の正しい出し方を具体的に解説。計算例やよくある疑問、成績を上げるための勉強の工夫まで、中学生と保護者に役立つ情報をわかりやすく紹介します。
評定平均って何?|高校受験でも大切な成績の目安
高校受験に向けて「評定平均」という言葉をよく耳にする中学生も多いかと思います。
定期テストの点数とは違い、通知表に書かれた「評定」から算出されるこの数値は、高校側が生徒の学力や態度を総合的に評価するための大切な指標です。
ここでは、まず「評定平均」とは何か、その意味や使われる場面について詳しく解説します。
1. 「評定」と「評定平均」はどう違う?
「評定」とは、通知表にある各教科の成績を5段階で表したものです。(※例えば、国語が「4」、数学が「3」といった数字がそれにあたります。)
これは、定期テストの点数だけでなく、授業態度や提出物、理解度なども含めた総合的な評価です。
一方で「評定平均」とは、各教科の評定をすべて合計し、教科数で割った平均値のことを指します。9教科の評定をすべて足して9で割れば、それがその学年の評定平均となります。例えば、9教科の評定合計が36点なら、評定平均は「4.0」となります。
2. 評定平均が使われる場面
評定平均は、ただの参考値ではありません。高校受験や進学に直結する重要な数値として、以下のような場面で使われます。
高校受験の選抜基準で「内申点」として使われる
多くの公立高校では、学力試験の点数と並んで「内申点(=評定平均)」が合否を左右する大きな判断材料になります。
都道府県や高校によっては、5教科よりも副教科を重視したり、9教科をすべて均等に扱ったりと、評価の仕組みに違いがありますが、いずれにしても通知表の成績が受験に影響を与えることは間違いありません。
推薦入試で重要になる「基準評定」
推薦入試を受ける場合、多くの高校で「基準評定」と呼ばれる最低ラインが設定されています。
例えば「評定平均4.0以上」といった条件を満たしていなければ、そもそも推薦を受ける資格が得られないケースもあります。
つまり、評定平均が足りないと、推薦という選択肢そのものがなくなってしまうこともあるのです。
成績証明書(調査書)で記載される項目
高校受験時に中学校から提出される「調査書」には、学年ごとの評定や学習の記録が詳細に記載されます。
この調査書をもとに、高校側は生徒の学力や人柄、継続的な努力を確認します。中3の成績だけでなく、中1・中2の評定もすべて載る地域も多いため、早めから意識して取り組むことが重要です。
3. 高校ごとに異なる「内申基準」にも注意
「内申点が大事」と言っても、その扱い方は高校ごとに異なります。
例えば、同じ偏差値の高校でも、ある学校は「9教科平均で4.0以上」が必要で、別の学校では「主要5教科を重視」としているケースもあります。
また、私立高校の場合は、独自の基準で合否を判断する学校もあり、一概に「評定平均が高ければ安心」とは言い切れません。
そのため、志望校を決める際には、内申点(評定平均)に関する基準を早めに調べておくことが大切です。中学の担任の先生や進路指導の先生に相談すれば、地域の高校の基準について具体的に教えてもらえるはずです。
内申点の計算についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「内申点の計算方法|自分の点数をシミュレーションしてみよう!」
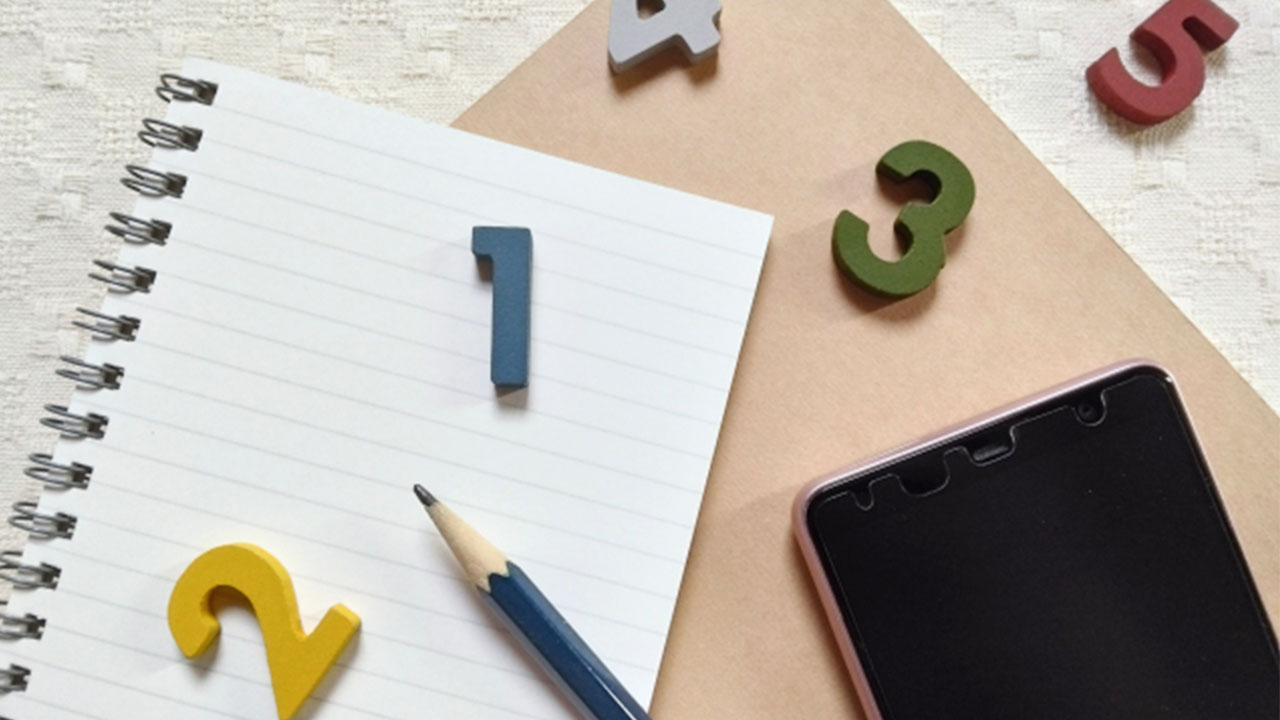
通知表を使った評定平均の出し方|計算方法を解説
「評定平均が大切」と言われても、具体的にどうやって計算すればよいのか分からないという中学生や保護者の方も多いと思います。
ここでは、通知表をもとにした評定平均の基本的な出し方や、実際の計算例、小数点の扱いまで、丁寧に解説します。自分の成績がどのくらいなのか、しっかり確認できるようにしておきましょう。
1. 通知表にある5段階評価が「評定」になる
中学校の通知表には、各教科ごとに「5」「4」「3」などの数字が記載されています。これがそのまま「評定」と呼ばれるものです。
この評定は、テストの点数だけでなく、授業中の取り組み方や提出物、授業内容の理解度などを総合的に評価した結果として決まります。
つまり、通知表に書かれているこの数字が、高校受験における「内申点」や「評定平均」の材料になるのです。
2. 9教科の評定を足して9で割るのが基本
評定平均は、通知表にある9教科すべての評定を合計して、教科数(9)で割ることで求めます。9教科とは、次のとおりです。
・【主要5教科】国語・数学・英語・理科・社会
・【副教科】音楽・美術・保健体育・技術・家庭(※技術と家庭は1教科として扱われます)
この9つの評定をすべて足し、その合計を9で割った数字が「その学年の評定平均」となります。
3. 実際の通知表を使った計算例を見てみよう
例えば、以下のような評定だった場合を見てみましょう。
| 教科 | 評定 |
|---|---|
| 国語 | 4 |
| 数学 | 3 |
| 英語 | 4 |
| 理科 | 3 |
| 社会 | 4 |
| 音楽 | 5 |
| 美術 | 3 |
| 保健体育 | 4 |
| 技術・家庭 | 4 |
この9教科の合計は「34」です。
したがって、評定平均は次のように計算します。
34 ÷ 9 = 約3.78
この「3.78」が、1年間の評定平均ということになります。
4. 「切り上げ」や「小数点」はどう扱う?
評定平均を計算したとき、「3.78」や「4.22」などの小数点が出ることはよくあります。ではこの数字をどう扱うべきでしょうか?
実際には、小数第2位までを記載するのが一般的です。たとえば「3.78」ならそのまま「3.78」として使います。(※勝手に「切り上げ」て「4.0」としてしまうと、正確な評価とは言えなくなってしまうので注意が必要です。)
ただし、学校や模試、資料によっては「小数第1位で四捨五入」される場合もあるため、どの単位で扱うかは志望校や中学校の進路指導で確認しておくと安心です。
内申点の換算方法ついてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「内申点の換算方法を知ろう|内申点の仕組みと計算方法について」

よくある疑問Q&A|評定平均について知っておきたいこと
評定平均について調べていると、「これってどうなるの?」と迷うポイントがいくつも出てきます。
ここでは、中学生や保護者からよく聞かれる疑問にQ&A形式でわかりやすく答えていきます。制度のしくみを正しく理解し、受験準備に役立てましょう。
1. 中1・中2の成績はどこまで影響する?
高校受験で提出される「調査書」には、基本的に中1〜中3までの全学年の成績が記載されます。
そのため、中1や中2の成績もしっかりと高校側に見られます。
特に公立高校の場合、中3だけでなく、3年間の評定を合計して平均を出す「3年合計型」や、学年ごとに重みをつけて平均する「傾斜配点型」が使われることもあります。
「中3で挽回すれば大丈夫」と考える人もいますが、実際は中1・中2の成績も重要な評価材料になるため、できるだけ早い段階から内申を意識することが大切です。
2. 5教科だけの評定平均と9教科の違いは?
「内申点=主要5教科だけ」と思っている人もいますが、高校受験で使われる評定平均は基本的に「9教科すべて」を対象としています。
つまり、副教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭)も、主要教科と同じようにしっかり評価されるということです。
また、一部の都道府県では副教科に2倍の重みをつける制度を取り入れている場合もあります。そのため、「副教科だから軽視していい」という考え方は非常に危険です。全教科にまんべんなく取り組む姿勢が、結果として評定平均アップにつながります。
副教科についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「副教科の勉強法について|テストで高得点を取るための対策」
3. 通知表の「観点別評価」と評定平均の関係は?
通知表には、
「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」
といった観点別の評価項目が記載されています。これらの観点別評価は、数値ではなく「A・B・C」などの段階で表されているケースも多いです。
この観点別評価の結果をもとに、教科ごとの最終評定(5段階)が決定されます。
例えば、「知識・技能」がAでも、他の観点がBやCだと、評定が4や3に落ちる可能性もあります。逆に、すべての観点がAなら、5がつく可能性が高まります。
つまり、「評定5を取るためにはテストだけでなく、普段の授業への取り組み方が大事」とよく言われるのは、こうした観点別評価が背景にあるからなのです。
観点別評価についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「観点別評価の基礎知識【中学生】|通知表はどうやってつけてる?」
4. どれくらいの評定平均があれば安心なの?
「どのくらいの評定平均なら合格できるのか?」というのは、多くの受験生が気になるポイントです。しかし、これは志望校によって大きく異なります。
例えば、偏差値が高い公立高校では「評定平均4.0以上」が求められることが多く、さらに推薦入試では「4.2以上」や「オール4以上」といった明確な基準が設定されている場合もあります。
一方、私立高校では内申よりも学力試験を重視する学校が多く、「3.0台」でも合格できるケースもあります。
大切なのは、「志望校の内申基準を早めに調べ、それに向けて計画的に行動すること」です。内申基準をクリアしていれば、受験本番のプレッシャーも減らせるというメリットもあります。
内申点についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「内申点はどこから高い?どこから低い?|内申点の目安を解説!」

評定平均を上げるには?|今からできる対策と工夫
評定平均は通知表の成績から算出されるため、「普段の学校生活の積み重ね」が結果に直結します。テストの点数だけでなく、日々の取り組みや意識の差が大きく影響するのが特徴です。ここでは、今すぐ取り組める4つの具体的な工夫を紹介します。苦手を克服し、できるところをしっかり伸ばして、評定平均を少しでも上げていきましょう。
1. 定期テストの点数アップが一番の近道
評定の決定に最も大きく影響するのは、定期テストの結果です。
特に主要5教科は、学力そのものが問われる場面も多く、テストの点数がストレートに評定に反映されやすい傾向があります。
「苦手教科は最低限の対策で…」という考えでは、全体の平均が下がってしまう原因になりかねません。大切なのは、どの教科も一定の点数を安定して取ることです。
点数に波があるよりも、着実に60点・70点台を維持している方が、評定にはプラスになります。
2. 提出物や授業態度も評価の対象になる
テストでいくら良い点を取っていても、「提出物を出していない」「授業中に話を聞いていない」といったことがあれば、観点別評価でマイナスとなり、評定は下がってしまいます。
逆に言えば、テストの点がそこまで高くなくても、課題を期限内に丁寧に提出することや、真面目に授業に参加することで、評価を補うことができます。特に、提出物は「出す・出さない」で評定が1段階変わることもあるほど重要な要素です。
普段のノート、ワーク、レポートなどはこまめに確認し、「出し忘れをゼロにする」ことがまず第一歩です。
3. 副教科(音楽・美術・保体・技家)も油断しない
副教科は「成績に入らない」と思われがちですが、実際は評定平均に大きな影響を与えています。
地域によっては、副教科の比重を2倍にして計算することもあるため、主要教科以上に副教科の重要性が高まるケースもあります。
副教科は「提出物・実技・授業態度」の比率が高く、普段の取り組み次第で評定が大きく変わります。絵が苦手、運動が苦手という子でも、真剣に取り組む姿勢を見せることで高評価につながることも多いです。
副教科で「4」や「5」が取れれば、全体の評定平均を底上げする強い味方になります。
4. 苦手教科によって平均を下げないように
「苦手な教科が1つあるだけで、評定平均が一気に下がってしまう」というのは、実はよくある話です。
例えば、他の8教科がすべて「4」でも、1教科が「2」になれば、それだけで平均が大きく下がってしまいます。
苦手な教科があるのは当然ですが、大事なのは“最低限の評価”を確保することです。
「2を3に上げる」「3をキープする」といった、小さな底上げを意識するだけでも、全体の評定は安定します。先生に質問したり、早めに復習に取り組んだりするなど、苦手に向き合う姿勢を持つことが、最終的に安心できる成績につながります。
反抗期についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「反抗期はいつから始まり、いつ終わるの?|接し方や注意点を徹底解説」
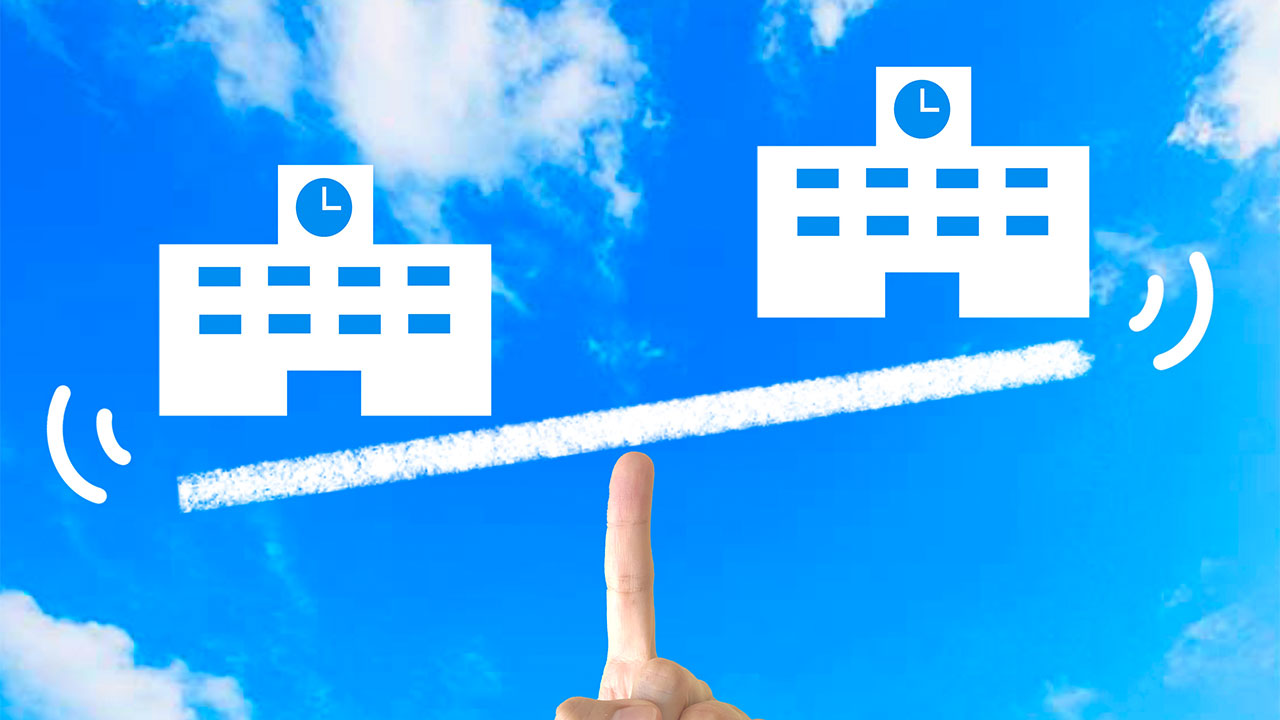
まとめ
評定平均は高校受験に直結する重要な指標であり、日々の積み重ねが結果に表れます。正しい計算方法を知り、自分の成績を客観的に把握することで、早めの対策が可能になります。
テストや提出物、授業態度を意識しながら、バランスよく取り組むことが、着実な成績アップにつながります。
家庭教師のマスターでは、内申点アップのための学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せ下さい。
もっと知りたい方はこちら
⇒【中学生コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
調査書(内申書)について徹底解説!|高校受験に向けて正しく理解しましょう!
-
高校受験の内申点とは?|内申書(調査書)・内申点の基礎知識ガイド
-
内申点は高校受験に関係ない?|合否への影響度について解説!
-
高校受験の勉強って何からすればいい?|中学生の為の受験勉強ガイド
-
【高校受験】効率の良い受験対策・受験勉強の方法をご紹介します!
-
偏差値って何だろう?|偏差値の意味や求め方(計算方法)を解説
-
偏差値を上げる方法とは?|受験生必見の勉強法を徹底解説!
-
オール4の偏差値はいくつ?高校受験で目指せる学校と学力の目安を解説
-
オール3の偏差値はいくつ?内申点3で目指せる高校と学力レベルを解説
-
内申点オール2の偏差値と学力目安|どんな高校に進める?成績アップ法も紹介























