勉強しない子を見捨ててもいいの?|メリット・デメリットと親が取るべき選択肢
公開日:2025年9月4日
更新日:2025年9月4日

「勉強しない子を見捨ててもいいの?」と悩んでいませんか?
このコラムでは、見捨てたときに起こりうるメリットとデメリットを整理し、親が本当に取るべき選択肢を解説します。
さらに、子どもを支えるための具体的なサポート方法も紹介しますので、保護者の方はぜひ参考にしてください。
「もう見捨てたい…」と思ってしまうのは普通のこと
子どもが勉強をしない様子を前にすると、多くの保護者が「もうどうしたらいいのか分からない」「いっそ見捨ててしまいたい」と感じることがあります。
これは決して特別な感情ではなく、むしろ多くの親が一度は経験する自然な思いです。親だからこそ諦めきれず、だからこそ心が疲れてしまうのです。
ここでは、なぜそのような気持ちに陥るのかを整理してみましょう。
1. 親の努力が報われず、限界を感じるとき
「一緒に計画を立ててみる」「毎日声をかける」「ご褒美を用意する」__親としてできることを精一杯試してきたのに、子どもが相変わらず勉強しない姿を見ると、報われない気持ちでいっぱいになります。
特に、親自身が仕事や家事で忙しい中、時間を削ってサポートしている場合、その徒労感はより強くなります。「ここまでやっても変わらないなら、もう放っておいた方が楽なのではないか…」と思ってしまうのも無理はありません。
また、親のエネルギーや忍耐にも限界があります。
最初は「子どものため」と前向きに関わっていても、繰り返される拒否や無関心に直面するうちに、やがて「もうこれ以上はできない」と感じる瞬間が訪れます。
これは親のメンタルが弱いわけではなく、人として自然な心理的防衛反応といえます。
2. 周囲と比べて焦りや不安が大きくなるとき
同級生の子どもが塾に通い、テストの点数を伸ばしている話を耳にしたり、親同士の会話で「うちの子は自主的に勉強している」と聞いたりすると、自分の子どもと比べてしまい、焦りや不安が一気に高まります。
学校の成績や模試の結果など、目に見える”点数”という形で差が広がっていくと、「このままでは取り返しがつかないのでは…」と心配になります。
さらに、周囲からの目も気になります。「なんで塾に通わせないの?」「親が甘やかしてるんじゃないか」と思われているような気がして、プレッシャーを感じることもあるでしょう。
このような焦りや不安が積み重なると、子どもに対して必要以上に厳しく接してしまったり、逆に「もう関わるのはやめよう」と突き放したくなったりします。
実際には親子の関係性が悪循環に陥っているだけなのですが、その渦中で冷静に見抜くのは難しいのです。
3. 子どもの将来を思うからこそ出てくる葛藤
親が「見捨てたい」と思ってしまう背景には、子どもの将来を真剣に心配する気持ちがあります。勉強しない姿を見て「このままでは高校進学や将来の就職に影響するのではないか」と不安になり、何とかしなくてはと焦ります。
しかし、無理に勉強させようとすると反発を招き、親子関係がこじれてしまいます。その一方で、手を引けば本当に勉強しなくなるのではという恐れもあり、親にとっては「関わる」か「距離を置く」かの間で揺れ動く、とても苦しい葛藤です。
つまり「見捨てたい」という感情は、子どもを本当にどうでもいいと思っているのではなく、「このままでは良くない」と強く思うがゆえの親の葛藤の表れです。愛情と責任感があるからこそ、悩み苦しむのです。

なぜ勉強しない?子どもの心理と原因を理解しよう
子どもが勉強しない背景には、単なる「怠け」や「やる気がない」といった一言では片づけられない、さまざまな理由があります。
親の目からは「どうして机に向かわないのか」と不思議に思えても、子どもなりに葛藤や壁を抱えているのです。原因を理解することで、叱る以外の関わり方やサポートの道が見えてきます。ここでは代表的な4つのケースを見ていきましょう。
1. 勉強のやり方がわからず動けない
特に小学生や中学生の段階では、「勉強の方法」そのものを身につけていない子が少なくありません。
例えば「テストに向けて復習をしなさい」と言われても、どこから手をつければいいのか分からず、「ノートを見直す」「ワークを解き直す」といった具体的な行動がイメージできないため、結果的に机に向かえず、ただ時間だけが過ぎてしまいます。
また、「勉強=長時間机に向かうこと」というイメージが先行してしまうと、「どうせ続かない」「やっても意味がない」と感じてしまう子もいます。これは意欲がないのではなく、行動を細かく分解できていないことが原因です。やるべきことを細かく分解し、勉強のやり方さえわかれば、一歩を踏み出せるケースは非常に多いです。
2. 苦手意識や失敗体験で諦めてしまう
過去のテストで思うように点が取れなかったり、問題集を解いても間違いばかりだったりすると、「自分はできない」という気持ちが強く残ります。すると新しい課題に取り組む前から「どうせまた失敗する」という諦めモードになり、勉強を避けるようになります。
特に小学校高学年〜中学生では、学年が上がるにつれて内容が難しくなり、一度つまずくと「どこから復習すればいいのか」分からなくなりがちです。
小さな苦手の積み重ねが大きな壁となり、「自分には無理」という気持ちを作り出してしまうのです。
この状態は、努力をしないのではなく、失敗の痛みから「挑戦しない」という選択をしていると言えます。親が見ると「サボっている」ように映りますが、実際には心のブレーキがかかっているのです。
3. 興味が他にあり集中が続かない
子どもの興味や関心はとても移ろいやすく、勉強よりも楽しいことに引き寄せられるのは自然なことです。ゲーム、動画視聴、SNS、部活動や友達との関わり__これらは手軽に楽しさや達成感を得られるため、どうしても「成果が出るまで時間がかかる勉強」よりも優先されやすくなります。
さらに、もともと集中力が短い子や、同じ作業を繰り返すのが苦手な子にとって、勉強は単調で退屈に感じられることがあります。その結果、「やろう」と思っても10分も続かず、結局机から離れてしまうのです。
こうした場合は「勉強より遊びを選んでいる」と一方的に叱るよりも、子どもの集中力の続く時間を考慮しながら勉強時間を区切るなどの工夫をすることが大切です。
4. 生活リズムや環境の影響で学ぶ土台が崩れている
勉強する以前に、生活リズムや環境が整っていないと、そもそも学習に向かう力が育ちません。
夜更かしや朝の寝坊で日中の集中力が落ちていたり、食事や運動が偏って体調が不安定だったりすると、机に向かうエネルギー自体が不足します。
また、家庭内の雰囲気も大きく影響します。常に「勉強しなさい」と言われ続ける環境では、プレッシャーが強すぎて逆にやる気を失ってしまうことがありますし、逆に全く関心を持たれない場合も「どうせ期待されていない」と感じてしまうことがあります。
つまり、「勉強しない」という行動の背景には、子どもの意志だけでなく、日々の生活や家庭環境が深く関わっているのです。
昼夜逆転の治し方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「昼夜逆転の治し方|不登校、引きこもり、ゲーム・ネットのやり過ぎの子ども」

勉強しない子を「見捨てる」ことで起こること
子どもが勉強をしない姿に疲れ果て、「もう見捨ててしまおうか…」と思うことは決して珍しくありません。実際に一歩引いて関わらなくなることで、親自身の気持ちが軽くなる場面もあるでしょう。
しかし、その影響は一時的な安らぎにとどまることが多く、長期的には子どもや親子関係に大きな影を落とす可能性があります。
ここでは「見捨てる」ことで生じる一見メリットに見えることと、実際に大きくのしかかるデメリットを整理してみましょう。
1. 一見メリットに見えること
親のストレスが減ることで関係が楽になる
毎日のように「勉強しなさい」と声をかけ続けることは、親にとっても強いストレスです。
その負担を手放せば、親の心が軽くなり、子どもに対してイライラをぶつける回数も減るかもしれません。結果的に親子の衝突が減り、関係が一時的に落ち着く可能性があります。
子どもが自分で考えるきっかけになる可能性
「誰も言ってくれないのなら、自分でやらなければ」と気づく子もいます。親があえて距離を取ることで、自分の行動を見直すきっかけになる場合もあるでしょう。
特に自立心の芽生えている年齢では、「親が何も言わない=自分が責任を持つしかない」と受け止める子もいます。
2. 実際に大きいデメリット
学力・勉強習慣の低下が加速する
勉強は一度離れると取り戻すのが難しくなります。学年が進むごとに内容は複雑になり、基礎が抜けたままでは理解できない部分が増えていきます。
親が見守ることをやめると、勉強習慣がますます根付かず、遅れが広がるスピードが加速する可能性があります。
「見放された」と感じて親子の信頼が揺らぐ
子どもにとって、親から「見捨てられた…」と感じることは深い心の傷になります。「自分は愛されていないのでは」「期待されていないのでは」と思い込み、自己肯定感が下がってしまう危険もあります。
信頼関係が損なわれれば、勉強だけでなく生活全般で親に相談しづらくなり、親子の距離がどんどん広がってしまいます。
将来の選択肢が狭まり後悔につながるリスク
勉強を放置したまま時間が過ぎると、高校進学やその後の進路で選べる道が限られてしまいます。
子どもが将来「もっと勉強しておけばよかった…」と後悔した時、親も「なぜあのとき関わらなかったのか」と後悔を抱えることになりかねません。
短期的には楽になっても、長い目で見れば大きな後悔を残すリスクがあるのです。
勉強しない子の末路についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「勉強しない子の末路とは?|将来の不安を解消する親の対応策について」

見捨てずに向き合うためにできるサポート
「勉強しない子を見捨てたくなる」気持ちは自然なことですが、実際には見捨てることが解決にはつながりません。むしろ、親の関わり方を少し変えるだけで、子どもが前向きに学習へ向かうきっかけを作ることができます。
ここでは、家庭で実践できる具体的なサポート方法を紹介します。
1. 小さな成功体験を積ませて「やればできる」に気づかせる
子どもが勉強を避ける大きな理由のひとつに「どうせできない」という思い込みがあります。
これを乗り越えるには、短時間で達成できる小さな課題から始めるのが効果的です。例えば「漢字を3つ覚える」「5分だけ計算練習する」といった取り組みでも十分です。
小さな成功体験を積み重ねることで、「やればできる」という自己肯定感が少しずつ芽生えます。この感覚が次の行動への自信となり、やがて勉強への抵抗感を和らげていきます。
子どもの自己肯定感についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「子どもの自己肯定感の高め方とは?|7つのNG行動についても解説」
2. 勉強のハードルを下げて入り口を広げる
「1時間勉強しなさい」といきなり言われても、多くの子どもにとっては重荷に感じられます。大切なのは、最初のハードルをできるだけ低くすることです。
例えば「まず1問だけ解いてみよう」「5分だけ机に座ってみよう」と声をかけると、子どもは動き出しやすくなります。
また、完璧を求めすぎず「途中でやめてもいい」と伝えることも大事です。取りかかるまでの負担が小さければ小さいほど、学習のスタートラインに立ちやすくなるのです。
3. 興味あることと勉強をつなげてモチベーションを高める
勉強そのものがつまらないと感じている子どもには、興味のある分野と結びつける工夫が効果的です。
例えば、ゲームが好きなら「ゲームに出てくる英単語を覚える」、電車が好きなら「時刻表を使った問題を出してあげる」といった形です。
勉強を「自分の好きなことと関わっている」と感じられると、子どもは自然と意欲を持ちやすくなります。興味を入り口にすることで、「勉強=楽しくない」という固定観念を和らげることができます。
小中学生向け学習についてもっと知りたい方はこちら
⇒「勉強は楽しい!」と実感できる方法|小中学生向け学習の工夫」
4. 親以外の第三者の存在を活用する
親がどれだけ根気強く声をかけても、反発して受け入れないことがあります。そんな時は、第三者の力を借りるのも有効です。学校の先生、家庭教師、塾の講師、あるいは年の近い兄姉や親戚でも構いません。
「親以外の人に言われたことなら素直に聞ける」という子は意外に多いものです。また、第三者の存在は親にとっても心の負担を軽くしてくれます。
外部のサポートを取り入れることで、親子の関係が落ち着き、勉強の取り組みやすさも変わってきます。
5. 生活リズムを整えて学ぶ力の土台をつくる
どれだけ声をかけても、子どもが眠かったり体調が不安定だったりすれば勉強は進みません。学習の前提となるのは、規則正しい生活リズムです。
まずは「早寝・早起き・朝ごはん」という基本を整えることが大切です。睡眠時間が不足していると集中力は著しく低下しますし、食生活の乱れもやる気に直結します。また、スマホやゲームの使用時間を見直すことで、自然と勉強の時間を確保できるようになります。
生活の土台を整えることは、親子にとって「勉強しなさい」と言う以上に効果的なサポートなのです。
午前中を有効活用するメリットについてもっと知りたい方はこちら
⇒「早起きは“勉強効率”の最強習慣!|集中力も成績も変わる朝学のメリット」
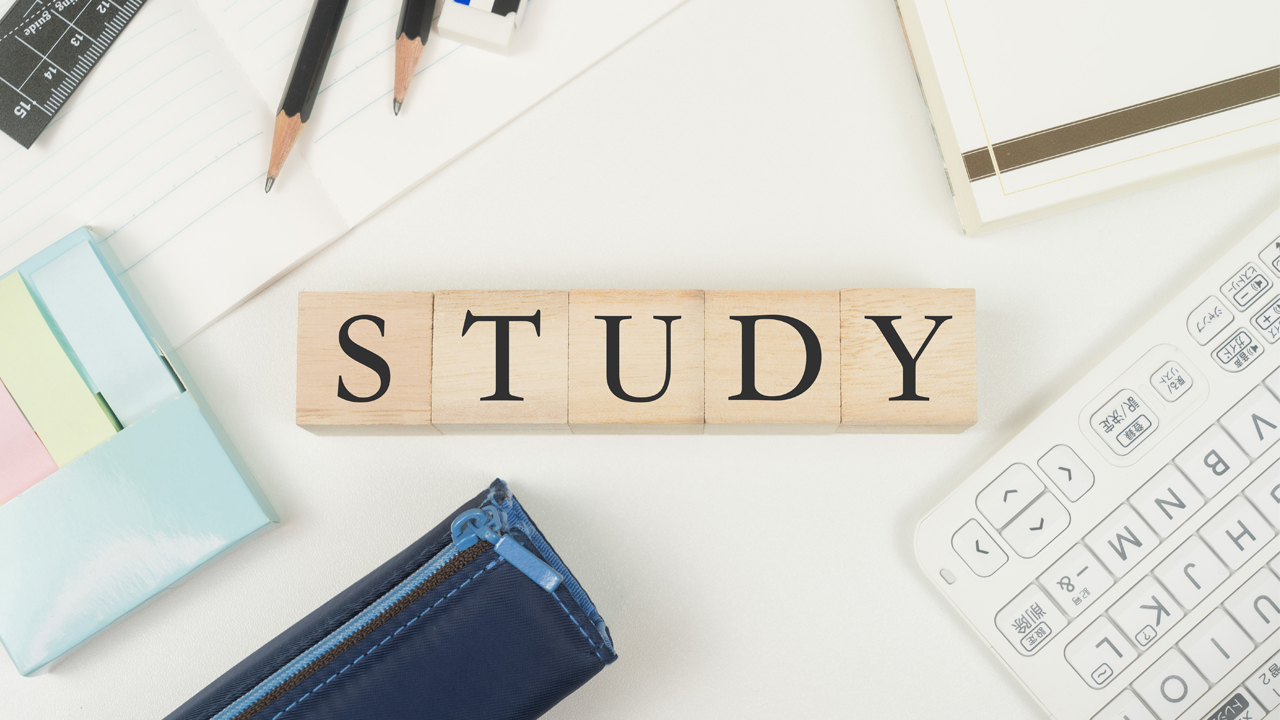
まとめ
子どもが勉強しない姿に疲れ、「見捨てたい」と思ってしまうのは珍しいことではありません。ですが、実際に突き放してしまうと、学力の低下や信頼関係の損失といった大きなリスクを抱えることになります。
大切なのは「見捨てるかどうか」ではなく、子どもに合った関わり方を工夫することです。小さな成功体験や生活リズムの改善、第三者の力を借りるなど、できることはたくさんあります。
焦らずに一歩ずつサポートを続けることで、子どもは必ず前に進む力を取り戻していきます。
家庭教師のマスターでは、勉強しない小中学生への学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せ下さい。
もっと知りたい方はこちら
⇒【小学生コース】について
⇒【中学生コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
勉強しない中学生をやる気にさせる方法|親の関わり方とNG行動も解説
-
子どもが勉強をしない理由|勉強させる方法と避けたいNG行動
-
勉強のやる気を出す方法【中学生編】|具体的な対策法をご紹介
-
勉強のモチベーションを上げる方法|短期戦向き7選と長期戦向き6選
-
勉強が家でできない理由と解決策|自宅学習で集中できる方法を伝授します!
-
勉強に集中する方法とは?|オススメ9つの方法をご紹介!
-
中学生をやる気にさせる魔法の言葉とは?|7つの言葉がけ
-
勉強中にイライラする理由は?今すぐできる対処法と親の関わり方
-
成績が上がる中学生の勉強方法とは?|ぐんぐん上がる!効果的な勉強法
-
「なぜ勉強するのか?」に答える名言とその解説|やる気が出る言葉を紹介
-
中学生の家庭学習がうまくいく方法|習慣化・やり方・苦手対策までまとめて紹介
-
勉強のやる気が出ない受験生はどうする?|その原因と対策方法
























