発達障害の子に塾は意味ない?“意味を持たせる”塾選びとサポートのコツ
公開日:2025年9月10日
更新日:2025年9月10日

発達障害の子どもにとって「塾は意味がないのでは?」と悩む保護者は少なくありません。
このコラムでは、塾通いが成果につながらない理由や、子どもの特性に合わせた塾選びの工夫を解説します。さらに、塾での学びを意味あるものにするために、家庭でできるサポート方法も紹介します。
本当に意味がない?|発達障害の子どもと塾通いの“現実”
発達障害のある子どもを持つ保護者の中には、「塾に通わせても意味がないのでは?」と感じる人が少なくありません。
実際、周囲と同じように塾に通わせても成果が出ず、むしろストレスばかり増えてしまうケースも見られます。
一方で、環境やサポートの条件が整えば、塾が子どもの学びを支える場となることもあります。つまり、「塾=意味がない」とは一概には言えず、どんな状況で意味を持つのかを理解することが大切です。
1. 「塾に通わせても伸びない」と感じるのはなぜか?
保護者が「塾に通わせても伸びない」と感じる背景には、いくつかの理由があります。
まず一つ目は、塾が「一斉授業」や「集団学習」を前提にしている場合です。
発達障害のある子どもは、注意が散りやすかったり、説明のスピードについていけなかったりすることがあり、周囲と同じペースで理解を進めるのが難しいことがあります。
その結果、「授業に出てはいるけれど内容が頭に入っていない」という状況になりがちです。
二つ目の理由は、「成果の基準」が一般的な学習塾と異なることです。
塾では定期テストの点数アップや模試の偏差値向上がゴールとして設定されがちですが、発達障害の子どもにとっては「授業を最後まで集中して聞けた」「宿題に取り組めた」こと自体が大きな成長の一歩になります。
保護者が点数だけを見てしまうと「意味がなかった」と判断してしまいやすいのです。
三つ目は、「本人のモチベーション」が伴っていないケースです。
親が良かれと思って塾に入れても、子ども自身が「通いたい」「学びたい」と感じていなければ、授業への参加姿勢は消極的になります。
結果的に「通わせても伸びない」という印象が強まってしまうのです。
2. 成果が出にくい3つの落とし穴
発達障害の子どもが塾に通う際には、特有の“落とし穴”が存在します。代表的なものを3つ挙げます。
まず一つ目は「環境のミスマッチ」です。
例えば大人数の教室や騒がしい雰囲気では、注意が散ってしまいやすい子どもにとって集中を保つのは至難の業です。
黒板やプリント中心の授業スタイルも、視覚優位や聴覚優位といった情報処理の特性に合わない場合、理解を妨げる要因となります。
二つ目は「サポート不足」です。
発達障害の特性を理解していない講師やスタッフが対応すると、子どもの困難さに気づけず「やる気がない」「努力不足」と誤解されてしまうことがあります。
そうなると本人の自尊心は傷つき、「塾=つらい場所」となり、通塾自体がストレス源になることもあります。
三つ目は「家庭との連携不足」です。
塾でどんな内容をやっているか、どこでつまずいているかを保護者が把握できないと、家庭学習とのつながりが途切れてしまいます。結果として、塾と家庭の学習がバラバラになり、「塾に行っても成績が伸びない」という感覚につながってしまいます。
3. 意味を生むケースと生まないケースの分かれ道
では、塾通いが「意味を持つケース」と「意味を持たないケース」は、どこで分かれるのでしょうか。
「意味を生むケース」は、子どもの特性に合った学習環境が用意されている場合です。
例えば、少人数制や個別指導であれば、自分のペースで学べるため理解が深まりやすいです。また、講師が発達障害に理解があり、「わからないところまで戻る」「できた部分を具体的に褒める」といった指導があれば、子どもの自己肯定感も高まり、学習意欲が育ちます。
さらに、家庭と塾が連携して「家庭での復習」や「学習習慣づけ」をサポートすれば、相乗効果で成果につながります。
一方、「意味を生まないケース」は、子どもの特性や学び方を無視して一律の指導が行われるときです。
「授業のスピードについていけない」「宿題の量が多すぎてこなせない」「叱責が多く自己肯定感が下がる」__こうした環境では「通うだけで疲れる」状態になり、学力どころか学習意欲そのものが失われてしまいます。
つまり、塾通いが「意味あるもの」になるかどうかは、子どもの特性に合った学習環境と、周囲の理解・サポート次第なのです。
発達障害の子の高校受験についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「発達障害(ASD・ADHD・LD・グレーゾーン)の子の高校受験対策」

タイプ別に解説|発達障害の特性と塾の相性
「発達障害」と言っても、子どもによって特性や得意・不得意は大きく異なります。
塾との相性もその子のタイプによって変わるため、「合う塾を選ぶ」ことが成果につながるかどうかの分かれ目になります。
ここでは代表的なADHD、ASD、LDの特性を取り上げ、それぞれの子どもに合う塾・合わない塾の傾向を解説します。
1. ADHD:不注意や集中の波が大きい子に合う塾・合わない塾
ADHD傾向の子どもは、不注意によるミスや集中の持続が難しいといった特性を持つことがあります。こうした子には、「短い時間で区切って学べる塾」が向いています。
例えば個別指導や少人数制の塾であれば、休憩を挟みながらテンポよく学習を進められるため、集中が切れやすい子でも取り組みやすいです。
逆に合わないのは、長時間の一斉授業や宿題の量が多い塾です。
45分〜90分の授業をじっと聞くことが求められる形式では集中が途切れ、理解度も下がりやすくなります。
また、宿題が多いと「やりきれない自分」に落ち込み、自己肯定感を損なうリスクもあります。
つまり、ADHD傾向の子に「時間の区切り」「適度な量の宿題で達成感を得る」「先生との会話の多さ」がカギとなります。
ADHDと集中力についてもっと知りたい方はこちら
⇒「ADHDと集中力の関係|過集中・不注意に悩む親のための対処ガイド」
2. ASD:こだわりが強く変化が苦手な子に合う塾・合わない塾
ASD傾向の子どもは、特定のルールややり方に強いこだわりを持ったり、急な変化に強いストレスを感じたりする傾向があります。
そのため、「ルールや予定が明確で、学習の流れが安定している塾」 が合いやすいです。
授業の進め方や宿題の出し方が一貫していると、ASD傾向の子どもは安心して学習に集中できます。また、静かで落ち着いた環境の塾も適しています。
反対に、授業の進め方が日によって変わる塾や、講師が頻繁に入れ替わる塾は合わない場合が多いです。変化が多いと不安が増し、学習どころではなくなってしまうからです。
また、集団の中で空気を読んだ行動を求められる雰囲気の塾も、ストレスにつながりやすいでしょう。
つまり、ASD傾向の子には「安心できる一貫性」「予測可能なルール」「落ち着いた環境」が大きなポイントになります。
3. LD:読み書きや計算に苦手さがある子に合う塾・合わない塾
LD(学習障害)の子どもは、知的な遅れはなくても、読み書きや計算といった特定の分野に強い苦手さを抱えています。
そのため、「苦手を補う工夫をしてくれる塾」 が向いています。
例えば、「板書中心ではなくプリントやタブレットを活用する」「読みの困難がある子には音声教材を取り入れる」といった柔軟な対応が必要です。
一方で合わないのは、教科書通りに一斉に進めていく塾です。基礎が定着していないまま授業が進むと、わからない部分が積み重なり、やがて「自分は勉強ができない」という思い込みにつながってしまいます。
また、テスト対策一辺倒の塾も、苦手克服には不向きです。
LDの子には「弱点を見極めてサポート」「教材や学習方法の工夫」「一歩ずつ戻って学べる環境」が相性の良いポイントとなります。
学習障害の診断テストについてもっと知りたい方はこちら
⇒「学習障害(LD・SLD)の診断テスト|症状別チェックリストをご紹介」

ここから塾に通わせる前に考えるべき3つの視点
発達障害のある子どもにとって、塾通いが必ずしもプラスになるとは限りません。入塾を検討する前に、「そもそも塾に行く目的は何か」「本人はどう感じているのか」「本当に塾でしかできないことなのか」を整理しておくことが大切です。
この見極めをするだけで、塾通いが子どもにとって“意味のある学び”になるかどうかが大きく変わってきます。
1.「なんのために」塾に通うのか?
まず最初に考えるべきは、塾に通う目的です。
定期テストの点数アップなのか、受験対策なのか、それとも家庭学習のペースを整えるためなのか__目的を明確にしないまま入塾すると、途中で「思っていた成果と違う」と感じやすくなります。
特に発達障害のある子どもは、一般的な「点数アップ」だけを成果としてしまうと効果があったかどうかを感じにくくなりがちです。
集中力が続いた、宿題に取り組めた、前より意欲的に発言できた__こうした小さな変化も「通う意味」に含めておき、「効果があった」と感じることが重要です。
2. 子ども本人が塾に通いたがってるかどうか?
保護者が良かれと思っても、子ども本人が通いたくない場合は長続きしません。
特に発達障害のある子どもは、嫌だと感じる環境では力を発揮しにくく、成果につながらないことが多いのです。
大切なのは、「塾に行きたい」という気持ちが本人にあるかどうかを尊重することです。
無理に通わせるのではなく、体験授業に参加して「ここなら大丈夫そう」と思えるかどうかを一緒に確認してみるとよいでしょう。
本人の納得感があるだけで、効果が出やすくなるはずです。
ADHDの子どもについてもっと知りたい方はこちら
⇒「「また逃げた…」ADHDの子どもが嫌なことから逃げる本当の理由とは?」
3. 本当に「塾じゃないとできないこと」なのか?
最後に考えるべきは、「塾以外の選択肢ではだめなのか?」という視点です。
今は家庭教師やオンライン学習、タブレット教材など多様な学び方があります。子どもの特性によっては、塾よりも個別指導の方が適しているケースも少なくありません。
大切なのは「塾に行かせること」ではなく、「子どもに合った学習の場を用意すること」です。塾でなければ得られないサポートや環境があるのかどうかを確認し、他の選択肢と比較することがおすすめです。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
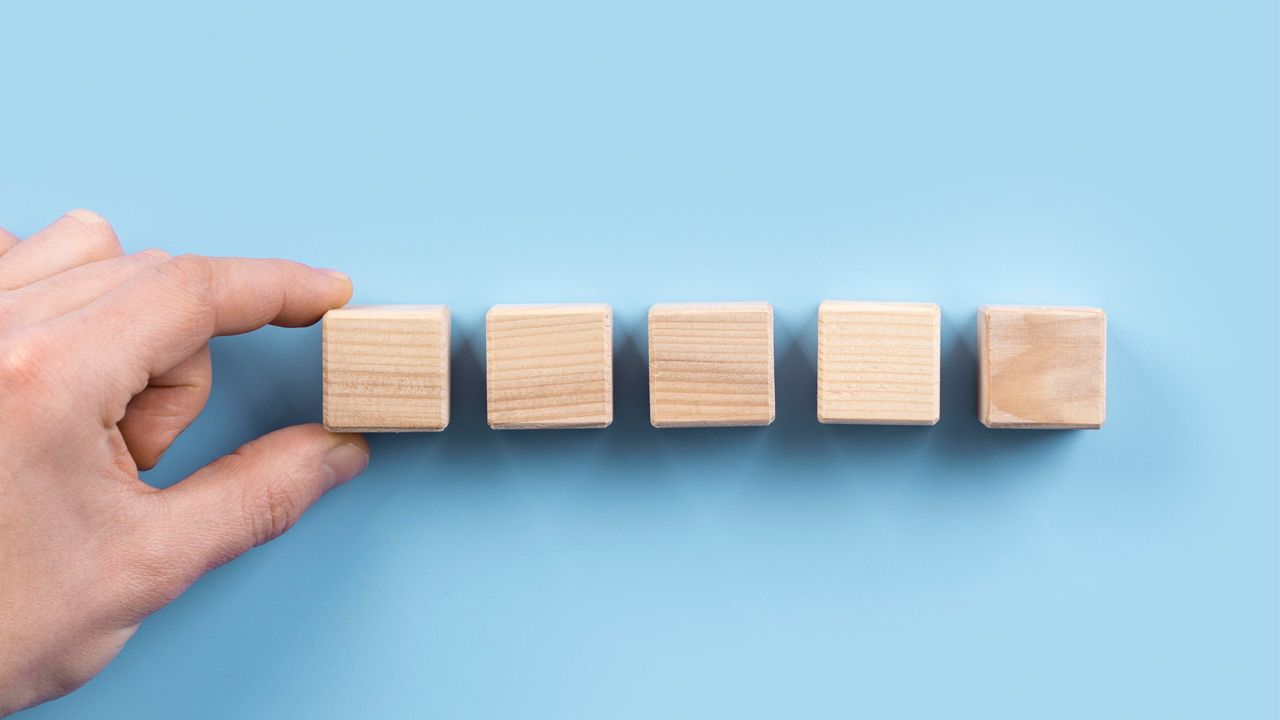
発達障害の子に合う塾選びの5つのコツ
「塾に通わせて意味がなかった・・」とならないようにするためには、子どもの特性に合った塾を選ぶことが不可欠です。
ただ「個別指導だから安心」といった表面的な条件だけでなく、指導スタイルや発達障害の特性への理解度、家庭との連携など、見えにくい部分こそが塾の成果を左右します。
ここでは発達障害の子に合う塾を選ぶ際に、ぜひチェックしておきたい5つのポイントを紹介します。
1. 先生が子どもの特性を理解してくれるかどうか?
一番大切なのは、指導にあたる先生が発達障害への理解を持っているかどうかです。
学習面の指導力があるだけでは不十分で、子どもの集中の途切れやすさや、こだわりの強さ、計算や読み書きのつまずきなどを理解し、受け止められるかがカギになります。
例えば、忘れ物が多い子に「また忘れたの?」と叱る先生ではなく、「どうやったら忘れないようにできるか」と建設的に声をかけられる先生の方が、子どもは安心して学べます。
体験授業や面談の際に「発達障害の子への対応経験がありますか?」と質問してみると、その塾の姿勢を見極めやすいでしょう。
2. 少人数または個別でのサポート体制があるか?
発達障害のある子どもにとって、周囲のペースに合わせる必要のある集団授業は不向きなことが多いです。一方で、少人数の個別指導であれば、理解度や集中のリズムに合わせて柔軟に授業を進められるため安心感があります。
また、個別指導といっても先生1人に生徒2〜3人を同時に見るスタイルの塾もあります。その場合「実際に子どもと先生がどのくらい1対1で関われるのか」を確認することが大切です。
サポートの手厚さは塾によって大きく差があるので、体験授業で具体的な様子を見て判断すると失敗が少なくなります。
家庭教師と個別指導塾の違いについてもっと知りたい方はこちら
⇒「家庭教師と個別指導塾の違いとは?【徹底比較】|お子さんに向いているのはどっち?」
3. 宿題や課題の量・難易度が調整できるか
塾によっては毎回大量の宿題を出すところもありますが、発達障害の子どもには大きな負担になりかねません。「やっていない=怠けている」と受け取られると、子どもは自信をなくしてしまいます。
大切なのは「宿題の量やレベルを調整してくれるかどうか」です。
例えば、同じ範囲でも問題数を減らしたり、基本問題に絞ったりといった柔軟な対応ができる塾であれば、無理なく続けられます。
保護者としては「この子にとって無理のない宿題の出し方をしていただけますか?」と確認することが重要です。
宿題をしない発達障害についてもっと知りたい方はこちら
⇒「宿題をしない発達障害のお子さんへの解決策とは?」
4. つまずいたところから戻ってくれるか
発達障害の子どもは、学年相応の内容に取り組む前に、過去の基礎に抜けがあるケースも珍しくありません。そのため「わからない部分まで戻って教えてくれるか」が塾選びの分かれ道となります。
一斉授業型の塾では「今の学年の範囲」だけを進めることが多く、過去の苦手は置き去りになりがちです。一方で、個別指導であれば小学校の内容までさかのぼるなど、柔軟な指導が可能です。
実際に私たちが指導した生徒に「小4の算数に戻ったことで、中学の数学が理解できるようになった」という例もあります。塾に確認するときは「戻り学習に対応できますか?」という視点を持つと安心です。
5. 保護者との連絡・相談が密に取れるか
最後に見落とされがちなのが、保護者との連携体制です。塾での様子が家庭に共有されなければ、家庭学習のサポートにつなげられません。
発達障害のある子どもの場合、「授業中に集中できた時間がどれくらいあったか」「どんな声かけに反応が良かったか」といった細かな情報がとても重要です。これを定期的に伝えてくれる塾は、子どもの学びを一緒に支えてくれるパートナーになり得ます。
保護者面談や日々のフィードバックがしっかりあるかどうかも、入塾前に必ず確認しましょう。

家庭での関わり方|塾通いを“意味のある時間”に変える工夫
どんなに良い塾を選んでも、通塾の時間だけで成果が出るわけではありません。子どもが塾で学んだことを定着させるには、家庭での関わり方が大きなカギを握ります。
特に発達障害のある子どもは、授業中の集中力や理解度に波があるため、「塾=ただ通うだけ」で終わらせず、家庭でのサポートを組み合わせることが欠かせません。
ここでは、保護者ができる4つの関わり方を紹介します。
1.「今日どうだった?」よりも「何が面白かった?」を聞く
塾から帰宅した時に、多くの親御さんが「今日はどうだった?」と尋ねます。しかし、この質問は「テスト結果は?」「どんな成長があったか?」といった意味に感じる子どもが多く、プレッシャーを与える場合があります。
代わりに「今日は何が面白かった?」「先生の話で印象に残ったことあった?」と聞いてみましょう。学びの中で少しでも楽しさや達成感を見つけられれば、それが塾へのモチベーションになります。
成果よりも体験に目を向ける問いかけは、子どもにとって安心感を与える効果があります。
2. 成果よりも取り組んだ時間や姿勢を褒める
テストの点数や順位だけに注目すると、どうしても「塾に行っても意味がない」と感じやすくなります。大切なのは、結果だけでなく「取り組んだ過程」をしっかり評価することです。
例えば「今日は最後まで席に座って頑張ったね」「宿題に取りかかるのが早かったね」といった声かけは、子どもに自信を持たせます。
発達障害の子どもにとっては、学習の「姿勢」や「机に向かった時間」自体が大きな成長です。家庭でその努力を認めることで、塾での学びがより意味あるものへと変わっていきます。
3. 塾で習ったことを家庭で一緒に学び直す
塾で学んだことは、家庭で一度振り返ることで定着度が大きく変わります。
特に発達障害の子どもは、理解したつもりでも記憶の定着に時間がかかることが多いため、「学び直し」の時間が有効です。
ただし「テスト形式で確認する」のではなく、「今日の授業で出てきた問題を一緒に解いてみよう」「先生がどんな説明をしてくれたの?」といった対話型の復習がおすすめです。
家庭内の安心できる環境で学び直すことで、「塾でわからなかったことを家庭で解決できる」サイクルが生まれます。
4. 無理に詰め込まず、休息と切り替えを優先する
発達障害の子どもにとって、塾に通うこと自体が大きなエネルギーを使う活動です。
帰宅後すぐに「宿題やりなさい」と詰め込むと、かえって反発や疲労感が強まり、塾そのものへのモチベーションが下がってしまいます。
大切なのは「休息と切り替え」の時間を確保することです。
帰宅後はまず好きなことをして気持ちをリフレッシュさせ、その後に勉強へと切り替える方がスムーズに取り組めます。
親が「頑張ったね、少し休もう」と声をかけるだけでも、子どもの心に余裕が生まれます。

まとめ
発達障害の子どもにとって、塾が必ずしも意味のある場所になるとは限りません。しかし「子どもの特性に合うかどうか」「先生や環境の理解があるかどうか」「家庭とどう連携できるか」によって、その価値は大きく変わります。
大切なのは「塾に行かせること」そのものではなく、「子どもに合った学び方をどう確保するか」という視点です。合わない塾に通い続けるのではなく、環境やサポートを見極めて選び、家庭での関わりを組み合わせることで、塾通いは子どもにとって意味のある学びの場へと変わっていきます。
家庭教師のマスターでは、発達障害のお子さん向けの学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
発達障害(ASD・ADHD・LD・グレーゾーン)の子の高校受験対策
-
発達障害の中学生の特徴と支援法
-
発達障害の小学生|その特徴や症状の理解、支援方法や接し方を解説
-
発達障害グレーゾーンの中学生の特徴|判断の仕方やサポート方法について
-
ADHDの子が宿題に取りかかれない理由と対策法について
-
勉強をしない中学生|発達障害のタイプ別に対策法をご紹介!
-
宿題をしない発達障害のお子さんへの解決策とは?
-
ADHDと集中力の関係|過集中・不注意に悩む親のための対処ガイド
-
ワーキングメモリーが低い子の特徴とよくある困りごと
-
発達障害・グレーゾーンの子どもが不登校になる原因とは?
-
発達障害とIQのホントの関係とは?|子どもの可能性を正しく理解しよう
-
ADHDとアスペルガーの違い|困りごとやサポート方法の違いを解説























