何度も注意しても治らないのはなぜ?|発達障害の可能性と家庭でできる対策
公開日:2025年7月24日
更新日:2025年7月24日

何度注意しても同じことを繰り返す子どもの行動に、悩んでいませんか?
それは単なる反抗や怠けではなく、発達障害などの特性が関係している可能性もあります。このコラムでは、原因の背景を丁寧に解説し、家庭でできる具体的な対応策をご紹介します。
やる気や性格の問題じゃない?|「何度注意しても治らない」の本当の理由
「何度言っても、また同じことをしている…」「どうしてできないの?」
子育てをしていると、こんな場面に何度も直面することがあります。
つい「やる気がないのでは?」「ふざけているのでは?」と考えてしまいがちですが、実はその行動の背景には、“意欲や性格”では説明しきれない理由があるかもしれません。
この章では、子どもの「治らない行動」に隠れているかもしれない真の理由について解説します。
1.「やればできる」が通用しない子どももいる
大人から見ると「簡単なこと」「前にも教えたこと」でも、子どもにとっては“毎回初めてのように感じている”ことがあります。
例えば「忘れ物をしない」「時間通りに動く」など、日常的な習慣も、子どもによってはうまく定着しません。
「やればできるはず」と思ってしまうのは、親の側の視点。子ども自身は、“やりたい気持ちはあっても、うまくできない”という葛藤の中にいることが多いのです。このズレを理解せずに叱り続けると、子どもは自信を失い、やる気そのものが削がれてしまうこともあります。
2. 叱っても届かないのは“伝え方”の問題かも
子どもに何度も注意しているのに反応が薄い、行動が変わらない…。そんな時は、伝え方が子どもに合っていない可能性があります。
例えば「ちゃんとして!」「何回言ったらわかるの?」といった言葉は、子どもにとっては曖昧で、どう行動すればいいのかが伝わっていない場合があります。特に発達障害の傾向がある子どもは、抽象的な言葉や大人の意図を読み取るのが苦手なことも多いです。
大切なのは、「何を」「どうすればいいか」を具体的に伝えることです。例えば「ランドセルに国語の教科書を入れてね」など、一つひとつを丁寧に示すことで行動に結びつきやすくなります。
3. 行動の裏に「理解のズレ」があることも
子どもが“できない行動”の背景には、「わかっているつもり」と「実際に理解できている」の間にズレがあるケースが少なくありません。
例えば、「片づけて」と言われて「片づけた」と本人は思っていても、大人から見ると全然できていない。このとき、子どもにとっては“ちゃんとやった”という認識なので、「なんで怒られるの?」という反発や混乱を招くことになります。
こうしたズレを減らすためには、行動のゴールを一緒に確認したり、写真や絵で“片づいた状態”を見せたりといった工夫が有効です。視覚的に共有することで、認識のすれ違いを少なくすることができます。
4. 脳の特性(発達障害)によって“できない”ことがある
何度も注意しても同じことを繰り返す背景には、発達障害の特性が関係していることがあります。これは、本人の努力や親のしつけとは無関係な「脳の発達の仕方」によるものです。
例えば、ADHD(注意欠如・多動症)の特性をもつ子どもは、「注意を向け続ける」「順序立てて行動する」ことが難しく、つい忘れてしまったり、途中で違うことに気を取られてしまったりします。ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、人の意図や暗黙のルールを読み取るのが苦手なことがあります。
こうした特性は、「頑張ればできる」「注意すれば直る」というものではありません。まずは“できないのが前提”だと捉えて関わり方を変えることが、親子のストレスを減らす第一歩です。

発達障害が関係していることも|特徴ごとの傾向を知ろう
「何度注意しても治らない」「同じことを何回言っても伝わらない」そんな行動の背景には、発達障害という“特性”が関係している可能性があります。
発達障害は一人ひとり症状が異なり、見た目にはわかりづらいことも多いため、「まさかうちの子が」と思われる方も少なくありません。
ここでは、代表的な3つの発達障害(ADHD・ASD・LD)と、グレーゾーンのケースについて、具体的な特徴を紹介します。
1. ADHD:止まらない行動、気が散りやすい
ADHD(注意欠如・多動症)の子どもは、じっとしていることが苦手だったり、集中が続きにくかったりする傾向があります。
例えば、授業中に体を動かしたくなってしまう、話しかけられてもすぐに別のことに注意が向いてしまう、順番を待つのが苦手で割り込んでしまう…など、「落ち着きがない」「話を聞いていない」ように見える行動が目立つことがあります。
しかし、これは本人の性格やマナーの問題ではなく、脳の「注意をコントロールする力」が弱いことが関係しています。「何度言ってもできない」という場合、そもそも“注意を保ち続ける力”に困難があるのかもしれません。
2. ASD:指示が伝わらない・空気が読めない
ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、人とのコミュニケーションや社会的なやりとりに難しさを抱えることが多いです。
例えば、あいまいな指示が伝わりにくい、「何でわかってくれないの?」という場面が多い、周りの雰囲気や空気が読めない、冗談や皮肉が通じにくい…などの特徴があります。また、自分なりのこだわりが強く、急な予定変更やルールの変更にパニックを起こすことも多いです。
こうした子どもは、「普通に言えば伝わるはず」と思って接していると、親子のあいだで繰り返し“すれ違い”が起きてしまいます。丁寧に説明する、視覚的に伝えるなど、特性に合った対応が必要になります。
3. LD:繰り返しても定着しない「読み書き・計算」
LD(学習障害)は、知的な遅れはないのに、「特定の学習分野」を極端に苦手とする発達障害です。特に「読む」「書く」「計算する」といった基本的な学習スキルでつまずきやすくなります。
例えば、何度練習しても文字が覚えられない、数字の位を間違える、音読で言葉を飛ばす・つっかえる、漢字が何度書いても身につかない…などの困難があります。
これは「努力が足りない」「勉強していない」わけではなく、脳の情報処理のしかたに偏りがあるため怒ります。画一的な方法ではうまくいかないことが多いため、その子に合った学び方を見つけることがカギになります。
4. グレーゾーンとは?診断の有無に関わらず支援は必要
「発達障害」とはっきり診断されるほどではないものの、日常生活や学習、対人関係で困難が見られる子どもたちもいます。こうしたケースは「グレーゾーン」と呼ばれ、医療的な診断はつかないこともあります。
しかし、困りごとがあることには変わりなく、子ども自身はつまずきを感じていることが多いです。グレーゾーンの子どもに対しても、周囲の理解と支援がなければ、自己肯定感の低下や二次的な問題(不登校・メンタル不調など)に発展することがあります。
大切なのは、「診断があるかどうか」ではなく、「今、困っているかどうか」に目を向けることです。
5. 「うちの子に限って…」と思った時こそ注意が必要
発達障害は外見ではわからず、「普通に会話もできるし、明るい子なのに…」と一見、発達障害の特性を持っているように見えないことも多いため、保護者が気づきにくいことも少なくありません。
そのような場合、「うちの子に限ってそんなはずはない」「もっと厳しくすれば変わるのでは?」と考えてしまうこともあるかもしれません。しかし、“しつけ”や“努力”だけでは改善しない難しさがある場合、親も子どももどんどん苦しくなっていきます。
「もしかして特性があるのかもしれない」と、一度立ち止まって見つめ直すことは、子どもにとっても、親にとっても大きな第一歩になります。早めに気づくことで、適切な支援や関わり方が見つかりやすくなります。
発達障害についてもっと知りたい方はこちら
⇒「発達障害の小学生|その特徴や症状の理解、支援方法や接し方を解説」
⇒「発達障害の中学生の特徴と支援法」
⇒「発達障害グレーゾーンの中学生の特徴|判断の仕方やサポート方法について」

叱る前に知っておきたい!親の気持ちが少しラクになる4つの考え方
「何度言っても聞かない」「もう限界…」と、思わず声を荒げてしまった経験は、どの親にもあるはずです。
けれど、叱っても状況が変わらないどころか、親も子どももますます疲れてしまう…そんな悪循環に陥ることも少なくありません。
実は、子どもの困った行動には、“叱っても響かない理由”がきちんとあることが多いのです。ここでは、親の気持ちが少し軽くなり、子どもとの関わり方を前向きに見直せる4つの視点をご紹介します。
1. 同じミスを繰り返すのは、覚えていない・わかっていないサイン
大人から見れば「前にも言ったよね?」と思うような行動でも、子ども自身は“「覚えていない」「そもそも理解できていなかった」”という場合があります。
これは怠けや反抗ではなく、記憶にとどめる力・理解して整理する力(ワーキングメモリー)に苦手さがあるサインかもしれません。特に発達障害のある子どもは、「その場ではうなずいても実は頭に入っていなかった」というケースもよくあります。
叱る前に、「この子は本当にわかっていたかな?」「どの部分が伝わっていなかったのかな?」と、少し立ち止まって考えてみるだけで、親子のストレスはぐっと軽くなることがあります。
ワーキングメモリーについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「ワーキングメモリーが低い子の特徴とよくある困りごと」
2. 視覚的なサポートが効果的
言葉で何度言っても伝わらないときは、“目に見える形”でサポートしてあげると、子どもが理解しやすくなります。
例えば、1日のやることをホワイトボードに書いたり、イラスト付きのスケジュール表やチェックリストを使ったりする方法です。特に発達障害のある子どもは、「聴覚」よりも「視覚」からの情報のほうが頭に入りやすいことがあります。
また、トラブルが起きやすい場面(例えば朝の支度や帰宅後の片づけ)をあらかじめ“見える化”しておくことで、子ども自身が自分の行動をコントロールしやすくなります。
3. タイミングを見て注意しないと逆効果になることも
子どもに注意するタイミングも、とても大切なポイントです。
例えば、子どもが興奮していたり、気持ちが高ぶっていたりするタイミングで注意しても、言葉はうまく届きません。それどころか、火に油を注ぐような結果になってしまうこともあります。
逆に、落ち着いているとき、気持ちが整理できる状態のときに伝えた方が、子どもも素直に受け止めやすくなります。
また、その場で注意できないときは、後から振り返って一緒に確認する方法(事後フィードバック)も効果的です。叱るのではなく、「あのときどうすればよかったと思う?」と問いかけることで、子ども自身に考えさせるきっかけにもなります。
4. 「ダメ!」ではなく、「こうしてね」の伝え方に変えてみよう
「ダメ!」「やめて!」という否定的な言葉は、つい口から出てしまいがちですが、子どもにとっては“「じゃあどうすればいいのか?」がわからない”こともあります。
そんなときは、「こうしてね」「こっちの方がいいよ」と、望ましい行動を“肯定的な言葉”で伝えることが効果的です。
例えば、「走っちゃダメ!」ではなく、「歩こうね」と伝える。これだけで、叱るよりもスムーズに行動が変わることがよくあります。
親の言葉を少し変えるだけで、子どもとのコミュニケーションが楽になる場面はたくさんあります。毎回ではなくてもいいので、まずは1日1回、伝え方を少しだけ意識してみることから始めてみましょう。
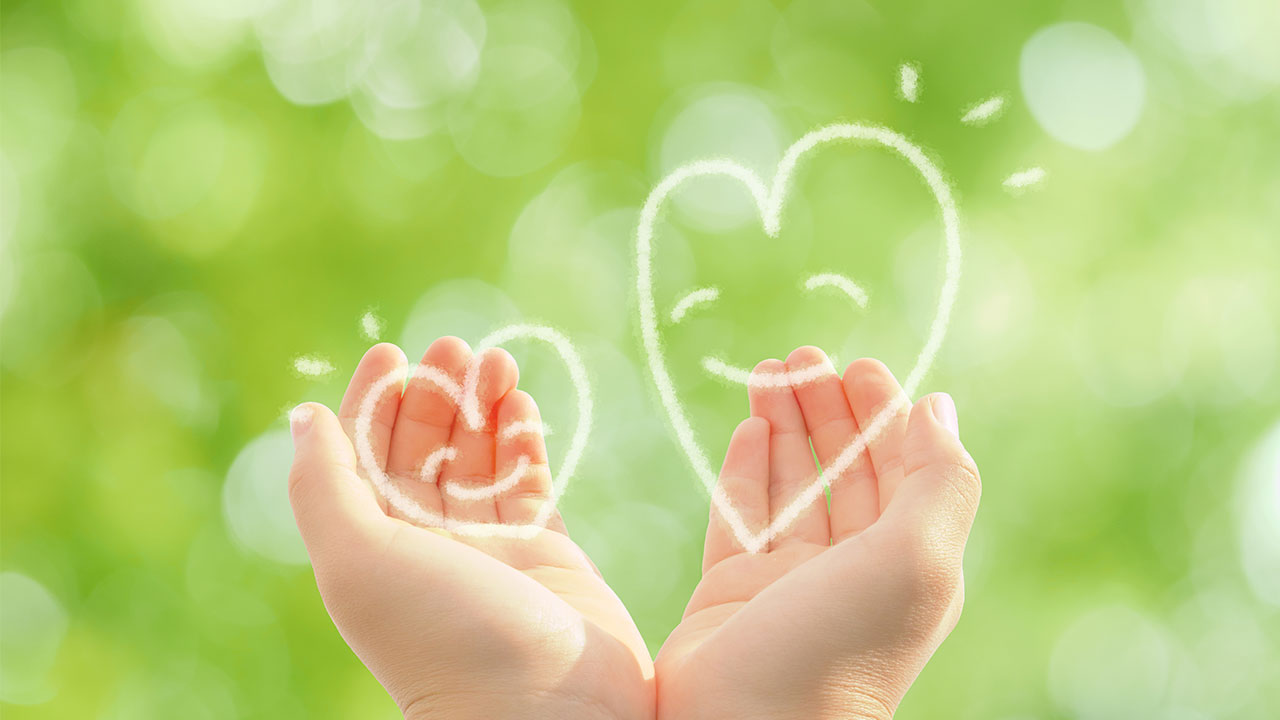
今日から試せる!家庭での具体的なサポート方法4選
子どもの行動が改善しないとき、「どう対応すればいいのか分からない」と悩む場面は少なくありません。
しかし、特別な知識や道具がなくても、ちょっとした工夫で子どもの反応が変わることもあります。
ここでは、今日から家庭で無理なく取り入れられる、発達特性に合った関わり方のコツを4つご紹介します。どれも簡単に始められる方法ばかりなので、ぜひ気軽に試してみてください。
1. スケジュール・ルールの“見える化”で安心感を
子どもにとって、「何をするのか」「どの順番でやるのか」が明確になっていることは、大きな安心感につながります。
予定やルールを口頭だけで伝えてもすぐ忘れてしまったり、混乱してしまったりすることがあります。
そんなときは、視覚的に“見える形”にするのが効果的です。例えば、ホワイトボードに1日の流れを書き出す、イラスト付きのスケジュール表を使う、ルールを紙にして貼るなどの方法があります。
とくに発達障害のある子どもは、言葉より視覚の方が理解しやすい傾向があるため、「いつ・なにを・どうするか」がわかるだけで、落ち着いて行動しやすくなります。
2. 1つずつ区切った声かけで“動きやすさ”が変わる
「片づけて、宿題やって、お風呂入って」など、いくつもの指示を一度に出すと、子どもはどこから手をつければいいのか分からなくなってしまうことがあります。特にADHDの特性がある子は、情報の整理や切り替えが苦手です。
そんなときは、行動を1つずつ区切って伝えることがポイントです。
例えば、「まずは机の上の本をしまってね」「次はプリントをランドセルに入れよう」と、順番に声かけするだけで、子どもの“動きやすさ”がぐんと変わります。
「何度言ってもやらない」のではなく、「やるべきことが分かりにくかっただけ」というケースは意外と多いのです。
3. できた瞬間にほめる!“即時フィードバック”の実践
子どもが何か良い行動をしたときは、できた“その瞬間”に、すぐにほめることが大切です。
「後で言おう」と思っているうちにタイミングを逃してしまうと、子どもは「自分が何をしたのがよかったのか」が分からなくなってしまいます。とくに発達障害の子どもは、過去の行動とフィードバックを結びつけにくいため、“すぐ伝える”ことが効果的です。
「ちゃんと宿題できたね」「静かに待ててえらいね」など、具体的な行動を言葉にしてほめることで、次もその行動をとりやすくなります。それが“できる自分”への自信にもつながっていきます。
4. 家族で対応方針を共有し「ブレない安心感」を作ろう
家庭内で対応の仕方がバラバラだと、子どもは混乱したり、不安定になったりすることがあります。例えば、母親は怒るけど父親は甘い、というような差があると、子どもはどちらに合わせていいのか分からなくなってしまいます。
そうならないために、家族であらかじめ「こういう時はこう対応しよう」という方針を共有しておくことが大切です。
ルールや声かけの仕方を家族全体で統一することで、子どもにとっても“「やることが決まっている」「見通しが持てる」ことが安心感につながります”。
家族で情報を共有することで、親自身も「一人で悩まなくていい」と感じられ、子育てがぐっとラクになるはずです。

困った行動に悩んだ時の相談先と支援サービス
「どう関わればいいか分からない」「これって発達の問題?」
そんな不安を感じたとき、家庭の中だけでなんとかしようとすると、親も子どもも追い詰められてしまいます。
でも、悩みを一人で抱え込む必要はありません。実は、発達の特性や子どもの困りごとについて相談できる場所は、身近なところにもいくつもあるのです。ここでは、すぐに頼れる3つの相談先とその特徴をご紹介します。
1. 学校の相談窓口
まず相談しやすいのは、日常的に子どもを見てくれている学校の先生やスクールカウンセラーです。
担任の先生は、家庭では見えにくい学校での様子を把握しており、「授業中どうしているか」「友達との関わり」など、客観的な情報を提供してくれます。
また、学校に配置されている“スクールカウンセラー(またはスクールソーシャルワーカー)”は、子どもの発達や行動、家庭の困りごとについての相談にも応じてくれます。
「ちょっと気になることがあるんですが…」と気軽に声をかけるだけでもOKです。大きな問題になる前に動くことで、支援につながりやすくなります。
2. 発達支援センターや地域の相談機関
市区町村には、子どもの発達や育ちに関する相談ができる公的な窓口が設けられています。例えば「児童発達支援センター」「子ども家庭支援センター」「発達相談窓口」などがそれにあたります。
ここでは、専門の相談員(臨床心理士、保健師、発達支援コーディネーターなど)が、子どもの行動や困りごとについて話を聞き、必要に応じて支援機関や療育サービスを紹介してくれます。
「診断はついていないけど気になる」「誰に聞けばいいか分からない」といった状態でも、最初の相談窓口として活用しやすい場所です。自治体のホームページなどで、住んでいる地域の相談機関を調べてみましょう。
3. 小児科・児童精神科など医療機関
「専門的な評価を受けたい」「発達障害かどうかを知りたい」と思ったときは、医療機関での相談や診察が必要になります。
まずは地域の小児科に相談してみるとよいでしょう。必要があれば、児童精神科や発達外来への紹介を受けられるケースもあります。発達障害の診断は、小児神経科・児童精神科・小児科の発達外来などで行われることが一般的です。
ただし、予約が混み合っていて数か月待ちになることもあります。そのため、困りごとが深刻になる前に、早めの相談や受診を検討することが大切です。
医療機関では、診断だけでなく、薬によるサポートや心理士によるカウンセリングなどの選択肢もあるため、支援の幅が広がります。

まとめ
子どもが何度注意しても同じことを繰り返すとき、それは「やる気がない」わけでも「親のしつけが足りない」わけでもありません。
背景に発達特性があることを知り、子どもに合った伝え方や関わり方を工夫することで、少しずつ前向きな変化が見えてくるはずです。
家庭だけで抱え込まず、必要に応じて相談先を活用しながら、子どもと一緒に「できた」を増やしていきましょう。
家庭教師のマスターでは、発達障害の疑いがあるお子さんの学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
発達障害の子どもを育てるのに疲れた方へ|大切な考え方と具体的な対策とは
-
発達障害グレーゾーンの中学生の特徴|判断の仕方やサポート方法について
-
発達障害チェックリスト【中学生のお子さん向け】
-
宿題をしない発達障害のお子さんへの解決策とは?
-
勉強をしない中学生|発達障害のタイプ別に対策法をご紹介!
-
ADHDの子が宿題に取りかかれない理由と対策法について
-
【高校生向け】ADHDの診断方法とは?
-
ADHDの子が片付けられない理由とは?|6つの改善策もご紹介!
-
ADHDと集中力の関係|過集中・不注意に悩む親のための対処ガイド
-
ADHDの子どもの好きな人への態度とは?
-
集団行動が苦手な子どもについて|心理的背景や効果的な対応方法とは?
-
自閉症の子の言葉が出ない理由とは?|サポート方法なども詳しく解説
-
発達障害とIQのホントの関係とは?|子どもの可能性を正しく理解しよう
-
ASD(自閉スペクトラム症)の兆候はいつ分かる?|チェックリスト付き
-
落ち着きのない子どもは発達障害?|他の可能性とサポート方法























