高校受験の過去問はいつから始めるべき? 学力別・志望校別にベストな時期を解説!
公開日:2025年5月27日
更新日:2025年5月27日

高校受験の過去問はいつから始めるべき?このコラムでは、学力別・志望校別に最適な開始時期を解説します。また、効果的な過去問演習の方法や注意点まで、志望校合格につながる過去問活用法を中学生・保護者向けにご紹介します。
過去問はいつから始めるべきか?
1. 【偏差値60以上の上位層】夏休み前スタートも視野に入れよう
学力が安定し、模試や定期テストで常に高得点を取っている上位層の生徒は、夏休み前から過去問に取り組むことも視野に入れてよいでしょう。
早めに出題傾向をつかんでおけば、2学期以降の勉強計画にも反映しやすくなり、苦手分野の洗い出しや応用力アップにもつながります。
ただし、この時期に大切なのは“演習の質”。過去問は「解くだけ」で終わらせず、復習と分析をしっかりセットで行うことがポイントです。
2. 【偏差値50前後の中堅層】基礎完成後の9〜10月が理想
偏差値50前後の中堅層の生徒にとっては、9月〜10月頃から過去問に取り組むのがベストタイミングです。
まずは夏までに、主要科目の基礎をしっかり固めることが最優先。
その土台ができてから過去問に進めば、自分の力がどこまで通用するのかが見えてきて、今後の対策も立てやすくなります。
この時期にスタートすれば、本番までに2〜3回は繰り返して取り組む余裕もあります。
3. 【基礎が不安な人】12月に入ってからでも遅くない!
まだ基礎に不安がある場合は、焦って過去問に手を出すよりも、まずは教科書レベルの理解や問題集での演習を優先しましょう。
そのうえで、12月に入ってから本番形式で過去問に取り組めば、まだ十分間に合います。
最初はうまく解けないこともあるかもしれませんが、それでも大丈夫です!
1回目は「今の実力を知るため」と割り切って、次につなげていく姿勢が大切です。
4. 【難関校を目指す人】可能な限り早期から手をつけよう
難関校を目指すなら、できるだけ早いタイミングで過去問に取り組み始めるのがおすすめです。
目安としては、夏休み前〜夏の間に1年分、秋には2〜3年分を解いて、出題傾向や記述問題のクセに慣れていきましょう。
早い段階で自分の課題を見つけて対策しておけば、それだけライバルと差をつけるチャンスが広がります。
また、難問や応用問題に慣れるための“実戦教材”としても、過去問はとても役立ちます。
5. 【私立高校が第一志望の人】公立志望より1〜2ヶ月前倒しで動こう
私立高校を第一志望にしている人は、公立高校よりも試験日が早い(1月〜2月)ため、過去問に取りかかるタイミングも少し早めが基本です。
目安としては、9月〜10月頃に一度解き始めておくと安心でしょう。
私立高校は学校ごとに出題傾向にクセがあることも多いため、なるべく早いうちから傾向をつかんで、ピンポイントで対策していくことがポイントです。
また、同じレベル帯の他校の問題も取り入れれば、実戦力をさらに高めることができます。
6. 【公立高校志望で内申重視の人】内申対策後の11月スタートが現実的
公立高校の中でも、内申点の比重が大きい学校を目指す場合(推薦入試など)は、まず定期テストや提出物、授業態度といった“内申対策”をしっかり優先することが大切です。
そのため、過去問に本格的に取り組み始めるのは、内申点が確定する11月以降が現実的なタイミングといえるでしょう。
学校の成績と並行して受験対策を進めるには、時間の使い方がポイントになります。
まずは1年分ずつ丁寧に取り組み、解きっぱなしにせず、復習をしっかり行うことで、着実に力をつけていけます。
高校受験の内申点についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高校受験の内申点とは?|内申書(調査書)・内申点の基礎知識ガイド」
内申点の計算についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「内申点の計算方法|自分の点数をシミュレーションしてみよう!」
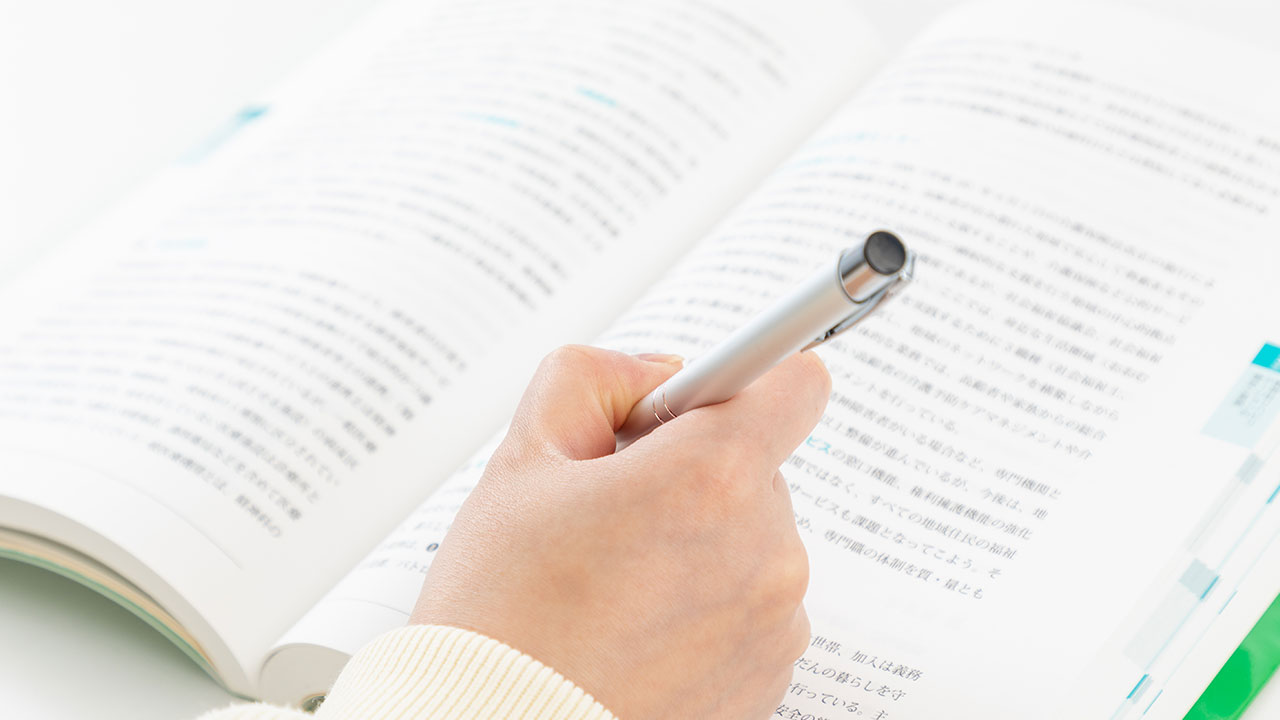
過去問を得点源に変える7つの方法
過去問は、入試直前期に“力試し”として解くだけのものではありません。正しく活用することで、得点力を高める最強の教材になります。
ここでは、過去問を本当の「得点源」に変えるための7つの具体的な方法を詳しく解説します。
1. 本番形式で実力を測る(1年分を1セットとして解く)
過去問に取り組むときは、本番と同じように制限時間を設定し、1年分を通して一気に解くのが基本です。科目をバラバラに解いたり、途中で休憩を挟んだりしてしまうと、自分の“本当の実力”は見えてきません。
本番形式と同様に取り組むことで、単に得点だけでなく、「試験中の立ち回り」も浮き彫りになります。
例えば、「最初の大問で時間をかけすぎて最後まで解けなかった」「マークミスをしてしまった」「後半に集中力が切れてしまった」といった、自分の“弱点”の気付きにつながります。
こうした発見は、普段の問題集演習では得られない、過去問ならではの気付きといえます。
そして忘れてはならないのが、解いた後の振り返り。
「時間配分は適切だったか?」「最後の見直しにどれだけ時間を残せたか?」といった点も必ず確認しておきましょう。
過去問演習を通して試験の時間感覚を身につけることが、本番での成功につながります。
2. 出題傾向を分析し、パターンを把握する
過去問を複数年分解くことで、出題傾向や問題形式に繰り返し現れるパターンが見えてきます。
例えば、「毎年関数が必ず出題される」「作文のテーマは社会的な話題が多い」「資料を読み取る問題が多い」といったものが挙げられるでしょう。
これらをしっかり分析せずに進めてしまうと、せっかくの演習が「ただ解くだけ」で終わってしまい、効果が半減してしまいます。
分析の方法としては、ノートやExcelを使って「出題内容の一覧表」や「よく出る単元のマップ」を作成するのが効果的です。
こうした傾向分析を行うことで、「どこに重点的に取り組むべきか」「どの部分に時間を割くべきか」が明確になり、「効率よく勉強を進めるための“地図”」となります。
特に私立高校のように、出題傾向が特徴的な学校では、この分析が合格へのカギになります。
3. 解答・解説を言語化し、理解を深める
過去問を解いたあと、ただ答え合わせをして終わりになっていませんか?
大切なのは、「なぜその答えになるのか」を自分の言葉で説明できるようにすることです。
これを「言語化」と言い、理解を深めるために非常に有効な方法です。
例えば、「この図形の問題は、補助線を引くことで相似な三角形ができると分かるから…」というように、解き方の過程を誰かに説明するように話してみましょう。
実際に声に出すのが難しい場合は、ノートに手順や理由を書いてみるだけでも十分です。
この「言語化」の過程を通じて、「わかったつもり」から「本当に理解できた」へとステップアップできます。
さらに、同じような問題が出たときに、素早く思い出しやすくなるという効果もあります。
4. 弱点を再演習し、効率的に穴埋めする
過去問を解く目的の一つは、「苦手な単元や間違いやすいパターンを見つけること」です。
間違えた問題をそのままにして次へ進んでしまうと、何度やっても同じミスを繰り返すことになります。ですから、まずは「なぜその問題を間違えたのか」を分析することが大切です。
例えば、
- 公式を覚えていなかったのか
- 問題文の読み取りが不十分だったのか
- ケアレスミスだったのか
など、間違えた原因が分かったら、それに応じて再演習の方法を変えることがポイントです。
間違えた問題は、同じ形式の問題集や参考書で似た問題を探して練習すると効果的です。
また、「間違いノート」を作って定期的に見返すことで、同じミスを防ぐことにつながり、得点アップへとつながっていきます。
ケアレスミスについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「ケアレスミスが多い小中高生|効果的な7つの対策法」
5. 同じ過去問は最低3回は解く
| 1回目 | 出題傾向を知るためや自分の弱点を見つけるための“試運転”として使いましょう。 |
|---|---|
| 2回目 | 間違えた部分がどの程度理解できるようになったかをチェックしましょう。 |
| 3回目 | 「すらすら解けるか」「時間内に得点できるか」の実践的なチェックをしましょう。 |
この3回のサイクルを意識すると、記憶も深まり、得点力が安定してきます。
特に直前期には、過去問の解き直しで「得点を取る感覚」を体にしっかりと染み込ませておくことが非常に重要です。
6. 同レベル他校の過去問にも挑戦する
第一志望の高校の過去問だけでは演習量が足りない場合や、似た出題傾向の学校が複数ある場合は、他校の過去問も積極的に活用しましょう。
特に、同じ偏差値帯・出題形式が似ている高校の問題に取り組むことで、さまざまな出題パターンに対応できる力が身につきます。
また、「初めて見る形式の問題でも考えて答えを出す力」「応用力・臨機応変な対応力」を養うことができ、本番での強さが増します。
私立高校を志望する生徒にとっては、併願校の過去問を解くことで試験慣れができ、緊張を和らげる効果も期待できます。
7. 直近3年分は必ず解く
過去問の中でも、直近3年分は特に優先して取り組みましょう。なぜなら、試験の形式や出題傾向は年ごとに少しずつ変わっており、最新の傾向をつかむことが本番対策に直結するからです。
直近の問題を解くことで、
- 時間配分の難しさ
- 設問の難易度や分量の変化
- 記述問題の有無や傾向の変化
など、本番試験に近い情報を手に入れることができます。
実際、近年の出題傾向に合わせた対策をしておくことで、「見たことがある!」と思えるような問題に出会える可能性も高くなります。最初は難しく感じても、1年分ずつ丁寧に解き、繰り返し演習することで確実に力がついてきます。
可能であれば、直近3年分を2回、3回と解き直すことで、より自信を持って本番に臨めるでしょう。

過去問を解くときの5つの注意点
過去問は受験対策の中でも特に効果的な教材ですが、使い方を間違えると“ただの練習”で終わってしまい、本来の効果を得られません。
ここでは、過去問演習でしっかりと力をつけるために、意識しておきたい5つのポイントを解説します。
1. 基礎力を確認する|“解ける土台”ができてから取り組もう
過去問はあくまで「実戦練習」のための教材です。
したがって、基本的な知識や解法が身についていない段階で取り組んでも、効果は薄く、かえって自信を失ってしまう可能性があります。
特に数学・英語・理科などでは、公式や文法、基本語彙などが曖昧なままだと、過去問の内容に太刀打ちできません。
まずは基礎レベルの問題集で「標準問題が8割以上解ける」状態を目指しましょう。
過去問は、「基礎の確認ができたうえで、実力を本番形式で試す」ために使うべきものです。
基礎が定着しているかどうかのチェックは、過去問演習を始める前の大切な準備です。
2. 時間配分を意識する|制限時間を必ず守るようにしよう
多くの受験生が、本番の試験で陥りやすいミスとして、「一つの問題をじっくり解きすぎて時間が足りなくなる」ことが挙げられます。
ですから、過去問を解く時は「必ず制限時間を守り、時間内に解き終える」ことをルールにしておきましょう。
本番の試験では、限られた時間の中で「どの問題を優先すべきか?」「どこで見切りをつけるべきか?」といった判断力も求められます。この判断力を鍛えるためにも、過去問演習では、正答率だけでなく、「時間の使い方」も振り返ることが大切です。
演習後には、「どの大問に何分かかったか」「見直しにどれくらい時間を確保できたか」を記録しておくと、本番での時間戦略の精度が高まります。
3. 模試・定期テストとのバランスを考える|演習過多にならないようにしよう
過去問演習を進める一方で、模試や学校の定期テストとの両立が重要になります。
特に公立高校を目指す場合は、内申点対策として定期テストの成績も非常に重視されるため、過去問ばかりに時間を取られないように注意しましょう。
また、模試の結果をもとに志望校の判定を見ながら、次の過去問演習の指針にするという流れも大切です。過去問・模試・学校の勉強をバランスよく配置し、「今の時期にやるべきこと」を見極めてスケジューリングすることも受験勉強には欠かせません。
やるべきことが多くなる時期こそ、「何をどれだけやるか」を冷静に見直す習慣を持ちましょう。
調査書(内申書)についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「調査書(内申書)について徹底解説!|高校受験に向けて正しく理解しましょう!」
4. モチベーションを管理する|“できない”時期も想定しておこう
過去問の解き始めの時期は、思うように点が取れず、落ち込んだり焦ったりすることがよくあります。しかし、これは普通のことであり、誰もが通る通過点です。
重要なのは、「できなかった=ダメ」ではなく、「ここが伸びしろ」と前向きに捉える視点です。点数だけを見て一喜一憂するのではなく、「どこができなかったか」「どう直せばいいか」に意識を向けることが、気持ちを前向きにするコツです。
また、「頑張って準備してから解いたのに、成果が見えない…」と感じた時のために、努力の記録(どの過去問を何回解いたか、ミスの傾向など)をつけておくと、振り返りの際に自信の支えになります。
モチベーション維持についてもっと知りたい方はこちら
⇒「勉強のモチベーションを上げる方法|テクニックを使ってやる気UP!」
5. 目的を明確化する|“こなすだけ”の演習にならないようにしよう
過去問を解く際に最も避けたいのは、「ただ数をこなすだけ」の学習です。
大切なのは、その年の過去問に取り組む“目的”を明確に持つことです。
例えば、
- 出題形式に慣れるために解く
- 時間配分の練習をするために解く
- 苦手単元のチェックのために解く
など、演習のたびに意図を持って取り組むことで、その過去問から得られる学習効果が大きく変わります。
また、終わった後の復習にも「目的」があるかどうかで質が変わります。
何のために復習をやるのか?が明確であれば、過去問は単なる練習以上に、“合格への道しるべ”になります。

まとめ
今回は「高校受験の過去問はいつからやるべきか」について解説してきました。
過去問は、受験勉強の仕上げではなく「得点力を鍛える実戦ツール」です。
始める時期や使い方を自分に合った形で見極め、目的を持って取り組むことで、合格にぐっと近づく力になります。
焦らず、丁寧に、そして戦略的に活用することが成功へのカギです。自分に合った方法で、過去問を最大限に活かしていきましょう!
家庭教師のマスターでは、受験生の過去問演習サポートも行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【高校受験コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!























