勉強ができるADHDの子の“見えにくい困りごと”と、家庭でできる支援のヒント
公開日:2025年8月12日
更新日:2025年8月12日
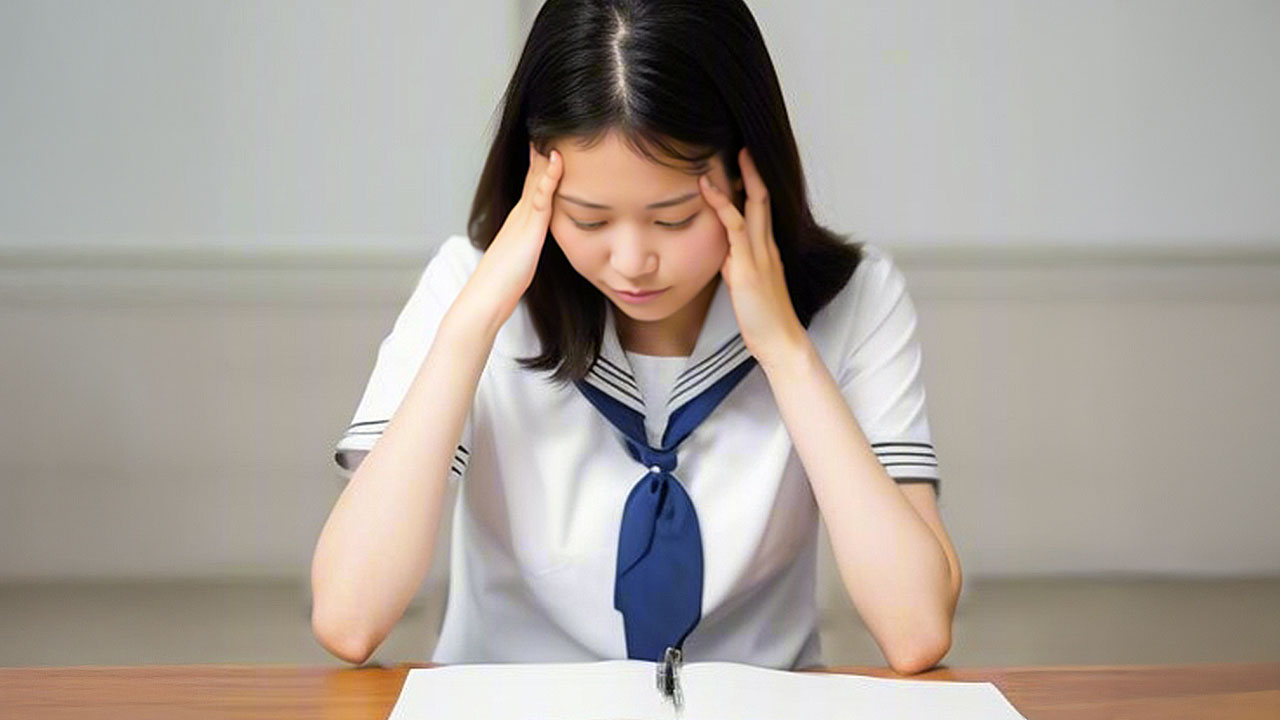
このコラムでは、勉強はできているのに、ADHDの特性が原因でさまざまな困りごとを抱える子どもについて詳しく解説します。
成績が良いからこそ気づかれにくい苦労や、家庭でできる支援のヒント、特性を活かす工夫もあわせてご紹介します。
勉強はできているのに困ってる?|見逃されやすいADHDのサインとは
「テストの点はいいのに、なぜか先生からよく注意される」
「家では全然落ち着きがないのに、勉強はできる」
このように、表面的には“問題なさそう”に見えていても、実は困りごとを抱えているADHDの子どもたちがいます。
ADHDというと、「落ち着きがない」「集中できない」「勉強が苦手」といったイメージを持たれがちですが、実際には知的能力が高かったり、成績は良かったりする子も少なくありません。しかし、だからこそ困っていることに気づかれにくく、「勉強ができるから大丈夫」と見過ごされやすいという問題があります。
ここでは、勉強はできているけれど、実はADHDの特性によって日常生活や学校で苦労している子どもたちの「見えにくいサイン」について見ていきましょう。
1. テストはできているのに、授業中はそわそわしてしまう
テストではしっかり点が取れる。でも授業中はイスをガタガタさせたり、体をゆらしたり、ノートをとる手が止まったりしてしまう…。__こうした“落ち着かない様子”は、ADHDの多動性・衝動性の特性からくるものかもしれません。
理解力がある子ほど、授業の内容をすばやく把握してしまい、そのあとに集中が切れることがあります。すると、手遊びを始めたり、別のことを考えたりと、注意が外へ向いてしまうのです。
この様な場合、「授業をきちんと聞けていない」「態度が悪い」と受け取られがちですが、本人としてはコントロールが難しいことも多いのです。
落ち着きのない子どもについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「落ち着きのない子どもは発達障害?|他の可能性とサポート方法」
2. 宿題や提出物が出せず、「だらしない子」と思われてしまう
学校のテストは良くても、宿題をやっていなかったり、提出物を出し忘れたりすることが続くと、周囲からは「怠けている」「ルーズな子」という印象を持たれやすくなります。
しかし、ADHDの子にはワーキングメモリの弱さや、タスク管理の苦手さを抱えている場合があります。「やらなきゃ」とは思っていても、何から手をつければよいかわからず後回しにしてしまったり、提出するタイミングを忘れてしまったりするのです。
実際には、「やらない」のではなく「忘れてしまっている」ことも多く、本人なりに苦しんでいることを理解する視点が大切です。
宿題をしない発達障害についてもっと知りたい方はこちら
⇒「宿題をしない発達障害のお子さんへの解決策とは?」
3. 注意が散りやすく、話の要点をつかみにくい
授業中の先生の話や、日常会話の中で、途中まで聞いていたのに急に内容が分からなくなる__そんな場面がよく見られる子もいます。
これは、ADHDの「注意のコントロールが難しい」という特性に由来しています。周囲の物音や気になることに意識が向いてしまうと、話の流れを一時的に“取りこぼして”しまうのです。
結果として、「聞いてなかったの?」「何回言えばわかるの?」と注意されやすくなりますが、本人は「聞こうとはしていた」ことが多く、失敗のたびに自己否定を深めてしまうケースもあります。
ADHDと集中力についてもっと知りたい方はこちら
⇒「ADHDと集中力の関係|過集中・不注意に悩む親のための対処ガイド」
4. できているのに自信がない、自己肯定感が低い
テストでは良い点を取っているのに、なぜか「自分はダメだ」と感じている__これも見えにくい困りごとのひとつです。
ADHDの子どもたちは、「忘れ物をした」「叱られた」「またできなかった」という経験を人一倍重ねています。その結果、「成績はいいのに、よく怒られる」「周りと同じように行動できない」という“できている部分と評価されない現実”とのギャップに悩み、自己肯定感を低くしてしまうことがあるのです。
本人の中では、「ちゃんとやろうとしているのに、うまくできない」「なぜ自分はダメなんだろう」と苦しみが積み重なっている可能性があることを忘れずに接することが重要です。
発達障害グレーゾーンの中学生についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「発達障害グレーゾーンの中学生の特徴|判断の仕方やサポート方法について」

支援が届きにくいのはなぜ?|勉強ができるADHDの子が抱える困りごとの見えにくさ
「勉強はできているのに、どうして支援が必要なの?」
そんな風に思われやすいのが、“できる”ADHDの子どもたちが直面している現実です。
彼らの困りごとは、目立ちにくく、誤解されやすいものばかりです。特に、成績が良いことで周囲に安心感を与えてしまい、「問題がない子」とみなされ、必要な支援や配慮が後回しにされるケースも少なくありません。
ここでは、勉強ができるADHDの子に支援が届きにくい背景を4つの視点から見ていきます。
1. 成績が良いと「困っていない」と見なされがち
ADHDに限らず、子どもに対する評価は「目に見える結果」によって判断されがちです。テストの点が良い、成績が上位にいる__そうした外側の成果だけを見ると、周囲の大人は「この子は大丈夫」「困っていない」と思い込みやすくなります。
しかし、成績が良いことと、発達障害に起因する困りごとは別問題です。
本人は日々の授業で集中を保つのに苦労していたり、忘れ物や提出物で叱られて自己肯定感が下がっていたりと、見えない部分でたくさんの負担を抱えているかもしれません。
2. 本人が困っていても、それをうまく言葉にできない
ADHDの子どもたちは、自分の困りごとを「説明する」ことが苦手とすることがあります。
例えば、「なんで宿題出せなかったの?」と聞かれても、うまく言葉にできず黙り込んでしまったり、「わからない」としか答えられなかったりすることがあります。
これは、自分の中で起きていることを整理して伝える“メタ認知”がまだ発達の途中であることや、失敗経験によって「どうせ言っても分かってもらえない」と感じていることも関係しています。
結果的に、「本人が困ってるように見えない」「意見がない」と誤解されてしまい、支援の機会を逃すことにもつながります。
3. 頑張りすぎて疲れているのに、気づかれない
勉強ができるADHDの子の中には、「周囲に迷惑をかけないように」と無意識に自分を律している子もいます。
忘れ物をしないよう何度も確認したり、授業中に動かないように緊張していたり、“普通に振る舞おう”と、ずっと気を張って過ごしている子も少なくありません。
それは、誰にも見えない“がんばり”であるため、非常に疲れやすく、エネルギーの消耗も激しくなります。しかも、「できている」ように見えることで、「もっとできるはず」と求められ、限界に近づいても誰にも気づかれない__そんな悪循環に陥ることもあるので注意が必要です。
4. 他の子の支援が優先されて、後回しにされてしまう
教室には、もっと目立って困っている子や、支援が必要だと明確にわかる子もいるかもしれません。そうした場合、どうしても「優先順位」がつけられてしまい、“見えにくい困りごと”を抱える子は後回しになりがちです。
「できる子なんだから、自分で何とかできるだろう」と思われてしまうこともありますが、実際には、目立たないところで困っている子こそ、丁寧なサポートが必要なケースも多いのです。

「勉強はできてるけど困っている」をどう伝える?|周囲の理解を得る4つのヒント
「勉強はできているが、ADHDの特性によって日常の中ではさまざまな困りごとを抱えている。」そんな子どもを支える保護者の中には、「先生や周りの大人に、この子の困りごとをどう伝えればいいのか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
「できている=困っていない」と受け取られてしまいやすい環境では、“支援が必要なこと”をうまく理解してもらう工夫が必要です。
ここでは、学校や周囲の大人に伝えるときに意識したい4つのポイントをご紹介します。
1. 学校には「勉強以外の困りごと」も伝えてみよう
先生に相談する時、つい「勉強のこと」に話が偏ってしまいがちですが、本当に困っているのは勉強“以外”の部分であることも少なくありません。
例えば、「忘れ物が多い」「提出物の期限が守れない」「友達との関係でトラブルになりやすい」など、生活面や対人面の困りごとも含めて、具体的に伝えることが大切です。
「成績はいいけれど、こんなところで困っています」と説明することで、先生側も「支援が必要な子」として受け止めやすくなります。
2. 「できる時」と「できない時」のギャップを言葉にする
ADHDの子どもは、その日の体調や環境、タイミングによってパフォーマンスが大きく変わることがあり、「昨日はできたのに、今日はできない」という状態があっても不思議ではありません。
この“波のある状態”が、誤解や不信感を生む原因になりやすいため、保護者から学校に「できる時とできない時がある」という特性を、あらかじめ伝えておくことが効果的です。
「集中できているときは力を発揮できるけれど、そうでないときは指示が入らなかったり、ミスが増えたりします」といったように、場面ごとの違いを言葉にして伝えることが大切です。
3. 成績よりも「どれだけ努力しているか」を知ってもらう
テストの点数や通知表の数字だけでは、子どもの“がんばり”は見えてきません。
ADHDの子の中には、日常的にものすごい集中力や工夫を使って“できている状態”を保っている子もいます。
例えば、「提出物を出せるように、家で毎日チェックリストを使って確認している」「授業中に集中するために、ノートに絵を描かないよう手を握って我慢している」など、裏側での努力を先生に伝えることで、評価の視点が変わることがあります。
“できている”のではなく、“頑張っているからできている”__その違いを理解してもらうことが、支援につながる第一歩になります。
4. 「診断名」ではなく、「困っている場面」を説明してみる
「ADHDです」とだけ伝えると、相手によっては偏ったイメージを持たれてしまうことがありますので、診断名だけではなく、「どんな場面で、どう困っているか」を具体的に伝えることが理解につながります。
例えば、「プリントをもらっても、ランドセルに入れる前に忘れてしまうことが多いです」「時間の切り替えが苦手で、休み時間のあとに集中するのに時間がかかります」といったように、具体的な状況を共有することで、“支援の必要性”が伝わりやすくなります。
また、診断名を共有するかどうかは家庭の判断で構いませんが、診断の有無にかかわらず、“困っている現実”に目を向けてもらうことが何より大切です。

勉強で力を発揮しやすくなる!ADHDの子に合った3つの環境とは?
ADHDの子どもは、「集中力がない」「勉強に向いていない」と誤解されがちですが、実は条件が整えば驚くほどの集中力や理解力を発揮することがあります。
つまり、「集中できるかどうか」は本人の能力ではなく、“環境との相性”に左右される部分が大きいのです。
ここでは、ADHDの子が持っている力をより発揮しやすくするために、家庭や学校で意識したい3つの環境づくりのヒントを紹介します。
1. 興味のある内容なら、驚くほど集中できる
ADHDの特性のひとつに、「過集中(ハイパーフォーカス)」があります。これは、自分が興味を持ったことに対して、ものすごい集中力を発揮する状態です。
例えば、好きな本は何時間でも読み続けられる、得意な分野の問題だけはすぐに解ける、というような子も少なくありません。
一方で、興味を持てない内容には全く集中できず、「やる気がない」「取り組む姿勢がない」と誤解されがちです。
そのため、家庭では「この子はどんなことに興味を持つのか」「どんな教科や単元だと前向きになれるか」を観察し、得意や好きの方向から勉強への入り口を作ってあげることが大切です。
ADHDの子どもについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「また逃げた…」ADHDの子どもが嫌なことから逃げる本当の理由とは?
2. ゴールが見えると、迷わず取り組める
ADHDの子どもは、見通しが立ちにくい課題や、終わりの見えない作業に不安や混乱を感じやすい傾向があります。
例えば、「これを全部やっておいて」と言われると、どこまでやればいいのか、どれくらい時間がかかるのかが見えず、始めることすら難しくなってしまうこともあります。逆に、「ここまでやれば終わり」とゴールが明確に設定されていると、安心して集中しやすくなります。
そのため、家庭で勉強するときは「10分間だけやってみよう」「3問解いたら休憩しよう」といったように、小さなゴールを設定してあげることで、取りかかりやすくなることがあります。
3. 小さな成功体験が自信につながる
ADHDの子どもは、日々の中で注意されたり失敗したりする経験が多く、自信を持つチャンスが少なくなりがちです。その中でも、「できた!」「先生にほめられた!」「いつもより集中できた!」といった小さな成功体験が、自己肯定感や学習意欲につながります。
たとえ短時間でも、自分の力でやりきれた感覚があれば、「自分にもできる」と思えるようになり、次のチャレンジへの意欲が高まります。
勉強を教える時は、正解や点数だけで評価するのではなく、取り組み方・工夫・粘り強さなど“プロセス”にも目を向けてほめてあげることが大切です。

ADHDの特性を活かした学び方の工夫とは?
ADHDの子どもは、学習面でも「できるところ」と「つまずきやすいところ」が極端に分かれることがあります。また、集中の波が大きく、やる気のある日とそうでない日の差も大きいため、“やる気がない”と誤解されたり、自分でもやりにくさを感じたりすることが多いのです。
でも実際は、その子に合った方法で環境を整えたり、取り組み方を工夫したりするだけで、驚くほどスムーズに進められることもあります。
ここでは、家庭でも実践できる、ADHDの特性に合わせた学び方の工夫を4つ紹介します。
1. タイマーや視覚で「集中タイム」に区切りをつける
ADHDの子どもは、時間の感覚をつかみにくく、「いつまで勉強すればいいのか分からない」「もう十分頑張ったつもりだけど、まだ終わってない」といった混乱が起きがちです。
そこで効果的なのが、タイマーや目に見える時計などを使って、「この時間だけ集中する」と決める方法です。
例えば、「5分だけやってみよう」と、時間に区切りをつけることで、取りかかりやすくなり、ダラダラ防止にもつながります。
さらに、終わった後には「ここまでできたね!」と声をかけてあげることで、達成感とモチベーションの維持にもなります。
2. 課題を細かく分けると、取りかかりやすくなる
ADHDの子どもは、「ワークをやりなさい」「この単元の復習をしておいて」など、ざっくりとした指示では、何から始めればいいのか分からずに手が止まってしまうことがあります。
ADHDの子は、学習の見通しが立ちにくい特性があるため、“小さく分けてあげる”ことが非常に重要です。
たとえば、「1行目の問題だけ先にやってみよう」「まずは漢字10個だけ書いてみよう」など、とにかく“最初の一歩”が踏み出せるように細分化してあげることで、取り組みやすさがぐっと上がります。
3. プリント形式だけではなく、多様な学習スタイルを活用する
机に向かって、ひたすらプリントを解く__そんな学習スタイルが合わない子もいます。
ADHDの子どもの中には、体を動かすことで集中しやすくなる子や、視覚や音での刺激がある方が理解しやすい子もいます。
例えば、
・単語カードを使って声に出しながら覚える
・ホワイトボードに書き出して学ぶ
・アプリや動画などのデジタル教材を使ってみる
など、様々なスタイルを試しながら「子どもに合う学習法」を見つけることが大切です。
4. 「最初の一問」があるだけで、勉強に取りかかりやすくなる
ADHDの子は、「勉強を始めるまで」に時間がかかることがよくあります。
いわゆる“エンジンがかからない”状態で、目の前に教材があっても手が動かず、結局後回しになってしまいます。
そんな時に効果的なのが、「最初の一問」をあらかじめ決めておく方法です。
「とりあえずこの1問だけやってみよう」と声をかけるだけで、最初のハードルが下がり、スッと取り組めることがあります。
一度手が動き始めれば、そのままの流れで続けられることも多いため、“始めやすさ”を意識した工夫はとても有効です。
ADHDの子についてもっと知りたい方はこちら
⇒「ADHDの子が宿題に取りかかれない理由と対策法について」

「できる子」に見えるからこそ気をつけたい|ADHDの子への接し方のポイント
勉強ができていて成績も良い__こうした表面的な結果だけを見ると、「この子は特に問題ない」と思ってしまうかもしれません。しかし、ADHDの特性を持つ子どもたちの中には、“見えないところでがんばり続けている”子が多くいます。
ここでは、勉強ができる子に見えるからこそ、親として気をつけたい4つの接し方のポイントをご紹介します。
1. テストの点が良くても「全部できるわけじゃない」ことを忘れずに
高得点を取ったときや、目に見える成果を出した時、親としてはつい「すごいね!」「なんでもできるんだね」と声をかけたくなります。しかし、ADHDの子どもは、“できたこと”の裏で沢山の「できないこと」や「苦手なこと」に悩んでいるかもしれません。
「点数は良かったけど、授業中は全然集中できなかった」「宿題は出せてない」「友達とのトラブルがあった」など、成績の影に隠れている困りごとに目を向けることも大切です。
2. 成績よりも「そこまでのがんばり」に目を向けよう
子どもが“できた時”に注目したいのは、結果だけでなく「そのプロセス」や「努力の質」です。
例えば、
・授業中に姿勢を保とうと頑張っていた
・苦手な科目にも前向きに取り組んでいた
・提出物の期限を守ろうと工夫していた
こうした小さな努力を見つけて、具体的にほめてあげることで、「分かってくれている」という安心感と、次のやる気につながります。
3. 「うまくいかない日」も受け入れてあげる
ADHDの子は、調子の波が大きく、昨日できたことが今日はできないということがよくあります。
そんな時に、「何でできないの?」「昨日はできたのに…」と責められると、自信を失くし、ますます力が出せなくなってしまいます。
「今日はうまくいかない日なんだね」「また明日やってみよう」といったように、“うまくいかない日もおおらかに受け入れる”という姿勢が、子どもの心の安定につながります。
4. 親が先に気づいてあげたい「がんばりすぎサイン」
ADHDの子は、「人に迷惑をかけないように」「普通に見られるように」と、必要以上に気を張って頑張っていることがあります。でもそれが長く続くと、ある日突然、疲れが爆発して動けなくなってしまうこともあります。
例えば、
・急に無口になる
・イライラしやすくなり、ちょっとしたことで怒る
・なかなか眠れない、または寝すぎてしまう
・勉強への意欲が極端に落ち自暴自棄になってしまう
こうした変化は、子どもが頑張りすぎているサインかもしれません。
子どもの「頑張っている姿」が見えにくいからこそ、親が先に気づいて、休ませたり、声をかけたりすることが重要になります。
発達障害の子どもについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「発達障害の子どもを育てるのに疲れた方へ|大切な考え方と具体的な対策とは」

まとめ
勉強ができていても、ADHDの特性によって見えにくい困りごとを抱えている子どもは少なくありません。大切なのは、成績だけで判断せず、努力の裏にある苦労や特性に気づき、適切にサポートしていくことです。子どもの「できる」を支えながら、「困っている」にも寄り添える関わりを目指していきましょう。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
ADHDの子が宿題に取りかかれない理由と対策法について
-
【高校生向け】ADHDの診断方法とは?
-
ADHDの子が片付けられない理由とは?|6つの改善策もご紹介!
-
ADHDの子どもの忘れ物が減る!親ができる対策&声かけガイド
-
ADHDと集中力の関係|過集中・不注意に悩む親のための対処ガイド
-
ADHDとアスペルガーの違い|困りごとやサポート方法の違いを解説
-
「また逃げた…」ADHDの子どもが嫌なことから逃げる本当の理由とは?
-
ADHDの子どもの好きな人への態度とは?
-
落ち着きのない子どもは発達障害?|他の可能性とサポート方法
-
発達障害グレーゾーンの中学生の特徴|判断の仕方やサポート方法について
-
発達障害チェックリスト【中学生のお子さん向け】
-
勉強をしない中学生|発達障害のタイプ別に対策法をご紹介!
-
発達障害(ASD・ADHD・LD・グレーゾーン)の子の高校受験対策























