不登校でも中学受験できる?|受験対策・塾以外の学び方・出願時の注意点を解説
公開日:2025年11月20日
更新日:2025年11月20日
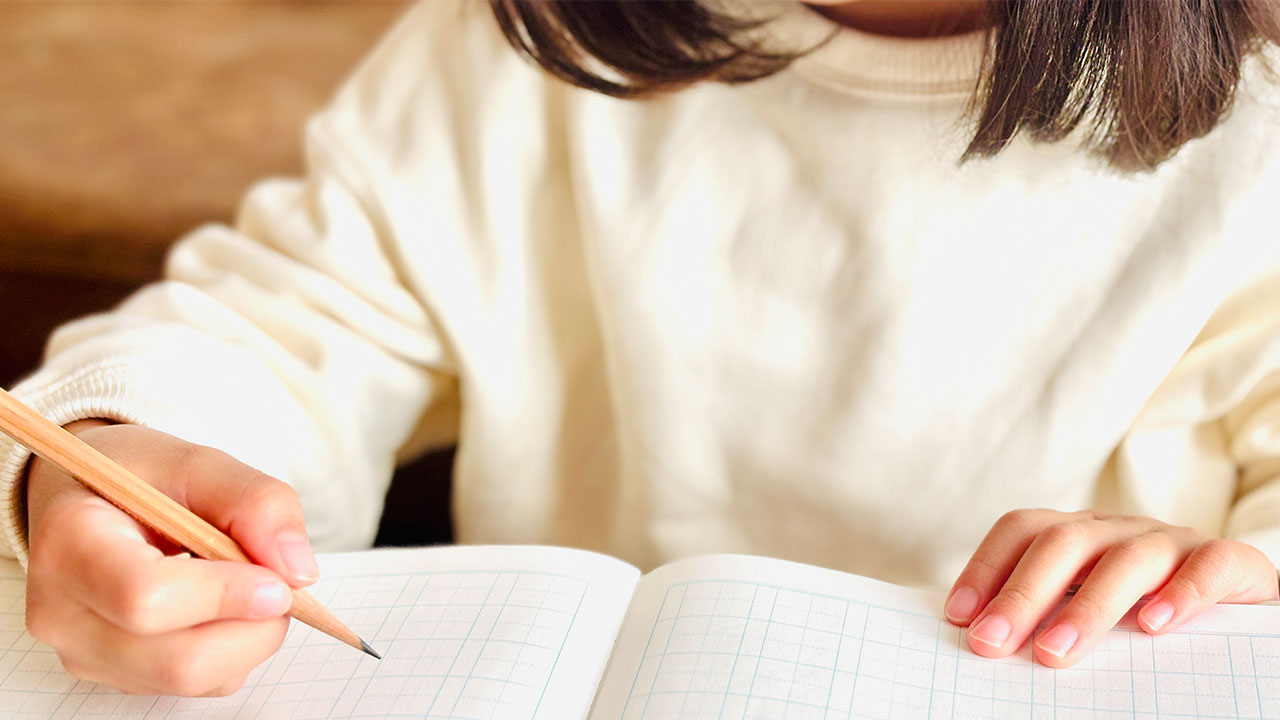
不登校の子どもでも中学受験は可能です。このコラムでは、不登校でも目指せる中学のタイプ、塾に通えない場合の勉強法、自宅学習の工夫、出願書類で気をつけるべき点などを詳しく解説します。
不登校という状況を理解し、子どもに合った中学受験を成功させるためのヒントが満載です。
不登校の小学生でも中学受験は可能?|最初に知っておきたい基本情報
不登校の小学生でも、中学受験を目指すことは十分に可能です。ただし、学校に通えていないという状況があるからこそ、事前に知っておくべきポイントがあります。
このセクションでは、不登校の子が中学受験に挑むにあたり、出席日数の影響や受験資格の有無、受験しやすい学校の特徴など、基本的な情報を丁寧に解説していきます。
1. 出席日数や通知表は中学受験にどこまで影響する?
中学受験では、出席日数や通知表の成績が直接的な合否に影響しない学校が多いのが実情です。
特に私立中学校の場合は、学力試験の得点が最も重視される傾向があるため、在籍小学校での出席状況が合否を左右することは基本的にありません。
ただし、一部の学校では調査書や報告書の提出が求められることもあり、その中に出席日数や学習態度が記載されるケースもあります。そういった場合には、小学校との連携や事前相談が必要になることもあるため、出願予定の学校の募集要項を早めに確認しておくことが重要です。
2. 学校に通っていなくても受験資格はあるの?
結論から言えば、学校に通っていなくても中学受験の資格はあります。
中学受験は「学力試験」を通じて選抜されるものであり、義務教育課程に在籍しているかどうかや、在籍状況にかかわらず受験できる学校がほとんどです。
一方で、国立中学校や一部の公立中高一貫校では、居住地域の制限が設けられている場合があります。また、書類に「学校長の推薦」が必要となるケースもあるため、不登校状態での在籍扱いや担任・学校長との関係については、事前の確認が不可欠です。
3. 不登校の子が受験しやすい中学のタイプとは?
不登校の子どもにとっては、「どんな中学を選ぶか」が受験成功のカギになります。
おすすめなのは、多様な学び方や個性を尊重する校風を持つ私立中学校です。中には、不登校や発達特性のある子どもを積極的に受け入れている学校もあり、面接などでその理解を深めることができます。
また、最近では「探究学習」「体験型授業」「ICT活用」など、一斉授業にとらわれない教育方針を掲げる学校も増えており、そういった学校では、これまでの学校生活にとらわれずに自分のペースで学べる環境が整っています。
4. 私立・国立・公立中高一貫校の違いと選び方
中学受験では、私立・国立・公立中高一貫校の3つのタイプから志望校を選ぶことになります。それぞれに特徴がありますが、不登校の子にとっては受験方法・校風・学びの柔軟さに注目して選ぶことがポイントです。
私立中学
私立中学は、入試日程・科目・学習スタイルの選択肢が多く、個別対応に理解のある学校も多いため、不登校の子にも向いています。
国立中学
国立中学は教育水準が高いものの、競争率が非常に高く、内部進学者が多い点に注意が必要です。
公立中高一貫校
公立中高一貫校は、適性検査型の入試が特徴で、内申点は問われない場合が多いですが、自治体によって制度や募集条件が異なるため慎重な確認が必要です。
公立中高一貫校についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「公立中高一貫校に向いている子の特徴|受験合格への対策もご紹介」
5. 中学受験を目指す時期とスタートタイミングの目安
不登校の子どもが中学受験を目指す場合、早めの情報収集と準備が重要です。
一般的には、小学3年生の終わり〜4年生のはじめにかけて、受験を視野に入れた学習をスタートする家庭が多いですが、不登校期間中の心理的・身体的状態によっては、スタート時期を柔軟に考えることも大切です。
大切なのは「〇年生になったから始めなければいけない」という固定観念にとらわれず、子どもの気持ちが前を向いたタイミングを逃さないことです。無理なスケジュールではなく、小さな目標設定から段階的に進めていく学習プランが理想です。
中学受験を始める時期にについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「中学受験の準備はいつからが正解!?塾に通う理想的なタイミングは?」
6. 不登校からの再出発として「環境を変える目的」で中学受験を選ぶ家庭も
中学受験を考える家庭の中には、「子どもの人間関係や学校環境をリセットしたい」という目的で受験を選ぶケースもあります。
不登校の原因が現在の学校やクラス環境にある場合、中学受験によって新しいスタートを切ることができるという点に、大きな期待を寄せる家庭も少なくありません。
実際、新しい学校では「過去の自分」を知らない友人や先生との出会いが待っており、前向きな気持ちで中学校生活をスタートできるチャンスになります。ただし、学校選びの際は、入学後にサポート体制があるかどうかも重視することが大切です。「環境を変える」ことだけに期待せず、入学後も安心して通える学校かどうかをしっかり見極めましょう。

不登校の子が塾に通えない場合の勉強方法
不登校の子どもにとって、塾に通うことが精神的・体力的に難しい場合も多くあります。とはいえ、中学受験を目指すうえでは、継続的な学習習慣の構築と受験に向けた知識の積み上げが不可欠です。
このセクションでは、塾に通わずに自宅などで学習を進める方法や注意点について、具体的に解説していきます。
1. 自宅学習は何から始めればいい?基礎固めのポイント
塾に通えない場合、まずは基礎学力の土台を整えることが最優先です。
特に算数・国語はすべての受験科目の基本となるため、最初に取り組むべき分野です。いきなり難しい問題に挑むのではなく、学年相当または少し戻ったレベルの基礎問題から始めることで、自信を持って学習を進められます。
また、1日の勉強時間を無理に長く取る必要はありません。「短時間でも毎日継続すること」が、理解の定着と学習習慣の形成につながります。
2. 市販の問題集と無料教材の使い方
市販の問題集は、基礎から応用まで段階的に学べる構成になっているものが多く、塾に通わない子にとって有力な学習ツールです。
特に「○年の総復習」や「中学受験向けの基礎問題集」など、レベルに合わせて選べるものを活用しましょう。
一方で、教育系サイトやYouTubeなどの無料教材も、理解の補助や飽きずに取り組む工夫として有効です。ただし、あれこれ使いすぎると内容が散漫になりがちなので、使う教材は目的を明確にして絞り込むことが大切です。
3. オンライン塾・家庭教師・映像授業の選び方
通塾が難しい場合でも、自宅にいながら指導を受けられる選択肢があります。
代表的なのが、家庭教師やオンライン家庭教師、そしてオンライン塾や映像授業です。不登校の子どもには個別対応型のサービスが向いており、自分のペースや得意・不得意に合わせて柔軟に学べます。
選ぶ際は、「不登校支援に理解があるか」「一方的な講義型ではなく対話があるか」などをチェックしましょう。
実際に体験授業を受けてみて、子どもが安心して取り組めるかどうかを見極めることが大切です。
もっと知りたい方はこちら
⇒【不登校コース】について
4. 通信教育・タブレット教材のメリットと注意点
通信教育やタブレット型教材は、スケジュール管理がしやすく、教材選びの負担が少ないというメリットがあります。特にタブレット教材は、アニメーションや音声を活用した解説が多く、視覚的・聴覚的に理解しやすい設計になっています。
ただし、教材のペースに合わせるだけで「やった気」になってしまうリスクもあります。受け身で進めるのではなく、理解度をチェックするテストや復習の工夫を取り入れていくことで、実力の定着につながります。
5. 子どもの特性に合わせた学習スケジュールの立て方
不登校の子どもは、体調や気持ちの波が大きくなりやすいため、一律のスケジュール管理は難しいこともあります。
そこで大切なのは、「午前中に10分だけ」「この日は好きな教科だけ」といったように、柔軟でストレスの少ない計画を立てることです。
また、予定通りに進まなくても責めずに、「できたことを認める関わり」が学習意欲の維持につながります。スケジュールは「守るもの」ではなく、「調整しながら使う道具」という意識を持つことがポイントです。
効果的な勉強計画の立て方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「効果的な勉強計画の立て方|計画倒れしないためのコツもご紹介!」
6. 保護者が勉強を見てあげる際のポイントと注意点
塾に通わない場合、保護者が学習の伴走者となることが多くなります。ただし、中学受験の内容は高度であり、親だけで十分に対応するのは現実的に困難な面もあります。
受験情報の収集、各科目の出題傾向への理解、志望校ごとの対策など、専門的な知識が求められる場面が多いためです。
そのため、保護者の役割は「直接教える」ことよりも、子どもが安心して学べる環境を整え、外部の力を適切に借りることにシフトするのが理想的です。無理にすべてを担おうとせず、「何に困っているのか」「どうすれば前に進めるか」を一緒に考えるサポーターとして関わることが大切です。
7. 模擬試験の受験で「今の学力」と「志望校との差」を知る
塾に通っていないと、自分の立ち位置や志望校との距離感がわかりにくくなります。
そのため、定期的に模擬試験を受けることが重要です。模試では、偏差値や順位などの客観的なデータが得られ、今後の学習方針を見直す手がかりになります。
現在では、自宅受験に対応した模試も増えており、不登校の子にも受けやすい形が整ってきています。模試は本番慣れにもつながるため、タイミングを見て積極的に活用しましょう。
8. 塾なし受験は難易度が高い|現実をふまえた対策が必要
中学受験は、単なる学力試験ではなく、出題傾向・時間配分・志望校別の対策が求められる高度な競争です。塾に通わない場合、それらを家庭だけで完結させるのは決して簡単なことではありません。
実際、塾なしで受験を乗り切った家庭の多くは、オンライン指導や家庭教師、通信教材を活用しながら、保護者が強力な情報収集とサポートを行っています。
塾に通えないことを不利と感じすぎず、その分の工夫と支援をどれだけ設計できるかが合否を分けるポイントになります。

不登校の子が中学受験を目指す時の心のケアとサポート
不登校の子どもが中学受験を目指す時、最も大切にしたいのは「学力」よりも「心の状態」です。勉強に取り組む意欲や安定した学習リズムは、心が整ってはじめて生まれるものです。
ここでは、不登校の子が安心して中学受験に向き合えるように、保護者としてできる心のケアやサポートの方法を具体的に紹介します。
1. 勉強より大事な「心の安定」が成功の鍵になる理由
中学受験の準備は長期にわたります。不登校の子どもにとっては、まず「安心して過ごせる環境」が整っていなければ、どんなに良い教材や指導法があっても、学びに集中することは難しいでしょう。
特に不登校の子は、自己否定感や不安を抱えやすく、新たな挑戦に踏み出すには大きなエネルギーが必要です。受験勉強のスタートにこだわりすぎず、まずは「心の回復」が優先であることを、家族全体で共有することが大切です。
2. 子どもの「やりたい気持ち」を尊重する関わり方
受験に向けて動き出す時、大切なのは「子ども自身の意思」です。
親が「このままじゃ将来が不安だから」と焦って主導すると、子どもはプレッシャーを感じて拒否的になりやすくなります。
小さなことで構いません。「好きな教科からやってみたい」「この学校の制服がかわいい」など、子どもの中にある“やってみたい気持ち”を拾い上げ、応援する姿勢が、前向きなステップにつながります。
3. プレッシャーを与えない声かけの工夫
「勉強しなさい」「このままで本当に大丈夫?」といった声かけは、不安をあおるだけで逆効果になることがあります。
不登校の子どもは、すでに「勉強できていない自分」を責めていることも多く、さらに追い詰められてしまう可能性があります。
代わりに、「今日はここまでできたね」「ゆっくりでいいよ」「一緒に考えてみようか」など、肯定と共感を軸にした言葉をかけるよう心がけましょう。“やらせる”ではなく“寄り添う”姿勢が、子どもの安心感につながります。
4. 自己肯定感を育てるために家庭でできること
受験を成功させるうえで、学力以上に重要なのが「自己肯定感」です。
「できない自分でも大丈夫」「がんばったら少しずつ進める」と思えることが、前向きな学びを支えます。
家庭では、小さな達成を積み重ねて褒めることが効果的です。例えば「10分机に向かえた」「一問解けた」だけでも、「よくやったね」と言葉にして伝えることで、“やればできる”という感覚が育っていきます。
子どもの自己肯定感についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「子どもの自己肯定感の高め方とは?|7つのNG行動についても解説」
5. 不安や落ち込みが強いときの対応と専門機関の活用
不登校の子どもは、受験という未知の挑戦に対して、強い不安や自己否定感に襲われることもあります。そのような時には無理に励ますのではなく、「つらいよね」「わかるよ」と感情を受け止める関わりが重要です。
また、必要に応じてスクールカウンセラーや心療内科、教育相談機関など、専門機関の力を借りることをためらわないことも大切です。第三者の存在が、子どもや親の心の支えになるケースも少なくありません。
不登校カウンセラーの役割についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「不登校カウンセラーの役割とは?|利用方法やメリットを解説します」
6. 親が「焦らず待つ姿勢」を持つためのヒント
受験を考えると、どうしても「スケジュール通りに進めたい」「早く勉強に取りかかってほしい」と思ってしまうものですが、焦る気持ちが子どもにプレッシャーを与えてしまうことがあります。
親自身も、「今は心の準備期間」「受験はゴールではなく通過点」という視点を持つことで、落ち着いて子どものペースに寄り添うことができます。
親が笑顔でいられることが、子どもにとって一番の安心材料になるのです。

出願や面接で不登校は不利になる?|中学受験の実態と対策
「不登校の経験があることは中学受験で不利になるのでは?」と不安に感じる保護者は少なくありません。
しかし実際には、不登校を理由に合否を決める学校はほとんどありません。むしろ、不登校の子どもに理解のある中学も増えており、伝え方や学校選びの工夫によってチャンスを広げることも可能です。
このセクションでは、出願書類や面接時に気をつけたいポイントを解説します。
1. 不登校経験を願書に書くべきか迷ったときの判断基準
願書の「本人情報」や「学校生活についての記述」で、不登校の事実に触れるべきかどうかは悩みどころです。
原則として、記載が必須でない場合は無理に書く必要はありません。ただし、現在の状況や学習への姿勢をポジティブに伝えられる場合には記載も一つの選択肢です。
例えば、「学校には通えなかったが、自宅で学習に取り組み、受験を通して新しい環境に挑戦しようとしている」など、前向きな意図や努力を伝えられる内容であれば、学校側の印象も変わります。この辺りは学校によって受け止め方が異なるため、志望校の方針や説明会の情報を確認したうえで判断しましょう。
2. 面接で問われることと、子ども・保護者の答え方の工夫
中学受験の面接では、「どうしてこの学校を志望したのか」「小学校生活はどうだったか」といった質問がされることがあります。
不登校であったこと自体を責められることはまずありませんが、聞かれた時には無理に隠すのではなく、簡潔かつ誠実に伝えることが大切です。
子ども自身が答える場合は、事前に「学校が合わなかったこと」「でも新しい環境にチャレンジしたいと思っていること」などを一緒に整理しておくと安心です。保護者も、「過去を責めるのではなく、今の前向きな姿勢を評価していただけたらありがたい」といった肯定的な表現でまとめる工夫が求められます。
3. 「志望動機」に不登校の経験をどう活かす?
不登校の経験があるからこそ、「この学校でなら前向きに頑張れそう」と感じる理由がある場合、それ
立派な志望動機になります。
例えば、「個性を尊重する校風にひかれた」「面倒見の良さや少人数制の教育に安心感を持った」など、その子なりの気づきや願いを言葉にすることがポイントです。
また、不登校の経験から「人の気持ちに寄り添えるようになった」「勉強の意味を自分で考えるようになった」など、内面的な成長を志望動機に織り込むことも良いでしょう。
重要なのは、過去の出来事を通して“どう変わりたいと思っているか”を明確に伝えることです。
4. 学校側が見るポイントと、不登校への理解の傾向
近年、多くの中学校では「不登校はその子の努力不足ではない」という理解が進んでいます。
入試の場面で学校が見ているのは、「現在どう学ぼうとしているか」「どのように学校生活に向き合う姿勢があるか」です。
特に私立中学校では、多様な生徒を受け入れようとする姿勢を示している学校も増えており、個別の事情を踏まえて柔軟に対応してくれるケースもあります。説明会や学校見学などでの雰囲気や質問対応を通して、その学校の“受け入れの空気”を感じ取ることも大切です。
5. 不登校に配慮してくれる中学校を見つける方法
不登校に理解のある学校を見つけるためには、学校説明会や個別相談の活用が非常に有効です。
説明会では「多様な背景の子どもに対応しています」といった表現に注目し、実際に教職員と話す中で、どこまで配慮があるか・どんな支援体制があるかを具体的に聞いてみましょう。
また、先輩保護者の体験談や口コミ、NPOや支援団体の学校紹介などから情報を得ることも有効です。さらに、個別対応を行っている学校であれば、出願前に面談を設定できる場合もあります。「子どもが安心して通えるかどうか」を第一に考えた学校選びが、不登校経験のある子どもにとっては最も重要です。

不登校からの中学受験を成功させた家庭の事例紹介
不登校の状態から中学受験に挑戦するという道のりは、決して平坦ではありません。しかし、さまざまな家庭が子どもに寄り添いながら、自分たちのペースで前に進んできた成功事例があります。
このセクションでは、保護者から伺ったリアルな声をもとに、不登校から受験に至った5つのケースをご紹介します。
1. 学校に行けなくなってから受験を決意したケース
小学校高学年になって突然登校を渋るようになったAさん。人間関係がうまくいかず、半年以上学校に通えない状態が続いていました。
そんな中、「今の学校に戻るより、新しい場所でスタートしたい」と子ども自身が話したのをきっかけに、家庭での中学受験準備を始める決意を固めました。
勉強のブランクはありましたが、基礎からゆっくり積み上げ、1年弱の準備期間で志望校に合格。親御さんは「受験が目的ではなく、“新しい環境へのパスポート”だったことが良かった」と話していました。
2. 通塾せずに家庭学習+オンライン指導で合格したケース
Bさんは、不登校による生活リズムの不安定さと外出への抵抗から、塾には一切通わずに家庭学習を選択しました。とはいえ、親だけでは教えるのが難しいと感じ、不登校支援に強いオンライン家庭教師を利用することにしました。
週2回の短時間指導と、日々のスケジュールを管理するサポートで、少しずつ自主学習の習慣が身についていきました。最終的には、受験直前期でも落ち着いて過ごすことができ、第一志望に合格。本人も「塾より合っていた」と感じていたそうです。
3. 「不登校に理解のある中学」に出会えた成功事例
Cさんの家庭では、学校見学に積極的に参加し、いくつかの私立中学と個別相談を重ねました。その中で出会ったのが、「一人ひとりの背景に配慮した入学対応」を明言していた私立中学です。
願書では不登校の経験にも触れ、面接でも正直に現在の状況を伝えたところ、学校側が深く理解を示してくれたそうです。入学後は、担任やカウンセラーのフォローも手厚く、安心して学校生活をスタートできたとのこと。
「この学校に出会えたことが、親子にとってのターニングポイントでした」と語ってくれました。
4. 勉強再開のきっかけは「得意な教科」との出会い
Dさんは不登校の期間中、勉強にまったく手がつかない状態が続いていましたが、たまたま観たテレビ番組をきっかけに、「理科のしくみって面白いかも」とつぶやいたことが始まりでした。
その言葉を聞いた親御さんは、理科の図鑑や実験キットを一緒に楽しむところから再スタート。そこから興味が広がり、少しずつ机に向かう時間が増えていきました。
最終的には4教科の勉強にも取り組めるようになり、自信をつけた状態で受験本番を迎えることができました。
5. 保護者の支えによって、子どもに見られた前向きな変化
Eさんは「中学受験をする」と言い出したものの、体調や気分に波があり、なかなか学習のペースが安定しませんでした。
親御さんは、「無理にやらせるよりも、子どもの気持ちが動くタイミングを大事にしよう」と考え、焦らずに伴走するスタンスを徹底。
「今日は机に向かえただけでえらいね」「やる気が出ない時はゆっくりしよう」と声をかけながら日々を重ねた結果、子ども自身が「やりたい」「がんばりたい」と言うようになったそうです。その後、短期間で集中して学習できるようになり、見事に合格をつかみました。

まとめ
不登校でも、中学受験を通じて新たな一歩を踏み出すことは可能です。
大切なのは、子どもの気持ちとペースを尊重しながら、合った学び方や環境を見つけていくことです。塾に通えなくても、工夫とサポート次第で受験を乗り越える道は開けます。焦らず丁寧に、子どもと一緒に未来を描いていきましょう。
家庭教師のマスターでは、不登校からの中学受験を目指すお子さんの学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にご相談ください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【中学受験コース】について
⇒【不登校コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
小学生が不登校になる主な原因と親がすべきサポート
-
不登校の小学生の家での過ごし方|昼間は何をさせる?
-
不登校になっても勉強に追いつく方法|学校に行かなくても勉強はできる!
-
子どもが不登校になる原因と親の対応方法とは?
-
子どもが学校を休む理由とは?|理由がわからない場合の対処法も解説
-
発達障害・グレーゾーンの子どもが不登校になる原因とは?
-
【令和5年度データ】不登校の割合はどれくらい?|小中高校別の傾向と支援の現状
-
不登校になりやすい家庭の特徴|その注意点や改善策もわかりやすく解説
-
子供が不登校になるのは母親が原因?|育て方の影響やサポート法について
-
不登校は単なる甘え??|不登校と甘えの関連性を考える
























