効率が良い勉強法とは?|小中学生におすすめのやり方と家庭でできる工夫
公開日:2025年10月8日
更新日:2025年10月8日

勉強時間は確保しているのに、なかなか成績が上がらない…そんな小中学生や保護者の方へ。
このコラムでは、非効率な勉強法の原因から、効率を高める具体的な方法、教科別の工夫、家庭でできるサポートまで詳しく解説します。
勉強の質を見直し、少ない時間でも成果につなげるヒントが満載です。
効率が悪くなってしまう8つの原因とは?
勉強時間をしっかり取っているのに、なかなか成果につながらない__そんな悩みを抱えている子どもは少なくありません。
その原因は、努力不足ではなく「やり方」にあるケースがほとんどです。特に小中学生の場合、無意識のうちに「効率の悪い勉強のクセ」が身についてしまっていることも多いです。
ここでは、よくある8つの非効率な勉強パターンを紹介し、それぞれの落とし穴について詳しく解説します。
自分やお子さんの勉強のやり方を見直すヒントとして、ぜひチェックしてみてください。
1. テキストを開いただけで満足してしまう「なんとなく勉強」をやっている
机に向かい、テキストを開いてペンを持つと「勉強した気分」になってしまうことがあります。
しかし、“なんとなく見ているだけ”では、知識は頭に定着しません。
内容を理解しようとせず、ただページを開いて終わるだけの勉強では、時間だけが過ぎてしまい、成果が出にくくなります。
「何を目的でこのページを開いたのか?」「覚えるべきポイントは何か?」と意識しながら取り組むことが大切です。ただ“やったことにする”のではなく、「どこができるようになったか」を自分で確認できる勉強を目指しましょう。
2. 答えを写すだけ・解説を読むだけの「受け身の勉強法」をやっている
答え合わせの際に、間違った問題の解説を読んで「なるほど!」と分かったとしても、自分でやり直して解けるようになっていなければ意味がありません。
受け身の勉強、つまり「読むだけ」「写すだけ」の勉強では、理解が浅く、本番のテストや応用問題には太刀打ちできません。
重要なのは、自分の頭を使って「再現できるかどうか」を確認することです。
特に間違えた問題は、「どう考えればよかったのか」「どこでつまずいたのか」を振り返り、自分の言葉で説明できるようにするのが効果的です。
3. ダラダラと時間だけが過ぎる「集中できない環境」で勉強している
勉強の効率は、「どれだけ長く机に向かっていたか」ではなく、「どれだけ集中して取り組めたか」で決まります。
しかし、テレビの音、スマホの通知、家族の話し声など、集中を妨げる要素が身の回りに多いと、勉強の質は一気に下がってしまいます。
また、メリハリのないスケジュールも集中力を下げる原因になります。だらだらと続けるよりも、「25分集中→5分休憩」のように区切って取り組む方が、ずっと効率的です。
環境を整え、「集中する時間」と「休む時間」を分けて考えるようにしましょう。
4. 授業を受けて終わりにしてしまい、学習内容が身についていない
小中学生の学習時間の大半は「学校の授業」です。ところが、授業をただ“受けっぱなし”にしているだけでは、知識はほとんど定着しません。
「先生の話を聞いてなんとなく分かったつもり」になっても、自分で説明したり問題を解いたりしてアウトプットしないと、本当に理解したとは言えないのです。
授業はあくまで“学びのきっかけ”です。授業で学んだ内容を、その日のうちに軽く復習するだけでも、理解度と記憶の定着は大きく変わります。また、予習で「どこが難しそうか」を先に見ておくと、授業中の集中力もアップします。
5. 自分に合っていない学習法を続けている
友達がやっているからといって、自分に合わない勉強法をまねしてもうまくいかないことがあります。
例えば、「書いて覚えるのが好きな子」もいれば、「読んだり聞いたりする方が理解しやすい子」もいます。
また、夜型の子が無理に朝早くから勉強しようとしても、眠くて頭に入らない…ということもよくあります。
勉強法には相性があるため、「やり方」だけでなく「時間帯」や「取り組み方」も自分に合っているかを見直すことが大切です。
6. スマホ・ゲームなどの誘惑で集中が途切れてしまう
スマホの通知や、ゲームの存在が気になる状態で勉強していては、集中できるはずがありません。
特に思春期の小中学生にとって、スマホ・ゲームの誘惑に打ち勝つのは簡単ではなく、気がつけば何度も手が伸びてしまうことがあります。
集中力を保つためには、勉強中はスマホを手の届かない場所に置く/アプリの通知を切る/ゲームは時間を決めておくといった「物理的な環境づくり」が重要です。
また、「30分だけ集中したら10分休憩でゲームOK」のようなご褒美ルールを作るのも効果的です。
7. 学習目標が曖昧で「何のためにやってるのか」が不明確
ただ「勉強しなきゃ」と思って机に向かっていても、目標がないままだと、やる気も集中力も湧いてきません。
何のために・どこまでやるかが見えていないと、「とりあえずやる」だけの作業になりがちです。
例えば、「今日の英語の宿題を終わらせる」だけではなく、「動詞10個を暗記する」といった具体的な目標を立てるだけでも、勉強の質は一気に上がります。
短期の小さな目標でもいいので、「達成感」を感じられるようにしておくことが、学習効率の向上につながります。
8. 親の過干渉や「やらせようとする姿勢」が子どものやる気を奪っている
「なんでこんなこともできないの?」「早く勉強しなさい!」といった声かけは、子どもにとってプレッシャーや反発心の原因になることがあります。
特に親が先回りして計画を立てすぎたり、細かく管理しすぎると、自分で考えて行動する意欲が育ちにくくなるのです。
やる気を引き出すには、「○○できたね」「自分で始められて偉いね」などの承認の言葉や、小さな成功体験を積ませる関わり方が効果的です。
子どもの勉強は「親が動かすもの」ではなく、「子ども自身が動けるように支えるもの」という意識で接することが、結果的に効率アップにつながります。
親の過干渉についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「親の過干渉が子どもに与える影響とは?」
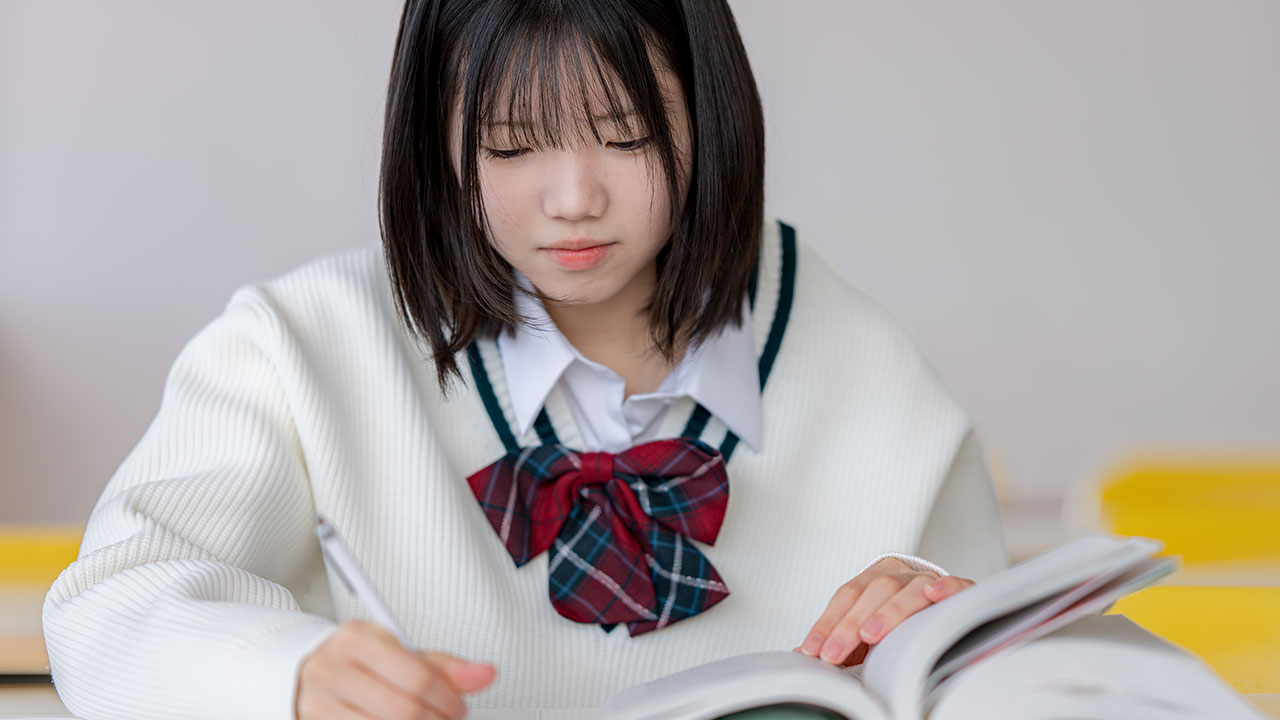
効率の良い勉強法と工夫7選
勉強時間をかけても成果が出にくいと感じている場合、やみくもに頑張るよりも「やり方」を見直すことが効果的です。
効率良く成果を出すには、時間の使い方や集中力の保ち方、記憶の定着方法などを工夫することが大切です。
ここでは、勉強の効率を高めるためにすぐ取り入れられる7つの方法をご紹介します。子どものタイプや家庭の環境に合わせて、できるところから実践してみてください。
1. 時間よりも「集中の質」を大切にする
長時間ダラダラと机に向かうより、短時間でも集中して取り組む方が、勉強の効果はずっと高くなります。
特に小中学生の場合、1時間以上ずっと集中し続けるのは難しく、無理に長時間続けると逆に効率が下がってしまいます。
「30分集中して、5分休憩」など、メリハリのある学習スタイルを意識すると、集中力を維持しやすくなります。勉強中に気が散りがちな子には、「時間を区切って集中する」ことから始めると良いでしょう。
2. 小さな目標設定と、反復で記憶に定着させる
「今日は○○ページまで終わらせる」「この5問を完璧にする」など、具体的で達成可能な目標を立てると、勉強に取り組む意欲が高まります。
漠然とした勉強ではなく、小さなゴールを設けることで、「できた!」という達成感も得られやすくなります。
さらに、覚えたことは繰り返し取り組むことで記憶に定着します。
人の記憶は時間とともに薄れるため、何度も見直す「反復学習」がとても重要です。翌日、1週間後など、タイミングをあけて復習することで、長期記憶につながりやすくなります。
3. 授業の効果を最大化する「予習・復習」のシンプルな習慣を身に付ける
学校の授業を受けっぱなしにするのではなく、予習と復習を組み合わせることで、理解度は大きく変わります。
予習では、「どこがポイントなのか」「どんな内容が出てくるか」をざっくり確認するだけで十分です。これだけで授業中の集中力が上がり、先生の話を「知っている内容」として捉えられるようになります。また、復習は、その日のうちに行うのが理想です。ノートを読み返したり、問題を解いて自分の理解を確認するだけでも、「理解したつもり」を防ぐことができます。
4. 集中が続かない子には「ポモドーロ勉強法」を取り入れる
ポモドーロ勉強法とは、「25分集中+5分休憩」を1セットとして、時間を区切って学習する方法です。
集中しやすい短い時間で区切ることで、飽きずに取り組みやすくなり、特に集中力が続かない子には効果的です。
タイマーを使って時間を管理すると、ゲーム感覚で取り組めるため、勉強へのハードルも下がります。勉強が苦手な子でも「これならできそう」と感じやすく、達成感を積み重ねていくことができます。
勉強に集中する方法についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「勉強に集中する方法とは?|オススメ9つの方法をご紹介!」
5. やる気が出ない子には「やる順番・時間の見直し」をする
やる気が出ない原因は、「やることが多すぎる」「難しそうに見える」「始めるタイミングが悪い」など様々です。
そうした場合は、勉強内容の順番や、取り組む時間帯を見直すだけでも効果があります。
例えば、最初に「簡単にできる問題」を取り入れてハードルを下げたり、「朝の頭がすっきりしている時間」に勉強したりすることで、スムーズにスタートしやすくなります。
勉強の始め方を工夫することで、自然とやる気が出るようになることもよくあります。
6. 時間管理アプリやタイマーを使って集中力を高める
勉強中に気が散ってしまう子には、タイマーや時間管理アプリを使うのもおすすめです。
「今は集中する時間」と意識させるきっかけになり、時間を可視化することで、目の前のことに集中しやすくなります。
特に「あと何分で休憩できる」という感覚があると、子どもは集中して頑張りやすくなります。
「勉強中は通知が来ない」アプリなども活用すれば、スマホによる中断を防ぐこともできます。
7. ノート術・暗記カード・チェックリストを使って記憶を定着させる
ただ教科書を読むだけでは、記憶はなかなか定着しません。
そこで役立つのが、学習内容を整理するノート術や、重要なポイントを繰り返せる暗記カード、学習の進み具合を確認できるチェックリストなどです。
「自分で書いてまとめる」「何度も見返す」「できたところにチェックを入れる」などの工夫を取り入れることで、記憶が深まり、理解度も高まります。
こうしたツールを上手く使えば、勉強の“見える化”にもなり、モチベーションの維持にもつながります。
暗記ノートについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「暗記ノートの作り方|小中高生のための簡単作り方ガイド」

教科別に見る!効率が良い勉強法のコツ
勉強を効率よく進めるためには、教科ごとに適した学び方を知っておくことも大切です。
すべての科目を同じ方法で勉強しようとしても、成果が出づらくなってしまうことがあります。
ここでは、小中学生が取り組みやすく、かつ効果の出やすい教科別の勉強法を紹介します。「なんとなくやっている」から一歩進んで、科目ごとに工夫を取り入れてみましょう。
1. 国語|文章読解と語彙力を同時に伸ばすには?
国語は「文章の意味を読み取る力」と「言葉の知識(語彙力)」の両方が問われる教科です。
読解問題で点が取れない子の多くは、文章の意味がわからないのではなく、「語句の意味や文の構造を正確に理解できていない」ことが原因です。
効率よく国語力を伸ばすには、「読む」だけで終わらせず、読んだ後に内容を要約する/知らない言葉を調べるといったステップを取り入れるのがおすすめです。
また、普段から本や新聞、教科書のコラムなどに触れ、言葉の使い方や表現の幅を増やすことも大切です。「語彙ノート」などを作って、使える言葉を自分のものにしていきましょう。
2. 算数・数学|「わかる」と「解ける」のギャップを埋める方法
授業を聞いて「わかったつもり」になっても、いざ自分で問題を解こうとすると手が止まってしまう…。
そんな経験がある子には、「理解」と「定着」の間にあるギャップを埋める勉強が必要です。
算数・数学は、考え方を身につける教科です。問題文を読んで、どうやって式を立てるのかを自分で説明できるかどうかがポイントになります。
「途中式を丁寧に書く」「解き方の流れを声に出して説明する」など、自分の思考を言葉にするトレーニングが効果的です。
また、同じ単元でもレベルの違う問題を段階的に解くことで、理解が深まり応用力も養われます。
3. 英語|単語・音読・文法をバランスよく取り入れる勉強法
英語は「語彙力」「リスニング」「文法理解」のバランスが重要な教科です。
一つの要素に偏ると、全体の力が伸びにくくなってしまうため、日々の学習では「声に出す」「書く」「聞く」などの複数の方法を取り入れることが効果的です。
例えば、覚えたい単語を声に出しながら書く・短文を音読して構文を身につける・CDや動画で発音やリズムを聞くなど、五感を使った学びが記憶に残りやすくなります。
文法の学習では、「例文を丸ごと覚える」といったインプット方法も有効です。単語だけでなく、使い方ごと覚えることで、実践力が身につきます。
4. 理科・社会|丸暗記ではなく「流れ」と「つながり」で覚える方法
理科や社会は、暗記中心の教科だと思われがちですが、ただ丸暗記するだけではすぐに忘れてしまいます。
重要なのは、「なぜそうなるのか?」「何と関係しているのか?」という流れや因果関係を意識して覚えることです。
例えば、社会の歴史なら「順番」だけでなく「時代背景」や「出来事同士のつながり」を考えることで、記憶が深まります。
理科であれば、実験の手順や現象の理由を理解しながら進めることで、応用問題にも対応できるようになります。
図やイラスト、年表、流れ図などのビジュアルを活用するのも効果的です。見てわかる・つなげて理解することで、学びがより定着しやすくなります。
中学生の勉強方法についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「成績が上がる中学生の勉強方法とは?|ぐんぐん上がる!効果的な勉強法」
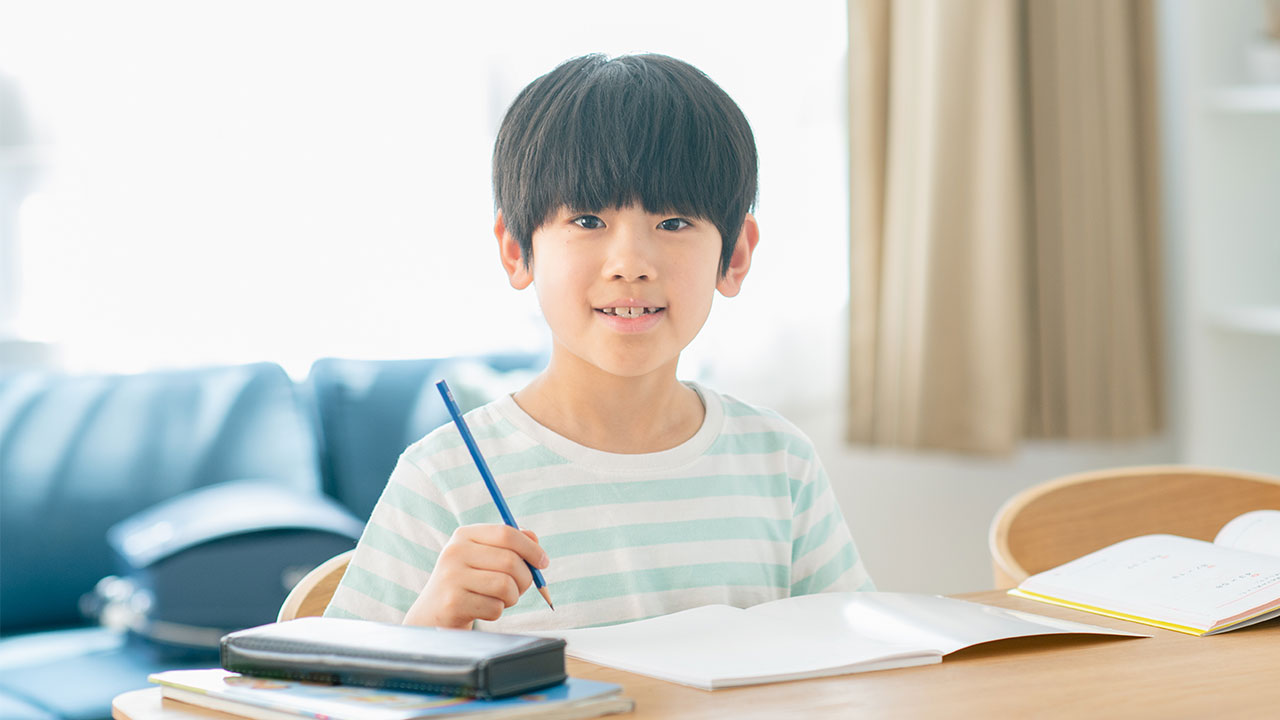
家庭でできる!子どもの勉強効率を高める5つのサポート法
勉強のやり方を見直すだけでなく、家庭での関わり方や環境づくりも、学習効率に大きく影響します。
特に小中学生の場合、まだ自分ひとりで勉強を管理するのが難しいため、保護者のサポートが大きな支えになります。
ここでは、家庭でできる5つの具体的なサポート法を紹介します。押しつけにならず、子どものやる気を引き出す関わり方を一緒に考えてみましょう。
1. 勉強に集中できる時間帯と環境を整える
まず大切なのは、子どもが集中しやすい環境をつくることです。
テレビの音や家族の声、スマホの通知音などが気になる状態では、せっかく勉強を始めても気が散ってしまい、効率は下がってしまいます。
また、子どもによって「集中しやすい時間帯」には違いがあります。朝が得意な子もいれば、夕方の方が頭が働くという子もいます。
本人に合ったタイミングで勉強できるよう、スケジュールを工夫すると良いでしょう。
勉強専用の場所を作ったり、決まった時間に取り組む習慣を整えたりすることで、「今は勉強する時間」と意識が切り替えやすくなります。
集中力が続かない子どもについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「集中力が続かない子どもたちへ|原因・年齢別対策・家庭でできる改善法を解説」
2. 子どもの性格に合った励まし方・関わり方
子どもによって、励まされてやる気が出る言葉や接し方は異なります。
頑張りを褒められると伸びる子もいれば、「見守ってくれている」と感じることで安心して取り組める子もいます。
例えば、「集中して取り組めたね」「昨日よりスムーズにできてたよ」といった行動を認める言葉は、自信を育てる助けになります。
逆に、結果ばかりを評価するとプレッシャーになり、モチベーションが下がることもあります。
子どもの様子をよく観察し、どんな関わりが一番前向きな気持ちにつながるのかを考えてみましょう。
中学生をやる気についてもっと知りたい方はこちら
⇒「中学生をやる気にさせる魔法の言葉とは?|7つの言葉がけ」
3. 口出し・管理しすぎが逆効果になるNGパターン
「早くやりなさい」「なんでできないの?」といった声かけは、子どものやる気を下げてしまう典型的なNGパターンです。
特に、毎日のように細かく口を出したり、スケジュールをすべて親が決めたりすると、子ども自身の「やろう」という気持ちが育ちにくくなります。
管理するのではなく、「自分で考えて動けるように支える」というスタンスが大切です。
何かうまくいかない時も、「次はどうしたらいいと思う?」と子どもに問いかけ、考える機会を与えてみましょう。
勉強の主役は子ども自身であることを忘れず、余白を残した関わり方を意識することが、結果的に効率アップにもつながります。
4. 計画の見直しや目標設定を「親子で一緒に」やると効果的
「自分で計画を立てるのが難しい」「何から手をつけていいかわからない」という子にとって、親と一緒にスケジュールを立てることは大きなサポートになります。
特にポイントとなるのは、「一方的に決めないこと」です。
子ども自身の意見や希望を取り入れながら、計画の優先順位や勉強の順番を一緒に考えていくことで、納得感が生まれ、実行力も高まります。
また、定期的に「計画どおりに進んでるかな?」と振り返る時間を設けることで、必要な見直しがしやすくなります。
5. 家庭では難しいときは、家庭教師やオンライン学習も活用してみる
「どうサポートすればいいかわからない」「家庭だけでは限界を感じる」という場合は、無理をせず外部の力を借りるのもひとつの方法です。
家庭教師やオンライン学習サービスには、子ども一人ひとりの性格や学習状況に合わせた指導をしてくれるところも多くあります。
特に、学校の勉強につまずきを感じている場合や、親子での勉強がうまくいかない時などは、第三者の存在がよい刺激になることもあります。
自宅にいながら利用できるオンラインサービスも増えているため、子どもに合った学び方を無理なく見つけるきっかけとして活用してみてください。

まとめ
効率よく勉強するためには、時間の長さよりも「やり方」と「環境」が大切です。
自分に合った勉強法を見つけ、教科ごとの工夫や家庭でのサポートを取り入れることで、少ない時間でも成果を出すことができます。
大切なのは、無理なく続けられる方法で、着実に「できる」を積み重ねていくことです。
家庭教師のマスターでは、勉強のやり方がわからないお子さんに向けた学習指導を行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せ下さい。
もっと知りたい方はこちら
⇒【小学生コース】について
⇒【中学生コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
成績を上げる方法とは?|勉強しても成績が上がらない子の為の勉強法
-
勉強のやる気を出す方法【中学生編】|具体的な対策法をご紹介
-
効果的なテスト勉強の仕方とは?|具体的なやり方を科目別に徹底解説
-
実力テストに強くなる!効果的な勉強方法を伝授します!【中学生向け】
-
効率よく漢字を覚える方法とは?|実践的な学習方法とコツ
-
現代文の勉強法|読解力と語彙力を鍛えるコツ
-
成績が上がるノートの取り方|上手なノートづくりのポイントとは?
-
偏差値を上げる方法とは?|受験生必見の勉強法を徹底解説!
-
英単語の効果的な覚え方9選【中学生・高校生必見!】
-
効果的な勉強計画の立て方|計画倒れしないためのコツもご紹介!
-
ポイントを押さえたノートまとめ方のコツ|小中学生向け簡単ノート術!
-
中学生の家庭学習がうまくいく方法|習慣化・やり方・苦手対策までまとめて紹介
























