エビングハウスの忘却曲線とは?勉強効率を上げる復習法と暗記術を徹底解説
公開日:2025年10月21日
更新日:2025年10月21日

エビングハウスの忘却曲線をわかりやすく解説します。このコラムでは、効率的な暗記法やテスト勉強・受験対策への応用例まで、成績アップにつながる学習法を詳しくご紹介します。記憶を定着させる学び方を身につけ、日々の勉強に活かしましょう!
エビングハウスの忘却曲線とは?
人間は「覚えたつもり」でも時間が経つにつれて記憶が薄れていきます。その記憶の減少を初めて科学的に研究し、グラフとして示したのがエビングハウスの忘却曲線です。
ここでは、忘却曲線がどのようにして誕生したのか、そして現在も多くの教育や学習に活用されている理由について詳しく解説していきます。
1. エビングハウスとは誰?心理学者のプロフィールと研究背景
忘却曲線を発表したのは、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスです。
彼は19世紀後半に活動しており、人間の記憶や学習に関する研究を科学的に分析した先駆者と言われています。当時は「記憶は目に見えない現象」とされ、科学的に測定することが難しい分野でした。
エビングハウスは、自分自身を被験者として実験を繰り返し、人間が覚えた内容は時間経過とともにどれくらい忘れてしまうのかを数値化することに成功しました。この研究は、心理学が「実験科学」として確立していく大きなきっかけにもなりました。
2. 忘却曲線が示す「記憶が薄れるスピード」|1時間後〜1か月後の具体的データ
エビングハウスが導き出した忘却曲線によると、人間の記憶は学習直後から急激に薄れていくことがわかります。
具体的には、以下のようなデータが示されています。
・学習から20分後には42%を忘れる
・1時間後には56%を忘れる
・1日後には74%を忘れる
・1週間後には77%を忘れる
・1か月後には79%を忘れる
この結果からわかるのは、「人間は覚えたことを最初の1日で大きく忘れる」ということです。つまり、復習を始めるタイミングは早いほど効果的ということが、科学的に裏付けられたといえます。
3. 実験方法とその限界|どのように記憶減少率を測定したのか
エビングハウスは、記憶を測定するために「無意味つづり」と呼ばれるランダムな文字列を使いました。例えば「DAX」や「QEF」のような、意味を持たないアルファベットの並びです。
これは、実験の純粋性を保つための工夫で、意味のある単語を使うと「理解」が記憶に影響を与えてしまうためです。
実験では、これらの無意味なつづりを一定数覚えたあと、時間を置いて再度思い出せるかを確認しました。その結果を数値化し、記憶がどれくらい失われていくかを測定しました。
ただし、この実験には限界もあります。実際の学習では、意味のある言葉や知識を覚えることが多いため、現実の記憶減少はグラフ通りではない場合もあります。
それでも、記憶が「最初に急激に失われる」という傾向自体は、現代の脳科学でも支持されています。
4. 忘却曲線が教育現場・ビジネスで広く使われるようになった理由
忘却曲線は、教育だけでなくビジネスや自己啓発の分野でも広く活用されています。その理由は、復習や情報管理のタイミングを決める上で非常にわかりやすい指標だからです。
例えば、学校教育では「小テスト」や「宿題」のタイミングを忘却曲線に基づいて設定することで、効率的な学習サイクルを作ることができます。
ビジネスでは、新入社員研修や資格試験対策で「1日後・3日後・1週間後」に確認テストを行うと、記憶の定着を高めることができます。
つまり忘却曲線は、単なる理論ではなく、実際の学習効率を大幅に向上させるツールとして多方面で活用されているのです。
5. 他の記憶理論(マジカルナンバー7・スパイシング理論)との違い
記憶に関する理論は忘却曲線だけではありません。よく知られているものに、「マジカルナンバー7」と呼ばれる理論があります。
これは、「人間が一度に記憶できる情報量は7±2個まで」という考え方です。例えば、電話番号が7桁前後なのはこの理論が背景にあります。
もう一つは、スパイシング理論です。
これは「一度にまとめて覚えるより、時間を空けて複数回覚えたほうが定着しやすい」という理論で、分散学習とも呼ばれます。
忘却曲線が「時間経過による忘却のスピード」を示すのに対して、スパイシング理論は「復習をどう組み合わせると効率的か」を説明しているといえます。
複数の理論を組み合わせて学習法を考えることで、記憶の定着をさらに高めることができます。特に忘却曲線とスパイシング理論は相性が良く、復習タイミングを決める目安として活用されています。

忘却曲線からわかる記憶のメカニズム
エビングハウスの忘却曲線は「記憶が時間とともに薄れる」という事実を示していますが、その裏側には脳の働きがあります。
記憶はただ消えていくのではなく、脳が必要な情報を取捨選択する過程で生じている現象です。
ここでは、忘却曲線をより深く理解するために、脳科学の観点から記憶の仕組みを解説していきます。
1. 人の記憶はなぜ薄れる?脳科学から見た「忘れる仕組み」
私たち人間が「忘れる」のは、脳が不完全だからではありません。むしろ脳は、生きるために不要な情報を積極的に整理しています。
脳には常に膨大な情報が流れ込んでおり、そのすべてを覚えていたらパンクしてしまいます。そこで、必要度が低い情報を「忘却」することで、重要な情報を優先的に残す仕組みを持っているのです。
特に、使われない記憶はシナプス(神経細胞同士の接続)が弱まり、脳内のネットワークから自然に消えていきます。これは、脳の「無駄なデータを整理する掃除機能」のようなものだと考えるとわかりやすいでしょう。
つまり、忘れることは脳にとって欠点ではなく、効率的な情報処理を維持するための機能なのです。
2. 短期記憶と長期記憶の役割と定着プロセス
記憶は大きく分けて短期記憶と長期記憶に分けられます。
短期記憶は、一時的に情報を保存するメモリのような役割を持ち、数秒から数分程度しか持続しません。例えば、電話番号を一時的に覚えて入力する時などがこれにあたります。
一方、長期記憶は何度も思い出したり使ったりすることで脳に定着した情報を指します。
短期記憶から長期記憶へ移行するには、「繰り返し学習」や「深い理解」が不可欠です。これは、脳内のシナプスを強化し、神経回路をより太く安定させるイメージです。
忘却曲線で急激に記憶が失われるのは、短期記憶が使われずに消えていくためです。逆に、適切なタイミングで復習することで短期記憶が長期記憶へと変化し、忘れにくい知識となるのです。
3. 記憶を保持するために重要な「想起」の働き
記憶を維持する上でカギとなるのが「想起」です。想起とは、覚えたことを「思い出す」行為のことを指します。
つまり、ただ眺めるだけの復習では記憶は強化されず、自分の頭で思い出そうとするプロセスがシナプスの結びつきを強めるのです。
例えば、教科書を何度も読み返すよりも、問題を解く・声に出して説明する・暗記カードで答えを隠して思い出すといった方法の方が効果的です。
これは脳に「この情報は重要だ」というサインを送ることになり、忘却曲線のカーブを緩やかにする役割を果たします。
4. 復習が「定着率を劇的に高める」理由を解説
忘却曲線が示すように、人は覚えたことを最初の24時間で大きく忘れてしまいます。しかし、適切なタイミングで復習することで記憶は劇的に強化されます。
復習は「もう一度覚え直す作業」ではなく、記憶のネットワークを再び活性化させる作業なのです。
特に効果的なのが、「間隔をあけた復習」です。学んだ直後ではなく、1日後・3日後・1週間後といった間隔を空けて復習すると、脳はその情報を「生き残るために必要なもの」と認識し、長期記憶に変換します。
これは、短期記憶から長期記憶への橋渡し作業であり、一度覚えたことを忘れにくくする最も確実な方法です。

勉強に活かす!忘却曲線に基づいた復習タイミング
忘却曲線を勉強に活用する上で最も重要なのは、「いつ復習するか」というタイミングです。
どんなに集中して覚えた内容も、復習の時期を誤ると記憶は急速に失われてしまいます。
ここでは、忘却曲線の理論をもとにした効率的な復習スケジュールを紹介します。
1. 最初の復習は24時間以内に行うべき理由
忘却曲線によると、人間は覚えた内容を最初の1日で急激に忘れることがわかっています。学習直後から24時間以内に復習することで、記憶の減少を大幅に抑えることが可能です。
例えば、授業で習ったことをその日の夜に軽く振り返るだけでも、記憶のカーブは大きく変わります。
ここでのポイントは「完璧に覚え直す」必要はないということです。軽く目を通すだけでも記憶が脳内で再活性化し、忘れにくい状態に変わります。
この初回復習を怠ると、次の日には半分以上を忘れてしまうため、「24時間以内に1回目の復習をする」ことを習慣にしましょう。
2. 2回目以降は「間隔を広げる復習」が効果的
2回目以降の復習では、「間隔を広げる」ことがポイントです。
同じ内容を短時間に何度も繰り返すと、一時的には覚えたつもりになっても、数日後にはすぐに忘れてしまいます。これは「詰め込み型学習」によく見られる現象です。
最初は短い間隔で復習し、回数を重ねるごとに少しずつ間隔を広げていくと、脳はその情報を「必要な記憶」として認識します。
この手法は分散学習とも呼ばれ、忘却曲線の研究結果と非常に相性が良い方法です。
3. 長期定着のための黄金スケジュール|1日後・3日後・1週間後・1か月後
具体的な復習タイミングの目安として、次の黄金スケジュールが効果的です。
・1日後:学習内容が急激に薄れる時期なので、軽く見直す
・3日後:忘れかけた頃にもう一度復習して記憶を強化
・1週間後:テスト形式で「思い出す作業」を中心に復習
・1か月後:完全に忘れていないかを確認し、弱点を補強
このように復習を段階的に行うことで、短期記憶が長期記憶に移行し、忘れにくい知識になります。
特に1日後と3日後の復習は記憶定着に大きく影響するため、最優先でスケジュールに組み込みましょう。
4. 定期テスト・受験に合わせた復習スケジュール例
忘却曲線は、テスト勉強や受験勉強でも応用できます。
例えば、定期テストの場合は以下のような流れがおすすめです。
・2〜3週間前:授業で学んだ範囲を全体的に復習し、理解を深める
・1週間前:問題演習を中心に行い、弱点を洗い出す
・前日〜当日:暗記カードやまとめノートで最終確認
受験勉強の場合はさらに長期スパンで計画を立てます。
模試や過去問を「1日後・3日後・1週間後」に解き直すことで、記憶を段階的に強化できます。
重要なのは、テスト前だけでなく日常的に復習を取り入れる習慣を作ることです。
5. 暗記カード・ノートを活用するコツと注意点
効率的な復習には、ツールの使い方も重要です。おすすめは暗記カードとまとめノートです。
暗記カードは、問題を見て答えを思い出す「想起」に特化しています。赤シートやアプリを活用して、隠して答える練習をしましょう。
まとめノートは、単に書き写すだけでなく、要点を整理して自分の言葉で書くことがポイントです。
ただし、ツールに頼りすぎると「作業だけして覚えた気になる」ことがあります。大切なのは、カードやノートを実際のテスト形式で使い、頭を使って思い出す練習を繰り返すことです。
暗記ノートについてもっと知りたい方はこちら
⇒「暗記ノートの作り方|小中高生のための簡単作り方ガイド」

効率的な暗記を助ける勉強法
忘却曲線を活用するには、復習のタイミングだけでなく「勉強法そのもの」も工夫することが大切です。
ただやみくもに覚えようとしても、記憶は定着せずすぐに忘れてしまいます。ここでは、記憶を効率よく強化するための代表的な学習法を紹介します。
1. アクティブリコール|思い出す学習法で記憶を強化
暗記で最も重要なのは、覚えたことを「思い出す」作業(想起)を繰り返すことです。
ただ教科書やテキストを眺めるだけだったり、ノートを何度も読み返すだけでは記憶は強化されません。
脳は「思い出す」過程で神経回路を強化し、忘れにくい記憶へと変化させます。
例えば、単語帳を使う際は答えを隠して自分の頭で答えを引き出す練習をしましょう。
また、問題集を解く、友達や家族に内容を説明するなどもアクティブリコールの一種です。
受動的な学習から能動的な学習に切り替えることで、記憶は驚くほど定着しやすくなります。
2. 分散学習|一度に詰め込まず間隔を空けて覚える
テスト前に一夜漬けで詰め込む勉強法は、一時的には得点につながるかもしれませんが、数日後にはほとんど忘れてしまいます。
これを防ぐために効果的なのが「分散学習」です。
分散学習とは、学習の間隔をあけて複数回繰り返す勉強法です。
例えば、1時間ぶっ通しで勉強するのではなく、25分×3回に分けて間に休憩を挟むと、脳が情報を整理する時間を確保できます。
また、1日にまとめて暗記するのではなく、1日目・3日目・1週間後と時間を広げて復習することで、忘却曲線のカーブを緩やかにできます。
この方法は、短期記憶から長期記憶への移行を促すため、受験勉強や資格試験などにも非常に有効です。
3. インターリービング|複数科目を交互に勉強する効果
「今日は数学だけ」「明日は英語だけ」というように、同じ教科をまとめて勉強するよりも、複数の教科を交互に学ぶ方が記憶定着に効果的な場合があります。これをインターリービングと呼びます。
例えば、30分数学を勉強した後に英語へ切り替え、さらに理科に移るといった方法です。
このやり方は、脳にとって「切り替えの刺激」になり、混乱しやすい内容を整理して記憶に残りやすくする効果があります。
特に似た分野の科目(例えば日本史と世界史など)は交互に学習することで、違いを意識でき、理解も深まります。
注意点としては、短すぎる時間で切り替えると集中力が途切れてしまうため、1教科20〜40分を目安にすると良いでしょう。
4. 睡眠と記憶定着の関係|寝る前の復習が最適な理由
記憶は、勉強している時間だけでなく、睡眠中にも整理・定着されます。
特に、寝る前に学んだ内容は睡眠中に脳が「整理作業」を行うため、翌日には記憶が強化されているケースが多いのです。
そのため、暗記が必要な内容は寝る30分前に軽く復習するのがおすすめです。
また、十分な睡眠時間を確保することも忘れてはいけません。睡眠不足の状態では脳が記憶をうまく処理できず、どんなに勉強しても覚えが悪くなってしまいます。
「夜に復習 → 睡眠 → 翌朝に軽く確認」という流れを習慣化することで、効率的な記憶定着が可能になります。
テスト勉強についてもっと知りたい方はこちら
⇒「テスト勉強の悩み解決! 3時間睡眠とオール、どっちがベスト?」
5. デジタルツールを活用した効率的な暗記法(アプリ・タイマー管理)
現代では、スマホやPCを使ったデジタル学習ツールも記憶の強化に大きな力を発揮します。
・暗記アプリ:間隔を自動調整して出題してくれるアプリを使えば、忘却曲線に合わせた復習が簡単に実践できます。
・タイマー管理:タイマーやスマホなどを使い、25分集中+5分休憩といったリズムで学習すると集中力が続きやすくなります。
・スケジュール管理アプリ:復習タイミングをカレンダーやリマインダーで可視化することで、学習の抜け漏れを防げます。
ただし、デジタルツールに頼りすぎると「設定ばかりに時間を使ってしまう」こともあるため、最初はシンプルに使い始めるのがポイントです。
効率的な暗記の方法についてもっと知りたい方はこちら
⇒「効率的な暗記の方法とは?|苦手な暗記を克服するオススメ8つの方法」

忘却曲線に関するよくある勘違いと注意点
忘却曲線は学習の指針としてとても役立ちますが、正しく理解していないと逆効果になるリスクもあります。
ここでは、忘却曲線に関してよくある誤解や注意すべきポイントを整理し、実践に役立つ正しい視点をお伝えします。
1. 忘却曲線は「全員が同じスピードで忘れる」わけではない
忘却曲線は、人間の記憶の減少を理論的に示したモデルにすぎません。
実際には、記憶が薄れるスピードは人によって異なります。
例えば、理解度が高い内容や興味を持って学んだ内容は忘れにくい傾向がありますが、苦手意識が強い分野や強いストレス下で覚えた情報は、より早く記憶が消えてしまいます。
そのため、忘却曲線のグラフを「絶対的な基準」として捉えず、自分の覚えやすさ・忘れやすさを把握したうえで復習計画を立てることが大切です。
2. 復習タイミングは教科や個人差によって変わる
忘却曲線を勉強に応用する際、「1日後・3日後・1週間後」という黄金スケジュールがよく紹介されますが、このタイミングがすべての人に当てはまるわけではありません。
例えば、数学の公式や理科の単語などの暗記中心の教科は早い段階で繰り返す必要がありますが、国語や社会の記述問題のように理解や思考を伴う教科は、少し間隔を空けて復習しても効果が出やすい傾向があります。
また、暗記が得意な人と苦手な人では、適切な間隔にも差が出ます。
復習の間隔は「理論通り」ではなく、自分の学習スタイルに合わせて微調整していくことが重要です。
3. 丸暗記だけでは「応用力」が身につかない理由
忘却曲線に沿って復習しても、やり方を間違えると「覚えたのに応用できない」という状況に陥ることがあります。
特に注意したいのは、丸暗記に頼りすぎることです。
丸暗記は短期的には得点につながりますが、理解が伴わないままでは時間が経つと忘れやすく、応用問題にも対応できません。
例えば、英単語を覚えるときにスペルだけを覚えても、例文や文脈で使わないとすぐに忘れてしまいます。理解と結びついた学習を意識することで、記憶がより強固になり、長期的な学力につながるのです。
4. 忘却曲線を意識しすぎて勉強が負担になるリスク
「忘れないうちに復習しなければ!」と忘却曲線を強く意識しすぎると、かえってプレッシャーになり、勉強が苦痛になることがあります。
特に、復習スケジュールを細かく決めすぎると「やらなきゃ」という気持ちが先行し、モチベーションが低下してしまうケースも少なくありません。
ですから、忘却曲線はあくまで目安として活用しましょう。
大切なのは「完璧にスケジュール通りにやること」ではなく、継続できるペースで無理なく復習を続けることです。
多少のズレがあっても、コツコツと復習を重ねる方が、長期的には大きな成果につながります。

テスト勉強・受験勉強での活用事例
忘却曲線は理論として理解するだけでなく、実際の勉強スケジュールに活かしてこそ真価を発揮します。
ここでは、定期テストや受験勉強、さらには日々の学習習慣に忘却曲線をどのように取り入れるかを、具体例を交えて解説します。
1. 定期テスト直前の最適な復習プラン
定期テスト前は、ただやみくもに勉強するのではなく、「直前期だからこそ効果的な復習」を意識しましょう。
忘却曲線を踏まえると、テストの3日前から急に勉強を始めるのは効率が悪く、記憶が定着しません。
おすすめの流れは次の通りです。
・2週間前:授業ノートや教科書を軽く読み返し、テスト範囲の全体像を把握する
・1週間前:苦手な単元を中心に復習し、問題演習を多めに行う
・3日前〜前日:暗記カードやまとめノートで最終確認。「思い出す作業」を意識する
・当日朝:新しい内容は手をつけず、軽く確認して記憶を安定させる
このスケジュールで復習すれば、直前期の焦りを減らし、安定した得点につながる学習ができます。
2. 小学生・中学生・高校生別|おすすめ復習ステップ
学年によって、適した復習方法は少しずつ異なります。
ここでは小学生・中学生・高校生それぞれにおすすめの方法を紹介します。
小学生
・復習は短時間×回数多めが基本です。10〜15分程度で良いので毎日継続しましょう。
・音読や親への説明など、声に出して覚える学習が効果的です。
・1日の終わりに「今日の授業を親子で一緒に振り返る時間」を作る。
中学生
・定期テストを見据えて、1日後・3日後・1週間後を目安に復習
・英単語や社会の暗記科目は「想起中心」の学習に切り替える
・部活動がある場合は、隙間時間を使った短時間復習を活用
高校生
・模試や入試を意識して長期スパンで計画を立てる
・複数科目をローテーションする「インターリービング学習」で効率化
・スマホアプリやタイマーで復習スケジュールを管理し、自己管理力を養う
3. 受験生向け|半年〜1年単位で考える長期学習計画
受験勉強では、短期間の集中よりも半年〜1年単位での計画性が大切です。
忘却曲線をもとに、学習内容を「覚える→復習する→定着させる」というサイクルで繰り返しましょう。
例:高校受験を控えた中学3年生の場合
・6〜4か月前:基礎固め。授業内容をその日のうちに復習し、忘れにくい土台を作る
・3〜2か月前:過去問や模試を活用し、弱点を発見→復習を徹底
・1か月前〜直前期:暗記カードやテスト形式で仕上げを行い、記憶を最終強化
重要なのは、「模試を受けっぱなしにしない」ことです。
模試後に1日後・3日後・1週間後の復習サイクルを実践することで、確実な成績アップにつながります。
効果的な勉強計画の立て方についてもっと知りたい方はこちら
⇒「効果的な勉強計画の立て方|計画倒れしないためのコツもご紹介!」
4. 苦手科目克服に効果的な「復習パターン」
苦手科目を克服するには、普通の復習だけでは不十分です。
忘却曲線を利用して、「覚える→忘れる→復習する」を繰り返すことが効果的です。
例:英単語が苦手な場合
・初回学習:20個程度に絞り、短時間で集中して覚える
・1日後復習:暗記カードで思い出す練習を中心に行う
・3日後復習:ランダム出題で本当に覚えているか確認
・1週間後復習:応用問題に取り組み、実践力をつける
苦手科目ほど最初の忘却が早いため、初回復習のタイミングが勝負です。
「覚えた直後からすぐ忘れる」を前提に、計画的に復習を組み込みましょう。
5. 保護者ができるサポートと声かけのポイント
忘却曲線を活用した勉強法は、保護者のサポートによって継続しやすくなります。
子どもが自分で復習スケジュールを立てるのが難しい場合は、次のような工夫が効果的です。
・復習する時間を一緒にスケジュール化する
・「やった?」「まだ?」ではなく、「どこが一番覚えやすかった?」と前向きな声かけをする
・結果よりも努力の過程を認めて褒める
保護者が「勉強を監視する立場」ではなく、「伴走する立場」になることで、子どもが安心して学習を継続できる環境が整います。
6. 実際に成績が上がった生徒の事例紹介
当社が指導した生徒の中には、忘却曲線を意識した復習法で大きく成績を伸ばしたケースがあります。
中学2年生Aさん
英単語が苦手で、テストでは平均点以下が続いていましたが、1日後・3日後・1週間後の復習サイクルを徹底した結果、2か月後には英語の点数が30点アップしました。
高校3年生Bさん
模試を受けっぱなしにしていた頃は伸び悩んでいましたが、模試後にすぐ復習を取り入れることで、偏差値が5ポイント上昇。志望校合格に近づきました。
このように、忘却曲線を活かした復習法は、コツコツ続けることで確実に成果が出る方法なのです。
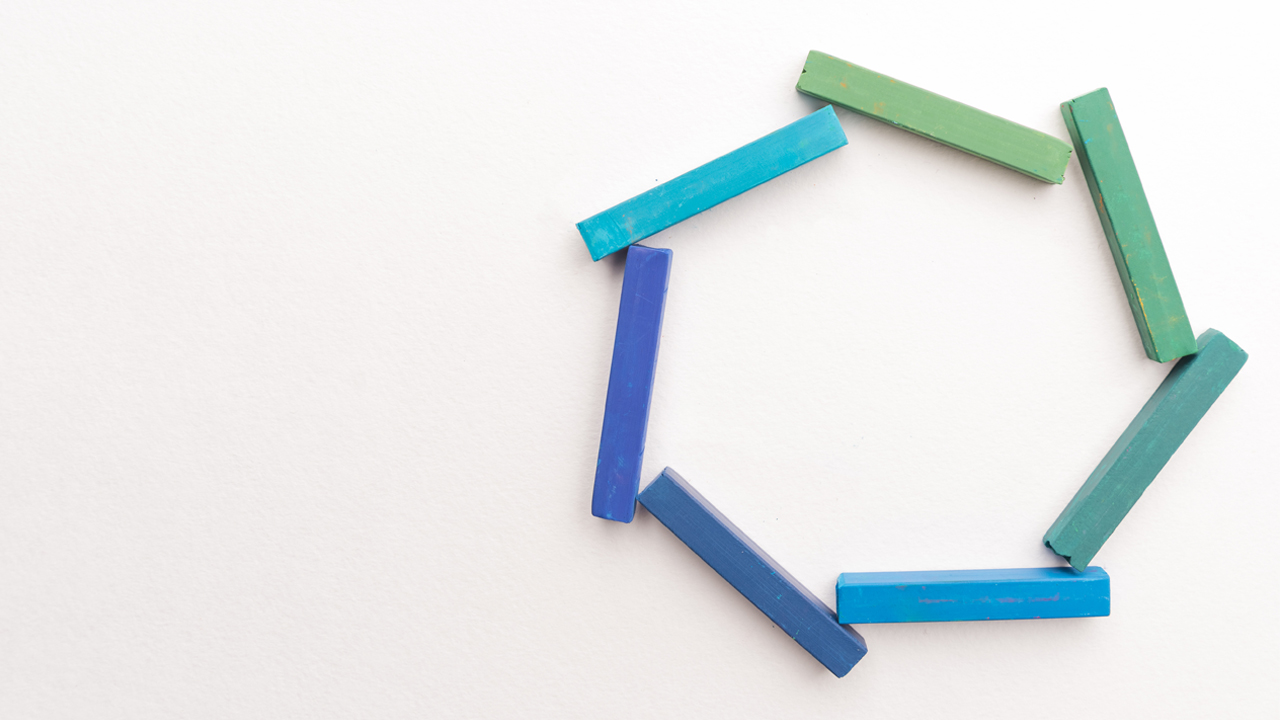
まとめ
エビングハウスの忘却曲線は、記憶が時間とともに薄れる仕組みを教えてくれるだけでなく、効率的な学習サイクルを作る指針にもなります。
正しいタイミングで復習を重ね、理解と想起を意識した学習を続ければ、短期記憶が長期記憶へと変化し、忘れにくい知識が身につきます。
無理のないペースでコツコツ積み重ねることが、勉強効率を最大化する最も確実な方法です。
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
効率よく漢字を覚える方法とは?|実践的な学習方法とコツ
-
中学生の家庭学習がうまくいく方法|習慣化・やり方・苦手対策までまとめて紹介
-
効率的な古文単語の覚え方と勉強法|古文が嫌いな中高生必見!
-
英単語の効果的な覚え方9選【中学生・高校生必見!】
-
「朝の勉強」が生む集中力と成果の秘密とは?|オススメの朝勉強も紹介
-
効率が良い勉強法とは?|小中学生におすすめのやり方と家庭でできる工夫
-
【学生必見!】勉強にオススメの場所とは?|場所や注意点まで解説!
-
成績が上がる中学生の勉強方法とは?|ぐんぐん上がる!効果的な勉強法
-
効果的なテスト勉強の仕方とは?|具体的なやり方を科目別に徹底解説
-
「勉強は楽しい!」と実感できる方法|小中学生向け学習の工夫
-
実力テストに強くなる!効果的な勉強方法を伝授します!【中学生向け】
-
音楽を聴きながらの勉強は良い?悪い?|学習への効果を徹底検証!
-
ポイントを押さえたノートまとめ方のコツ|小中学生向け簡単ノート術!
-
勉強中に眠い時は寝たほうがいい?|仮眠の効果や最適な時間を詳しく解説
-
集中力が続かない子どもたちへ|原因・年齢別対策・家庭でできる改善法を解説























