共通テスト英語リスニング対策|得点戦略から勉強法・テスト本番まで徹底解説
公開日:2025年9月24日
更新日:2025年9月24日

共通テスト英語リスニングで得点を伸ばすには戦略が必要です。
このコラムでは出題傾向や苦手の原因、シャドーイングやディクテーションなどの勉強法に加え、得点アップのための学習スケジュールや本番当日の注意点も紹介。
リスニングを得点源に変えて、合格に一歩近づきましょう。
共通テストのリスニング|出題傾向と概要
共通テストの英語リスニングは、従来のセンター試験と大きく変わった点が多く、十分な理解と対策が必要です。
ここでは試験の基本ルールから出題形式の特徴までを整理し、全体像を押さえていきましょう。
1. 試験時間・問題数・読み上げ回数など基本ルール
リスニングの試験時間は約30分で、問題数は6つの大問から構成されています。
設問は全部で約30問となり、1問あたりの解答スピードも重要です。
音声の読み上げは1回のみのものと2回読み上げのものが混在しており、前半は2回読み上げが中心、後半になると1回読み上げが増えるのが特徴です。
このため「聞き直せない前提」で集中力を保つことが求められます。
2. リーディングと同じ100点!高配点になった背景
共通テストの大きな特徴は、リスニング100点・リーディング100点と配点が同じになった点です。
センター試験時代はリスニングが50点で比重が低く、「おまけ」のように考えていた受験生も少なくありませんでした。しかし、現在はリスニングが得点源となる重要パートであり、大学入試改革で「聞く力」が重視されていることが反映されています。
つまり、リスニングを軽視すると合否に直結する時代になっています。
3. 前半・後半で難易度が変わる出題形式
リスニングは前半と後半で形式や難易度に大きな違いがあります。
前半(第1〜第2問)は短い会話や簡単な説明が中心で、2回読み上げが多いため比較的得点しやすい構成です。
一方、後半(第3〜第6問)は長文の会話や説明文が出題され、読み上げは1回のみで、難易度が上がります。
そのため、前半で確実に得点を重ね、後半では「部分的な理解」でも得点できる戦略を立てることが重要です。
4. 会話・説明文・図表問題の特徴と対策ポイント
共通テストのリスニングでは、会話文・説明文・図表問題がバランスよく出題されます。
会話文は場面設定を素早く理解すること、説明文は要点把握力を高めることがポイントです。
また、図表問題では音声の内容とグラフや表の情報を照合する力が求められます。特に図表問題は情報が多いため、先に図表を眺めて「どの情報に注目すべきか」を予測しておくと正答率が上がります。
問題ごとに求められるスキルは異なるため、日頃の練習で形式に慣れておくことが大切です。

共通テストのリスニングで点を落とす典型的な原因
リスニングは単語力や文法力があっても、思うように点が取れないことがあります。その多くは「聞き取れない」のではなく、特有のつまずきポイントに原因があります。
ここでは受験生がよくハマりやすい4つの落とし穴を解説します。
1. 音声変化(リエゾン・弱形)に慣れていない
英語は単語ごとに発音されるわけではなく、音がつながったり、省略されたりします例えば “want to” が 「ワナ」 のように聞こえるリエゾンや、弱く発音される弱形に慣れていないと、知っている単語でも聞き取れないことがあります。学校の授業や参考書で学んだ発音と、実際のリスニング音声が異なって感じるのはこのためです。普段からネイティブ音声に触れる習慣を持つことが克服の第一歩です。
2. ネイティブスピードに耳が追いつかない
共通テストのリスニングは日常会話に近いスピードで進みます。
単語を一つずつ追って理解しようとすると間に合わず、途中で置いていかれることがあります。これは「耳が遅れている」のではなく、処理方法の問題である場合が多いです。
英語を「かたまり(チャンク)」で理解する練習を重ねると、スピードへの抵抗感が軽減されます。
3. 聞き取れても内容理解が間に合わない
単語や文は聞き取れていても、問題に答える時間になると、「何を言っていたか思い出せない」ことがあります。
これは、音声を記憶に留める負担が大きすぎて、内容理解が追いつかないためです。
ポイントはすべてを覚えようとせず、設問に関係する情報を選択的に聞くことです。
過去問演習を通じて「問題がどこに答えを求めているか」を意識しながら聞く練習をすると改善できます。
4. 試験環境(音質・緊張)で集中を乱される
共通テストのリスニングでは、受験者一人ひとりにICプレーヤーとイヤホンが配布され、個別に音声を聴きます。それでも、普段の自宅や授業で聞く音声や音質が異なる為、聞き取りにくく感じることがあります。また、緊張によって集中力が乱れることも少なくありません。
模試などの際から本番を意識して、「一度聞き逃しても切り替える」訓練をしておくと、環境や緊張に左右されにくくなります。
在学する高校で実物を確認したり、事前に大学入試センターのホームページにて操作方法などを確認しておくのも良いでしょう。

得点を伸ばすためのリスニング戦略
リスニングは暗記や長時間の勉強量だけではなく、戦略的な取り組み方で得点を伸ばせる分野です。共通テストでは平均点が毎年大きく変動するため、「何点を狙うのか」を明確にしながら効率的に学習していくことが重要です。
ここでは実際に役立つ4つの戦略を紹介します。
1. リスニングで「平均点+10点」を狙う意味
共通テストのリスニングは、年度によって平均点が55〜65点前後で推移しています。
つまり、リスニングで70点台を安定して取れれば「他の受験生に一歩リード」できます。
リーディングで高得点を狙うよりも、リスニングで平均点+10点を積み重ねる方が、効率よく全体の得点を伸ばせます。
戦略的に「確実に稼げる分野」として位置づけると効果的です。
2. 時間配分と集中力のピークを意識する
リスニングは約30分の試験で、最後まで集中を切らさずに聞き続ける必要があります。
特に後半の第4〜第6問は難易度が上がるため、ここで集中力が落ちると得点を大きく損なう可能性があります。意識すべきは「集中のピークを後半に持っていく」ことです。前半は余裕を持って聞き、後半で頭をフル回転させるリズムを作る練習をしておくと、本番でも安定した得点につながります。
3. リーディングより得点しやすい設問を見極める
共通テストでは、リスニングは設問がシンプルで、選択肢もリーディングに比べて短い傾向にあります。
そのため「正しい戦略で臨めば、リーディングより得点しやすい」場面も多くあります。
例えば、会話文の「誰が・何を・どうしたか」を押さえる設問や、図表問題の「情報一致」を問う設問は、部分的理解でも正答できるケースがあります。
全てを完璧に聞き取ろうとせず、得点源になる設問を確実に拾う姿勢が重要です。
4. 過去問の平均点・正答率から逆算して目標点を設定
リスニングで実力をつけるには、「感覚で目標を立てる」のではなく、過去問や予備校の模試データから逆算することが大切です。
過去問や予備校の模試では設問ごとの正答率がわかるため、学習段階では「正答率が高い問題は確実に正解できるようにする」「正答率が低い問題は理解の優先度を調整する」といった優先順位をつけることができます。
このように事前に到達ラインを明確にして練習することで、現実的な目標点を設定しやすくなります。
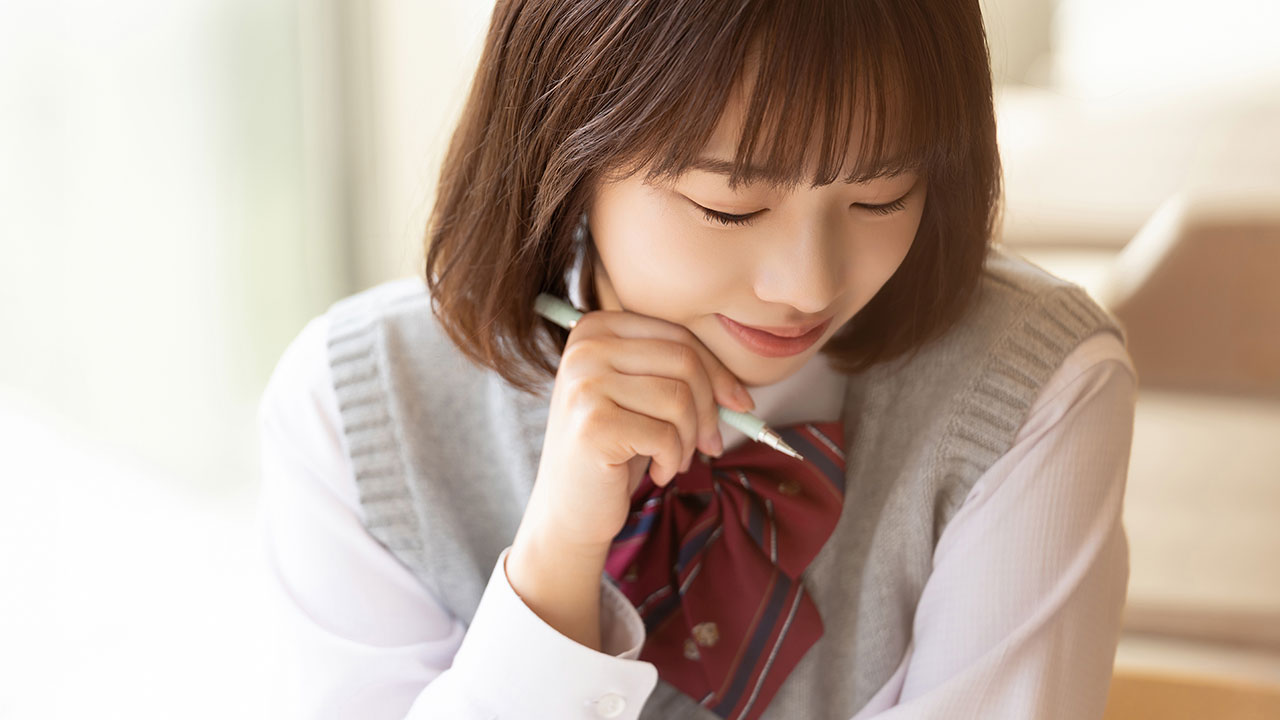
共通テスト英語リスニング力を伸ばす効果的な勉強法
リスニングはただ「英語をたくさん聞けば伸びる」というものではありません。共通テストで安定して高得点を取るには、段階的にスキルを積み上げる学習法が必要です。
ここでは4つの代表的な勉強法を詳しく解説します。それぞれ目的が異なるので、組み合わせて実践することで効果が最大化します。
1. シャドーイングで「音」と「意味」をリンクさせる
シャドーイングは、英語の音声を聞きながら1〜2語遅れて口に出す練習法です。
これにより「聞く」「理解する」「発音する」という複数の処理を同時に行い、英語を日本語に訳す前に内容を直接理解できるようになります。
最初はスクリプトを見ながら行い、イントネーションやリズムを真似ることを重視しましょう。慣れてきたらスクリプトなしで挑戦し、本番のスピードに対応できるよう練習すると効果的です。
毎日5〜10分の積み重ねでも、数週間で「耳が慣れてきた」と実感できるでしょう。
2. ディクテーションで細かい音を聞き取る力を養う
ディクテーションは、音声を一時停止しながら聞こえた通りに書き取る学習法です。
自分の弱点を「可視化」できるのが最大のメリットで、例えば冠詞の「a」や「the」、動詞の語尾の「-ed」、複数形の「-s」など、細かい部分を聞き落としていることに気づけます。
おすすめは「短い音声を繰り返す」ことです。
いきなり長文に挑戦すると挫折しやすいため、最初は30秒程度の教材で十分です。
書き取った後は必ずスクリプトと照合し、なぜ聞き取れなかったのかを分析しましょう。
音声変化が原因であれば、同じ部分を集中してリピートすることで弱点を克服できます。
3. チャンクリーディングで文意をかたまりで理解する
リスニングでは「単語を順番に処理」していると追いつけません。重要なのは、チャンク(意味のかたまり)で理解する力です。
例えば、
・“at the end of the day” → 「一日の終わりに」
・“would you mind if〜” → 「〜してもよろしいですか」
といった表現を、単語単位ではなく「ひとまとまり」で覚えておくと、聞いた瞬間に意味が浮かぶようになります。
普段の勉強では、英文にスラッシュを入れて音読する「スラッシュリーディング」を取り入れると効果的です。これを続けることで、リスニング中に頭の中で自動的に区切りができるようになり、理解スピードが格段に向上します。
4. 過去問・模試で実戦形式に慣れる
どれだけ基礎トレーニングを積んでも、最終的に必要なのは実戦形式での慣れです。
共通テストのリスニングは約30分続くため、集中力の持続や1回読み上げ問題への対応力が求められます。
過去問や模試を取り組む際は「本番に近い環境で」行うことが大切です。スマホやイヤホンを使い、同じ制限時間で解いてみると、本番への耐性がつきます。
解き終わったら答え合わせだけで終わらせず、スクリプトを確認しながら音声をリピートし、聞き逃した部分を重点的に復習しましょう。
こうした復習を徹底することで、得点が安定しやすくなります。

生活に組み込むリスニング習慣
リスニング力は一度に長時間勉強しても伸びにくく、毎日の積み重ねが効果を発揮します。特に通学や就寝前といった「スキマ時間」を上手に活用すれば、自然と耳が英語に慣れていきます。ここでは日常生活に無理なく取り入れられる4つの習慣を紹介します。
1. 通学時間を「耳トレ」の時間に変える
電車やバスでの通学時間は、リスニングの練習に最適なインプットの場です。参考書を開く必要はなく、イヤホンで英語音声を流すだけでも学習として成立します。
また、毎日同じ教材を繰り返し聞くことで、音のパターンが定着しやすくなります。
最初はスクリプトを確認して内容を理解し、その後は音声だけで「意味が頭に浮かぶか」を試すと効果的です。
2. 毎朝10分のリスニングで脳をウォームアップ
朝起きてすぐの時間は脳がクリアで、集中力が高まりやすいタイミングです。
毎朝10分程度、ニュースや短い会話文を聞くだけでも、その日一日の英語学習に良いリズムを作れます。
シャドーイングを取り入れるとさらに効果的で、音声に追随する感覚を養えます。
朝の短い習慣は、試験本番での「耳の立ち上がり」を早める助けにもなります。
「朝の勉強」が生む集中力と成果についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「朝の勉強」が生む集中力と成果の秘密とは?|オススメの朝勉強も紹介」
3. 寝る前のリスニングで記憶定着を助ける
睡眠前に聞いた情報は、脳内で整理され、記憶に残りやすいとされています。
寝る前に5〜10分程度、共通テスト形式の会話や説明文を聞くことで、音声のリズムや表現が自然に定着していきます。
ただし「理解しようと必死になる」のではなく、リラックスしながら聞き流す感覚で取り入れることが大切です。
負担を感じず継続できるのが、寝る前リスニングの大きな利点です。
4. 家庭でできる保護者サポート(教材・環境づくり)
リスニングの学習は、家庭の協力で効率が大きく変わることがあります。
例えば、静かな場所を確保してあげるだけでも、集中力が高まります。
また、教材選びで迷う生徒に対して、保護者が「同じ教材を継続して使う」よう促してあげると、学習の一貫性が保たれます。
さらに、学習用スピーカーを用意したり、リスニングに取り組んでいる姿をポジティブに声かけをすることで、継続のモチベーションにつながります。
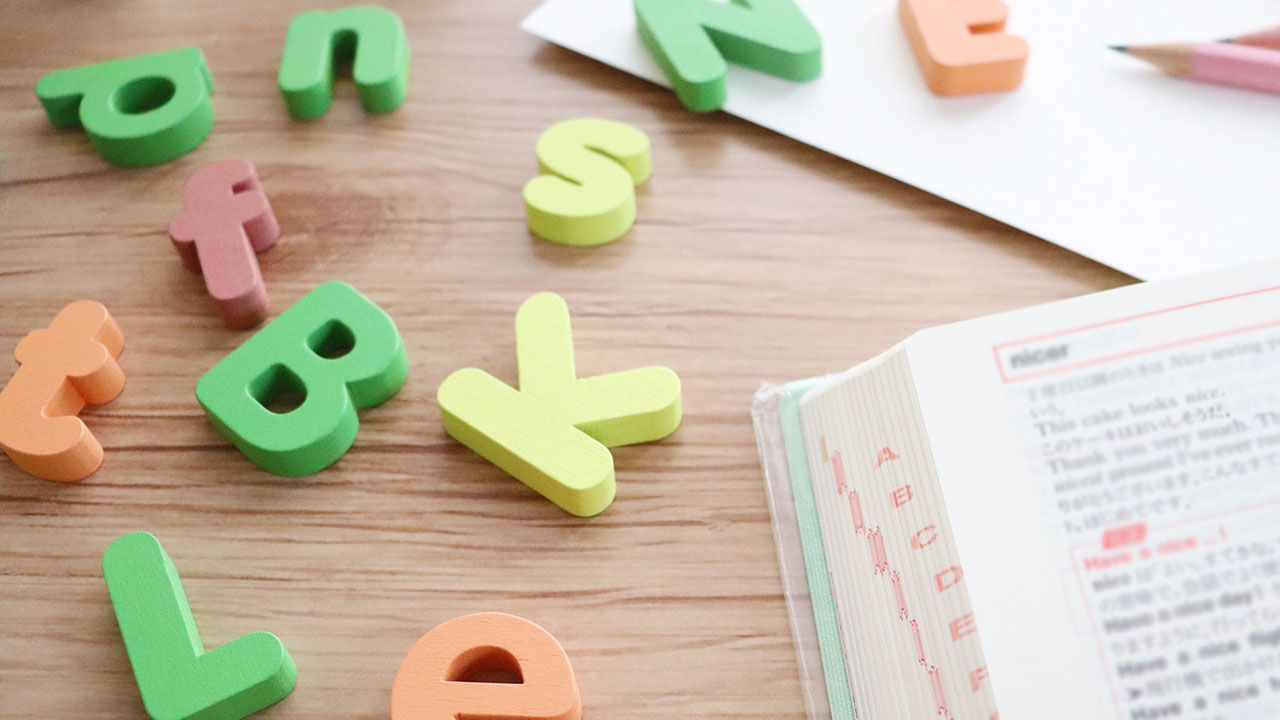
共通テスト直前・当日のリスニング対策
リスニングは一度きりの音声で解答しなければならないため、試験当日のコンディションや心構えが点数に大きく影響します。普段の勉強が十分でも、直前の準備や会場での振る舞いが不十分だと、実力を出し切れないこともあります。
ここでは「残り1週間の過ごし方」と「本番での具体的な立ち回り」を押さえておきましょう。
1. 1週間前にやるべき最終調整
試験1週間前は「新しい教材」ではなく、これまで取り組んできた教材の総仕上げに時間を充てることが重要です。特に、自分が聞き取れなかった設問や苦手な音声変化(リエゾン・弱形など)を重点的にやり直しましょう。
また、この時期は「本番と同じ時間帯に練習する」こともおすすめです。
共通テストの英語リスニングは午後に行われるケースが多いため、午後の時間に模擬練習をすることで脳と耳を当日のリズムに慣らすことができます。
さらに、毎日30分程度を必ずリスニング専用に確保し、耳を“試験モード”に調整すると安心です。
2. 会場での音量チェックと集中の切り替え方
共通テストの英語リスニングは、個別のICプレーヤーとイヤホンで実施されるため、開始前に音量調整のテスト放送はありません。そのため、試験中の音量や音質は事前に確認しておくことが重要です。
さらに、会場の音環境は普段のイヤホン学習とは大きく異なる場合があります。音がこもって聞こえたり、周囲の雑音が気になることもありますが、その際に大切なのは「これが本番の音だ」と意識を切り替える力です。
模試や過去問を解く時から「スピーカーで音を流す」「雑音のある場所で練習する」といった工夫をしておくと、環境の違いに左右されにくくなります。
3. 聞き逃したときにリカバリーするコツ
リスニングの失点で多いのは「一度聞き逃しただけで焦り、残りの内容にまで影響する」ケースです。
聞き取れなかった部分があっても、残りの音声に集中し直すことが何より重要です。
例えば、話の冒頭を聞き逃しても、会話の途中で「誰が・何を・どうしたのか」という核心情報は再び出てくることがあります。また、設問の選択肢を見れば「何が問われているか」が絞り込めるため、部分的に理解しても正答にたどり着けることがあります。
大切なのは「全部を完璧に聞く」のではなく、必要な情報だけを確実に拾う意識を持つことです。
4. マークミス・時間切れを防ぐ工夫
リスニングで大きなリスクとなるのは、マークずれや解答の書き忘れです。音声は待ってくれないため、後からまとめてマークするのは非常に危険です。ですから、解いたらすぐにマークすることを基本ルールとして徹底しましょう。
また、迷った問題には印をつけて「仮の解答」を入れておくのがおすすめです。空欄のまま時間切れになるのを防げます。模試の段階から「解答とマークまでをセットで行う」習慣をつけておくことで、本番でも自然に手が動くようになります。
さらに、時計を気にしすぎると集中が乱れるため、区切りのタイミングで残り時間を確認する程度にとどめると良いでしょう。

まとめ
今回は共通テストのリスニングについて解説してきました。
共通テストのリスニングは、基礎練習と戦略を組み合わせれば確実に伸ばせる分野です。
出題傾向を理解し、日々の習慣にリスニングを取り入れ、本番での対応を意識すれば「安定して得点源」にできます。積み重ねた努力を信じて、試験当日は自信を持って挑みましょう。
家庭教師のマスターでは、共通テストリスニング対策のサポートを行っています。
ご興味のある方は、気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【大学受験コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
大学受験にかかる費用は!?|受験料やその他の費用まで徹底解説!
-
大学受験の勉強時間はどれくらい?|学年別の目安と時間のつくり方
-
【2024年版】英検準1級は大学受験に有利になる?|優遇する大学もご紹介!
-
大学受験のために塾・予備校に行くべきか?|それぞれの違いと選ぶ基準を解説!
-
大学受験の調査書とは?|調査書の内容や役割を徹底解説!
-
【高校生必見】共通テストとセンター試験の違いは?|変更点を徹底解説!
-
大学オープンキャンパスの服装はどうする?|制服・私服どっちが正解?
-
公募推薦で合格する人の共通点とは?|受かるための準備・対策も解説
-
大学指定校推薦の仕組み|校内選考の基準や対策を解説!
-
自己推薦入試とは?|他の推薦入試との違いや、合格の秘訣を徹底解説
























