高校受験「社会」の勉強法|得点源に変える傾向・攻略法を徹底解説!
公開日:2025年9月8日
更新日:2025年9月8日

「社会は暗記科目だから後回し…」そんな受験生必見! このコラムでは、高校受験の出題傾向や分野別勉強法、スケジュールの立て方、弱点克服のコツまで、得点源化に必要な全ステップをまとめました。今日から社会の点数を上げる第一歩を踏み出しましょう。
高校受験で「社会」を得点源にすべき3つの理由
高校受験の勉強といえば、多くの人が「英語・数学・国語」の主要3科目に重点を置きがちです。
もちろん主要科目の比重は大きいのですが、実は「社会」も合否を左右する重要な科目です。しかも、正しく勉強すれば短期間でも点数を伸ばせる可能性が高いため、戦略的に「得点源」として活用する価値があります。
ここでは、その理由を3つに分けて解説していきます。
1. 社会が合否を左右する科目になるのはなぜか
社会は暗記中心の科目と思われがちですが、実際の入試においては1点差・数点差で合否が分かれることが多い科目です。
特に公立高校入試では、基本的に5教科の合計点で合否が決まるため、主要科目が得意でも社会で失点すると全体の得点バランスが崩れてしまいます。
また、上位校を狙う生徒ほど主要科目の学力差は小さく、「社会や理科のちょっとした差」が結果を左右することも少なくありません。そのため、社会を軽視せず、安定して得点できるようにしておくことが、合格可能性を大きく高めるポイントになります。
2. 理科より安定して得点しやすい理由
理科と社会は同じ配点で扱われることが多いですが、実際には社会の方が比較的安定して得点しやすい科目です。
理科は計算問題や実験考察など思考力を必要とする出題が多く、勉強量の割に得点が安定しにくい傾向があります。これに対して、社会は知識を覚えれば解ける問題が多く、努力が点数に直結しやすいのが特徴です。
特に短期間で得点アップを目指す場合、社会の基礎知識を固めるだけで一気に20〜30点伸びることもあり、勉強の効率を考えても非常に「コスパの良い」科目と言えるでしょう。
3. 暗記科目なのに差がつく背景とは?
「社会は暗記科目だから簡単に点が取れる」と思われがちですが、実際には得点差がつきやすい科目でもあります。その背景には、暗記の仕方に工夫が求められる点があります。
例えば地理では地図や統計資料を読み取る力、歴史では出来事の因果関係や時代の流れ、公民では制度の仕組みや時事問題との関連を理解する力が必要です。丸暗記だけでは対応できない問題も多く、知識を「つなげて理解」しているかどうかで得点差につながります。
さらに入試問題では、似た用語を組み合わせたり複数の資料を比較させたりといった工夫がされており、表面的な暗記では対応が難しい一方、理解を深めた生徒は安定して高得点を取れます。
つまり社会は「覚え方次第で差がつく」科目であり、知識を整理しながら理解する学習法が合格への近道となります。
効率的な暗記の方法についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「効率的な暗記の方法とは?|苦手な暗記を克服するオススメ8つの方法」

高校受験の「社会」の出題範囲と傾向
「社会」と一口に言っても、その中には地理・歴史・公民という3つの大きな分野があります。
さらに、入試問題では単純な暗記だけでなく、資料を読み取る力や論理的に説明する力も問われるようになってきています。
ここでは、社会の出題範囲と傾向を整理して、効率よく勉強を進めるための視点を押さえていきましょう。
1. 社会の3分野(地理・歴史・公民)の概要
まずは3分野の特徴を大まかに理解しておきましょう。
地理
日本や世界の自然環境、産業、地形、気候などを学ぶ分野です。
白地図や地図帳を使った学習が基本で、統計データやグラフを読み取る問題も頻出です。
暗記だけでなく、「知識を関連付けて理解する」ことが大切です。
歴史
原始から現代までの出来事を、時代の流れに沿って学ぶ分野です。
単なる年号暗記ではなく、出来事同士の因果関係や社会の変化を理解しているかどうかが問われます。文化史が出題されることも多く、人物・建築・文学など幅広い知識が必要です。
公民
現代社会の仕組みを学ぶ分野で、憲法や政治制度、経済の基本、国際社会の動きなどが範囲に含まれます。
実生活と関連する内容が多いため、ニュースや時事問題と結び付けて学ぶと理解が深まりやすいでしょう。
参照: 文部科学省「中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編」
2. 配点と出題形式の特徴(選択式・記述式・資料読解など)
社会は、単なる選択肢問題だけでなく、資料を読み取る問題や短文記述が多いのが特徴です。
配点は学校や都道府県によって異なりますが、多くの入試では「知識問題」と「思考・表現問題」の両方を組み合わせ、バランスを取る形が主流となっています。
選択式(マークシート・語句選択)
基礎知識を直接問う問題が中心です。選択肢の中から答えを選ぶ形式がほとんどです。選択式問題(マークシート・語句選択)は、知識が正確かどうかを判定します。
資料読解問題
地図や統計表、グラフ、歴史年表、憲法の条文などを読み取り、知識と照らし合わせて答える形式です。知識を活用する力や整理力が求められます。
記述式
近年は「短文で答える」問題を導入する自治体が増えており、単なる暗記ではなく、自分の言葉で正しく簡潔に説明できるかどうかが試されます。
3. 公立高校と私立高校での出題傾向の違い
公立高校
公立入試では、幅広い基礎知識をバランスよく問う傾向があります。
資料問題が多く、教科書レベルの内容を正確に理解しているかが試されます。極端に難しい問題は少ないものの、ケアレスミスを防ぐ正確さが合否に直結します。
ケアレスミスについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「ケアレスミスが多い小中高生|効果的な7つの対策法」
私立高校
私立入試は学校ごとに出題傾向に大きな違いがあります。
難関校では、難度の高い資料問題や記述問題が出題され、時事問題との関連も深く問われることがあります。
一方で、基礎力の確認に重点を置いたシンプルな問題を出す学校もあります。そのため、各校の過去問研究が非常に重要です。
4. 時事問題がどの分野にどう出るか
社会の入試では、時事問題がほぼ毎年のように出題されます。
時事問題は教科書の知識とリンクして問われることが多く、単なるニュースの暗記ではなく「基本知識と結びつけて理解しているか」が得点差につながります。
地理
世界の人口問題や環境問題、産業統計などが最新のデータを元に出題されることが増えています。
歴史
戦後○年や憲法施行○年といった周年記念、また歴史的な出来事と現代を結びつける形で出題されることがあります。
公民
国際関係や経済政策、選挙制度など、ニュースに直結するテーマがよく出題されます。

高校受験に向けた時期別の社会勉強スケジュール
社会は「暗記科目」と言われるだけに、直前に詰め込めばなんとかなると思われがちです。
しかし、実際には範囲が広く、統計や資料問題などの応用力も求められるため、計画的に学習を進める必要があります。特に、中学3年間の流れを意識して「基礎固め → 全範囲復習 → 得点力アップ → 直前仕上げ」という段階を踏むことが重要です。
ここでは、時期ごとの効果的な取り組み方を紹介します。
1. 中1〜中2でやっておきたい基礎固め
中学1・2年のうちは、受験を意識しすぎる必要はありません。
ただし、この時期に教科書レベルの基礎知識を理解・定着させておくことが、受験期の伸びにつながります。
⚫︎ 授業と学校ワークを大切にし、定期テスト対策で知識を整理する
⚫︎ 地理は白地図を使い、国や地域の特徴を「手を動かして書き込みながら覚える」習慣をつける
⚫︎ 歴史は出来事を単発で覚えるのではなく、流れを物語のようにつなげて理解する
⚫︎ 公民はまだ本格的には登場しないが、ニュースを親子で話題にするなどして興味を持つ
この段階で大切なのは「社会に苦手意識を持たないこと」です。
基礎が崩れると、中3になってから社会が大きな負担になってしまいます。
2. 中3春〜夏にやるべき「全範囲復習」の進め方
中3に入ると、本格的に受験を意識した勉強が必要になります。
特に春から夏休みまでの時期は、社会の3分野を一度通して復習することが重要です。
⚫︎ 1週間ごとに地理・歴史・公民をローテーションして進める
⚫︎ 教科書と学校ワークを使い「基礎知識を抜けがないようにチェック」する
⚫︎ 苦手分野はこの段階でしっかり補強する(例:統計資料が弱いなら夏までに集中演習)
⚫︎ 夏休みには過去問や模試で「今の実力」を確認し、弱点を明確にする
夏までに基礎を固めておけば、秋以降は「得点力アップの学習」に余裕を持って取り組めます。
3. 中3秋〜冬の得点力アップ対策
秋以降は、いよいよ入試本番を意識した演習中心の学習になります。基礎知識のインプットは終えていることを前提に、得点力を伸ばすためのアウトプット練習に重点を置きましょう。
⚫︎ 過去問や入試形式の問題集を繰り返し演習する
⚫︎ 資料問題・記述問題に特化して練習する
⚫︎ 間違えた問題は「なぜ間違えたのか」を分析し、ノートなどに整理する
⚫︎ 模試の解き直しを必ず行い、弱点分野を克服していく
この時期は「得点の安定感」を身につけることが最大の目的となります。
毎回の演習で70〜80%取れる状態にしておけば、本番でも力を発揮できます。
4. 直前1か月でのラストスパート術
直前期は「知識の総点検」と「本番対応力の仕上げ」が中心です。
新しいことに手を出すのではなく、これまで学習してきた内容を整理することが得点に直結します。
⚫︎ 間違い直しノートを見返し、弱点を克服する
⚫︎ 白地図や年表を使って「一問一答形式」で知識を確認する
⚫︎ 過去3年分の入試問題を本番同様に解き、時間配分をシミュレーションする
⚫︎ 時事問題をチェックし、最新のニュースと基礎知識を関連付ける
特に入試直前1か月は、精神的に不安になりやすい時期です。「ここまでやった」という安心感を持てるように仕上げをしておくことが大切です。
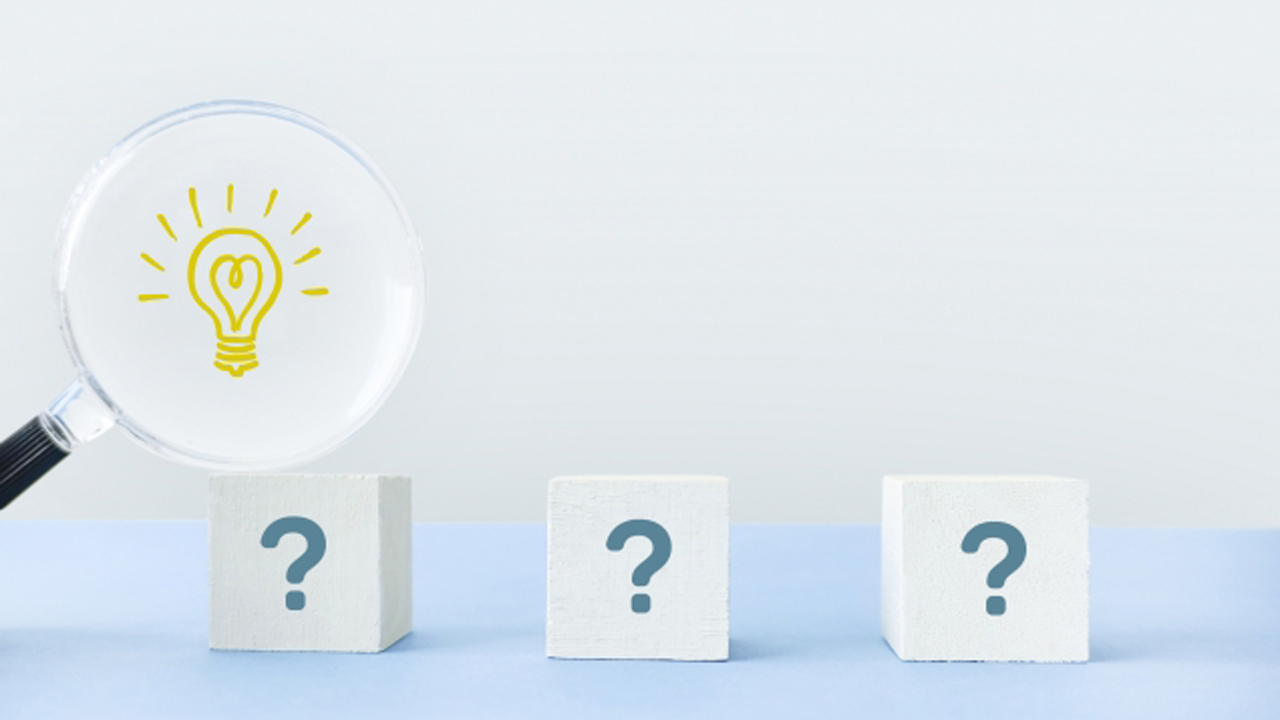
分野別の勉強法
社会は「地理・歴史・公民」の3分野に分かれており、それぞれ特徴も勉強法も異なります。単純に暗記するだけでは得点に結びつかないため、分野ごとに適した学習法を取り入れることが大切です。
ここでは、それぞれの分野を効率的に攻略するためのポイントを詳しく解説します。
1. 地理の勉強法
地理は「地図や資料を読み解く力」が得点に直結します
暗記だけに頼らず、手を動かしてアウトプットする習慣を身につけることで、知識が定着しやすくなります。
白地図、地図帳を使ったアウトプット中心の学習
地理の基本は「場所を覚える」ことです。
白地図に国名や都市名、山脈や川などを書き込むことで、知識をアウトプットしながら整理できます。地図帳も必ず横に置いて学習すると、位置関係や地形がイメージしやすくなります。
統計資料、グラフ問題の解き方
入試では農業や工業の生産量、人口の推移などを示した統計表やグラフが頻出です。単に数値を暗記するのではなく、「なぜこの数値になるのか」を考えることが重要です。
例えば、北海道で小麦が多いのは気候や土地条件による、という因果関係を理解することで応用問題にも対応できます。
時事ニュースと関連付けて覚える
地理はニュースとの関連が強い分野です。
オリンピック開催地や国際問題、自然災害などを地図で確認するだけでも、知識が記憶に残りやすくなります。日常のニュースを学習に取り入れる工夫をしましょう。
2. 歴史の勉強法
歴史は「時代の流れをつかむこと」が最も重要です。
単発の出来事だけを覚えても定着しにくいため、時代の移り変わりや出来事の因果関係を意識して学ぶことが大切です。
年号暗記よりも因果関係理解を優先
もちろん主要な年号は覚える必要がありますが、それ以上に「なぜその出来事が起きたのか」「その後にどんな変化をもたらしたのか」を理解することが大切です。
例えば「鎌倉幕府が滅びた理由」と「その後の室町幕府との違い」を押さえることで、知識がつながっていきます。
時代ごとの流れをストーリー化
歴史を物語のように捉えると、断片的な知識も理解しやすくなります。自分なりに「人物関係図」や「出来事のつながりマップ」を作るのも効果的です。
特に模試や入試では、時代をまたぐ横断的な比較問題も出題されるため、全体像を意識しましょう。
文化史を効率的に押さえるコツ
文化史は、暗記する人物名や作品名が多く、苦手になりやすい分野です。
効率的に学ぶには「時代ごとの特徴とセットで覚える」ことが大切です。
例えば「安土桃山時代=豪華絢爛な文化」「江戸時代前期=元禄文化」のように、キーワードを軸にまとめると効率的に整理できます。
3. 公民の勉強法
公民は「現代社会の仕組み」を学ぶ分野です。
内容が抽象的に感じられることもありますが、実生活やニュースと結びつけることで理解が深まります。
制度や仕組みをイメージで理解
選挙制度や三権分立などは図解で整理すると理解しやすくなります。
例えば「国会=法律を作る」「内閣=法律を実行する」など、役割をシンプルにイメージして理解すると良いでしょう。
憲法、政治、経済の基礎知識整理
憲法は条文の丸暗記ではなく、「基本的人権」「三大原則」など大枠の理解が必要です。
経済分野では、需要と供給や金融の仕組みなど、日常生活に直結する知識が問われます。
基礎を固めると応用問題にも対応しやすくなります。
時事問題対策と最新ニュースの活用法
公民は特に時事問題と関連が深い分野です。
例えば選挙や国際会議、経済ニュースなどはそのまま入試に出ることがあります。
新聞やニュースアプリを活用し、出題されそうなテーマを整理すると得点につながります。

社会に強くなる共通勉強テクニック5選
社会は暗記の比重が大きい科目ですが、ただ丸暗記に頼っても本番では点数が安定しません。効率よく知識を定着させ、入試問題に対応できる力を身につけるには、勉強のやり方に工夫が必要です。
ここでは、どの分野にも共通して使える「社会に強くなるための勉強テクニック」を5つ紹介します。
1. 「3回復習法」で短期記憶を長期定着に変える
社会は情報量が多く、1回覚えただけではすぐ忘れてしまいます。
そこで有効なのが「3回復習法」です。
1回目:学んだその日のうちに復習
2回目:翌日にもう一度確認
3回目:1週間後に再チェック
このサイクルを繰り返すことで、短期記憶を長期記憶に変え、入試本番まで知識を維持しやすくなります。特に一問一答形式や暗記カードを使うと効果的です。
2. 過去問演習で出題パターンと弱点を発見
過去問は「入試で何が問われるのか」を知る非常に有効な教材です。
最低でも過去3〜5年分を解き、出題パターンを把握すると良いでしょう。
・「毎年必ず出るテーマ」を見つける
・自分が間違いやすい問題を分析する
・解答時間を計って実践的に練習する
過去問演習を通じて、自分の弱点を明確にし、それを重点的に補強すると効率よく得点力が伸ばせます。
3. 間違い直し専用ノートの作り方
社会の勉強で伸びる生徒ほど「間違い直し」を重視しています。
テストや演習で間違えた問題をまとめる「専用ノート」を作りましょう。
・問題文や資料をそのまま貼る、または書き写す
・間違えた理由をメモする
・正しい解答や重要ポイントを簡潔にまとめる
同じミスを繰り返さない仕組みを作ることで、知識が定着しやすくなります。
直前期には、このノートを見返すだけで効率的に総復習に活用できます。
ノートのまとめ方についてもっと知りたい方はこちら
⇒「ポイントを押さえたノートまとめ方のコツ|小中学生向け簡単ノート術!」
4. 試験時間を意識した演習で時間配分を身につける
社会の入試問題は資料問題や記述問題が多く、時間が足りなくなることがあります。
そこで、普段から「時間を計って解く練習」を取り入れると良いでしょう。
・過去問や模試形式の問題を「本番と同じ制限時間」で解く
・1問あたりにかけられる時間の目安を把握する
・難しい問題に固執せず、取れる問題から解く練習をする
時間感覚を磨いておくことで、本番でも落ち着いて解答しやすくなります。
5. 資料問題を毎日1問解く習慣
社会の入試で最も差がつきやすいのが「資料問題」です。
地図、グラフ、統計表、写真などを読み解く力は、短時間で身につくものではありません。
そこでおすすめなのが「毎日1問の資料問題演習」です。
短時間でも続けることで、統計の読み取りや地図の特徴を見抜く力が徐々に鍛えられます。
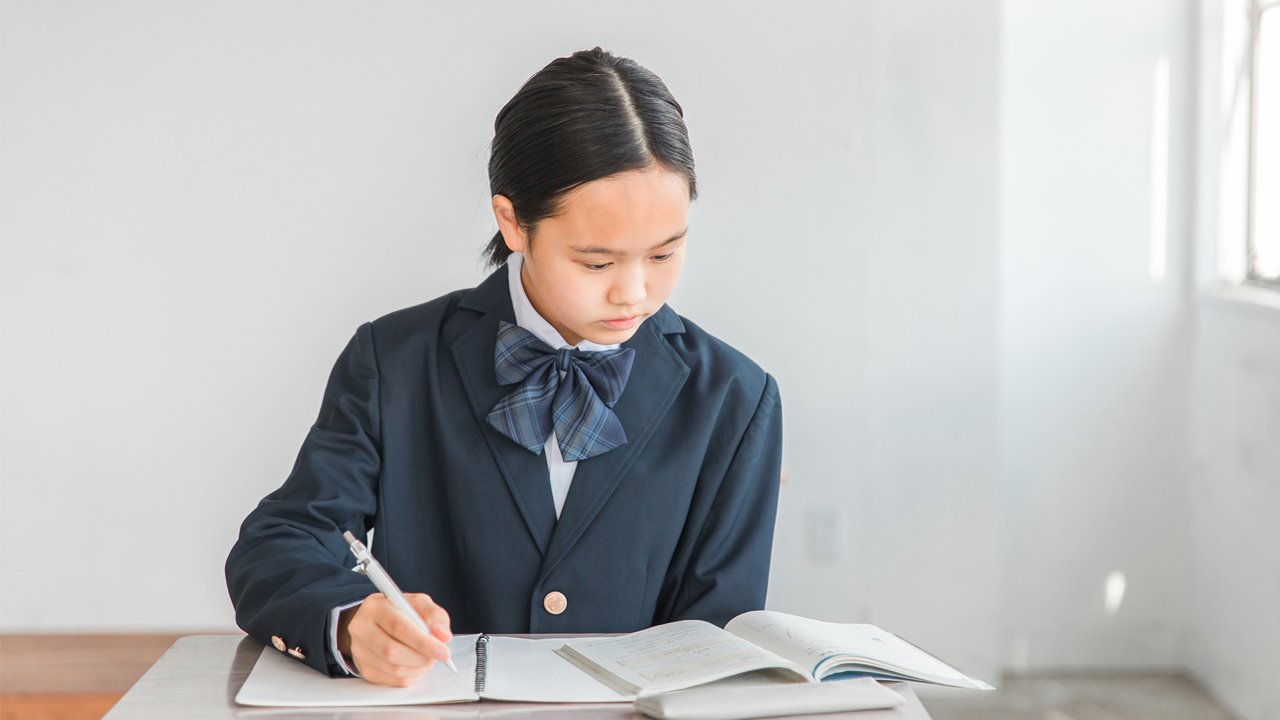
社会が苦手な人の弱点克服と失敗回避法7選
社会は暗記中心の科目なので「直前に詰め込めば大丈夫」と考える人が多いですが、実際には範囲が広く、応用力が問われるため、苦手を残したまま入試に臨むと大きな失点につながります。
ここでは、よくあるつまずきや失敗を取り上げながら、その克服法を解説していきます。
1. 地理で「覚えたのに点が取れない」場合の対処
用語や地名は覚えているのに得点に結びつかない場合、多くは「位置と理由」が結び付いていないことが多いです。
白地図に産地・気候・地形を自分の手で書き込み、地図帳でその都度確認しながら、「なぜそこにその産業が発達したのか」「その気候では何が育つのか」と因果まで声に出して説明してみましょう。
統計やグラフは数値を丸暗記するのではなく、上位・下位の理由を地理的条件と関連づけて言語化するのがコツです。模試や問題集の資料問題は、解答を見る前に「読み取れる事実→考えられる理由→結論」の順でメモを取り、思考の型を身につけることで安定して得点につながっていきます。
2. 歴史が「覚えられない・混同してしまう」場合の克服法
歴史の混乱は、出来事を点で覚えていることが原因です。
各時代の「政治・経済・社会・文化」の流れを一枚の年表に縦横で書き足し、前後の因果関係を矢印で結んで物語として捉え直すと理解が深まります。
日本史と世界史が同時期にどう連動していたかを横並びにして比較すると、出来事の位置づけが明確になります。
人物や文化は「時代の特徴」とセットで覚えると混同しにくく、例えば建築なら様式のキーワード、文学ならテーマの違いを短いフレーズで付記すると記憶の手がかりになります。
3. 公民が理解できず、暗記だけになってしまう場合の改善策
公民は、仕組みをイメージできるかがポイントとなります。
三権分立や法律が成立過程、選挙制度から議席配分までを簡単な図に整理し、役割や手順を自分の言葉で説明できるようにします。
経済分野は、日常の出来事と結びつけると理解がより深まります。
ニュースで見た物価や金利、為替などのテーマを教科書の用語に翻訳し直すクセを付けると、記述でも理由を書けるようになります。
4. 資料問題・記述問題が苦手な場合の練習法
資料問題は“読み取りの手順”を意識すると取り組みやすくなります。
まず、題意と単位を確認し、資料から言える事実を二つ以上言語化して理由を一つ考えます。
記述は「結論→理由→具体」の順で短く整えると点が入りやすくなります。
例えば、「A地域は畑作が盛んだ。降水量が少なく気温年較差が大きいからで、小麦の作付面積が高い統計とも一致する」のように書く練習をすると効果的です。
最初は模範解答を音読・要約して型を真似し、徐々に自分の表現に置き換えることで安定して解答できるようになります。
5. 暗記カードだけで終わらないための工夫
暗記カードは入口として有効ですが、出口(運用)に結び付けないと本番で活かせません。
カードで想起した用語を一問一答や資料問題に当てはめ、理由を一行添えるまでをセットにすると効果的です。
さらに、「友達や家族に30秒で説明する」「自分に音声で教える」など、口頭でアウトプットを取り入れると、理解が不十分な箇所が明確になります。
間違えたカードは束ねて“再挑戦ゾーン”に回し、翌日と一週間後に再チェックすることで、短期記憶を長期定着に移すことができます。
6. 時事問題を早めに着手する重要性
時事問題は、直前の一夜漬けでは幅広く対応できません。
月ごとにテーマを三つ選び、要点を約100字程度にまとめ、地理・歴史・公民のどの単元と関連するかを一言で紐づけておくと効果的です。
例えば、エネルギー価格なら、資源の分布(地理)、産業構造の変化(歴史の現代史)、物価と金融政策(公民の経済)と関連付けて整理できます。
模試や解説冊子のトピックは付箋で管理し、テスト直前に見返せる“自分専用の時事まとめ”にしておくと安心です。
7. 苦手分野を残さず仕上げる学習計画の立て方
学習計画は、「いつ何を終わらせるか」だけでなく、「どの状態になったら合格」と定義するのがポイントです。
・夏までに全範囲を一周して弱点リストを作成する
・秋は得意7割・苦手3割の配分で演習を回し、苦手分野は同一テーマを短時間で三日連続反復して記憶の定着を図ります
・直前一か月は新しい範囲を増やさず、間違いノート・時事まとめ・白地図・年表の総点検に絞ります。
さらに、週に1度は本番形式での通し演習を取り入れ、時間配分やミスの傾向を確認し、改善点を翌週の計画に反映させましょう。

まとめ
今回は高校受験の社会の勉強法について解説してきました。
社会は「暗記すれば良い科目」ではなく、計画的な学習と工夫次第で確実に得点源へ変えられる科目です。出題傾向を理解し、時期ごとに戦略的に取り組み、地理・歴史・公民の特性に合わせた勉強法を実践すれば、安定して高得点を狙えます。
苦手を放置せず、日々の学習の中で克服していくことが合格への近道です。社会をしっかり味方につけて、高校受験を有利に進めていきましょう。
家庭教師のマスターでは、社会が苦手なお子さんに向けた学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【高校受験コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
【高校受験】効率の良い受験対策・受験勉強の方法をご紹介します!
-
高校入試の数学|中学生必見!よく出る分野とオススメ学習法を紹介!
-
高校受験の英語を点数アップするコツとは?|合格への必勝テクニック
-
理科が苦手な中学生へ!効率的な勉強法と克服のコツを解説
-
高校入試「社会」のよく出る問題を徹底解説|頻出テーマと得点アップのコツ
-
高校入試の作文の書き方と注意点|カンタン早わかりガイド!
-
高校入試の小論文の丸わかり完全攻略ガイド!|模範解答例・解説付き
-
英語のリスニングが上達するコツ|苦手な人にオススメの勉強法
-
英語の長文読解のコツ|問題の解き方から勉強法まで徹底解説!
-
英単語の効果的な覚え方9選【中学生・高校生必見!】
-
古文が苦手な中学生へ|高校入試に向けた“つまずかない”勉強法
-
効率的な古文単語の覚え方と勉強法|古文が嫌いな中高生必見!























