受験のストレスを軽くする方法|症状・原因・効果的な解消法まとめ
公開日:2025年11月6日
更新日:2025年11月6日
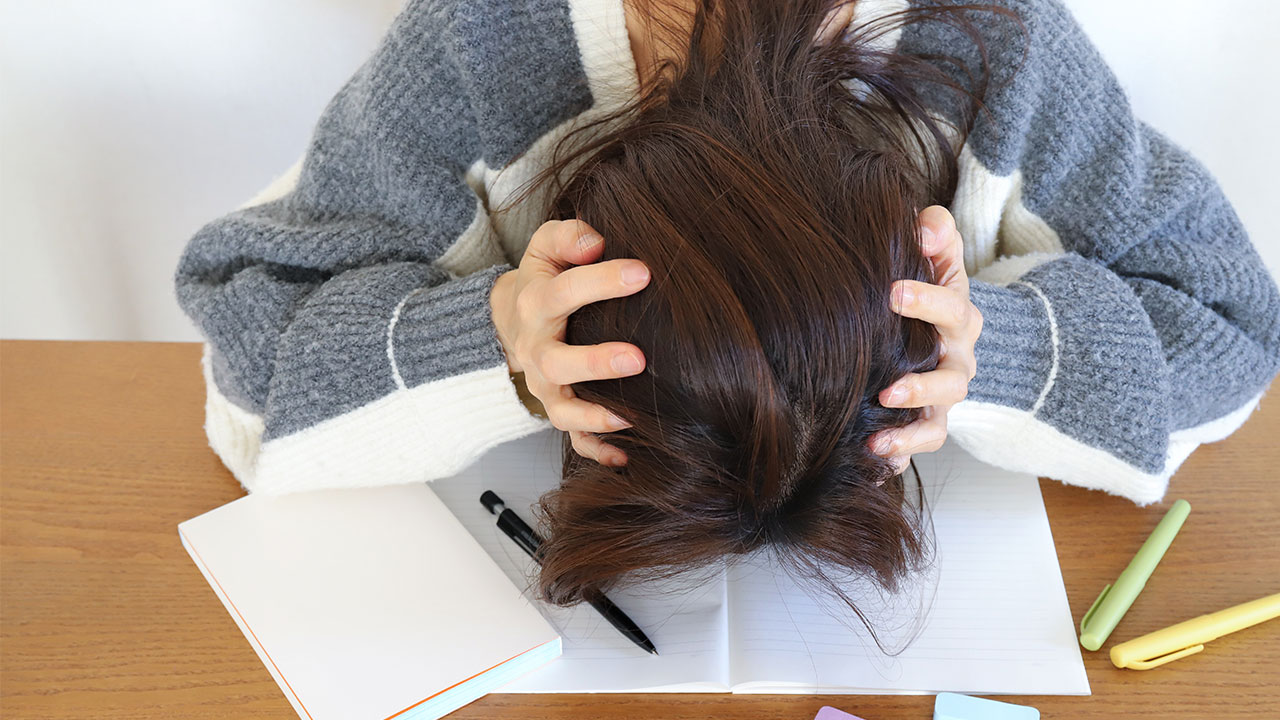
受験のストレスで頭痛や不眠、集中力低下などが起きていませんか?
このコラムでは、受験ストレスによる症状や原因をわかりやすく解説し、家庭でできる解消法や予防の工夫を具体例とともにご紹介します。
受験生と保護者が一緒に取り組める実践的なストレス対策がわかります。
受験のストレスで起こりやすい症状とは?
受験生は日々の勉強や模試、学校生活などで心身に大きな負担を抱えています。
ストレスが強くなると体や心にさまざまな変化が現れ、それが勉強の効率や受験本番のパフォーマンスにも影響を与えます。
ここでは、受験ストレスによって起こりやすい代表的な症状を詳しく見ていきましょう。
1. 頭痛・腹痛・食欲不振など身体的な不調
強いストレスを受けると、自律神経のバランスが乱れ、体に不調が現れることがあります。
受験生に多いのは頭痛や腹痛、食欲不振です。特に試験前日や模試当日など緊張が高まる場面では、普段は元気な受験生でも急に腹痛を訴えたり、朝食が喉を通らなかったりすることがあります。こうした症状は一時的で済むことも多いですが、長引けば体力の低下や集中力への悪影響につながります。無理に我慢せず、休養と栄養補給を心がけることが大切です。
2. イライラ・不安感などの精神的な変化
ストレスは心の働きにも影響しやすくなります。
模試の結果や周囲との比較によって、イライラが増えたり、不安感が強くなったりすることがあります。
特に受験期は「勉強しなければならない」という焦りが強く、ちょっとした出来事でも気分が落ち込みやすくなります。保護者や友人との会話が減り、部屋にこもりがちになることもありますが、これは必ずしも「やる気がない」わけではなく、心が疲れているサインとして受け止めてあげましょう。
3. 集中力の低下や勉強の効率ダウン
ストレスが高まると、脳の働きが一次的に低下し、集中力が続かない状態になりがちです。
「勉強しているのに内容が頭に入らない」「同じ問題を何度も間違えてしまう」といった状況が増えると、自己嫌悪や焦りが強まり、悪循環に陥りやすくなります。そのような時は、思い切って短時間の休憩を取り、心身をリセットしてから勉強を再開すると効率が改善しやすくなります。
4. 睡眠リズムの乱れや不眠
受験期は夜遅くまで勉強したり、緊張で眠れなかったりと、睡眠リズムが崩れやすい時期です。
眠れないまま焦ってベッドで過ごすと、脳がかえって覚醒してしまい、不眠が慢性化することもあります。
睡眠不足は記憶力や判断力を低下させ、翌日の集中力や学習効率に悪影響を及ぼします。寝る前はスマホの使用を控え、軽いストレッチや深呼吸を取り入れて、リラックスして眠りにつく習慣を身につけましょう。
5. モチベーション低下や無気力感
ストレスが限界に近づくと、「何もしたくない」「勉強する気持ちがわかない」といった無気力感が現れることがあります。
これは単なる怠けではなく、心が疲れているサインです。
無理に勉強を続けると逆効果になることがあるため、短期間でも良いので休養と気分転換を意識して取り入れましょう。保護者は「頑張れ」という言葉よりも、「今日は少し休もうか」といった安心感を与える声かけのほうが有効とされています。

受験ストレスがたまる5つの主な原因
受験生が抱えるストレスには必ず背景があります。
「もっと頑張らなきゃ」という気持ちだけでは解消できず、知らず知らずのうちに心身に負担がかかってしまいます。
ここでは、受験ストレスがたまりやすい代表的な5つの原因を詳しく見ていきましょう。
1. 成績や模試の結果へのプレッシャー
受験期になると、模試や定期テストの結果が自分の価値の指標のように感じてしまうことがあります。
「前回より偏差値が下がった」「志望校の判定がE判定だった」という事実に一喜一憂し、焦りや不安で勉強が手につかなくなる生徒も少なくありません。
本来、模試は現状を知るためのツールですが、受験生はどうしても「合格・不合格」の判断材料として捉えがちです。
プレッシャーを和らげるには、結果だけに目を向けるのではなく、「次に何を改善するか」という行動目標に意識を切り替えることが大切です。
2. 周囲からの期待や比較によるストレス
親や先生、友人などの周囲の期待は励みになる一方で、大きなプレッシャーになることもあります。
特に「兄弟が有名校に合格している」「友達が次々と志望校を決めていく」などの状況は、自分を無意識に比較してしまい、心にストレスをため込む原因となります。
また、SNSで友人の勉強記録や合格報告を目にすることで、自分が取り残されたように感じることもあります。周囲と比較するのではなく、「自分のペースで着実に前進している」という自己肯定感を保つことが重要です。
3. 勉強と部活・人間関係の両立によるストレス
受験生の多くは、勉強だけでなく部活動や友人関係にも時間とエネルギーを使っています。
「部活をやめるべきか続けるべきか」「友人との時間を削ってでも勉強すべきか」という葛藤がストレスの一因になることもあります。
また、友人との距離が偏ると孤独感が増し、遊びすぎると勉強時間が不足するなど、バランスを取るのが難しい時期です。一人で抱え込まず、先生や家族と相談しながら優先順位を明確にすることがストレス軽減につながります。
4. 生活リズムの乱れや休養不足
夜遅くまで勉強したりスマホを使いすぎたりすると、生活リズムが崩れやすく、受験生が抱えやすい悩みです。
睡眠不足や不規則な食事は体調だけでなく、集中力や記憶力の低下にもつながります。
「勉強時間を増やしたい」という思いから休養を削ると、かえって効率が低下し、結果的にストレスが増すことがあります。毎日同じ時間に起きて寝る、食事をしっかりとるなど基本的な生活習慣を整えることが、心身の安定に欠かせません。
5. 将来や進路への不安・不満
志望校選びや進路の決定は、受験生にとって大きなストレスです。
「もし合格できなかったらどうしよう」「この進路は本当に自分に合っているのか」という将来への不安が強まると、勉強への集中力が低下することがあります。
また、親や先生の意見と自分の希望が食い違うと、「自分の気持ちを理解してもらえない」という不満を抱きやすくなります。一人で悩みを抱え込まず、信頼できる大人に相談しつつ進路を考えることが、安心感につながります。

受験ストレスを軽くするための実践法
受験ストレスは避けることが難しいものですが、日常の工夫や考え方の転換によって軽くすることができます。
ストレスを放置せず、体と心をケアすることで勉強効率が上がり、前向きに受験期を乗り越えられます。ここでは、今日から取り入れられる具体的な実践法を紹介します。
1. 勉強の合間にできるリフレッシュ習慣
長時間勉強を続けると、集中力が切れ、ストレスを感じやすくなります。
ポイントは「短時間で心身をリセットすること」です。
5分間だけ目を閉じて深呼吸をしたり、軽くストレッチをするだけでも脳がリフレッシュされやすくなります。また、外の空気を吸ったり、窓際で陽の光を浴びるなど、気分転換できる行動を意識的に取り入れると良いでしょう。
ストレスについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「ストレスがたまってつらい…」中学生のストレス発散方法をご紹介!」
2. 睡眠・食事・運動で整える体と心
受験期こそ基本的な生活習慣が大切です。
睡眠は記憶を定着させるために重要で、夜更かしして勉強するよりも、しっかり眠るほうが結果的に効率が上がります。
食事は脳のエネルギー源となる炭水化物や、集中力を支えるタンパク質を意識して摂ることが大切です。
また、軽い運動はストレスホルモンを減らす効果があるため、朝の散歩やストレッチなどを日課にすると、心身の調子を整えやすくなります。
睡眠と学習の関係についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「睡眠と学習の関係を徹底解説|効率を高める勉強法と理想の睡眠習慣」
3. 家族、友人、先生に相談して気持ちを軽くする
一人で悩みを抱え込むと、ストレスが増すことがあります。
気持ちが限界に近づく前に、信頼できる相手に相談することが大切です。
家族には「つらい」という気持ちを素直に話し、友人や先生には勉強や進路の悩みを打ち明けると、安心感を得られやすくなります。話すことで頭の中が整理され、「自分は一人じゃない」という支えを感じられることが心の安定につながります。
4. 勉強計画と休憩時間の上手な取り方
ストレスが強くなる背景には、勉強計画の詰め込みすぎがあることがあります。
1日の勉強時間をただ増やすのではなく、「午前中は暗記科目」「夜は復習」といったメリハリをつけた計画を立てることが重要です。
また、50分勉強したら10分休憩するなど、適度な休憩を挟むことで集中力が持続しやすくなります。
「休むことも勉強の一部」と考え、罪悪感を持たずにリフレッシュしましょう。
5. スマホやSNSとの付き合い方を見直す
SNSは便利な一方で、ストレスの一因にもなり得ます。
他人の勉強進捗や合格報告を見ると、自分と比較して落ち込むことがあります。
通知を切る、勉強アプリ以外はタイマーで使用時間を制限するなど、スマホとの距離を工夫すると良いでしょう。「勉強が終わったら30分だけ見る」など、自分なりのルールを決めると、気持ちが安定しやすくなります。
6. 保護者ができる声かけとサポート例
保護者の声かけは、受験生の心に大きな影響を与えます。
「頑張れ」という言葉よりも、努力を認めて安心させる言葉が効果的です。
例えば、「昨日より集中できてたね」「努力しているのをちゃんと見てるよ」と伝えると、子どもは安心して勉強に向かえます。また、模試結果が悪かった時はすぐに叱るのではなく、「どこを見直すか一緒に考えよう」と伴走する姿勢を示すことがストレス軽減につながります。
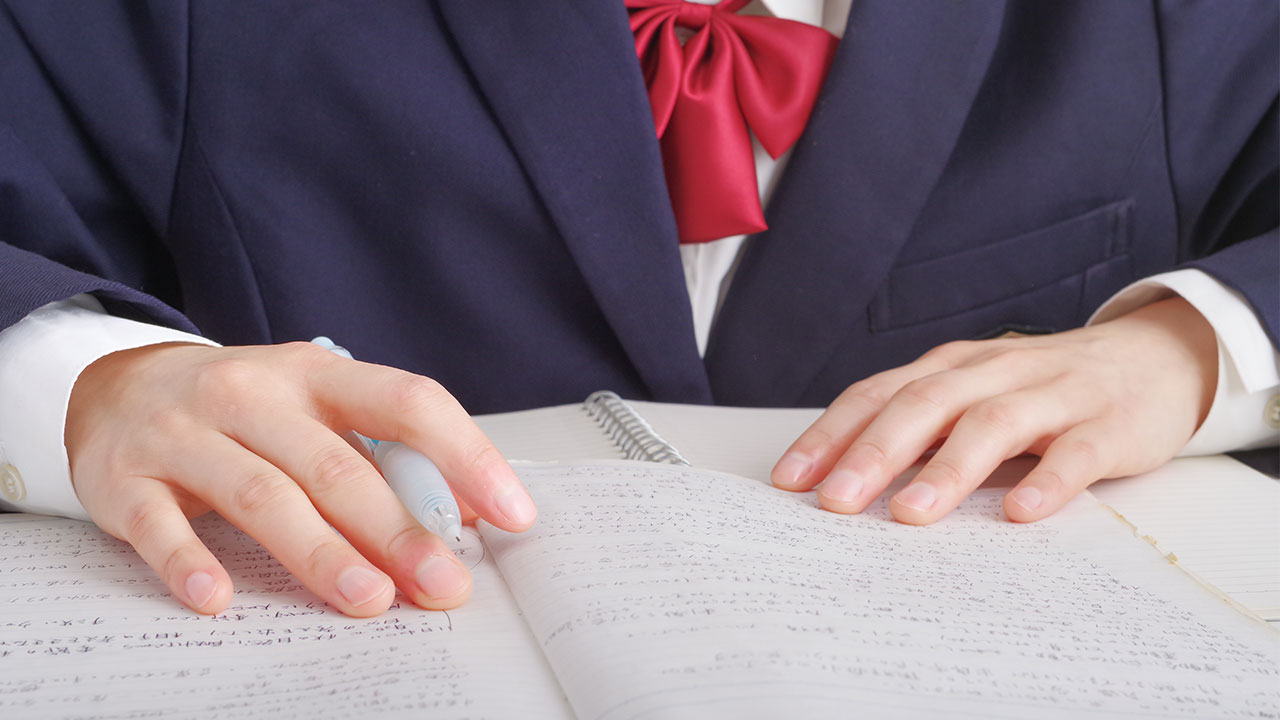
実際の事例|ストレスを乗り越えた受験生の体験談
受験ストレスは誰にでも起こりうるものですが、正しいサポートや環境づくりによって乗り越えることができます。
ここでは、実際に指導の現場で出会った生徒たちのリアルなエピソードをもとに、ストレスから立ち直った事例を紹介します。
同じような悩みを抱える受験生や保護者の方にとって、きっとヒントになるはずです。
1. 模試結果に落ち込みやる気を失った生徒のケース
中学3年生のAくんは、第一志望校を目指して頑張っていましたが、秋の模試でE判定を取ってしまいました。
結果を見た瞬間から「もう無理だ」と思い込み、勉強時間は大幅に減少。
保護者も「頑張れ」という言葉しかかけられず、さらにプレッシャーを感じさせてしまいました。
そこで指導では、まず「判定は現状を知るためのもの」という認識を伝え、次の一歩を明確にする学習計画を一緒に作成しました。
さらに、過去の小さな成功体験を振り返り、「できることは必ず増えている」という自信回復の声かけを実施しました。
少しずつ勉強への意欲を取り戻し、最終的には模試の判定がB判定まで上がり、本番で合格をつかむことができました。
2. 家族との関係悪化から回復したケース
高校2年生のBさんは、親からの「もっと勉強しなさい」という言葉に強いストレスを感じていました。
勉強しても褒められず、模試の結果が悪いと叱責される日々が続き、ついには家庭内で口をきかなくなってしまいました。
このままではストレスが限界に達すると感じたため、指導時に保護者面談を実施しました。
保護者には、「結果ではなく努力を認める声かけ」を意識してもらい、Bさんには本音を話せる場を作りました。
すると、少しずつ会話が増え、家庭の雰囲気も改善しました。
Bさんは「親に応援されている」と感じられるようになり、ストレスが和らいだことで集中力が高まりました。
最終的には志望校へのモチベーションが上がり、自分から学習計画を立てる姿勢が見られるようになりました。
3. 生活リズムを整えて集中力を取り戻したケース
浪人生のCくんは、夜型生活が続き、昼過ぎに起きて夜中に勉強するという不規則な生活習慣になっていました。
模試でも集中力が続かず、成績が伸び悩んでいたため、まずは生活リズムを整えることからスタート。
朝起きる時間を30分ずつ早め、起床後に軽い運動を取り入れるなど、段階的な改善を行いました。また、寝る前はスマホを使わず、読書やストレッチでリラックスする習慣をつけるようアドバイスしました。
最初は大変でしたが、2週間ほどで生活リズムが安定し、朝から勉強できるようになりました。その結果、集中力が向上し、模試の成績も少しずつ上昇。「やれば変われる」という達成感が自信につながり、本番に向けて前向きに取り組めるようになりました。

まとめ
受験ストレスは誰にでも起こりうるものですが、原因を理解し、日常生活の中で少しずつ対策していくことで軽減することができます。
心や体にサインが出た時は無理をせず、家族や周囲と協力しながら前向きに乗り越えていきましょう。
家庭教師のマスターでは、受験を控える生徒への学習サポートを行っています。
ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【中学受験コース】について
⇒【高校受験コース】について
⇒【大学受験コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
「ストレスがたまってつらい…」中学生のストレス発散方法をご紹介!
-
受験がつらい…と感じた時に読むコラム|心をラクにする考え方と勉強の工夫
-
「学校に行くのがつらい…」子どもが抱える悩みと親ができるサポート法とは?
-
「学校に行きたくない、疲れた」と感じる理由と解決策
-
勉強中にイライラする理由は?今すぐできる対処法と親の関わり方
-
【中学受験】なぜ差がつく?失敗する家庭・成功する家庭の決定的な違い
-
勉強に集中する方法とは?|オススメ9つの方法をご紹介!
-
高校受験の勉強って何からすればいい?|中学生の為の受験勉強ガイド
-
受験に落ちた時の切り替え方と前向きな対策とは?【高校受験編】
-
【高校受験】効率の良い受験対策・受験勉強の方法をご紹介します!
-
高校受験はいつから間に合う?|始める時期と準備について
























