不登校で昼夜逆転…親はどう向き合う?原因・対応法・相談先を解説
公開日:2025年10月27日
更新日:2025年10月27日

不登校の子どもの昼夜逆転に悩む保護者の方に向けて、原因や放置リスク、家庭でできる改善ステップ、支援先まで丁寧に解説し、「ゲームやスマホが原因?」「無理に朝型に直すべき?」といった疑問にもお答えします。実際に改善した家庭の事例も紹介しながら、親としてできることを一緒に考えていきます。
不登校の子が昼夜逆転になるのはなぜ?
不登校になると、しばしば生活リズムの乱れが見られ、その中でも「昼夜逆転」は多くの家庭が直面する問題です。
最初はたまたま夜遅くまで起きてしまっただけだったのに、気がつくと完全に昼夜逆転してしまった…というケースは珍しくありません。
この章では、昼夜逆転がなぜ起こるのかを、心理・身体・環境など多角的な視点から紐解いていきます。
1. 昼夜逆転は不登校のよくある二次症状
不登校の子どもにとって、昼夜逆転は“原因”というより“結果”として起こる二次的な問題であることが多いです。
例えば、学校に行かなくなると朝起きる必要がなくなり、夜遅くまで起きている生活が続くことで、次第にリズムが逆転していきます。
また、外との関わりが減り刺激の少ない生活になることで、昼夜の区別がつきづらくなります。
さらに、昼間は親や家族の目があり気を張ってしまう子も、夜になると気が楽になるという感覚から夜型の生活を選ぶこともあります。
2. 生活リズムが崩れるメカニズムとは?
人間の体内には「体内時計(サーカディアンリズム)」があり、これによって睡眠・覚醒のリズムが保たれています。特に朝の光を浴びることは、体内時計をリセットする大きなスイッチとなっています。
しかし、不登校で朝に起きない生活が続くと、光を浴びる機会が減り、体内時計がズレていきます。これにより、夜になっても眠気が来ず、翌日も起きられないという悪循環が生まれます。
こうした生理的なリズムの乱れが、生活全体を不規則にしてしまうのです。
3. 昼夜逆転の原因|心理・環境・身体面から考える
昼夜逆転には複数の要因が絡み合っています。
まず心理面では、「学校に行けない自分」に対する罪悪感や焦りがある一方で、それを考えずに済む夜に安心感を覚える子がいます。つまり、夜が“逃げ場”になっているのです。
環境面では、登校しないことにより朝のルーティン(起床・登校)が消えるため、時間感覚が希薄になりがちです。さらに、家庭内でも明確な生活リズムが共有されていない場合、昼夜逆転はより進みやすくなります。
身体面では、もともと睡眠障害や自律神経の乱れが背景にあることもあります。
思春期の子どもは特にホルモンバランスが不安定で、ただでさえ昼夜のバランスを崩しやすい時期にあることも理解しておくべきです。
4. ゲーム・スマホが原因とは限らない理由
昼夜逆転の原因として、よく「ゲームやスマホのやりすぎが原因では?」という声が上がります。
確かに、夜間のスマホやゲーム利用がリズムを乱す一因になっていることはありますが、それがすべての原因ではないことも多いのです。
そもそもゲームやスマホは、「何もしない時間がつらい」「誰ともつながっていないと不安」といった子どもの内面のストレスの逃げ場として機能している場合があります。表面的な行動だけに注目して制限すると、かえって不安や孤立感が強まるリスクもあるため、根本的な背景を見ていくことが大切です。
ゲーム・ネット依存の子どもへの対策についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「ゲーム・ネット依存の子どもへの家族の接し方|セルフチェックリスト付き」
5. 「甘え」ではなく、脳の機能変化が関係している場合も
昼夜逆転が続くと、周囲の大人から「だらしない」「甘えている」と捉えられてしまうこともあります。
しかし、実際には脳の働きに変化が起きているケースもあるため、単なる本人の意志の弱さとは言えません。
特に、うつ症状や発達特性のある子どもは、脳内の覚醒リズムがズレやすい傾向があります。その結果として、夜になると目が冴えてしまい、朝は極端に眠くなるという現象が起きるのです。このような場合は、医療や専門的な支援が必要になることもあるため、「叱って直す」ではなく「理解して支える」視点が欠かせません。

昼夜逆転のままでも大丈夫?|放置リスクと問題点
「昼夜逆転しているけれど、今は無理に直さなくてもいいかな…」と様子を見るご家庭も少なくありません。
確かに、無理に生活リズムを整えようとすると、かえって逆効果になることもあります。ただ、長期間の放置はさまざまなリスクをはらんでいることも事実です。
この章では、昼夜逆転を放置した場合に起こりうる問題や注意点を解説します。
1. 生活リズムが崩れたまま放置するとどうなる?
昼夜逆転が習慣化すると、体内時計が完全にズレた状態で固定されてしまいます。
一度ズレた生活リズムは、自然には元に戻りにくく、修正には数ヶ月単位の時間と工夫が必要になることもあります。
さらに、昼間に活動せず、夜に一人で過ごす時間が長くなることで孤立感が強まる傾向があります。
このような生活が長引くと、家族との関わりや社会との接点も減り、心理的な不安定さを助長してしまうリスクもあります。
2. 心身の不調(不安・抑うつ・体調不良)を引き起こすことも
昼夜逆転の生活が続くと、自律神経のバランスが乱れやすくなり、体調不良を訴えるケースも少なくありません。例えば、頭痛や胃の不調、倦怠感などの身体症状が見られるようになることもあります。
また、昼間に人と関わる機会がない状態が続くと、不安感や抑うつ状態が強くなることもあるため注意が必要です。眠れない・起きられないといった問題だけでなく、心身全体の健康が損なわれる可能性があることを、保護者として理解しておくことが大切です。
3. 昼夜逆転の影響が長期化すると復学・進路に支障も
昼夜逆転のままの生活が数ヶ月〜年単位で続くと、学校復帰のハードルが一気に上がってしまいます。
たとえ本人に「そろそろ学校に戻りたい」という気持ちが芽生えたとしても、朝に起きられない体になってしまっていることで、実際の行動に移せないというジレンマに陥るのです。
また、進学や進路選択の場面で、「昼夜逆転のままでは面接や試験に対応できない」といった現実的な壁が生じることもあります。将来的な選択肢を広げるためにも、少しずつでも生活リズムの改善をめざす意識は持っておきたいところです。
4. 「昼に起こす・無理に寝かせる」は逆効果になりやすい
昼夜逆転を直そうとして、「朝に無理やり起こす」「夜は強引に寝かせる」といった対応を取ってしまうケースもあります。
しかし、これはかえって逆効果になることが多く、子どもとの信頼関係を損なう原因にもなります。
本来眠くない時間帯に無理やり布団に入れても、眠れないことで自己嫌悪が強まり、「やっぱり自分はダメなんだ」と感じてしまうこともあります。
リズムの改善は、“命令”ではなく「小さな働きかけの積み重ね」で行う必要があります。
5. 子どもに「罪悪感」や「自己否定感」を植えつけないために
昼夜逆転の状態が続くと、子ども自身が「こんな生活じゃダメだよな…」と罪悪感を抱いていることが多いです。
そこに追い打ちをかけるように「早く起きなさい」「普通は朝起きるものだ」といった言葉をかけてしまうと、自己否定の感情を強めてしまう恐れがあります。
特に思春期の子どもは、言葉の裏にある「期待」「評価」「がっかり感」を敏感に受け取ります。親の言葉が善意であっても、子どもには「自分は受け入れられていない」と感じられることもあるのです。大切なのは、「リズムを整えたい」と子ども自身が思えるような関わり方をすることです。
昼夜逆転の治し方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「昼夜逆転の治し方|不登校、引きこもり、ゲーム・ネットのやり過ぎの子ども」
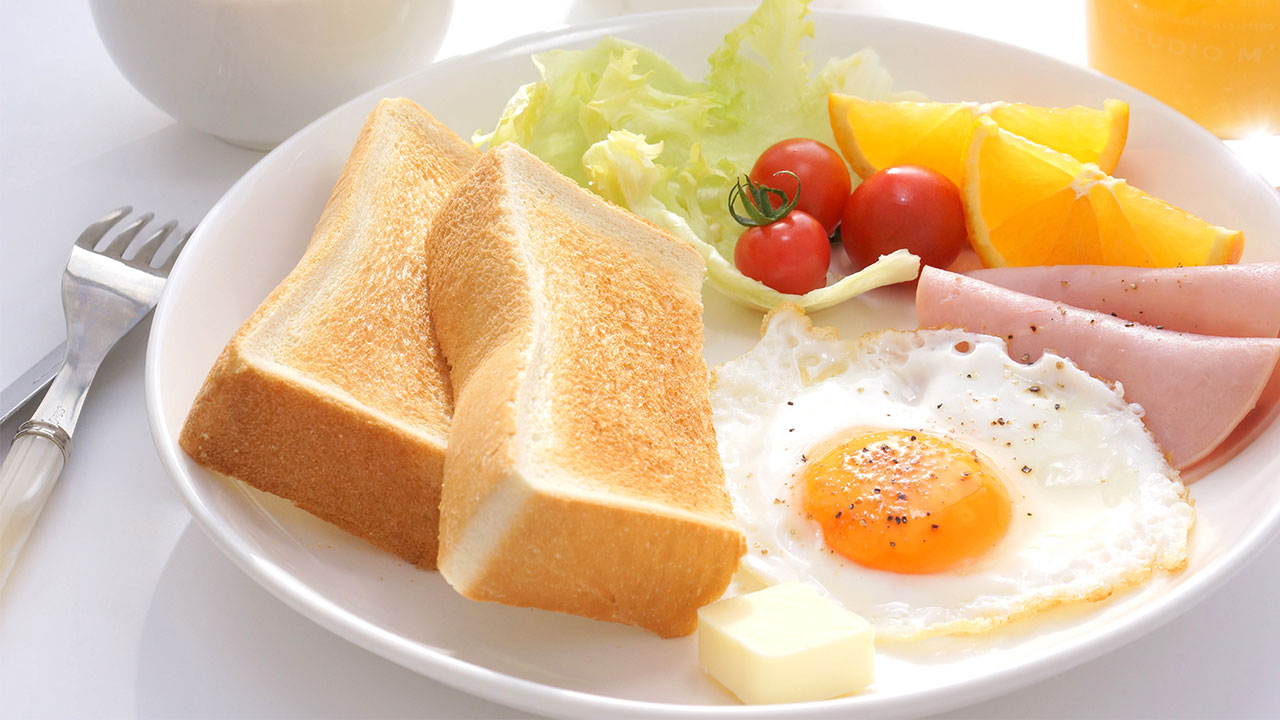
昼夜逆転の改善に向けた家庭でのステップ
昼夜逆転の生活を元に戻すには、「朝に起きなさい」と言うだけではなかなかうまくいきません。子ども自身の心と身体の状態に寄り添いながら、少しずつ生活リズムを整えていく工夫が必要です。
この章では、家庭で取り組める具体的な改善ステップを5つに分けてご紹介します。どれも無理のない範囲から始められる内容なので、焦らず、できることから実践してみてください。
ステップ 1|まずは子どもの現状を「否定せず理解」する
最初のステップは、リズムを正す前に子どもの現状をそのまま受け止めることです。
「なんで起きられないの?」「また夜更かし?」と責めるのではなく、今の状態に至った背景や気持ちに目を向ける姿勢が大切です。
本人も「このままじゃいけない」と感じていることが多く、そこに否定的な言葉を重ねると、自信や意欲がさらに下がってしまいます。
まずは「夜の方が落ち着くんだね」「今は昼に起きるのがしんどいんだね」と共感的に声をかけて、安心できる土台をつくりましょう。
ステップ 2|生活リズムを整える小さな習慣をつくる
次に意識したいのは、小さな習慣からリズムを整えていくことです。
いきなり「朝7時に起きよう」とするのではなく、「昼の12時にはカーテンを開ける」「14時には軽食を取る」といった行動のリズムを作りなおすことから始めましょう。
特に効果的なのが、「同じ時間に同じことをする」というリズムの軸を家庭内に作ることです。
決まった時間に声かけする、おやつタイムを一緒に楽しむなど、親子の関わりと時間の感覚をリンクさせていくと、自然と体内時計も安定しやすくなります。
ステップ 3|昼間に少しでも「外の刺激」を与える工夫
体内時計を整えるためには、昼間に外の光や音に触れることが不可欠です。
とはいえ、外出が難しい場合は、ベランダに出る・カーテンを開ける・窓際で本を読むなどでも十分効果があります。
また、軽い散歩や買い物への同行など、「行く・帰る」が明確な短時間の外出もおすすめです。
身体を動かし、外の空気を感じることで、脳と身体に「今は昼だ」と伝える刺激が入ります。最初は5分でも構いません。無理なく、繰り返せることを大切にしましょう。
ステップ 4|スマホ・ゲームとの付き合い方を見直す
夜型生活を支えてしまいやすいのが、深夜のスマホ・ゲーム利用です。
ただ、これらを一方的に取り上げるのではなく、「どんな時間に・どう使うか」のルールを親子で考えることが重要です。
例えば「0時以降はアラームをかけて一旦終了」「夕方以降はリビングで使う」といった環境設定の工夫が、本人の意思に頼りすぎずに行動を変える手助けになります。重要なのは、「使ってはいけない」ではなく、「どう使えば快適に暮らせるか」を一緒に考える対話です。
ステップ 5|失敗してもOK。「リズム回復」は数ヶ月単位で見る
生活リズムを整えるプロセスは、何度もつまずきながら少しずつ進むものです。「せっかく昼に起きてたのに、また夜型に戻った…」という日があっても、それは“ゼロ”に戻ったわけではありません。
むしろ、以前よりも「朝に起きようとした経験」「昼間に人と会えた日」が積み重なっていること自体が前進の証です。改善には数週間〜数ヶ月のスパンで取り組む必要があり、短期的な成否に一喜一憂しないことが大切です。
親の落ち着いた姿勢が、子どもにとって最大の支えになります。

家庭だけで難しい時は?|外部の支援や相談先を知っておこう
昼夜逆転の改善は、家庭の中だけで取り組もうとすると限界を感じてしまうこともあります。子どもの状態がなかなか変わらない時、親が焦ったり不安になったりするのは自然なことです。
そんな時こそ、外部の支援や専門家の力を借りることが、回復の大きな助けになります。ここでは、昼夜逆転を含む不登校に対応しているさまざまな相談先と、その役割をご紹介します。
1. 児童精神科・思春期外来で相談できること
昼夜逆転が長期化していたり、睡眠障害・不安感・気分の落ち込みなどが強く見られる場合は、児童精神科や思春期外来での相談を検討しましょう。
医師による診察を通じて、身体的・心理的な背景にアプローチすることができます。
必要に応じて、軽い睡眠調整の薬の処方や、専門的なカウンセリング、認知行動療法などが提案されることもあります。親子で悩みを抱え込まず、医療の力を“安心の手段”として活用することは、けっして特別なことではありません。
2. スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーとの連携
学校に籍がある場合は、スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)と連携することも有効です。彼らは、学校と家庭の“橋渡し役”として、子どもの状況に合わせた関わり方を一緒に考えてくれます。
例えば、「登校のプレッシャーはかけずに、まずは生活リズムの相談だけしたい」といった希望にも対応してくれる場合があります。
学校との関係が気まずくなっている時こそ、こうした中立的な立場の専門職の力が活きてきます。
3. 不登校支援団体やフリースクールの役割
地域や全国で活動している不登校支援団体やフリースクールも、昼夜逆転や生活の乱れへの支援に慣れた存在です。
フリースクールでは、子どものペースに合わせた柔軟な時間割を組んでくれるところも多く、朝が苦手な子でも通いやすい配慮があります。
また、団体によっては、親向けの講座や座談会、LINE相談などを行っているところもあり、保護者自身の孤立感を和らげる場にもなります。
「誰にも相談できない」と感じたときは、こうした場に一歩踏み出すことが回復への第一歩になります。
フリースクールについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「フリースクールの5つのタイプと子どもに合った選び方」
4. 家庭教師や訪問支援など、家に来てくれる選択肢もある
外に出るのが難しい時期には、家庭に来てくれる支援サービスが現実的で安心感も高いです。
特に、不登校対応に慣れた家庭教師や訪問型支援者は、子どものペースに寄り添った関わりが可能です。
勉強だけでなく、生活面の見守りや会話の中でのメンタルサポートも期待できる場合があり、「他人と関わる練習の第一歩」にもなります。
本人が「この人なら話せそと思える相手に出会えると、昼夜逆転改善のきっかけになることも多いです。
もっと知りたい方はこちら
⇒【不登校コース】について
5. 通信制・サポート校の昼夜逆転に配慮した取り組み例
中学生〜高校生の場合、将来の進路選択として通信制高校やサポート校も視野に入ってくるでしょう。
これらの学校の中には、昼夜逆転や不規則な生活リズムに理解を示し、ゆっくりと再スタートできる環境を整えているところもあります。
例えば、「夜間コース」「登校日数を選べる柔軟な制度」「オンライン主体のカリキュラム」など、生活リズムに合わせて学習を続けられる工夫がある学校も増えてきました。
「今すぐ朝型に戻す」ことにとらわれすぎず、その子の生活に合った進路を一緒に探す視点も大切です。
通信制高校についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「通信制高校とは?気になる仕組みを徹底解説!」
不登校特例校についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「学びの多様化学校(不登校特例校)で叶える多様な学びのカタチ」

昼夜逆転の改善事例|実際の家庭で起きた変化と支援の力
昼夜逆転の問題に悩む家庭は少なくありません。「うちの子は特別」「もう戻れないのでは…」と感じてしまうこともあるでしょう。
しかし、どのケースも即効性のある改善ではなく、小さな積み重ねや環境の工夫がきっかけとなって変化が始まっています。
ここでは、実際に昼夜逆転から抜け出すヒントを得られた4つの家庭の事例をご紹介します。
1. 中1男子|ゲーム依存と無気力→フリースクールで朝型生活に
中1のAくんは、小学校高学年の頃から学校生活に違和感を抱くようになり、進学後すぐに不登校に。
しばらくすると、昼夜が完全に逆転し、深夜3時頃までゲームを続ける毎日になってしまいました。そして、起こしても起きず、昼過ぎにようやく活動を始める生活が数ヶ月続きました。
保護者は「叱っても無意味」と分かっていながらも、ゲーム漬けの生活に苛立ちと不安を募らせていたそうです。そんな中、地元のフリースクールを知り、「週1回の見学だけでも」と提案したそうです。最初は嫌がっていたAくんも、「午後からなら行ってみてもいい」と承諾しました。
通い始めると、他の不登校の子どもたちとの交流や、大人に評価されない“安心できる場所”の存在が、Aくんにとって大きな転機になりました。
少しずつ生活にも変化が現れ、半年後には自ら朝9時に起きて準備をするようになり、週3回の通所が習慣化し、ゲームの時間も自然と減っていきました。
保護者さまは「無理に朝起こしてもダメだった。でも、“外に出たい理由”ができたことが大きかった」と語っています。
2. 中2女子|夜型で昼起きられず→ペットとの生活で朝に変化
中2のBさんは、思春期特有の不安定さや人間関係のストレスから学校に行けなくなり、完全な不登校になりました。
昼間は部屋から出ず、深夜にSNSや動画視聴に没頭する日々が続いていました。朝はどんなに起こしても反応せず、家族との会話も激減し、「何もやる気が起きない」「自分なんて必要ない」と口にすることもありました。
そんなある日、もともと動物好きだったBさんのために、母親が保護猫を迎えることを提案。最初は乗り気ではなかったものの、猫が家に来ると少しずつ関心を示し、自然と“お世話”を始めるようになりました。
「ご飯は朝あげないとかわいそう」「昼寝してる姿がかわいいから見ていたい」__そんな気持ちが芽生え、Bさんの中に“朝を迎える理由”が生まれたのです。
やがて朝11時頃に起き、猫と過ごすのが日課に。親との会話も増え、生活全体に温かいリズムと心の余裕が戻ってきました。
保護者さまは「子どもに必要だったのは、“叱咤”ではなく“癒し”だった」と振り返っています。
3. 小6男子|親の声かけでプレッシャー→家庭教師が“中立役”に
小6のCくんは、登校渋りが徐々に増え、不登校になったタイミングで昼夜逆転も始まりました。
お母さまは「せめて朝だけでも起きよう」と毎日声をかけていましたが、Cくんは次第にその言葉に責められているような感覚を抱くようになってしまい、次第に親子関係もギクシャクした空気が漂っていました。
転機となったのは、不登校支援に強い家庭教師の導入でした。
先生は最初から勉強の話はせず、「最近どんな時間に起きてる?」「昼に眠くならない?」と生活リズムや気持ちを対話ベースで聞き出すスタイルで接してくれたそうです。Cくんは、親には言えなかった「起きなきゃと思っても体が動かない」といった葛藤を、先生には素直に話すことができました。
お母さまは「家庭教師の先生が来るようになって、親が“無理に何とかしよう”としなくなり、Cくんの表情が柔らかくなった」とおっしゃっていました。やがて生活リズムにも少しずつ変化が出始め、午後から家庭教師との学習→午前中に起きて準備するというルーティンが定着し、家庭内にも再び穏やかな空気が流れ始めました。
4. 高1男子|不登校歴2年→昼夜逆転のまま通信制で進路確保
高1のDくんは中学3年の頃から学校に行けなくなり、そのまま高校にも進学せず、2年以上昼夜逆転の生活を続けていました。
生活リズムは深夜3時就寝、午後2時起床が習慣化。保護者も「無理に直させても逆効果だった」と感じ、見守る日々が続いていました。
高校への進路も本人が関心を持たず、「もうどうでもいい…」と投げやりな態度に__。ただ、お母さまが何気なく通信制高校のオンライン説明会を見せたところ、Dくんが「これはちょっと気になる」と反応を示しました。
その学校は登校が少ない・自分のペースで学べることが特徴で、昼夜逆転の状態からでも学びやすい仕組みが整っていました。
最初は夜中に動画授業を受け、少しずつ課題提出も進めるようになりました。次第に、「昼間の方がネットが早いから」と午前中に起きて作業する日も増え、少しずつ昼型への戻りが見え始めたとのことです。
お母さまは、「“生活を変えさせる”より、“今の状態でもできる環境”に出会えたことが一番大きかった」と話していました。完全に直すのではなく、その子の状態に合った選択肢を探すことが、本人の前向きさにつながることを教えてくれるケースです。

まとめ
昼夜逆転は、単に生活習慣の問題ではなく、子どもの心や環境と深く結びついた状態です。
無理に直そうとするよりも、まずは現状を理解し、少しずつ整える関わり方が大切です。家庭だけで難しい時は、支援先を上手に頼りながら、子どもに合ったペースで進めていきましょう。
焦らず寄り添う姿勢が、変化のきっかけになります。
家庭教師のマスターでは、不登校のお子さんの学習サポートを行っています。気になる方は気軽にご相談ください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【不登校コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
不登校になりやすい家庭の特徴|その注意点や改善策もわかりやすく解説
-
【令和5年度データ】不登校の割合はどれくらい?|小中高校別の傾向と支援の現状
-
不登校の出席扱いに?|オンライン授業で学校を出席扱いにする方法を解説
-
不登校の中学生は何をするの?|昼間の過ごし方や家でやること
-
不登校の小学生の家での過ごし方|昼間は何をさせる?
-
不登校になった女子中学生への支援策|その原因と対応方法とは?
-
不登校になっても勉強に追いつく方法|学校に行かなくても勉強はできる!
-
引きこもりと不登校の違いとは?|引きこもりになる原因を解説します
-
高校生の不登校はやばい!?|その理由と対策方法について
-
子どもが学校を休む理由とは?|理由がわからない場合の対処法も解説
-
スマホ依存症の治し方【中学生版】|セルフチェックリスト付き・家庭でできる対策とNG行動























