HSP/HSCの「あるある」を場面別に紹介|子どもへの接し方とサポート方法
公開日:2025年11月18日
更新日:2025年11月18日
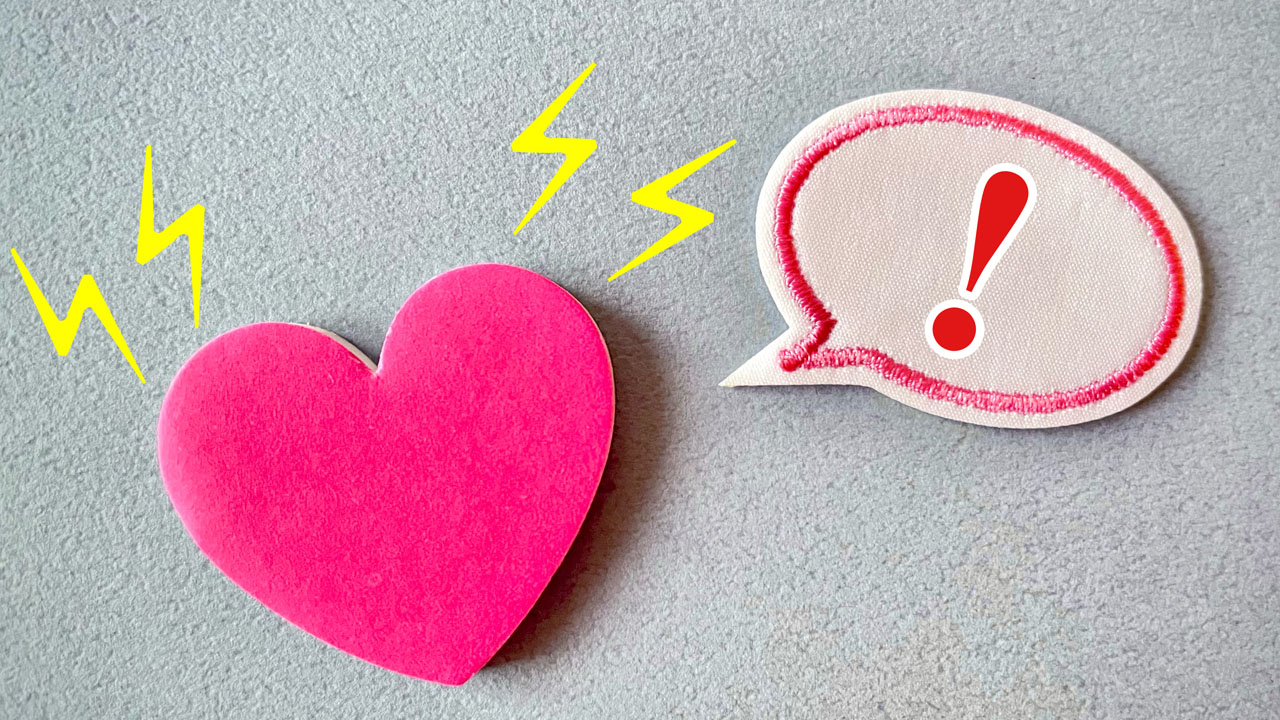
「ちょっとしたことにすぐ気づく」「人の表情に敏感で疲れやすい」そんな子どもの様子に心当たりはありませんか?
このコラムでは、HSP/HSCの子によく見られる“あるある”を家庭・学校・友達関係・部活動など身近な場面ごとに紹介し、保護者ができるサポート方法も紹介します。
HSP/HSCとは?|敏感で繊細な子どもの特徴を知ろう
「HSP」「HSC」という言葉を耳にする保護者の方は増えています。どちらも「とても敏感で繊細な気質」を指すものですが、実際には大人と子どもで呼び方が違います。
まずは両者の違いや特徴を整理しながら、「敏感さ」がどのように表れるのかを見ていきましょう。
1. HSPとHSCの違いをわかりやすく整理
「HSP(Highly Sensitive Person)」は大人を含むすべての人に使われる言葉で、生まれつき刺激に敏感な気質を持つ人を指します。
一方「HSC(Highly Sensitive Child)」は、子どもに焦点を当てた呼び方であり、学校生活や友達関係など子ども特有の場面でその敏感さが現れます。つまり、HSCはHSPの子ども版であり、呼び方が年齢によって変わると理解するとイメージしやすいでしょう。
2. 生まれつき持っている「敏感さ」という気質
HSPやHSCは病気や障害ではなく、生まれ持った気質です。
小さな音や人の表情、環境の変化などを強く感じ取りやすい特性があり、それは努力で「なくす」ことはできません。
ただし、この敏感さは「弱点」ではなく、人一倍周囲に気づける力として生きていく上で大きな意味を持つこともあります。子どものうちに「これは特性なんだ」と理解しておくことが、安心につながります。
3. 「5人に1人」とも言われるHSP気質
研究によれば、HSPの割合は人口のおよそ20%程度だとされています。つまり、5人に1人は敏感な気質を持っていると考えられています。
決して珍しいわけではなく、クラスや友達グループの中にも必ず一定数いるということです。
ただし敏感さの現れ方は人それぞれで、「大きな音に弱い子」もいれば「感情に深く共感しやすい子」もいます。同じHSP/HSCでも個性の幅がある点を理解しておくことが大切です。
4. 繊細さは「弱み」であり「強み」にもなる
HSP/HSCの子どもは、周囲の刺激を強く受け取るため疲れやすい・不安になりやすいといった弱みを抱えることがあります。
一方で、その敏感さは人の気持ちに寄り添える力や細かい変化に気づける力につながり、芸術や学問、人間関係の場面で大きな強みになることもあります。
つまり、繊細さは「短所」と「長所」の両方の顔を持っており、環境次第で輝く資質になり得るのです。
HSPの特徴についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「HSPの特徴を持つ子どもについて|セルフチェックやサポート方法も紹介」

HSP/HSCあるある【家庭編】|家の中で見られる行動や反応
HSP/HSCの子どもは、一番安心できるはずの「家庭」の中でも繊細さが強く表れることがあります。
小さなことにすぐ反応したり、家族の雰囲気を敏感に察したりする姿に、保護者は「なぜこんなに気にするのだろう?」と不思議に思うかもしれません。
ここでは家庭でよく見られる“あるある”の具体例を紹介します。
1. 小さな物音にも「誰より早く」気づいてしまう
ドアのきしむ音、冷蔵庫のモーター音、階段を上る足音__。他の家族が気づかないような小さな音にも、HSP/HSCの子どもはすぐに反応します。
例えば「夜中に家族がトイレに立っただけで目が覚める」「隣の部屋の物音に耳を澄ませてしまう」といったケースもあります。こうした過敏さは、安心して眠れない・集中できないことにつながりやすいのです。
親からすると「そんな音くらいで起きなくても…」と思うかもしれませんが、子どもにとっては身体が勝手に反応してしまう感覚に近いものなのです。決してわざと気にしているのではなく、生まれ持った特性が原因です。
2. テレビの音や家族の会話が大きいと「すぐに疲れてしまう」
リビングでテレビをつけながら家族が話していると、HSP/HSCの子どもは頭が混乱してしまい、強い疲労感を覚えることがあります。
「声が重なって聞き取れない」「頭に情報が入りすぎて処理できない」という状態になり、にぎやかな場がストレスの原因になってしまうのです。
親からすれば「にぎやかで楽しい時間」でも、子どもにとっては刺激が多すぎて心身が消耗する空間になってしまうことがあります。その結果、部屋にこもってしまったり、「静かにしてほしい」と訴えることも珍しくありません。
3. 服のタグや素材のチクチクが「どうしても気になる」
服の裏についているタグや、セーターの毛糸、制服の硬い素材など、肌に触れる刺激に敏感なのもHSP/HSCの特徴です。
「ちょっとくらい我慢して」と言われても、本人にとっては痛みや不快感に近いストレスとして感じられます。登校前に「この服は着たくない!」と泣き出す子も少なくありません。
大人から見ると「わがまま」や「神経質」に見えるかもしれませんが、実際には感覚が人より強く反応しているだけです。
衣類選びに時間がかかったり、同じ服ばかり着たがるのは、その子にとって「安心できる素材」を求めているからとも言えます。
4. 兄弟姉妹のひとことに「深く傷ついてしまう」
兄弟げんかの中での何気ないひとことや、冗談まじりの言葉でも、HSP/HSCの子どもは心に大きなダメージを受けてしまうことがあります。
「お前はドジだな」と言われただけで、“自分はダメな人間だ”と深刻に捉えてしまうのです。
兄弟姉妹にとっては軽口でも、本人の中では長く残り、寝る前に思い出して涙が出ることもあります。こうした敏感さから「兄弟の一言がトラウマになる」ことも少なくありません。
5. 家族の機嫌をすぐ察して「不安でいっぱいになる」
家族の表情や声色が少し変わるだけで、「怒っているのかな?」「自分のせいかな?」と考えてしまうのがHSP/HSCの子どもです。
他人の感情を読み取る力が強すぎるために、必要以上に不安を抱えてしまいます。
例えば、親が仕事で疲れていて少し黙っているだけでも、子どもは「何か悪いことをしたのかもしれない」と思い込んでしまいます。結果的に、家族の感情に振り回される状態になり、心が休まらないのです。
6. 寝る前にその日の出来事を思い出して「涙が出る」
一日の終わりに布団に入ると、HSP/HSCの子どもはその日にあった出来事を細かく思い出し、嫌だったことを反芻して涙を流すことがあります。
「友達に言われたひとこと」「授業での小さな失敗」など、他の子なら気にしないような出来事を、繰り返し考えてしまうのです。
これにより寝つきが悪くなったり、翌日の気持ちにまで影響が出ることもあります。親から見ると「もう忘れなさい」と言いたくなる場面ですが、本人にとっては心から離れない記憶であり、時間をかけて消化するしかないのです。
7. 突然の来客に「心がざわざわしてしまう」
予定外の来客は、HSP/HSCの子どもにとって大きなストレスになります。
親しい人であっても「どう対応したらいいのか」「部屋に入ってこないかな」と考えすぎて、安心できるはずの家が急に落ち着かない場所になってしまうのです。
例えば、親の友人が急に訪ねてきただけで、子どもが泣き出したり、自室に閉じこもってしまうこともあります。これは「人に会うのが嫌い」というよりも、突然の変化に心がついていけないために起こる反応です。

HSP/HSCあるある【学校編】|授業や行事での困りごと
学校生活は、多くの子どもにとって成長や学びの場ですが、HSP/HSCの子にとっては日常のあらゆる場面が強い刺激となることがあります。
教室の音や友達との関わり、テストや行事など、一見「普通」に見える出来事が大きな負担やストレスにつながることも少なくありません。
ここでは、学校でよく見られる“あるある”を紹介します。
1. チャイムや放送の大きな音に「体がびくっとする」
授業開始や終了を告げるチャイム、全校放送のアナウンスなど、大きな音が突然鳴る場面はHSP/HSCの子どもにとって苦手のひとつです。
体がびくっと反応して心臓がドキッとしたり、音が頭に響いてその後の授業に集中できなくなることもあります。
多くの子はすぐに気持ちを切り替えられますが、敏感な子は音の衝撃を引きずってしまうため、他の子より疲れやすいのです。
2. 先生の怒った声が「頭から離れなくなる」
授業中に先生が注意の声を上げると、たとえ自分が叱られたわけではなくても、強いショックを受けてしまうことがあります。
「怒鳴り声が耳に残って、放課後まで頭から離れない」という子もいます。
HSP/HSCの子は、声のトーンや感情のこもった言葉をそのまま体で受け止めてしまうため、心に深く刻まれてしまうのです。結果として「学校に行くとまた怒鳴り声を聞くかもしれない」と不安を抱くことにもつながります。
3. テストになると「緊張で実力を出し切れない」
テスト本番になると、頭が真っ白になったり、手が震えてしまうなど、過度の緊張で本来の力を出し切れないことがあります。
家では解ける問題でも、テスト中に「間違えたらどうしよう」という不安が先立ち、実力を発揮できないのです。
周囲の生徒が答案用紙に集中している音や、先生の歩く足音なども気になってしまい、さらに焦りが増してしまいます。
4. 体育や運動会の声援に「ぐったりしてしまう」
体育の授業や運動会などでは、歓声や応援の声が響き渡ります。多くの子はそれを励みに感じますが、HSP/HSCの子は大きな声のエネルギーに圧倒されてしまうことがあります。
「終わった後にどっと疲れてしまい、その日の授業に集中できない」ということも少なくありません。
本人にとっては「楽しくない」というよりも、刺激の強さに心身がついていけないことが大きな理由です。
5. グループ活動で「意見を言えずに苦しくなる」
授業の中で行われる班活動やグループワークは、人との関わりが密になる時間です。HSP/HSCの子どもは、周りの目や反応を気にしすぎて、自分の意見を言えずに黙り込んでしまうことがあります。
「言いたいことはあるけれど、誰かに否定されたらどうしよう」と考えすぎて、話す前に心が疲れてしまうのです。
その結果、活動中に消耗してしまい、家に帰るとぐったりしてしまう子もいます。
6. 発表の場で「顔が真っ赤になって涙が出そうになる」
授業中の発表や学年行事でのスピーチなど、人前に立つ場面では、極度の緊張を感じやすいのも特徴です。
「クラス全員が自分を見ている」と意識すると、顔が真っ赤になり、声が震え、涙ぐんでしまうこともあります。
HSP/HSCの子にとっては、発表そのものよりも「注目される状況」が強い負担になっているのです。頑張りたい気持ちと不安がせめぎ合う葛藤が、本人を苦しめることもあります。
7. 行事や遠足のあと「翌日はぐったり休みたくなる」
遠足や発表会、運動会といった学校行事は楽しい一方で、HSP/HSCの子どもにとっては大量の刺激が一度に押し寄せるイベントです。
そのため「当日は頑張って参加できても、翌日はぐったりして動けない」ということがよくあります。
「みんな楽しんでいるのに、どうしてうちの子だけ疲れるのだろう」と保護者は疑問に思うかもしれません。けれども、それは繊細さゆえに人一倍エネルギーを使っているからです。むしろ、頑張って一日を過ごした証でもあるのです。
8. 教室のざわざわに「集中が切れてイライラする」
授業中の小さな私語や、休み時間のにぎやかな声など、教室特有のざわめきもHSP/HSCの子には強い刺激になります。
「ノートに集中したいのに、周りの声が耳に入ってきてイライラしてしまう」と感じることも少なくありません。
周囲からすると「気にしすぎ」と思えるような環境音でも、敏感な子には大きな負担となり、学習効率を下げる要因になります。結果として「学校での学びが嫌になる」きっかけになる場合もあります。

HSP/HSCあるある【友達関係編】|気をつかいすぎてしまう場面
学校や家庭に続いて、子どもの成長に大きな影響を与えるのが「友達関係」です。HSP/HSCの子どもは、友達とのやり取りの中でも人一倍敏感に反応し、必要以上に気をつかってしまうことがあります。
周囲から見ると「優しい子」「気が利く子」に見えることも多いのですが、本人にとっては強い疲労やストレスを伴うことも少なくありません。
ここでは、友達関係でよく見られる“あるある”を見ていきましょう。
1. 友達の表情や声色の変化を「敏感に感じ取る」
HSP/HSCの子は、友達のちょっとした表情の変化や声のトーンにすぐに気づいてしまう傾向があります。
「怒っているのかな」「嫌われたかな」と考え込み、相手の気持ちを深読みして不安になるのです。
その結果、友達がただ疲れているだけでも「自分のせいかもしれない」と思い込み、気に病んでしまうことがあります。
2. 相手を怒らせないように「言葉を選びすぎる」
友達と会話するとき、一言で関係が壊れてしまうのではと心配して、発言に時間がかかる子もいます。
「こう言ったら気を悪くするかな」「あの子の意見を否定していないかな」と考えすぎて、自然に話せなくなるのです。
そのため、会話がぎこちなくなったり、後から「余計なことを言ったかも」と反省して疲れてしまうこともあります。
3. 仲間外れが怖くて「嫌でも合わせてしまう」
「仲間外れにされたらどうしよう」という恐怖心から、本当はやりたくない遊びや行動にも合わせてしまう子が多いです。
例えば「鬼ごっこは苦手なのに参加する」「ゲームのルールに納得できなくても黙って従う」など、自分の気持ちを後回しにしてしまいます。
その結果、友達との時間が楽しいはずなのに、心の中では消耗してしまうことがあります。
4. 友達のトラブルを「自分のことのように心配する」
友達同士がけんかしたり、落ち込んでいる姿を見ると、HSP/HSCの子どもはまるで自分が当事者のように心配します。
「どうにかしてあげたい」「仲直りしてほしい」と強く願い、必要以上に肩入れしてしまうのです。
時には、自分まで落ち込んだり、夜になっても考え続けて眠れなくなることもあります。
5. 「断れない性格」で疲れてしまう
友達から何かを頼まれると、本当は嫌でも断れないのがHSP/HSCの子どもです。
「断ったら嫌われるかも」「関係が悪くなるかも」と考え、結局引き受けてしまいます。小さな頼みごとが重なると、気づかないうちに大きな負担となり、心身の疲れが溜まっていきます。
6. 何気ないひとことを「深く考え込み落ち込む」
友達が無意識に言ったひとことが、頭から離れなくなることがあります。
「その言葉って本気だったのかな」「嫌われたサインかもしれない」と考え続けて、一人で落ち込んでしまうのです。
他の子にとっては冗談でも、敏感な子には大きな心の傷になることもあります。
7. 遊びの約束が急にキャンセルされると「大きなショックを受ける」
「楽しみにしていた遊びが急にキャンセルになった」ときの落ち込みは、HSP/HSCの子にとってとても大きなものです。
「自分と遊びたくなかったのかな」と考えてしまい、強い孤独感に襲われることもあります。
約束の変更は誰にでも起こり得ることですが、敏感な子にとっては「信頼を裏切られた」と感じるほど重く受け止めてしまうのです。
8. 大人数よりも「少人数や一対一が安心」
HSP/HSCの子どもは、大人数の集団が苦手なことが多いです。
大勢の中にいると「誰に気をつかえばいいのか」「空気を壊さないようにしなきゃ」と神経をすり減らしてしまうのです。
その一方で、一対一や少人数の関係では安心感を持ちやすいため、じっくりと関係を深めることができます。こうした環境の方が、本来の力や魅力を発揮できる場合も多いです。
友達と遊びたくない症候群についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「「友達と遊びたくない症候群」の子どもに親ができる寄り添い方と対処法」

HSP/HSCあるある【部活動・習い事編】|がんばりすぎて疲れてしまう
学校生活の中でも、部活動や習い事は子どもの成長にとって大きな経験になります。仲間との協力や達成感を得られる一方で、HSP/HSCの子どもにとってはその場の人間関係やプレッシャーが過敏に作用しやすいのも特徴です。
周囲からは「まじめで努力家」「一生懸命でえらい」と見られがちですが、本人の内面では強いストレスや疲労を抱えていることも少なくありません。
ここでは、部活動や習い事でよく見られる“あるある”を紹介します。
1. 先生やコーチのトーンに「敏感に反応してしまう」
部活動や習い事では、先生やコーチの指導の声に強く反応してしまうことがあります。注意のトーンが少し強いだけで胸がドキドキする、あるいは「怒られた」と感じて涙ぐんでしまう子もいます。
指導者からすれば「普通の声かけ」でも、HSP/HSCの子にとっては心に突き刺さるほど大きな刺激になるのです。
2. 小さなミスを「ずっと気にしてしまう」
練習や本番でのちょっとしたミスが、いつまでも頭から離れないのも特徴です。
「みんなは気にしていないのに、本人だけが“あの時の失敗”を繰り返し思い出して落ち込む」ことがあります。
そのため、新しい挑戦を前にしても「また失敗するかも」と自信を持てなくなることが少なくありません。
3. 試合や発表会の緊張で「普段通りにできない」
試合や発表会など「本番」の舞台では、HSP/HSCの子どもは人一倍強い緊張を感じます。
練習では問題なくできていたことでも、観客や審査員、先生の視線を意識すると手足が震えたり、頭が真っ白になってしまうのです。
本人は「ちゃんとやりたい」という気持ちが強い分、普段の力を出せないことに自己嫌悪を抱きやすいのも特徴です。
4. 仲間に迷惑をかけたと思って「強い自己嫌悪に陥る」
練習中にミスをして仲間の足を引っ張ったと感じると、必要以上に自分を責めてしまうことがあります。
「自分のせいで負けたらどうしよう」「みんなに嫌われるかも」と考え込み、強い自己嫌悪に陥るのです。
その気持ちが積み重なると、楽しいはずの活動が「苦しい時間」に変わってしまいます。
5. 褒められると「もっとがんばらなきゃ」と無理をする
先生や仲間に褒められると嬉しい反面、「次はもっと頑張らないと」と過剰にプレッシャーを抱えてしまいます。
「期待に応えたい」という思いが強すぎて、休むべきときにも休めず、結果的に疲れ果ててしまうのです。
6. 新しい練習や環境の変化に「強い不安を感じる」
練習メニューの変更や、練習場所の移動など、ちょっとした変化にも敏感に反応します。
「今日はいつもと違う…」「どう対応したらいいんだろう」と不安が膨らみ、練習に集中できなくなることもあります。
これは「環境に柔軟に適応するのが苦手」というより、先が見えない状況に敏感に反応してしまうために起こるものです。
7. 帰宅後「動けないくらい疲れ果てる」
部活動や習い事から帰ってくると、心身ともにエネルギーを使い果たしてしまう子が多いです。
「ご飯も食べずに寝てしまう」「何も手につかない」など、疲労が強く出るのは、活動中に常に周囲に気を配り、緊張し続けているからです。
外から見ると「元気に参加できていた」のに、家では電池が切れたようにぐったりする姿に、保護者が驚くこともあるでしょう。
8. 途中で「もう続けられない」と思ってしまう
心身の疲れが積み重なると、活動そのものを「続けられない」と感じることがあります。
「楽しいはずなのに、緊張や不安でつらい」「このまま頑張り続けるのは無理」と思い詰めてしまうのです。
このとき、周囲から「根性がない」と言われるとさらに追い込まれ、自己否定感が強まる原因になります。
9. 周りよりも長く練習しようとして「自分を追い込みすぎる」
HSP/HSCの子どもは、真面目さゆえに「もっと頑張らなきゃ」と感じやすく、自主的に練習を増やしてしまうことがあります。
「みんなよりできないと嫌われるかも」「迷惑をかけたくない」という思いから、必要以上に自分を追い込んでしまうのです。
結果的に、疲労やストレスで逆に力を発揮できなくなるという悪循環に陥ることも少なくありません。

HSP/HSCの子をどう支える? |保護者にできるサポート方法
ここまで紹介してきたように、HSP/HSCの子どもは家庭・学校・友達関係・部活動など、日常のあらゆる場面で敏感さを抱えています。
親としては「どうすれば子どもが少しでも楽に過ごせるのか」と悩むことも多いでしょう。大切なのは、「繊細さを否定せず、その子の個性として受け止めること」です。
ここでは保護者ができる具体的なサポート方法を紹介します。
1. 安心して過ごせる環境を整える
HSP/HSCの子にとって、まず大事なのは安心感のある居場所です。
家の中では大きな音を避けたり、落ち着ける部屋を用意したりといった工夫が役立ちます。
例えば「勉強は自分のペースでできる静かなスペース」「好きな物に囲まれてリラックスできるコーナー」など、心が休まる環境づくりを意識しましょう。
2. 無理に「慣れさせよう」としない
「たくさん経験すれば慣れるはず」と思ってしまいがちですが、HSP/HSCの子にとっては逆効果になることがあります。
強い刺激に繰り返しさらされると、不安や恐怖が積み重なってしまうことがあるのです。
必要なのは「避けさせる」ことではなく、本人のペースで少しずつ挑戦できる機会を作ることです。保護者が「無理に慣れさせるのではない」という姿勢を持つだけで、子どもは安心できます。
3. 気持ちを受け止めて「共感する」
「そんなことで泣かなくてもいいのに」「気にしすぎ」と否定してしまうと、子どもは自分の感じ方を信じられなくなることがあります。
大切なのは「そう感じるのは自然なことだよ」と伝え、気持ちに共感する姿勢を見せることです。
例えば「大きな音でびっくりしたんだね」「その言葉が嫌だったんだね」と言葉にしてあげると、子どもは「わかってもらえた」と安心し、心の回復が早くなります。
4. 一人の時間や休息を大切にする
HSP/HSCの子どもは人一倍刺激を受けやすいので、日常的に休息とクールダウンの時間が欠かせません。
友達や家族と過ごすことが嫌なのではなく、一人で心を整理する時間が必要なのです。
「一人で絵を描く」「静かに本を読む」「お気に入りの音楽を聴く」など、落ち着ける習慣を持つことはエネルギーを回復するためにとても重要です。
5. 学校や習い事の先生に理解をお願いする
家庭で支えるだけでなく、学校や習い事でも周囲の理解を得ることが不可欠です。
「大きな音や怒鳴り声に敏感です」「行事のあとに疲れが出やすいです」といった情報を先生やコーチに伝えておくと、配慮をしてもらえることがあります。
保護者が橋渡し役となり、安心して過ごせる環境を一緒に作ることが子どもの安定につながります。

まとめ
HSP/HSCの子どもは、家庭や学校、友達関係や部活動など、あらゆる場面で敏感さゆえの生きづらさを感じやすい一方で、その繊細さは人一倍の思いやりや豊かな感受性につながる大切な個性でもあります。
大切なのは「気にしすぎ」と否定するのではなく、その子らしさを受け止め、安心できる環境と理解を用意することです。
保護者の共感とサポートがあれば、繊細さは弱みではなく「強み」として輝いていきます。
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
HSPの特徴を持つ子どもについて|セルフチェックやサポート方法も紹介
-
子どもの人見知りを治すには?|原因・年齢別対応・家庭でできる克服法を紹介
-
起立性調節障害なのに、なぜ遊びには行けるのか?|理由や症状を詳しく解説
-
母子分離不安は母親のせい?|原因と対応策について解説
-
【なぜ母親にだけ反抗する?】反抗挑戦性障害(ODD)の子どもとの接し方・改善策
-
「友達と遊びたくない症候群」の子どもに親ができる寄り添い方と対処法
-
「学校に行きたくない、疲れた」と感じる理由と解決策
-
集団行動が苦手な子どもについて|心理的背景や効果的な対応方法とは?
-
不登校になりやすい家庭の特徴|その注意点や改善策もわかりやすく解説
-
不登校になる子とならない子の違いとは?|それぞれの特徴を解説
























