大学受験の一般入試に調査書は関係ある?|合否への影響を徹底解説
公開日:2025年7月29日
更新日:2025年7月29日
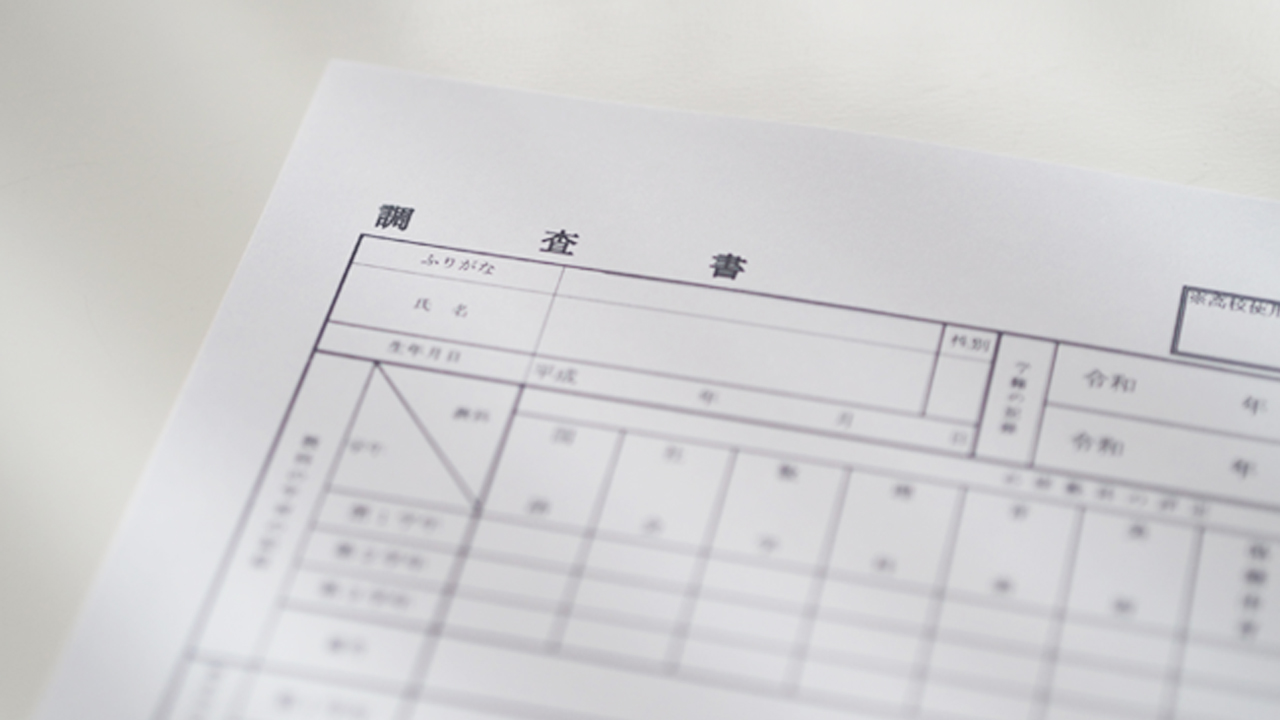
大学受験の一般入試で提出が求められる「調査書」。実際に合否に影響はあるのでしょうか?
このコラムでは、調査書の役割、取得方法、影響の程度、内申点を上げる工夫まで、大学受験に役立つ情報をわかりやすく解説します。
大学の一般入試に調査書は関係ある?|気になる合否への影響を整理しよう
「大学受験の一般入試に調査書は関係あるの?」という疑問を抱く高校生や保護者は少なくありません。
推薦入試では大きな意味を持つイメージがある一方で、一般入試では試験の点数が合否を左右するという印象が強いですよね。
実際、一般入試における調査書の扱いは大学によって異なります。
ここでは、調査書がどのような役割を果たすのか、合否にどの程度影響するのかについて、整理して解説していきます。
1. 【結論】多くの大学では合否に影響しないとされている
まず結論から言えば、「大学の一般入試において調査書が合否に大きな影響を与えるケースは少ない」とされています。
一般入試では、原則として学力試験(筆記試験)や面接などの試験成績が重視されるため、調査書は形式的に提出を求められるだけの大学が大半です。
実際、各大学の入試要項などにも「調査書は参考程度に閲覧する」「必要に応じて利用する」といった表現が多く見られます。例えば、早稲田大学では、調査書を「参考資料」として活用する旨が明記されています。
そのため、評定平均や欠席日数、活動記録が直接的に合否に直結することは、ほとんどないと考えてよいでしょう。
2. 調査書の提出が求められる理由
では、合否にほとんど影響しないにもかかわらず、なぜ多くの大学で調査書の提出が必須とされているのでしょうか?
主な理由の一つは、「入試の形式を問わず、出願者の基本情報を大学側が把握するため」です。
調査書には、学力以外にも出欠状況・活動記録・生活態度などの学校生活に関する情報が記載されており、受験生の人柄や校内での様子を知るための補足資料として用いられます。
また、大学側としては、入学後に重大な問題行動が生じるリスクの有無を最低限確認する必要があります。例えば、著しく多い欠席や停学・退学処分の履歴などがあれば、面接時の判断材料とされることもあります。
このように、調査書は合否判断の主要材料ではなく、「出願者情報の確認」や「大学のリスク管理」の観点から提出が求められているのです。
3. 一部の大学・学部では調査書が評価対象になるケースもある
ただし、すべての大学・すべての学部で「完全に関係ない」とは言い切れません。
一部の大学では、学力試験が同点だった場合の判定材料として調査書を利用すると明記している場合があります。
また、筑波大学のような国公立大学を中心に「調査書を点数化し、一定の割合で合否に加味する」としている学部も存在します。例えば、医療系や教育系など、「人物評価」を重視する学部では、出席状況や活動実績、評定平均などが加点の対象になることがあるのです。
このように、大学や学部の方針によっては調査書が一定の評価対象になるケースもあるため、志望校の入試要項は必ず確認しておく必要があります。
4. 合否判断で実際に重視される要素|学力試験や面接
一般入試では、基本的に学力試験の得点が合否を決定づける最重要の評価項目です。
大学入学共通テスト(旧・センター試験)や大学独自の筆記試験、小論文、面接などの得点が合計され、その順位によって合格者が決まります。
一部の大学では、面接や小論文を含めた「総合評価型」の選抜も行われますが、それでも学力試験の配点が圧倒的に高く設定されていることがほとんどです。
このように、調査書の情報はあくまで“補助的な要素”として見られるに過ぎず、得点源にはならないケースが一般的です。
5. 調査書をどこまで意識するべきか?
結論として、一般入試をメインで受験する受験生にとっては、調査書を過度に気にする必要はありません。普段の授業態度や内申点を気にしすぎて、本来力を入れるべき筆記試験対策が疎かになってしまっては本末転倒です。
ただし、調査書が点数化される国公立大学や学部を志望する場合は、ある程度意識して学校生活を送ることが重要です。
特に以下の点に注意しましょう:
・欠席日数が極端に多くならないようにする
・提出物や授業態度に注意を払う
・評定平均(成績)が大きく低下しないよう努める
また、志望校の最新の入試要項を確認し、調査書が評価対象かどうかを把握しておくことが大切です。必要に応じて、調査書の内容について担任の先生に事前に相談しておくのも有効です。
冷静に情報を精査し、過不足のない対策を取ることが受験成功のカギとなります。

そもそも調査書って何?|仕組みと内容をやさしく解説
大学受験の出願書類として「調査書」が求められることは多いですが、そもそもどんな内容が書かれていて、誰が作成しているのか、具体的に理解している人は意外と少ないかもしれません。
このセクションでは、調査書の構成や作成ルール、推薦入試との違い、高校による差などをわかりやすく解説していきます。調査書の役割を正しく理解することで、受験対策に対する意識の持ち方も変わってくるはずです。
1. 調査書に書かれる主な項目(成績・出欠・活動・特記事項)
調査書には、以下のような項目が記載されます。
これは文部科学省が定める全国共通の書式に基づいており、高校3年間の学校生活を総合的に記録した「公的な書類」となっています。
調査書には、以下のような項目が記載されます。
これは文部科学省が定める全国共通の書式に基づいており、高校3年間の学校生活を総合的に記録した「公的な書類」となっています。
| 学習成績の状況 (評定平均) | 高校1年〜3年までの各教科の評価が記載され、平均値が「評定平均」として算出されます。 |
|---|---|
| 出欠の記録 | 各学年ごとの欠席・遅刻・早退の日数が記載されます。 長期欠席には理由の記載もされる場合があります。 |
| 行動の記録・特別活動等 | 授業態度、生活面の様子、部活動、生徒会活動、ボランティア活動など、定性的な記述も含まれます。 |
| 総合所見 | 担任や進路担当の先生が、本人の努力や成長、人柄などについて文章で評価します。 |
このように、調査書は単なる「成績表」ではなく、学校生活全体の記録として、大学等の受験先に提出されます。
参照:文部科学省「令和8年度大学入学者選抜実施要項について(通知)」
2. 調査書の作成者と評価の基準は?
調査書は、原則として在籍している(または在籍していた)高校が作成する公式文書であり、主に担任の教員や進路指導部の教員が担当します。
評定(成績)の評価基準
文部科学省が定める指導要領に従って、以下の要素を総合的に評価して決定されます。
・定期テストの得点
・授業への取り組み姿勢
・提出物や小テストの結果
・課題レポートや観察記録など
これらを基に、各教科ごとに5段階の評定が付けられます(原則、絶対評価)。
出欠・活動記録の作成方法
・出欠の記録は、学校が日々の出席簿をもとに学校が正確に記録します。
・部活動や生徒会、ボランティア活動などの特別活動も、生徒からの活動報告や指導教員の記録に基づいて記載されます。
総合所見の記述方法
・総合所見は、担任教員が中心となり、学年団・関係教員と情報を共有したうえで作成します。
・生徒の努力、成長、人柄などを、客観的な観察と記録に基づいて記述するのが原則です。
このように、調査書の内容は個人の印象や主観ではなく、学校としての公式記録と基準に基づいて作成される文書です。
当然ながら、生徒本人が内容を修正・変更することはできません。
3. 推薦・総合型と一般入試での調査書の扱いの違い
一般入試では、調査書は基本的に「補足資料」としての扱いにとどまります。
一方で、推薦入試(学校推薦型選抜)や総合型選抜(旧AO入試)では、調査書の重要度が格段に上がります。
推薦・総合型では、調査書に記載された内容がそのまま人物評価の基準や出願条件の一部として使われることが多いため、以下のようなポイントがより重視されます。
評定平均が出願条件になる
・多くの大学で、「評定平均が4.0以上」などの基準を満たしていなければ出願できない場合がある
・出願時点の評定平均(1年~3年次の成績の平均)で足切りが行われる場合もあります
欠席・活動実績も評価対象
・無遅刻・無欠席、ボランティアや委員会活動、部活動での役職歴などが、人物評価や主体性のアピール材料として高く評価されます。
・特別活動の記録や行動の記録欄が、面接時の質問内容の参考になるケースも多く見られます。
総合所見の内容が合否に影響することもある
・担任による総合所見は、面接や志望理由書とあわせて読まれ、志望動機や人間性を評価する材料になります。
・記述内容の一貫性や人物像の裏付けとして、提出書類との整合性も見られることがあります。
そのため、推薦・総合型を志望する場合は、1年次からの学校生活全体を意識して過ごす必要があり、一般入試とは準備の軸が異なります。
成績・出席・活動・所見の4つが一体で評価されるという意識を持つことが重要です。
4. 高校ごとの調査書の違いに注意しよう
調査書は全国共通のフォーマットに沿って作成されるものの、細かい内容や記述の分量、所見の書き方などは高校ごとに差が出ることがあります。
例えば、
・活動歴の記録が詳細な学校と、あっさりとした学校
・総合所見を具体的に記述する学校と、定型文中心の学校
・評定の付け方が厳しい/緩いなどの学校風土の違い
等があり、こうした違いは、特に推薦入試や総合型選抜を考えている人にとっては重要です。
もちろん、大学側もある程度は高校ごとの傾向を把握してはいますが、受験生自身が「自分の高校ではどう書かれるのか?」を把握しておくことで、戦略的に受験方式を選ぶ判断材料にもなります。
必要に応じて、担任の先生に調査書の内容や評定の付け方について相談してみるとよいでしょう。

調査書のもらい方は?|在校生・卒業生のケース別に解説
大学受験では、出願書類として調査書の提出が求められることがほとんどです。調査書は自分で作成するものではなく、高校に申請して発行してもらう必要がありますが、その流れや注意点は、在校生と卒業生で少し異なります。
このセクションでは、調査書の取得方法についてケース別に解説するとともに、トラブルを防ぐための準備や注意点についても紹介します。
1. 在校生が調査書をもらう手順と注意点
在校生の場合、調査書の申請から受け取りまでの流れは、学校内の進路指導室や担任の先生を通じて行われます。
一般的な手順は以下の通りです。
1)担任または進路指導の先生に申請の意思を伝える
2)指定の申請書に必要事項を記入する(宛先・提出日・部数など)
3)学校が発行し、数日後に受け取り(封筒入りで厳封される)
注意点としては、
・出願日よりも早めに申請すること(1週間以上前が望ましい)
・受け取り後は封筒を開けないこと(開封無効となる大学が多い)
・必要な部数を事前に確認しておくこと(併願校が多い場合は複数部必要)
高校によってルールや所要日数が異なるため、早めに担任に相談し、学校の流れを確認しておくことが大切です。
2. 卒業生が調査書をもらう手順と注意点
卒業生の場合は、すでに高校を離れているため、直接学校に連絡して申請する必要があります。
申請の一般的な流れは次の通りです。
1)まずは高校の事務室または進路指導部に電話で連絡する
2)卒業年度・氏名・用途・必要部数などを伝え、申請方法を確認する
3)郵送・窓口どちらで受け取るかを選び、必要書類(身分証・申請書)を提出
4)発行後、指定の方法で受け取る(郵送の場合は返信用封筒が必要)
注意点としては、
・学校によっては事前予約が必要だったり、発行に日数がかかる場合があります
・卒業後5年以上経過していると発行不可になるケースもあるので、確認が必要です
・郵送申請の場合は切手・封筒・身分証のコピーなどを同封する指示が出ることが多いため、対応を誤らないようにしましょう
在校生と比べ、手続きがやや煩雑になるため、早めに準備しておくと安心です。
3. 発行にかかる期間・費用・有効期限
調査書の発行には、通常3〜5日程度かかることが多いですが、進路希望者が多い時期(10〜1月頃)には1週間以上かかることもあります。
また、発行には学校ごとに手数料(1通数百円)がかかることもあります。無料で発行してくれる学校もありますが、卒業生の場合は有料が一般的です。
有効期限については、多くの大学では「発行から3か月以内」や「出願日からさかのぼって○か月以内」の調査書を求めています。古い調査書では受理されない可能性があるため、出願前になるべく最新のものを発行してもらうことが重要です。
4. トラブルを防ぐためのポイント(早めの申請・複数部取得など)
調査書の申請では、以下のようなトラブルが起こることがあります。
・申請が遅れて出願に間に合わない
・必要部数を間違えて追加申請が必要になる
・郵送手配が不十分で調査書が届かない
・厳封済みの封筒を開けてしまい無効になる
これらを防ぐためには、
・願書締切の2週間前には申請を済ませる
・あらかじめ多めの部数を申請しておく(予備含めて)
・提出形式(郵送/持参)や大学ごとの指定条件を確認しておく
といった準備が有効です。
特に併願校が多い受験生や、卒業後に再受験を目指す方は、早め早めの行動が大切になります。
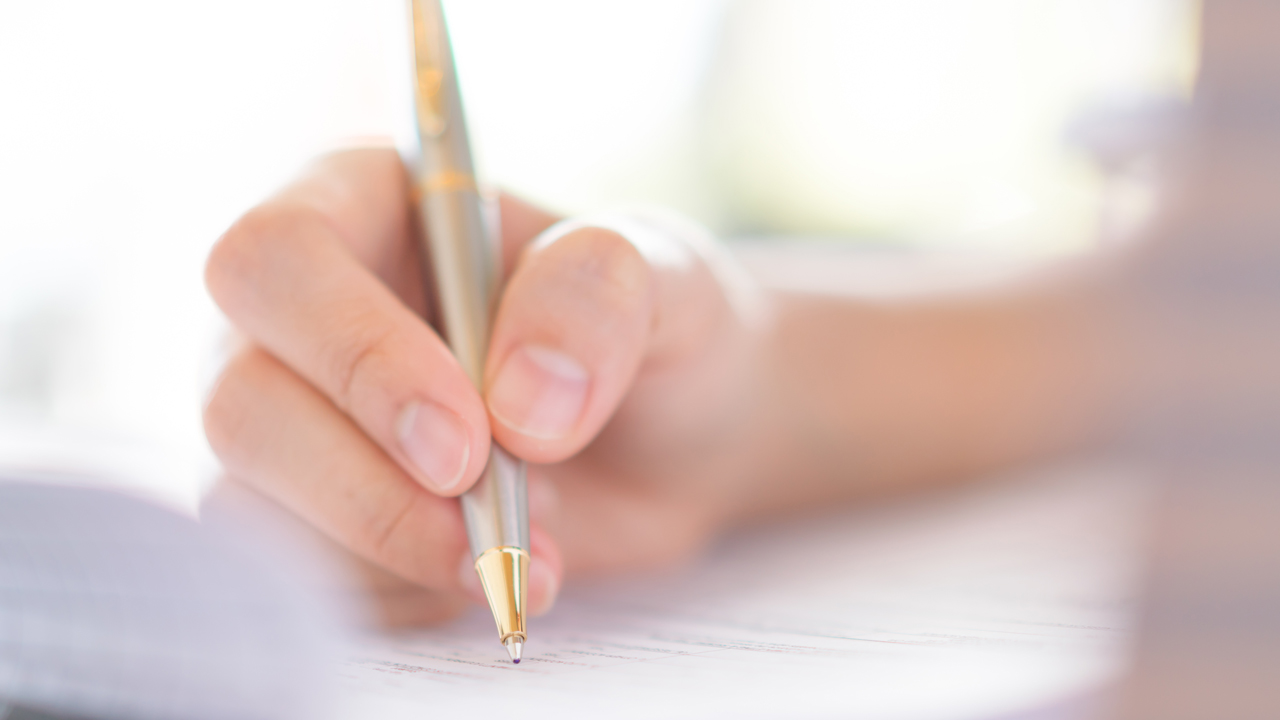
推薦入試や総合型選抜も視野に入れる場合|内申点を上げるための行動とは
一般入試ではあまり重視されない調査書ですが、推薦入試(学校推薦型選抜)や総合型選抜では、調査書が合否を左右する重要な評価資料となります。
特に評定平均(内申点)は、出願資格の条件になることもあり、普段の学校生活の積み重ねが結果に直結します。
このセクションでは、調査書の内容をより良くするために、高校生活の中でできる具体的な取り組みを5つ紹介します。推薦・総合型を少しでも視野に入れている人は、ぜひ早いうちから意識しておきましょう。
1. 授業態度や提出物を丁寧にする
評定(いわゆる内申点)は、定期テストの点数だけでなく、授業中の態度や課題への取り組みも含めた「総合的な評価」によって決定されます。
これは文部科学省の「観点別評価」に基づく指導要録記載要領にも明記されており、テストだけ頑張れば良いというものではありません。
・授業中の発言や集中力
・ノートの取り方や提出物の期限遵守
・小テストや課題への取り組み姿勢
など、日常の行動が先生にしっかりと見られており、記録にも残されます。
毎回の授業を「成績につながる機会」と捉え、丁寧かつ真剣に取り組むことが、内申アップの第一歩と言えるでしょう。
参照:文部科学省「〔別紙3〕高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等」
2. 定期テストの成績を安定させる
定期テストの得点は、評定(内申点)を決定する上で最も重視される要素の一つです。
特に、推薦入試(学校推薦型選抜)や総合型選抜では、「評定平均が4.0以上」「4.3以上」といった出願条件を課す大学が多く、全教科で安定した成績を取ることが求められます。
安定した成績を取るためのポイント
・苦手科目も放置せず、早めに補強・復習をする
・テスト前に計画的な学習スケジュールを立てる習慣をつける
・ケアレスミスや提出忘れなどで減点されないように注意する
定期テストの点数は、努力の積み重ねで改善できる要素です。
少しずつでも平均点を上げていくことを目指しましょう。
効果的なテスト勉強の方法についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「効果的なテスト勉強の仕方とは?|具体的なやり方を科目別に徹底解説」
3. 欠席・遅刻を減らす工夫をする
調査書には、欠席・遅刻・早退の回数が正確に記録され、大学側にもそのまま提出されます。
特に、推薦入試や総合型選抜では、出席状況が「自己管理力」や「継続力」の指標として見られるため、無断欠席や遅刻が多いとマイナス評価につながることもあります。
体調管理や生活習慣の改善を意識し、
・就寝・起床の時間を安定させる
・朝が弱い場合はサポート策を家庭で整える
・記録が残ることを意識し、正当な理由がある場合は必ず連絡・証明を残す
といった対策が有効です。“当たり前のことを当たり前に続ける”ことが、確実な評価につながります。
4. 部活動や学校行事に積極的に参加する
調査書には、部活動・生徒会・学校行事・ボランティア活動などの参加実績も記録されます。
特に、推薦入試や総合型選抜では「人物評価」や「主体性・協調性・継続力」の判断材料として、これらの活動が重要な役割を果たします。
調査書に記載される具体的な内容
・どの学年で、どのような活動に取り組んでいたか(例:部活動、委員会、生徒会)
・部長や実行委員などのリーダー経験、表彰歴
・校外での活動(地域ボランティア、資格取得、コンテスト参加等)も、学校に報告していれば記載される場合あり
これらの活動実績は、「特筆すべき事項」として総合所見や活動欄に反映される可能性が高く、単なる付加情報ではなく、評価対象の一部となっています。
重視されるのは「実績」よりも「取り組む姿勢」
・表彰歴や大会成績だけでなく、継続して取り組んだ熱意や、チームやクラスへの貢献も重要視されます。
・実績を誇示することではなく、誠実に取り組んだ経験が、調査書の中で人物像としてにじみ出ることが大切です。
5. 先生とのコミュニケーションを大切にする
調査書の「所見欄」は、担任の先生が本人の人物像や学校生活の様子を記述する欄です。
ここでは、学力だけでなく人柄・態度・成長の様子などが評価されるため、普段からの信頼関係が非常に重要になります。
・授業後に質問に行く、相談するなどの積極性
・指示や連絡を丁寧に受け取る姿勢
・問題があったときに誠実に対応する態度
これらの積み重ねが、先生からの好印象につながります。
「推薦に向けて準備している」ことを早めに共有しておくことも効果的です。
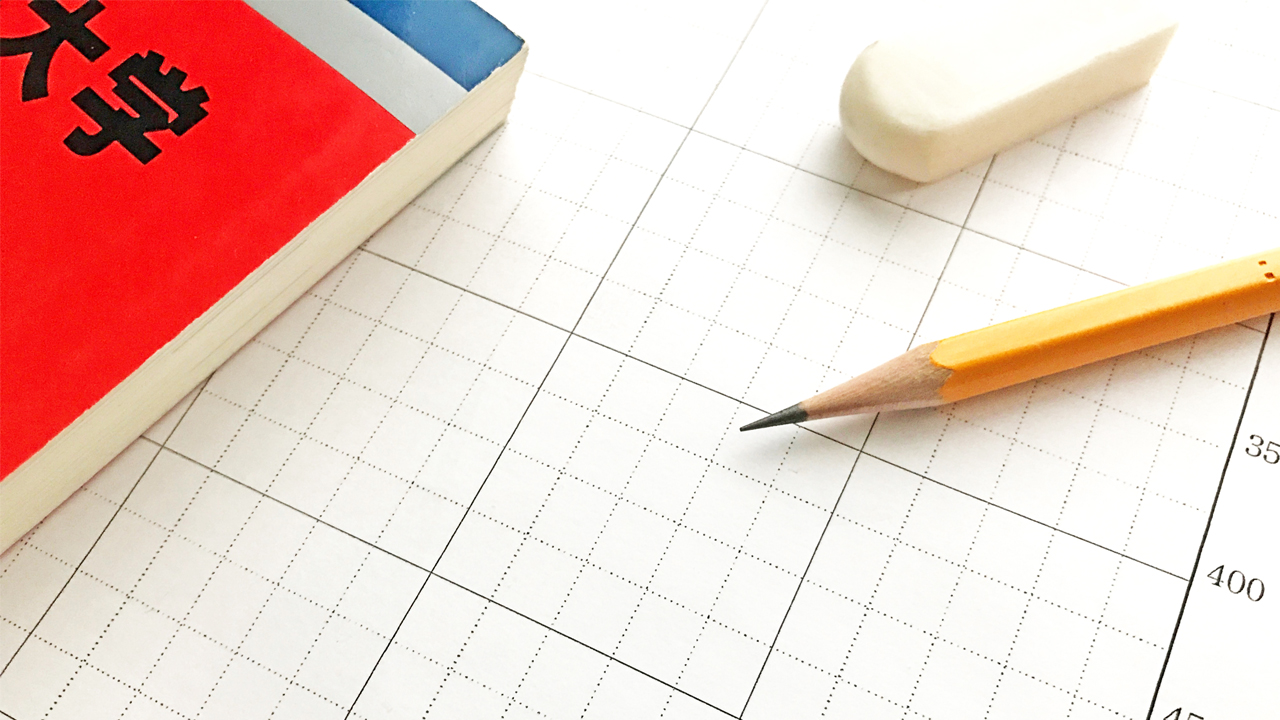
まとめ
今回は「大学の一般入試に調査書は影響するのか」について書いてきました。
大学の一般入試では、調査書の提出は求められても、合否への影響はほとんどないのが一般的です。
ただし、一部の大学・学部では例外もあるため、志望校の方針を事前に確認しておくことが大切です。また、推薦入試や総合型選抜を視野に入れる場合は、普段の学校生活の積み重ねが調査書の評価につながります。
目的に応じて、調査書との向き合い方を整理しておきましょう。
家庭教師のマスターでは、大学受験を目指す生徒さんへの学習サポートを行っています。
ご興味のある方は気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【大学受験コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
【高校生必見】共通テストとセンター試験の違いは?|変更点を徹底解説!
-
大学受験の勉強時間はどれくらい?|学年別の目安と時間のつくり方
-
大学受験にかかる費用は!?|受験料やその他の費用まで徹底解説!
-
大学オープンキャンパスの服装はどうする?|制服・私服どっちが正解?
-
大学受験のために塾・予備校に行くべきか?|それぞれの違いと選ぶ基準を解説!
-
公募推薦で合格する人の共通点とは?|受かるための準備・対策も解説
-
学校推薦型選抜に落ちる確率は?|落ちる確率を下げる方法も解説!
-
大学指定校推薦の仕組み|校内選考の基準や対策を解説!
-
指定校推薦で落ちた例はある??|落ちる理由や対策を解説!
-
自己推薦入試とは?|他の推薦入試との違いや、合格の秘訣を徹底解説























