ASDの子どもが苦手としやすいこと|理由とサポート方法を解説
公開日:2025年10月6日
更新日:2025年10月6日

このコラムでは、ASDの子どもが苦手になりやすい場面をわかりやすく解説します。曖昧な指示や予定変更への対応、感覚過敏などの背景と、家庭や学校でできるサポート方法を紹介します。
日常の関わり方を見直すヒントを知りたい保護者の方に役立つ内容です。
ASDの子どもが苦手になりやすい主な場面
ASDの子どもには、生活や学習の中で「つまずきやすい場面」がいくつかあります。これらは単なる性格の問題ではなく、脳の特性や感覚の違いから生じるものです。
ここでは、保護者の方が特に気づきやすい5つの場面について詳しく見ていきましょう。
1. 曖昧な会話や「空気を読む」場面が難しい
家庭で「ちょっと待っててね」と伝えた時、子どもが「何分待てばいいの?」と真剣に聞き返してくることがあります。これは、曖昧な言葉や比喩表現を理解するのが難しいためです。また、「空気を読む」という感覚的な判断が苦手なため、場の雰囲気に合わせた行動が取りづらいこともあります。その結果、周囲とのズレが起こりやすく、誤解を招いてしまうことも少なくありません。
2. 急な予定変更や環境の変化への対応
ASDの子どもは、例えば「今日はスーパーに寄ってから帰ろう」と急に予定を変えると、パニックになって泣き出すようなこともあります。ASDの子どもは見通しのなさに強い不安を感じやすいため、スケジュールの変更が大きなストレスになるのです。環境の変化にも敏感で、教室の座席移動や担任の先生の交代といった出来事でも、強い動揺を示すことがあります。このような反応は「融通がきかない」わけではなく、安心が失われる可能性があることへの拒否反応なのです。
3. 得意・不得意の差が極端に出る学習や生活
ASDの子どもは、ある分野では驚くほどの集中力を発揮する一方で、別の分野ではほとんど手をつけられないことがあります。例えば、算数の図形問題は得意でも、文章を読み解く国語には強い苦手意識を持つといったケースです。この「凸凹の学習スタイル」は、保護者や教師が「なぜこれだけできるのに、こっちは全然できないの?」と感じやすい部分です。しかし、これは能力の問題ではなく、脳が情報を処理する方法の違いによるものです。
4. 感覚過敏による音・光・触覚への反応
掃除機の音に耳をふさいで部屋から逃げたり、蛍光灯の光を「まぶしすぎる」と訴えるなど、ASDの子どもには感覚過敏が見られることがあります。これは、音・光・触覚といった刺激を過剰に受け取ってしまう脳の特性が関係しています。
他の人にとっては気にならない小さな音や衣服のタグのチクチク感でも、子どもにとっては耐えがたいストレスになることがあります。その結果、落ち着きを失ったり、学校生活に支障をきたすこともあります。
5. 人間関係や友達づきあいでのつまずき
ASDの子どもは、友達との遊びの中でルールを守りすぎてしまい「融通がきかない」と誤解されたり、冗談を真に受けて人間関係のトラブルになることがあります。ASDの子どもは「表情」や「その場の空気」を読み取るのが難しく、会話のキャッチボールにズレが生じやすいのです。
その結果、「友達と一緒にいると疲れる」「グループに入れない」と感じ、孤立感を強めてしまうこともあります。
人間関係でのつまずきは、自己肯定感の低下にもつながりやすいため、早めの理解とサポートが大切です。
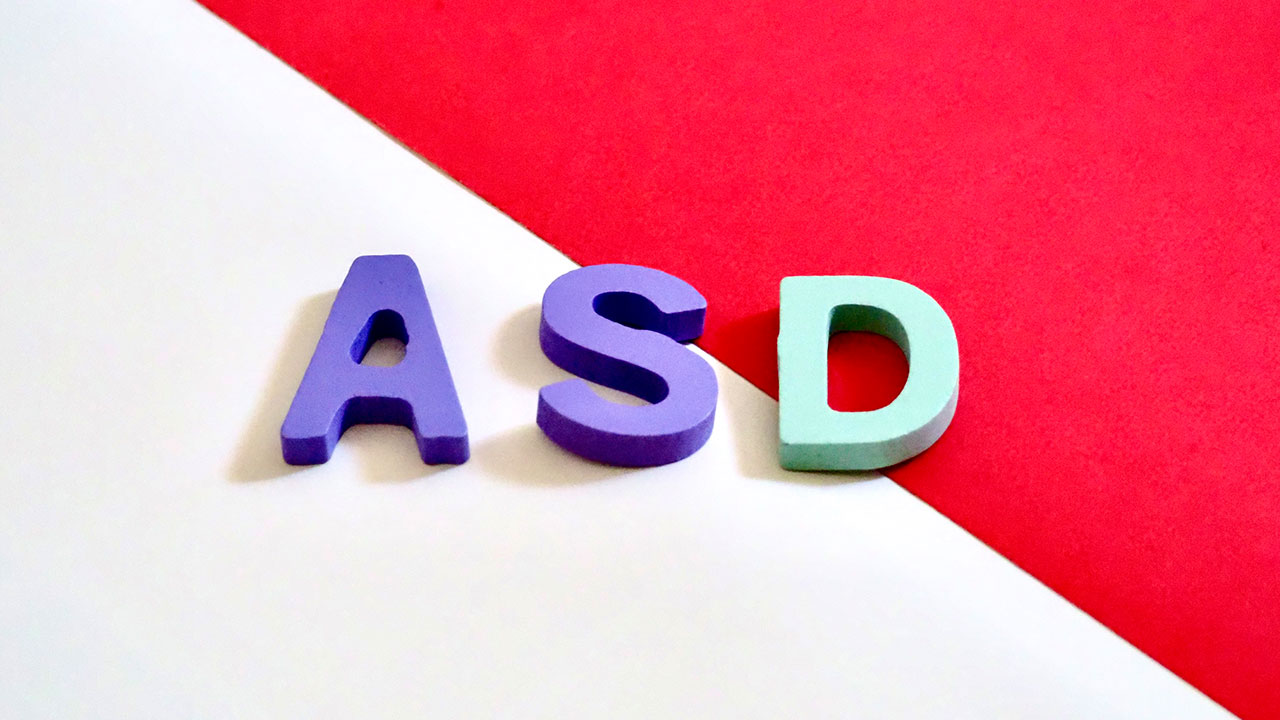
ASDの子どもが苦手を抱える理由
ASDの子どもの「苦手さ」には必ず理由があります。本人が怠けているわけでも、わがままを言っているわけでもありません。背景には、脳の情報処理の仕方や感覚の受け取り方の違いがあります。
ここでは、代表的な4つの理由を詳しく解説していきます。
1. 曖昧な表現や比喩が理解しにくい脳の働き
上述のように、「ちょっと待っててね」と言うと、「どのくらい?」と必ず聞き返してくる子がいます。あるいは「手を貸してね」と言った時に、物理的に「手」を差し出してしまうこともあります。これはASDの子どもが言葉を文字通りに受け取りやすいために起こる場面です。
脳の情報処理において、ASDの子どもは具体的な情報を求める傾向が強く、比喩や抽象的な言葉は混乱を招きやすくなります。例えば「もう少し頑張って」という励ましも、「もう少し」とは何を意味するのかが理解できず、不安やストレスにつながることがあります。
そのため、周囲が「当然わかるだろう」と思っている会話の多くが、子どもにとっては分かりにくい難問になってしまうのです。
2. 見通しが持てないことが不安につながる
ASDの子どもにとって、予定の変更は大きなストレスになります。
この背景には、次に何が起こるか分からないことへの強い不安があります。
ASD以外の子どもなら柔軟に切り替えられることでも、ASDの子どもは「見通しが立たない=安全ではない」と感じやすいのです。
学校生活でも同じで、時間割の変更や先生の交代、席替えといった出来事は予想以上の動揺を引き起こします。保護者からすると「そんなことで?」と思うかもしれませんが、子どもにとっては「安心できる世界」が崩れる体験なのです。
3. 興味や関心が狭く集中しすぎる特性
「電車の時刻表を完璧に覚えているのに、算数ドリルは一切やろうとしない」「図鑑に載っている恐竜の名前はすらすら言えるのに、宿題の漢字は全然書けない」__こうした「極端な得意・不得意」はASDの子どもによく見られる特徴です。
これは、脳が情報を処理する際に「好きなもの」「興味があるもの」に過剰に集中しやすい性質と関係しています。好きな分野では抜群の集中力を発揮する一方、関心のない課題にはエネルギーが向かず、拒否や回避につながります。この凸凹は一見すると「わざとやっていない」「努力不足」に見えますが、実際には脳の特性から来るものであり、本人の意志だけではコントロールできない部分なのです。
4. 感覚処理の違いから生まれる困りごと
「掃除機の音が怖くて部屋から飛び出す」「服のタグがチクチクして着られない」「蛍光灯の光がまぶしすぎて黒板が見られない」__こうした日常的な困りごとは、ASDの子どもに多く見られる感覚過敏の例です。
ASDの子どもは、音・光・匂い・触覚などの刺激を過剰に強く感じる場合があります。逆に、痛みに気づきにくい、強い感覚を求めるといった感覚鈍麻があるケースもあります。
これらはいずれも脳の感覚処理の仕組みの違いから生じており、本人の努力でコントロールできるものではありません。
周囲からすると「大げさ」に見える反応も、子どもにとっては本当に「居心地が悪い体験」なのです。

苦手さを和らげるサポート方法|家庭・学校・支援機関でできること
ASDの子どもの苦手さは、無理に矯正するものではなく「支援と環境調整」で和らげていけるものです。保護者や教師、地域の専門機関が連携することで、子どもは安心を感じながら力を発揮できるようになります。
ここでは、具体的にできるサポートを詳しく紹介します。
1. 家庭では「短く・具体的な伝え方」を意識する
「早く準備して」と声をかけたとき、子どもが動かずに固まってしまうことがあります。これは「準備」と言われても何をすべきかが分からず、曖昧な言葉に戸惑っているためです。
こうした場面では「ランドセルを背負って、靴を履こう」というように、短くて具体的な指示を出すことが有効です。段階を区切って伝えることで、子どもは安心して動き出すことができます。
この工夫を繰り返すことで、子ども自身も「次に何をすればよいか」を理解しやすくなり、結果として自立の一歩につながります。
2. 学校では「合理的配慮」や個別対応を相談する
学校生活では、時間割変更や集団行動の多さから困難が生じやすくなります。例えば「体育祭の音が大きくて参加できない」「席替えで集中できなくなった」などのケースです。
こうした場合は、学校と相談して「一部を見学にする」「落ち着ける席に座る」といった合理的配慮を検討することが重要です。これらは法律でも保障されている権利であり、特別なことではありません。学校側が理解しやすいように、家庭での様子や子どもが苦手とする具体的な状況をエピソードとして伝えると、より適切な対応につながります。親が一人で悩むより、先生と共に工夫を考えることで、学校生活のハードルは大きく下がります。
3. 得意分野を伸ばして自信を育てる
ASDの子どもは「電車」「昆虫」「絵を描くこと」など、突出した興味を持つことがあります。
保護者から見ると「勉強に役立つの?」と疑問を感じるかもしれませんが、この集中力は本人にとって大きな強みです。
得意分野を認め、伸ばしてあげることで「できることがある」という自己肯定感が育ちます。その経験が他の学習や活動への挑戦にもつながりやすくなるのです。例えば鉄道好きの子には地図を使って算数を結びつけたり、イラストが得意な子には国語の作文をマンガ風に描かせたりするなど、得意を勉強に橋渡しする工夫も可能です。苦手を責めるのではなく、得意を伸ばすことで自信と挑戦意欲が育ちます。
子どもの自己肯定感についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「子どもの自己肯定感の高め方とは?|7つのNG行動についても解説」
4. 感覚過敏には便利グッズを活用
掃除機や花火の音に耳をふさいで逃げたり、服のタグを嫌がって泣き出すなど、感覚過敏は生活の大きな妨げになります。こうした場合、本人の努力では解決が難しいため、環境を整えることが第一です。
遮音性の高いイヤホン、サングラス、タグを外した服などの利用は、子どもが落ち着いて生活するための大きな助けになります。学校にも「サングラスを使ってよいか」などを相談し、安心して過ごせる環境を整えていきましょう。この対応は決して「甘やかし」ではなく、子どもが周囲と同じように学び・生活に参加するための現実的な支援です。このような合理的配慮によって、子どもが活動の幅を広げることが可能になります。
5. 支援機関・専門家と連携して一人で抱え込まない
家庭や学校だけで支え続けるのは大きな負担です。困った時には、発達支援センターや地域の相談機関、医療・福祉の専門家に相談しましょう。
例えば「子どもが学校に行けなくなった」「家庭学習がまったく進まない」といった深刻な状況も、支援機関とつながることで具体的な解決策や制度の利用方法を知ることができます。
保護者が「自分だけで解決しなければ」と抱え込むと疲弊しやすくなりますが、外部とつながることで気持ちの負担も軽くなり、子どもにとっても安心できる環境が広がります。
発達障害支援センターの全国の一覧はこちらから検索できます。

まとめ
ASDの子どもが抱える苦手さは、特性ゆえに生じる自然なものです。しかし、理由を理解し適切な工夫を重ねることで、不安や困りごとは和らげることができます。
家庭や学校、支援機関が連携しながら寄り添うことで、子どもは安心できる環境の中で自分らしい力を伸ばしていけます。
大切なのは「苦手を責める」のではなく「支える視点」で向き合うことです。
家庭教師のマスターでは発達障害(ASD)のお子さんに向けた学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にご相談ください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
ASD(自閉スペクトラム症)の兆候はいつ分かる?|チェックリスト付き
-
自閉症の子の言葉が出ない理由とは?|サポート方法なども詳しく解説
-
ADHDとアスペルガーの違い|困りごとやサポート方法の違いを解説
-
発達障害の小学生|その特徴や症状の理解、支援方法や接し方を解説
-
発達障害の中学生の特徴と支援法
-
発達障害グレーゾーンの中学生の特徴|判断の仕方やサポート方法について
-
宿題をしない発達障害のお子さんへの解決策とは?
-
WISC-IV知能検査(ウィスク-4)の結果の見方と検査内容
-
ワーキングメモリーが低い子の特徴とよくある困りごと
-
WISCで処理速度だけが低いのはなぜ?|子どもの特徴と接し方のヒント
-
発達障害の子どもが行う「オウム返し(エコラリア)」とは?
-
発達障害とIQのホントの関係とは?|子どもの可能性を正しく理解しよう























