発達障害の中学生は嘘をつくことが多い?|その背景と対応策をわかりやすく解説
公開日:2025年9月1日
更新日:2025年9月1日

このコラムでは、発達障害の傾向がある中学生が本当に嘘をつきやすいのかどうかについて、詳しく解説します。
あわせて、「なぜ嘘をついてしまうのか?」という背景や心理的な要因についても、発達障害のタイプ別にご紹介します。お子さんの嘘でお困りの保護者は是非ご覧下さい。
発達障害の子どもは本当に嘘をつきやすいのか?
思春期の子どもは誰でも多少の嘘をつくものです。友達との関係や家庭でのやり取りの中で、本音を隠したり、都合の良いことだけを言ったりするのは珍しくありません。
ただし、発達障害のある中学生の場合、その嘘の背景や頻度、パターンが少し異なることがあります。
ここでは「普通の嘘」との違いや、発達障害の特性が嘘につながる理由を整理しながら、背景にある心理を見ていきます。
1. 思春期特有の「普通の嘘」と「発達障害の子どもの嘘」の違いとは
思春期の「普通の嘘」は、多くの場合、自立心やプライバシーを守るために生まれます。例えば「友達と出かけると言って本当は一人で行動していた」など、自分の行動や感情を親に知られたくないという気持ちからつくものです。
一方、発達障害の子どもの嘘は、意図的なごまかしというよりも、困りごとを回避するための反射的な言動である場合が多く見られます。約束を忘れたことを隠すために「もうやった」と言ってしまったり、事実を曖昧にして怒られるのを避けたりします。見かけは同じ「嘘」でも、その背景には特性からくる苦手さや不安が関係している点が大きな違いです。
2. 「その場しのぎ」の発言が「嘘」になってしまうことも
発達障害の子どもは、相手の気持ちや状況を瞬時に読み取ることが苦手な場合があります。そのため、質問されたときに深く考えず、「とりあえず怒られない答え」や「場が収まりそうな返事」を先にしてしまうことがあります。
例えば、宿題を忘れたときに「持ってきたけど家に忘れた」と答えてしまうなど、本人にとっては咄嗟の防御反応であっても、結果的には事実と違う内容になり「嘘」と受け取られてしまいます。
このような場合、意図的な計画性はなく、その瞬間を乗り切るための発言が、後から信頼関係を損ねる原因になってしまうことがあります。
3. 発達障害の特性からくる嘘が「自己防衛になりやすい」理由
発達障害には、注意力の散漫さ、感覚の過敏さ、想定外の出来事への苦手さなど、日常生活でストレスや不安を感じやすい特性があります。これらの特性が重なると、「怒られる」「失敗を注意される」場面が増えやすくなります。
そうした経験が積み重なると、「本当のことを言ったらまた怒られるかもしれない」という予測が強く働きます。その結果、事実を隠したり言い換えたりして、心理的な安全を守ろうとするようになります。つまり、嘘は悪意からではなく、自己防衛のための反応として繰り返されやすくなるのです。
4. 自己肯定感の低さが防衛的な嘘を生む
発達障害のある子どもは、周囲との比較や失敗体験の多さから、自己肯定感が低くなりやすい傾向があります。自分に自信が持てない状態では、「できなかったこと」「間違えたこと」を正直に話すことが、自分の価値をさらに下げてしまうように感じられます。
そのため、「自分を守るために事実を曲げる」という行動が出やすくなります。例えばテストの点数を実際より高く言う、宿題を提出したかどうかを誤魔化すなどが典型です。
こうした嘘は一時的に安心感を与えるかもしれませんが、長期的には信頼関係をさらに傷つけることにつながります。
子どもの自己肯定感についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「子どもの自己肯定感が低いのは親のせい?|原因と家庭でできるサポート方法」
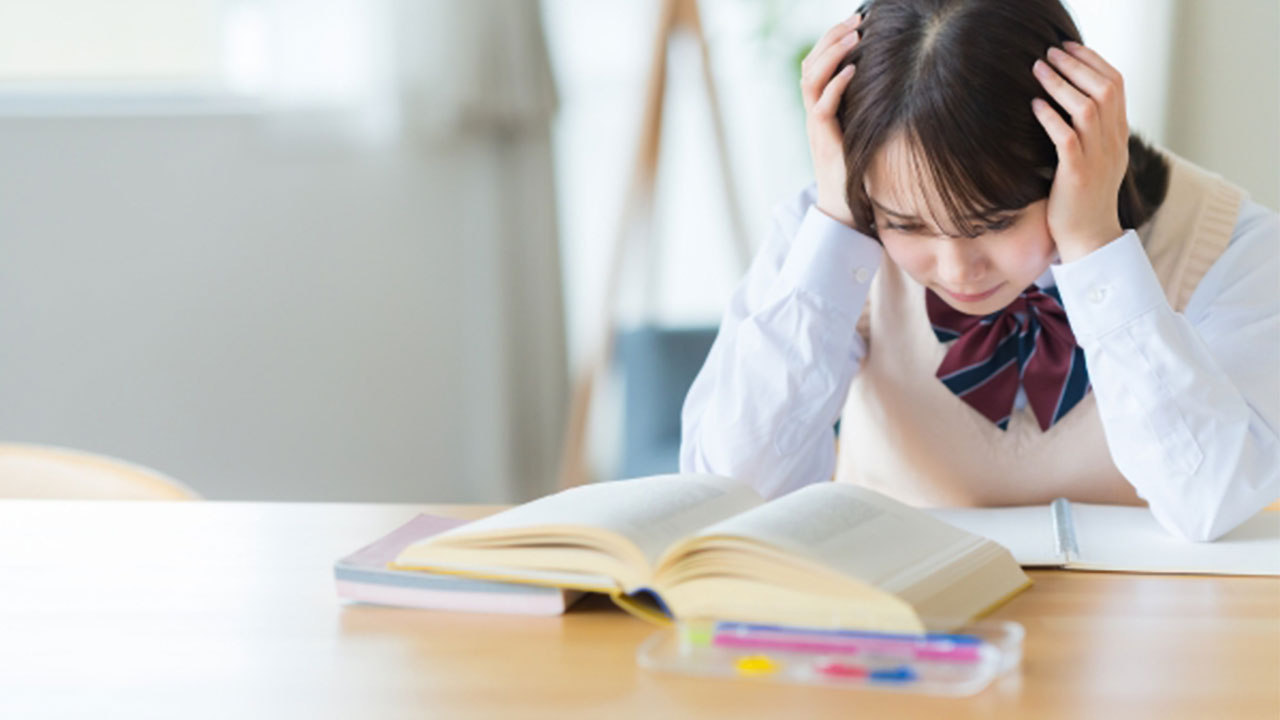
【タイプ別に解説】発達障害の特性がどのように「嘘」と結びつくのか
発達障害とひと口に言っても、その特性は人によって異なります。嘘の背景も「性格の問題」や「反抗期」だけで片づけられるものではなく、それぞれの特性と日常生活での経験が関係しています。
ここでは代表的なタイプごとに、嘘が生まれやすい状況や心理を整理します。
1. ADHDの場合|衝動性や忘れ物が嘘につながる
ADHD(注意欠如・多動症)では、衝動的に行動してしまう特性や、物事を忘れやすい特性がよく見られます。
例えば、宿題を提出し忘れた時に「持ってきたけど先生に渡し忘れた」と咄嗟に答えるのは、深く考えた嘘ではなく瞬間的な“逃げ道”です。
また、忘れ物や失敗の回数が多いと「またか」と思われる不安から、事実を隠そうとする行動が強まりやすくなります。この場合、嘘は叱られることや否定から自分を守るための一時的な回避行動であり、悪意のあるごまかしとは異なります。
ADHDについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「ADHDの子どもの忘れ物が減る!親ができる対策&声かけガイド」
2. ASDの場合|思い込みによるすれ違い
ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、相手の意図や感情を読み取ることが苦手な場合があります。そのため、相手がどの程度事実を求めているか、どの部分を重要視しているかを理解しきれず、結果的に事実と異なる答えを返してしまうことがあります。
さらに、「こうだったはず」という自分の思い込みが強い場合、本人としては正しいと思って話していても、周囲からは「嘘をついている」と受け取られてしまうこともあります。
加えて、叱られることや否定を避けたい気持ちが強く、意図的に情報を省く・変える行動が出やすい傾向もあります。
3. LDの場合|勉強のつまずきから防衛的な嘘が出る
LD(学習障害)は、読む・書く・計算するなど特定の学習分野に困難がある状態を指します。学習の場で繰り返し失敗や遅れを経験すると、「できない自分を見られたくない」という防衛心が強くなります。
例えば、宿題をやっていない理由を「ノートを忘れた」「問題がわからなかった」と正直に言えず、「家に置いてきた」や「昨日はやる時間がなかった」といった別の理由に置き換えることがあります。これもまた、自分の苦手さを隠すための防衛的な嘘です。
学習障害の診断テストについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「学習障害(LD・SLD)の診断テスト|症状別チェックリストをご紹介」
4. 協調運動障害(発達性協調運動障害)の場合|苦手を隠すための嘘
発達性協調運動障害(DCD)は、体の動きをイメージ通りに行うことが難しい特性です。体育や美術、家庭科など、運動や手先の器用さを必要とする場面で困難が目立ちやすくなります。
こうした場面で失敗や不器用さを見られるのを避けるため、「前はできた」「今日は調子が悪い」など事実と異なる発言をしてしまうことがあります。本人は自分を良く見せたい気持ちや恥ずかしさから話している場合も多く、根底には「周囲と比べられたくない」という思いが隠れています。
5. 複合的な発達障害の場合|複数の困りごとが重なり、嘘が“対処手段”としてクセづくことも
ADHDとASD、LDとDCDなど、複数の特性が重なっている子どもも少なくありません。この場合、忘れやすさ・理解のズレ・苦手分野の多さなど、日常での困りごとが複数同時に起こりやすくなります。
そうした環境では、嘘が一度きりの回避手段ではなく、日常的な「トラブル回避の方法」として定着してしまうことがあります。
本人も「これしか乗り切る方法がない」と感じ、無意識に嘘を選んでしまうケースもあるため、早い段階で安心して事実を話せる環境作りが重要です。
発達障害チェックリストについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「発達障害チェックリスト【中学生のお子さん向け】」

「嘘」が引き起こす本当の困りごと|家庭・学校で起こりやすい誤解と悪循環
発達障害のある子どもの嘘は、多くの場合、悪意や計画性からではなく、困りごとを回避するための防衛反応です。しかし、周囲からは「信用できない」「反抗している」と受け取られやすく、家庭や学校での人間関係に影響が出ることがあります。
ここでは、嘘が続くことで起こりやすい誤解や悪循環について整理します。
1. 嘘をついた本人が一番苦しんでいる|自己嫌悪と罪悪感の悪循環
嘘をつく瞬間は、その場をしのぐために安心感が得られるかもしれません。しかし後になって「やっぱり言わなければよかった」「本当のことを言うべきだった」と自己嫌悪に陥る子は少なくありません。この罪悪感が強くなると、次に似た状況になったとき「もう失敗したくない」という気持ちが働き、また嘘をつく…という悪循環に陥ります。本人にとってもつらいサイクルなのです。
2. 嘘を叱られるより“わかってもらえないこと”がつらい
嘘が見つかった時、多くの大人は「なぜ嘘をついたのか」と問い詰めます。しかし発達障害のある子どもにとっては、「嘘をついてしまった理由を理解してもらえないこと」そのものが大きなストレスになります。
「どうせわかってもらえない」と感じると、正直に話す意欲が薄れ、事実を隠す方が楽だと考えるようになります。これは信頼関係の崩れにつながる大きな要因です。
3. 徐々に“バレなければOK”の思考に変わっていく怖さ
嘘を繰り返すうちに、「怒られないためにはバレなければいい」という発想が強まることがあります。この思考は、日常的なやり取りから友人関係、将来的な社会生活にまで悪影響を及ぼします。
本来は一時的な防衛行動だった嘘が、「身を守る方法」として定着してしまうと、後で修正するのが難しくなります。
早い段階で安全に本音を話せる場を作ることが大切です。
4. 正直に話すことで損をした経験が「本音」を封じ込める
過去に正直に話したことで怒られたり、不利な扱いを受けたりした経験があると、「本当のことを言うと損をする」という気持ちが強くなりがちです。
その結果、事実を話すよりも、都合のよい答えを選ぶ傾向が強まります。これが続くと、子どもは自分の本音や感情を表に出せなくなり、本音を封じ込めたまま生活するクセがついてしまいます。

嘘を責めるより、安心できる環境作りを|子どもが本音を言えるための5つのコツ
発達障害のある子どもの嘘を指摘して責めるだけでは、ますます本音を隠しやすくなります。必要なのは、「正直に話しても大丈夫」と子どもが心から感じられる環境です。ここでは、そのために家庭や学校でできる関わり方を5つのコツにまとめます。
1. 事実確認よりも「安心感」を優先する
嘘が疑われる場面では、親や教師はつい「本当はどうなの?」と事実確認を急ぎたくなります。しかし、子どもにとってはその問いかけがすでに「怒られる予兆」に感じられ、防衛反応を強めてしまいます。
特に発達障害のある子は、過去の経験から、「正直に言うと必ず怒られる」という学習が染みついている場合があります。その状態で事実を追及されれば、ますます事実から目をそらし、嘘で自分を守ろうとするのは自然な反応です。
まずは事実を問い詰めるのではなく、落ち着いた声で「話してくれてありがとう」「大丈夫、怒らないよ」と安心を与える言葉をかけます。この時、表情や声のトーンも重要です。焦りや苛立ちがにじむと、言葉だけ優しくても安心感は届きません。
安心が先にあることで、子どもは「この人は敵じゃない」と感じ、少しずつ自分から事実を話す準備が整います。
2. 「嘘を見抜く」より「本音を引き出す」関わり方に変える
嘘を見抜こうとする姿勢は、どうしても「犯人探し」の雰囲気を作ってしまいます。特に相手が子どもであれば、その空気だけで緊張し、余計に本音を言うことから遠ざかります。
代わりに「嘘を見抜く」ことを目的にせず、「本当はどうしたかったの?」「その時、どんな気持ちだった?」など、気持ちや背景を聞き出す方向に切り替えることが大切です。
発達障害のある子は、自分の感情や状況を言葉にするのが難しいこともあります。その場合は、選択肢を示してあげるのも有効です。
「やるのを忘れちゃった?それとも時間が足りなかった?」のように、責めずに答えやすい形で問いかけると、防衛心が下がります。
「本音を引き出す関わり方」は、単発で終わらせず、日常会話の中で繰り返すことで効果が蓄積します。
3. 正直に話したときの“ポジティブな体験”を積ませる
正直に話しても嫌な思いをしなかった経験は、「本当のことを言っても大丈夫」という安心感を育てます。
例えば、宿題をやっていなかったことを正直に話した場合、「正直に言ってくれてありがとう。じゃあ今日はどうやって取り戻そうか?」と前向きに解決策を一緒に考えましょう。
このような対応を繰り返すと、子どもは「隠すよりも正直に言った方が楽だし、助けてもらえる」と学習します。逆に、正直に言ったのに強く叱られたり、周囲に悪口を言われたりすると、その経験がトラウマになり、今後ますます事実を隠す方向に進んでしまいます。
保護者や教師が意識すべきは、「正直さに報酬を与える」という考え方です。報酬といっても物やお金ではなく、「ありがとう」「助かったよ」という感謝や、「次はこうしてみよう」という前向きな提案が十分なご褒美になります。
4. 「どうせ怒られるし…」を封じる、予防的な声かけを意識する
子どもが嘘をつく前に、「失敗しても怒らないから教えてね」「困ったら早めに言ってくれたら一緒に考えよう」と日頃から伝えておくことは非常に効果的です。
これを習慣化しておくと、失敗や困りごとがあった時に、嘘で切り抜ける選択をする可能性が下がります。
また、この予防的な声かけは、ただ口にするだけでなく、実際にそういう対応を取ることで信頼が積み上がります。もし子どもが困りごとを打ち明けたら、「言ってくれて嬉しかったよ」と肯定的に返し、すぐに解決のステップに移るのが理想です。
この積み重ねが、「どうせ怒られるし…」という固定観念を崩していきます。
5. 本人なりの“言いやすい手段”や“言いやすい相手”を用意しておく
正直に話すのが難しい子どもにとって、「どうやって伝えるか」は大きなハードルです。口頭で話すのが苦手なら、メモ、メール、LINEなど、別の手段を使うだけでも、打ち明けやすさが格段に上がります。
また、「お母さんには言いにくいけど、お父さんなら言える」「先生より保健室の先生に話す方が楽」というケースもあります。
重要なのは、「この人、この方法なら言いやすい」という安全ルートを本人と一緒に見つけておくことです。
例えば、「困ったことがあったらこのノートに書いて机に置いてね」「学校で何かあったら保健室に行ってもいいよ」と事前に決めておけば、嘘でごまかすよりも低リスクな選択肢になります。

まとめ
発達障害のある中学生が嘘をつく背景には、多くの場合「自分を守るため」という切実な理由があります。
大切なのは嘘そのものを責めるのではなく、本音を安心して話せる環境を整えることです。日々の関わりの中で、理解と信頼を積み重ねていけば、子どもは少しずつ正直に向き合えるようになります。
家庭教師のマスターでは、発達障害があるお子さんへの受験サポートを行っています。ご興味のある方は、気軽にお問合せください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
発達障害(ASD・ADHD・LD・グレーゾーン)の子の高校受験対策
-
発達障害の中学生の特徴と支援法
-
発達障害グレーゾーンの中学生の特徴|判断の仕方やサポート方法について
-
発達障害の子に合った高校の選び方|進路の選択肢と地域の受け入れ校を紹介
-
勉強をしない中学生|発達障害のタイプ別に対策法をご紹介!
-
宿題をしない発達障害のお子さんへの解決策とは?
-
勉強ができるADHDの子の“見えにくい困りごと”と、家庭でできる支援のヒント
-
ADHDの子どもの忘れ物が減る!親ができる対策&声かけガイド
-
ADHDとアスペルガーの違い|困りごとやサポート方法の違いを解説
-
学習障害(LD・SLD)の診断テスト|症状別チェックリストをご紹介
-
WISC-IV知能検査(ウィスク-4)の結果の見方と検査内容
-
ワーキングメモリーが低い子の特徴とよくある困りごと
























