IQが低い子どもに見られる特徴とは?|困りごとと家庭でできるサポート
公開日:2025年8月20日
更新日:2025年8月20日

IQが低いと言われ、「もしかして…?」と感じたとき、親は不安でいっぱいになるのは当然です。
このコラムでは、IQが低い子どもに見られる特徴や、学校・日常生活での困りごと、それに対して家庭でできる具体的なサポートについて丁寧に解説します。
IQが低いってどういうこと?|数値の意味と知っておきたい4つの前提知識
IQ(知能指数)という言葉はよく耳にしますが、その数値が何を意味しているのか、誤解されているケースも少なくありません。特にお子さんのIQが低いと知ったとき、保護者としては不安を抱くのが自然です。しかし、IQの数値だけで子どもの全てを判断することはできません。ここでは、IQに関して知っておくべき基本的な4つのポイントをわかりやすく解説していきます。
1. IQは「頭のよさ」を単純に測るものではない
「IQが高い=頭が良い」「IQが低い=頭が悪い」といったイメージを持たれがちですが、IQは本来、そのように単純に“頭の良さ”を測るものではありません。IQとは「知的能力の発達の度合い」を示す指標であり、知的な処理速度、記憶力、理解力、論理的思考力などのバランスを測るものです。
また、学力や成績とは必ずしも比例しません。例えば、言語理解が弱くてもグラフの読み取りが得意な子どももいれば、逆に数字に強くても指示を聞くのが苦手な子どももいます。つまりIQは、あくまで“ひとつの目安”として受け止めることが大切なのです。
2. IQの測定方法と注意点
IQは一般的に、年齢別の標準的な発達水準と比べて、どれくらい認知的に発達しているかを数値化したものです。
例えば、標準的なIQは100とされ、これより高ければ「平均より高い」、低ければ「平均より下」とされます。検査では複数の分野(言語理解・知覚推理・作動記憶・処理速度など)を評価し、それらの合算で全体的なIQ(全検査IQ)を算出します。
注意したいのは、IQはあくまで一時点での結果にすぎないということです。子どもの発達は日々変化しており、環境や経験によって伸びていく力も多くあります。IQの数値だけを重く捉えすぎて、「うちの子はダメだ」と決めつけてしまうのは避けましょう。
3. 知能検査でわかること・わからないこと
知能検査(WISCなど)は、子どもの認知機能の得意・不得意を把握するうえで有効なツールです。検査を通して、「何がわかりにくいのか」「どのような情報処理が苦手か」を客観的に知ることができます。これにより、適切な支援方法を考える手がかりになります。
ただし、知能検査にも限界があります。子どもの性格、体調、検査時の緊張、検査者との相性などによって結果が左右されることもあり、本人の可能性や人柄、感情面の力までは測れません。以上のことから、「IQだけで全てがわかる」と考えるのは誤りです。
4. 知能指数が低い=能力がない、ではない理由
IQの数値が低い水準であっても、それが「能力がない」ということにはなりません。むしろ、“認知の偏り”があるだけで、他の面では強みを持っている子どもも多いのです。
例えば、会話が苦手でも絵を描くことが得意だったり、計算が苦手でも人を笑顔にする才能があったりします。
また、IQの低さによって「わかるのに時間がかかる」「説明の工夫が必要」という場合もありますが、それは“努力しても理解できない”という意味ではありません。適切なサポートや学び方を工夫すれば、子ども自身が力を発揮できる場面は必ずあります。
大切なのは、数字よりも「その子らしさ」に目を向け、本人にあったサポートをしてあげることです。
WISC-IVの結果の見方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「WISC-IV知能検査(ウィスク-4)の結果の見方と検査内容」
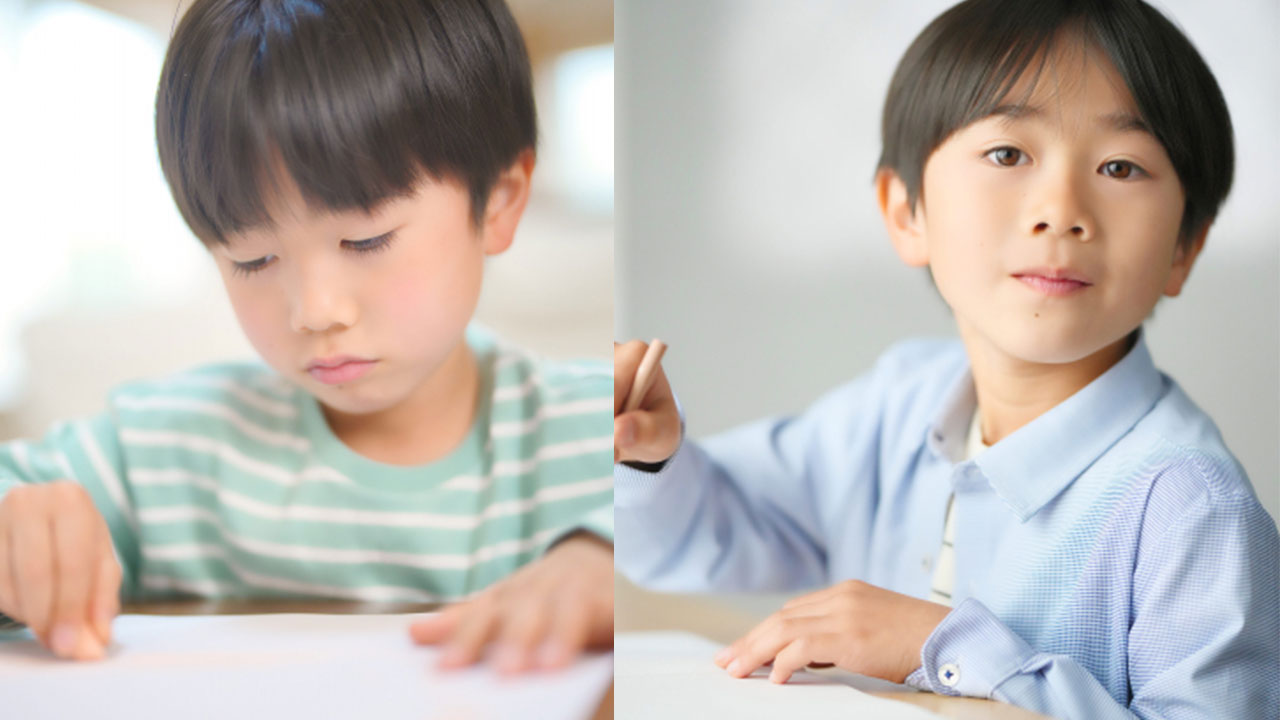
IQが低い子どもに見られやすい4つの特徴とは?
IQが低いと言われる子どもたちは、周囲と比べて「やりづらさ」を感じる場面が多くあります。ただし、それは「努力していないから」でも「育て方が悪いから」でもなく、情報の理解や処理に時間がかかる特性によるものです。
ここでは、日常生活や学校生活の中でよく見られる4つの特徴について解説します。
1. 言葉や会話の理解に時間がかかることがある
IQが低い子どもは、先生や親が話した内容をすぐに理解できず「え?なに?」と聞き返すことが多かったり、説明の途中で意識が離れてしまったりすることがあります。これは聞いた言葉の意味を頭の中で整理し、理解するのに時間がかかるためです。
例えば、「じゃあこのプリントは家に持って帰って、明日また持ってきてね」と言われても、途中で混乱して「今やるの?」「置いとけばいいの?」と勘違いしてしまうケースもあります。そのため、話の内容を短く区切って伝えたり、確認の時間を取ったりする工夫が必要です。
2. 自分の気持ちや考えを言葉で表現するのが苦手
IQが低い子どもは、「どう思った?」「なにが嫌だったの?」と聞かれても、自分の気持ちをうまく言葉にできず、黙り込んでしまうことがあります。これは言語的な表現力の問題だけでなく、「自分の中で気持ちを整理する力」が育ちにくいことも関係しています。
例えば、友達とケンカをした理由を聞いても「知らない」「ムカついた」など漠然とした言葉しか返ってこないことがあります。このような場合、「〇〇されてイヤだったのかな?」など気持ちを代弁してあげる声かけが効果的です。
3. 複数の指示や変化に混乱しやすい
「上履きを持って帰って、ランドセルに連絡帳入れて、それから着替えてね」といった複数の指示を一度に受けると、どれかを忘れたり順番がバラバラになったりすることがあります。
また、急な予定変更や初めての場所へのお出かけでも戸惑いや不安が強く出る場合があります。これは、処理できる情報の量に限界があったり、変化への見通しが立てづらかったりする特性によるものです。
対応としては、「まずは上履き、そのあと連絡帳だよ」と順番に伝える、視覚的な予定表を使うなどのサポートが効果的です。
4. 忘れ物やミスが多く、「だらしない」と誤解されがち
毎日のように忘れ物をしたり、宿題のやり忘れがあったりして、先生や親から「ちゃんとしなさい」「また忘れたの?」と叱られる場面も少なくありません。
ただ、IQが低い子どもは怠けているわけではなく、やるべきことを頭にとどめておく作業が苦手で、意識の問題ではないことが多いのです。
つまり「だらしない」のではなく「脳が忘れやすい」と理解することが大切です。
以上のことより、カバンの中身を一緒に確認する、持ち物チェック表を作って貼っておくなど、忘れ物をしにくくなる仕組みで補うことが効果的です。

学校生活で出やすい困りごととその背景
IQが低い子どもは、日々の学校生活の中でさまざまな困りごとに直面します。ただ、それは「怠けているから」でも「やる気がないから」でもありません。授業のペースや人間関係の中で、本来の力を発揮しづらい構造があるのです。
ここでは、学校で見られやすい具体的なつまずきと、その背景にある理由を解説します。
1. 授業内容が理解しきれず「わからない」が積み重なってしまう
IQが低い子どもは、授業で先生の話が聞き取れても、その意味を理解し、内容をつなげて考えることが難しい場合があります。そのため、「なんとなく分かった気がするけど、実はよく分かっていない」という状態がおこりやすくなります。
例えば、英語・国語の読解問題や算数の文章題など、複数の情報をまとめて考える場面では特につまずきやすく、理解できなかった経験が積み重なることで、「勉強はつまらない」「自分には勉強は向いてない」という思い込みを強めてしまうこともあります。
2. 話についていけず、集中が切れやすくなる
IQが低い子どもは、授業中、先生の話が速かったり内容が難しかったりすると、集中力が続かず、ぼんやりしてしまうことがあります。これは、ただ気が散っているのではなく、情報処理が追いつかずに“ついていけない”感覚に陥っているためです。
その結果、「ちゃんと聞いてない」「やる気がない」と見なされがちですが、実際には「理解したくてもできない」という心の葛藤を抱えていることも多いのです。
3. 周りの子と比べられて自信を失いやすい
IQが低い子どもは、同じクラスの友達が問題をスラスラ解いたり、発表で上手に話したりしているのを見ると、「自分だけできていない…」と劣等感を感じやすくなります。
さらに、先生や親が悪気なく「○○ちゃんはできてるのに」などと比較することで、自己肯定感がどんどん下がってしまいます。
このような経験が積み重なると、「どうせやってもムダ」と学ぶ意欲そのものを失ってしまうこともあります。比べるのではなく、子ども自身の成長に目を向ける関わり方が大切です。
子どもの自己肯定感についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「子どもの自己肯定感の高め方とは?|7つのNG行動についても解説」
4. 支援が必要でも「特別扱いされたくない」気持ちがあり反発してしまう
IQが低い子どもは、支援学級や通級などのサポートを受けることで学びやすくなるケースもありますが、「みんなと同じようにしたい」「目立ちたくない」という思いが強く出ることもあります。
特に高学年になると、「特別扱いされている」と感じた途端に反発したり、支援を拒んだりすることがあります。これは自尊心の現れでもあるため、無理に押し付けず、本人の気持ちに寄り添いながらタイミングを見ていくことが大切です。

家庭内で出やすい困りごととその背景
IQが低い子どもは、学校だけでなく、家庭の中でも「なんでこんなことができないの?」と感じてしまう場面が多くあります。
ここでは、日常生活で困りごとが出やすい代表的な4つの場面を取り上げ、その背景にある理由やサポートのヒントを解説します。
1. 着替え・準備などの身の回りのことに時間がかかる
朝の支度やお風呂の後の着替えにやたらと時間がかかり、「早くして」と何度言っても進まない…。そんな場面に心当たりはありませんか?
これは決して“だらけている”わけではなく、やることの順番が分からなかったり、一つの動作に集中するのが難しかったりするために起こることが多いのです。
「靴下どこ?」「先に何すればいいの?」と毎回聞いてくる場合は、やることを“見える化”してあげることが効果的です。絵や写真を使って出かける支度をわかりやすくしてあげることで、頭の中を整理してあげましょう。
2. スケジュール管理や順序立てが難しい
「このあと何するんだっけ?」「まだ宿題やってないの?」といったやり取りが日常的になっている場合、時間や予定の見通しが立てづらいタイプかもしれません。
IQが低い子どもは、頭の中で「今」「次」「その次」の順番を並べて考える力(ワーキングメモリ)が弱い傾向があります。そのため、複数の予定を覚えておくことや、優先順位を考えることが苦手です。
時間割のように1日の流れを「見える形」して整理したり、「終わったらチェックするリスト」を用意したりすることで、行動がスムーズになることがあります。
ワーキングメモリーについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「ワーキングメモリーが低い子の特徴とよくある困りごと」
3. 環境や予定の変化にパニックになりやすい
IQが低い子どもは、「今日は〇〇に行く予定だったのに、中止になった」と聞いたとたん泣き出したり、急に誰かが来ると不機嫌になったりすることがあります。これは、変化を一度にたくさん受け取ると、頭の中の処理が追いつかず、不安や混乱に繋がるからです。
そういった場合には、前もって予定を伝えておく、変更がある場合は理由と代替案を一緒に伝えるなどの工夫で、安心感を持ちやすくなります。
4. 買い物やお手伝いなど「実行機能」が求められる場面でのつまずき
IQが低い子どもは「これ買ってきて」と頼んだのに忘れて帰ってきたり、「お皿を運んでね」と言っても途中で別のことをし始めたり…、一見“ちゃんとやらない”ように見える行動の裏には、「実行機能(行動の計画→記憶→実行までの流れ)」の弱さが関係していることがあります。
例えば、買い物で「牛乳・卵・パンを買う」と言われても、記憶の中に保持できず、1つ目で止まってしまうことがあります。また、「お皿を運ぶ→机を拭く→飲み物を出す」というような一連の作業を順番通りにこなすのも難しいケースがあります。
このような場合、メモを書いて渡す、1つずつ指示を出す、終わったことを確認できるチェックシートを使うなど、“具体的な仕組み”でサポートすることが効果的です。

「苦手」があっても伸ばせる!家庭でできる3つの学習サポート
IQが低い子どもは、学習面でもつまずきを感じやすいものです。かと言って「できないこと」だけに目を向けすぎると、自信を失い、学ぶ意欲そのものが落ちてしまいます。
だからこそ大切なのは、「どう伸ばすか」ではなく、「どうやったらその子が“できた”を実感できるか」を一緒に考えることです。
ここでは、家庭でできるシンプルかつ効果的なサポート方法を3つご紹介します。
1. 小さな「できた!」を積み重ねて自己肯定感を育てよう
学習の成果は、子どもにとって「自分はできるかもしれない」という感覚に繋がってこそ意味があります。特にIQが低い子どもは、「わからない」「また間違えた」といった経験を繰り返すことで、自信を失いやすくなっています。
そのため、最初から難しい問題に取り組ませるよりも、「この問題ならできる」というレベルからスタートし、成功体験を重ねることが重要です。
例えば、「3問中1問正解できた」でも十分です。「やったね!自分でできたね」と声をかけ、本人の努力を認めてあげることが、次のやる気に繋がります。
2. 教科書にこだわらず、その子に合ったやり方で理解を助けよう
教科書の内容が難しすぎて、本人がやる気をなくしてしまっている場合は、「学校の教材に合わせる」よりも「その子に合った教材や方法を使う」方が効果的です。
例えば、音読が苦手な子には読み上げ機能のあるアプリを使って一緒に聞いてみたり、図やイラストを多く使った学習マンガを取り入れたりしても構いません。大事なのは、本人が理解できる形に“翻訳”してあげることです。
保護者が「こうしなきゃ」と思いすぎず、子ども自身が、“わかる・伝わる・楽しくなる”ような学び方を一緒に見つけていくことが、学習の第一歩になります。
3. 授業の前に「予習」することで授業中の自信に繋げよう
IQが低い子どもは、その場で新しい情報を理解し、整理し、すぐに使うという流れが苦手な場合が多いです。そのため、授業中に「ついていけない」「何をやっているか分からない」と感じてしまうこともあります。
そこで効果的なのが、「予習」です。といっても難しいことをする必要はなく、次の授業で出てくる言葉や内容に“あらかじめ触れておく”だけでも大きく変わります。
例えば、「明日は『かけ算』をやるみたいだね。一緒に九九を確認しておこうか」と軽く導入しておくだけで、授業中に「これ知ってる!」という安心感が生まれ、本人の自信や集中力にも繋がります。

IQが低くても大丈夫|“その子らしさ”を活かすためにできること
IQの数値を目にしたとき、「うちの子はこの先大丈夫なんだろうか…」と不安になるのは当然のことです。でも、子どもの未来は数値だけで決まるものではありません。大切なのは、その子の「苦手」ではなく、「できること」や「好きなこと」に注目し、のびのびと力を伸ばしていくことです。
ここでは、子ども自身の持つ“らしさ”を活かしながら、家庭でできる関わり方や支援の考え方を紹介します。
1. IQの数値にとらわれず、長所を見つけて活かす視点を持とう
IQはあくまで「認知の傾向や特性」を示す一つの指標にすぎません。そこに優劣があるわけではなく、その子がどんな形で情報を理解しやすいか、どう学びやすいかを知る手がかりになるものです。
例えば、勉強は苦手でも、人懐っこくて人との関わりが得意な子、細かい作業が好きな子、絵や音楽に感性を発揮する子など…そうした“その子らしい強み”に目を向けることが、今後の成長の土台になります。
「どんな能力があるか」ではなく、「どんな環境なら力を発揮しやすいか」という視点を持つことで、子どもへの見方がぐっと柔らかくなるでしょう。
2. 苦手を叱るより、得意を認めることで前向きな変化が生まれる
「なんでできないの?」「ちゃんとやって」とつい言いたくなってしまう場面は多いものです。でも、苦手を繰り返し指摘されると、子どもは「どうせ自分なんか…」と心を閉ざしてしまいます。
逆に、得意なことや頑張ってできたことを見つけて声をかけると、子どもは非常に前向きに変わっていきます。「すごいね!」「昨日より早くできたね!」「ちゃんと覚えてたね!」といった言葉が、子どもの中に「自分はできるかもしれない」という気持ちを育てていきます。
苦手を“直す”のではなく、得意を“伸ばす”ことで、自然と苦手にも向き合う力が育っていくのです。
3. 必要なら支援制度や専門機関も上手に活用しよう
家庭での工夫だけではサポートしきれない場合、学校や自治体にはさまざまな支援制度があります。例えば、通級指導教室や特別支援学級、スクールカウンセラーの利用などは、困りごとに応じた手助けが受けられる選択肢です。
また、発達相談や療育センターなどの専門機関に相談することで、子どもの特性をより深く理解し、適切な支援方法を一緒に考えてもらうことも可能です。
「うちの子が特別扱いされるのはかわいそう」と思ってしまうかもしれませんが、支援は「その子に合った学び方や成長の形を見つけるチャンス」でもあります。無理せず、一人で抱え込まず、必要に応じて専門的なサポートも取り入れていきましょう。

まとめ
IQが低い子どもにも、必ずその子なりの強みや可能性があります。数値だけにとらわれず、困りごとには具体的な支援を、得意なことには自信を育てる関わりを持つことが重要です。子ども一人ひとりのペースに寄り添いながら、家庭の中でできることを少しずつ積み重ねていきましょう。
家庭教師のマスターでは、発達障害のお子さんへの学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にご相談ください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
発達障害とIQのホントの関係とは?|子どもの可能性を正しく理解しよう
-
発達障害チェックリスト【中学生のお子さん向け】
-
WISC-IV知能検査(ウィスク-4)の結果の見方と検査内容
-
学習障害(LD・SLD)の診断テスト|症状別チェックリストをご紹介
-
WISCで処理速度だけが低いのはなぜ?|子どもの特徴と接し方のヒント
-
WISC-4の知覚推理(PRI)が低いとどうなる?|子どもの特徴と支援法
-
ADHDの子が宿題に取りかかれない理由と対策法について
-
ADHDの子が片付けられない理由とは?|6つの改善策もご紹介!
-
「また逃げた…」ADHDの子どもが嫌なことから逃げる本当の理由とは?
-
ADHDの子どもの忘れ物が減る!親ができる対策&声かけガイド
-
ADHDと集中力の関係|過集中・不注意に悩む親のための対処ガイド
























