学校から帰るとグッタリ…ADHDの子が“疲れやすい”本当の理由とは?
公開日:2025年8月18日
更新日:2025年8月18日

「帰ってきたらグッタリ…」ADHDの子どもは、日常の中で気付かないうちに大きな疲労を抱えることがあります。
このコラムでは、子どもが疲れやすい背景を特性別に解説しながら、学校で起きやすい“見えない疲れ”の具体例、家庭でできるサポート方法をご紹介します。
疲れて当然だった?|ADHDの特性から見る“見えにくい疲労”
ADHDの子どもが「疲れやすい」と感じるのには、ちゃんと理由があります。
一見、元気そうに見えても、心や体はずっとがんばり続けていることがあるからです。
ここでは、ADHDの特性ごとに、子どもがどのような“見えにくい疲れ”を抱えているのかを解説します。
1. 落ち着いて座っているだけでしんどい|多動性が抱える「動けないつらさ」
ADHDの中でも「多動性」が強い子は、本来体を動かすことで気持ちを落ち着けたり、集中を保ったりしています。
そんな子にとって「じっと座っていなければならない授業中」は、それだけで大きなストレスになります。
まるで「走りたいのに止まっていないと怒られる」ような時間が続くのです。
周囲にはわからない「動きたいのに動けない苦しさ」が、じわじわと疲れとして積み重なっていきます。
2. 思ったことを我慢するのに疲れる|衝動性が引き起こす「心の消耗」
「今それ言っちゃダメだよ」「勝手に動いちゃダメ」__
ADHDの衝動性が強い子は、思いついたことをパッと口にしたり、すぐに行動に移してしまいがちです。
しかし、年齢が上がると「我慢しなきゃ」「怒られないようにしなきゃ」と、本人なりに必死にブレーキをかけようとします。
この“我慢し続ける”という行動自体が、心に大きな負荷をかけています。
「気をつけなきゃ」「失敗しないようにしなきゃ」と気を張り続けることで、精神的に消耗してしまうのです。
3. 周りに合わせようと必死|不注意型の「見えない努力」
不注意型のADHDの子は、忘れ物が多かったり、話を聞き漏らしたりしやすい傾向があります。
そのため、周囲に遅れまいと「ちゃんとしなきゃ」と努力していることが多く、本人なりに強いプレッシャーを感じています。
「みんなのペースについていかなきゃ」「先生に怒られないようにしなきゃ」と、見えないところで頭をフル回転させて頑張っていることも珍しくありません。
こうした「目に見えない努力」は、周囲からは分かりづらいものの、心と脳を確実に疲れさせているのです。
4. 過集中の反動で一気にバテる|好きなことでも疲れてしまう理由
ADHDの子どもには、「過集中」といって、一つのことにものすごく集中し続ける特性がある子もいます。これは、一つのことに極端なほど集中し続けてしまう状態を指します。
一見「集中できているならいいこと」と思われがちですが、この状態はエネルギーをかなり消耗します。しかも、過集中の後はまるで電池が切れたように疲れ果ててしまい、動けなくなったり、イライラが爆発したりすることもあります。
「好きなことをやっているのに疲れてる」というギャップに、周囲が戸惑うこともあるかもしれません。
5. よく寝てるはずなのに疲れが抜けない|睡眠の質と神経の過敏さの関係
「ちゃんと寝てるのに、朝から疲れている」__これはADHDの子どもによく見られる特徴の一つで、睡眠時間は足りていても、睡眠の質が十分でないことが影響している場合があります。
ADHDの子は、感覚過敏や入眠の困難さ、夜中に何度も目が覚めるなどの問題を抱えていることも多く、脳や体がしっかりと休めていないまま朝を迎えてしまっている可能性があります。
また、日中の疲れが残ったままだと、学校生活にも影響が出てきます。
「なんとなく元気がない」「動きが鈍い」などのサインは、こうした“見えない睡眠の疲労”からきているかもしれません。
発達障害チェックリストについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「発達障害チェックリスト【中学生のお子さん向け】」

親には見えにくいけど、本人はヘトヘト|学校生活で疲れやすい場面とは?
子どもが学校から帰ってくると、ぐったりしていたり、ちょっとしたことでイライラしたりすることはありませんか?
一見普通に過ごしているように見えても、ADHDの子にとって学校生活は「疲れる場面の連続」です。
ここでは、日常の中にひそむ“見えない疲れやすさ”の具体例を、学校での場面別に解説します。
1. 授業中じっと座り続ける|「動かない」こと自体がストレスに
「ただ座って授業を聞く」__大人からすれば当たり前のことに思えるかもしれません。
しかし、多動傾向のある子にとっては、この「じっとしている」こと自体が大きなストレスです。
体を動かすことで気持ちを落ち着けている子にとっては、長時間椅子に座り続けるだけでエネルギーを消耗してしまいます。
さらに、「静かにしていないといけない」「勝手に動くと注意される」と意識すればするほど、心も緊張状態になり疲労が溜まりやすくなります。
周囲からは「落ち着きがない」と見られがちですが、本人は“動けない苦しさ”と必死に戦っているのです。
落ち着きのない子どもについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「落ち着きのない子どもは発達障害?|他の可能性とサポート方法」
2. 次々に出る指示と課題|処理が追いつかず、ずっと頭がフル回転
授業中には、「教科書を出して」「プリントを配って」「ノートを取って」「問題を解いて」など、次々と指示が出されます。
ADHDの子は、情報を整理したり、複数の指示を一度に処理したりするのが苦手なことが多く、頭の中がすぐにいっぱいいっぱいになってしまいます。
さらに、「○○日までに出してね」など、提出期限も加わると混乱しがちになります。
本人は一生懸命やっているつもりでも、ついていけないことに焦りや不安を感じ、それが“ずっと気を張っている状態”を作ります。
その結果、元気そうに見えても、内心は脳がフル稼働しており、疲弊しやすくなってしまうのです。
3. 空気を読む・合わせる|対人関係に気を使いすぎて脳が疲れる
学校でのグループ活動では、「今は黙っていた方がいいかな?」「こう言ったら嫌がられるかな?」など、周囲の空気を読む力が求められます。
ADHDの子どもは、場の雰囲気を読み取ったり、自分の発言や行動を調整したりすることが苦手な傾向があります。
だからこそ、「失敗しないように」「嫌われないように」と、無意識に神経をすり減らしていることも少なくありません。特に人間関係に敏感な子は、「うまくやらなきゃ」と気を使いすぎて、必要以上に疲れてしまうこともあります。
大人が思う以上に、子どもにとっての“対人関係”は大きなエネルギーを消耗する要因なのです。
4. 「自由な時間」がむしろ落ち着かない|予定がない=不安でいっぱい
「休み時間くらいリラックスできるでしょ?」と思われがちですが、ADHDの子にとっては「自由時間」がかえって苦手なケースもあります。
予定や指示がない時間になると、「何をしたらいいのか分からない」「声をかけるタイミングがつかめない」など、不安や戸惑いが大きくなってしまうのです。
また、急に周囲がざわついたり、活動の自由度が高まったりすることで、刺激が一気に増えてしまうという面もあります。
その場にいるだけで気持ちが落ち着かず、エネルギーを消耗してしまう子もいます。
大人から見れば「何もしていない時間」でも、子どもにとっては気を張り続ける場面であることを、頭に入れておきたいポイントです。
5. 授業・掃除・帰りの会…切り替えの連続|ADHDの脳がついていけない
学校では、一日の中で習う教科が変わり、行事があり、掃除や帰りの会があり…と、「次から次へとやることが変わる」場面がたくさんあります。
ADHDの子どもにとって、こうした“切り替え”が何よりも難しい課題です。
例えば、「授業で集中していたのに、すぐに次の準備をしないといけない」「休み時間から授業モードに戻れない」など、ひとつの活動から別の活動へスムーズに移るのが難しく、そのたびに脳が混乱しやすくなります。
この「切り替え疲れ」は積み重なると、帰宅後のグッタリ感やイライラの元になりやすいです。
表面的には問題なくこなしているように見えても、脳内では目まぐるしく場面が変わることで疲れがたまっているのです。
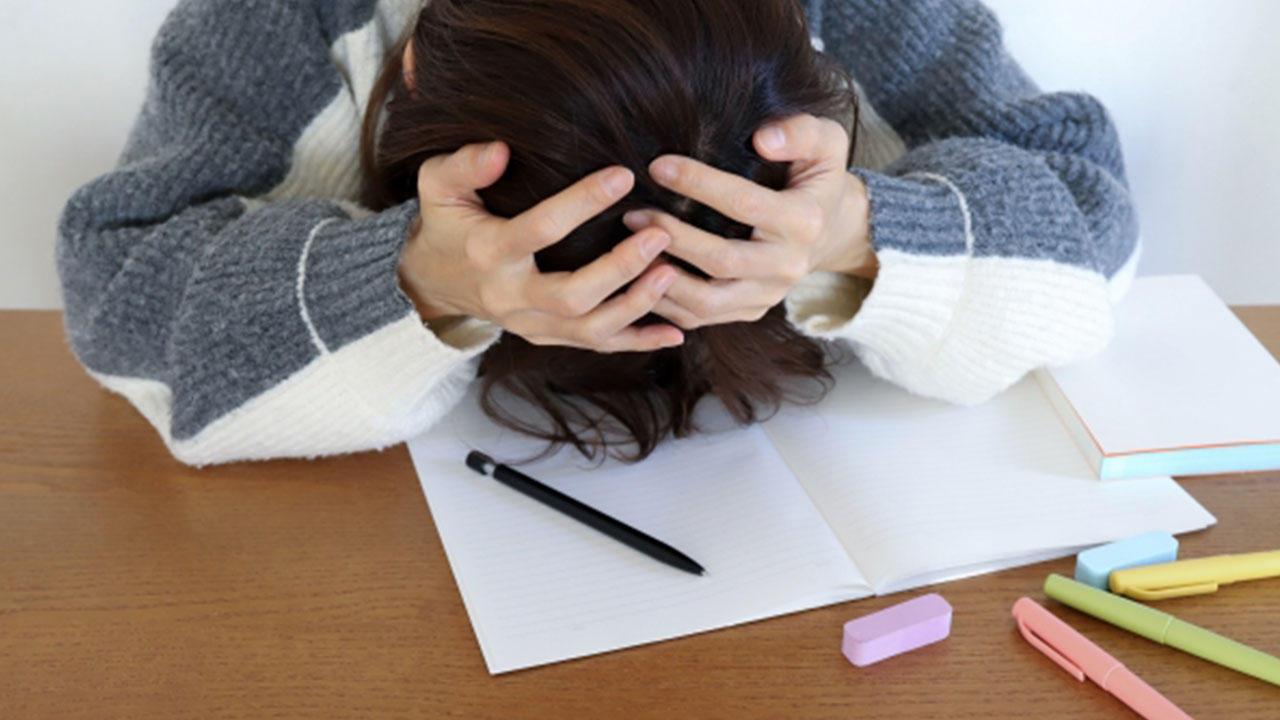
疲れがたまるとどうなる?|行動と感情に現れる“サイン”
ADHDの子どもは、毎日の学校生活や周囲との関わりの中で、目に見えにくい疲労を積み重ねていることがあります。
そしてその疲れは、徐々に「行動」や「感情」の形で表に出てきます。
一見「わがまま」や「反抗的」に見える様子も、実は「疲れきっている」というサインかもしれません。
ここでは、疲れが限界に近づいたときに出やすい変化について解説します。
1. 小さなことで爆発する・急に泣く|感情コントロールの限界
普段は落ち着いていても、些細なことをきっかけに突然怒り出したり、泣き出したりする__。
これは、感情のブレーキが効かなくなるほど疲れているサインかもしれません。
ADHDの子は元々感情をコントロールするのが難しい傾向がありますが、そこに「疲労」が加わると、より爆発的になりやすくなります。
「怒りっぽいな」「ヒステリックだな」と感じる前に、「もしかして今日は疲れてる?」という視点を持ってみると、見えるものが変わってくるはずです。
2. ダラダラ・無気力に見えても「がんばりの反動」かもしれない
帰宅後に宿題もせず、何もする気力がないように見える__そんな「ダラダラ」は、単なるサボりではなく“がんばりすぎた反動”のこともあります。
学校で全力を出し切って、家ではもう動く力が残っていない。
そんな「電池切れ」のような状態は、ADHDの特性のある子ほど起こりやすいものです。
「ちゃんとしなさい」と注意したくなる場面かもしれませんが、まずは「今日はきっとがんばったんだね」と声をかけて、心を休ませてあげることが大切です。
3. わざと?甘えてる?|幼い行動が増えるときの背景にあるもの
急に赤ちゃん言葉を使ったり、必要以上にベタベタ甘えてきたり、理由もなく拗ねたり…
年齢にそぐわないような“幼い行動”が増えることがあります。
こうした行動は、心が疲れきって安心を求めているサインとして現れていることがあります。
学校や集団生活で気を張りつづけたあと、「安心できる人に甘えたい」「受け入れてほしい」という気持ちが、わざとらしく見える形で出てくるのです。
「甘えているんじゃなく、満たされようとしている」__そんな視点で関わることで、子どもも少しずつ落ち着きを取り戻していきます。
発達障害(グレーゾーン)についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「発達障害(グレーゾーン)の中学生が幼く見える理由とは?」
4. 「学校行きたくない」が続くとき|心と体の疲労を見逃さないために
「なんとなく朝がつらい」「休みたい」「学校に行きたくない」__こうした言葉が増えてきた時、そこには身体的な疲労だけでなく、心の疲れもたまっている可能性があります。
ADHDの子は、日々「周りと合わせよう」「怒られないように」と無意識に努力しているため、知らず知らずに限界が近づいていることもあります。
それが「登校の渋り」や「体調不良」といったかたちで現れるのです。
「サボりたいだけじゃない?」と受け止めてしまう前に、「疲れがたまっていないか」「安心できているか」といった角度から見てあげることが、子どもの支えになります。
発達障害・グレーゾーンの子どもについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「発達障害・グレーゾーンの子どもが不登校になる原因とは?」

日々できる少しの工夫で変わる!|家庭での“疲労対策”アイデア
ADHDの子どもにとって、学校は思っている以上にエネルギーを消耗する場所です。
だからこそ、家に帰ってきたときの「過ごし方」が、その日の疲れを和らげる大きなカギになります。
ここでは、毎日の暮らしの中で取り入れられる、疲労を和らげる工夫を紹介します。
どれも今日からすぐに実践できることばかりなので、できるところからぜひ取り入れてみてください。
1. 帰宅後すぐに「指示しない時間」をつくる
学校から帰ってすぐに「宿題やった?」「手を洗って」「着替えて」と声をかけたくなる気持ちはよくわかりますが、子どもは既に学校で“がんばりのフルコース”を終えた状態かもしれません。
そんな時はまず、「何も言わない時間」を5〜10分でも作ってみましょう。
ランドセルを置いてホッとできる時間を確保することで、頭と心のクールダウンができ、結果的にその後の行動もスムーズになることがあります。
「おかえり、今日は疲れたでしょ。まずはゆっくりしていいよ」と声をかけるだけで、子どもにとっては大きな安心に繋がります。
2. 「静かな空間」と「安心できるリズム」を用意する
ADHDの子は、音や光、匂いなどの刺激に敏感な子も多く、家の中でもリラックスできないことがあります。
そのため、帰宅後に落ち着ける「静かな空間」があると、心身の疲れを回復させやすくなります。
例えば、カーテンを閉めて薄暗くした部屋、音楽やテレビをしばらく止める、好きなぬいぐるみやクッションを用意する__そんなちょっとした環境づくりが効果的です。
また、「帰ってきたらまず麦茶を飲む」「ひと息ついたら着替える」などの決まったリズムを作ることで、安心して切り替えができるようになります。
3. 「まだできてない」より「今日ここまでがんばったね」
宿題や片づけなど、やるべきことが残っていると、つい「早くやって」「まだ終わってないでしょ」と言いたくなる場面もあるかもしれませんが、そう言われると子どもは「また怒られた」「やっぱりダメだ」と感じてしまい、かえって動けなくなることもあります。
そんな時は、「ここまでできたね」「今日はこの頑張りがすごかったね」と、今できていることに目を向ける関わり方を心がけてみましょう。
疲れがたまっている時ほど、「認められた」「わかってもらえた」という安心感が、子どもをまた次の一歩へと後押ししてくれます。
子どもの自己肯定感についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「子どもの自己肯定感の高め方とは?|7つのNG行動についても解説」
4. スケジュールには「休む時間」もセットで入れる
「学校→宿題→お風呂→寝る」と、1日の中にやることが詰まっていると、子どもは常に“次の予定”に追われてしまいます。
ADHDの子は見通しを持つことが苦手な反面、予定が決まっていると安心する傾向があります。
だからこそ、「休む時間」もあえてスケジュールに組み込んでおくと、「今は休んでいい時間なんだ」と自分を許せるようになります。
例えば、「宿題の後に20分おやつ&自由タイム」「夕食後にゆったりタイム」など、休憩を“予定の一部”として可視化するのがポイントです。
「何もしていない時間」ではなく、「ちゃんと休んでいる時間」になることで、回復力がグッと高まります。

まとめ
ADHDの子どもが「疲れやすい」のは、決して気のせいではなく、日常の中で多くのエネルギーを使ってがんばっているからです。
}行動の裏にある見えない努力や疲れに気づき、家庭で少しの工夫を重ねていくことで、子どもが安心して力を回復できる環境が整っていきます。
無理なくできることから始めて、子どもの心と体の疲れにやさしく寄り添っていきましょう。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
























