ADHDの子どものIQは平均より低い?|関係性と正しい理解を解説
公開日:2025年10月1日
更新日:2025年10月1日
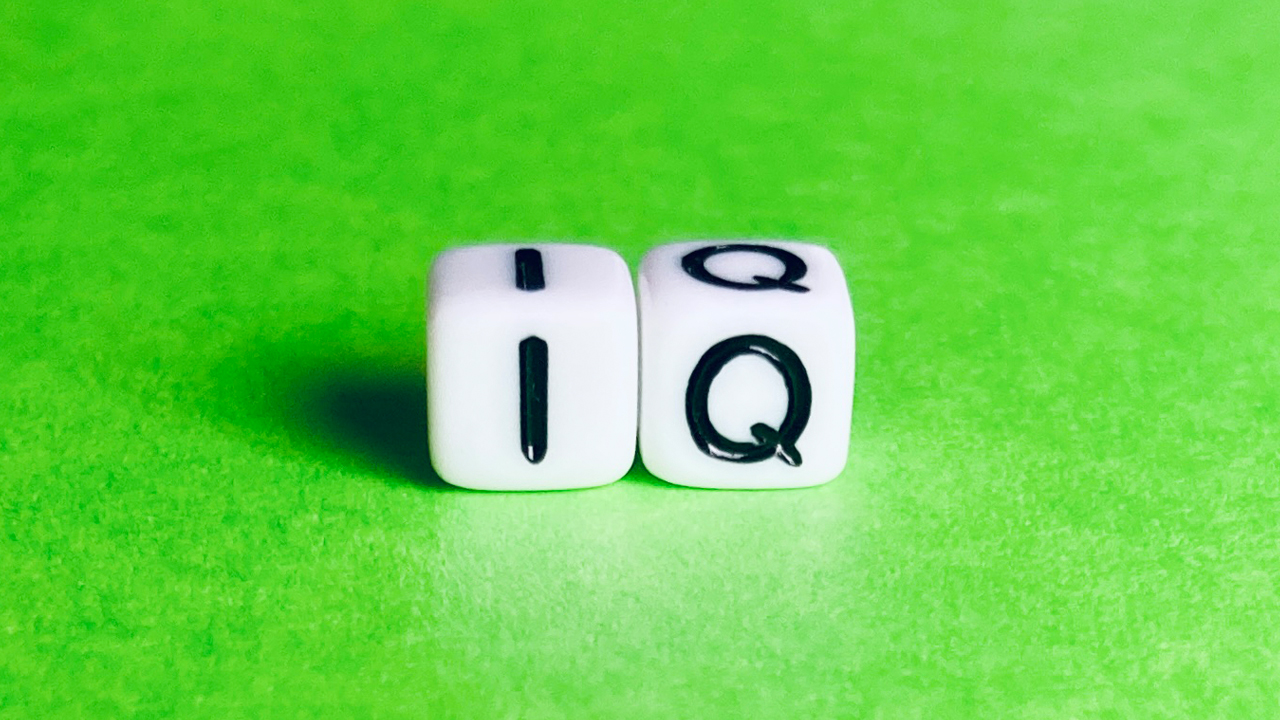
「ADHDの子どものIQは平均より低いのか?」気になる疑問にわかりやすく解説します。
このコラムでは、IQが低いとは限らないこと、幅広いばらつきがあること、そして数値にとらわれず子どもの特性や得意を理解する大切さについてご紹介します。
ADHDの子どものIQは本当に平均より低いのか?
ADHDの子どもの「IQは平均より低いのでは?」という疑問は、多くの保護者が一度は考えることです。
インターネットや周囲の声の中には、「ADHDの子は勉強ができないからIQも低い」といった誤解も少なくありません。しかし、ADHDは知能の高さそのものを示す診断ではなく、注意や行動の特徴を表すものです。実際には平均的なIQを持つ子も多く、むしろ幅広い分布を示すのが特徴です。
ここでは、誤解を解きながら正しい理解を深めていきましょう。
1. ADHDだからといってIQが低いとは限らない
まず押さえておきたいのは、「ADHD=知能が低い」という考え方は間違いだということです。
ADHDは「注意の持続」「衝動性」「多動性」などの傾向を指す診断名であり、知能指数(IQ)を直接表すものではありません。
例えば、同じADHDと診断された子でも、IQが高い子もいれば平均的な子もいます。中には学力面で大きな成果を出している子も少なくありません。
つまり、ADHDという診断だけで「IQが低い」と決めつけることはできないのです。
2. ADHDの子どものIQは幅広く分布している
一般的にADHDの子どものIQは、「低い子もいれば非常に高い子もいる」というようにばらつきが大きいことが特徴です。
これは、IQの平均値そのものは大きく下がらないものの、個人差が極めて大きいことを意味しています。実際に、ある子は平均よりやや低めに出ることもありますが、別の子はIQ120以上といった高い数値を示すこともあります。こうした幅広さは「ADHDだからIQが必ず低い」という先入観を打ち消すものです。
親御さんにとって大切なのは、「数値は一人ひとりで大きく違う」という事実を理解することです。
3. 学力(成績)とIQは別物として考える必要がある
IQと学校での成績は必ずしも一致しません。
ADHDの子どもの場合、「知識を理解する力」はあっても「課題を計画的にこなす力」や「集中を持続させる力」でつまずきやすいため、テストや提出物の成果に影響してしまうことがあります。
そのため、平均的なIQを持っていても「成績が振るわない」という現象が起こりやすいのですが、逆に、IQがそれほど高くなくても、サポートや学習方法の工夫次第で成績を上げることも可能です。
つまり、IQの数値だけを見て「学力」を判断するのは難しく、学校の成績には別の力が大きく影響していることを忘れてはいけません。
4. 「強みと弱みの凸凹」を理解することが大切
ADHDの子どもは、知能検査の中でも得意な分野と苦手な分野の差がはっきり出やすい傾向があります。
例えば、「言語理解は高いが処理速度は低い」「発想力は豊かだがワーキングメモリが弱い」といった形です。このような「凸凹(でこぼこ)」は、ADHDの子どもの特性を理解する上でとても重要なポイントです。
保護者がこの特徴を知っていれば、得意分野を伸ばしながら苦手分野を補う工夫ができます。
単純に「IQが高い」「低い」と見るのではなく、子どもの持つ凹凸を把握し、その子に合った学び方やサポートを探すことが、長期的な成長につながります。
WISC-IVの結果の見方についてもっと知りたい方はこちら
⇒「WISC-IV知能検査(ウィスク-4)の結果の見方と検査内容」
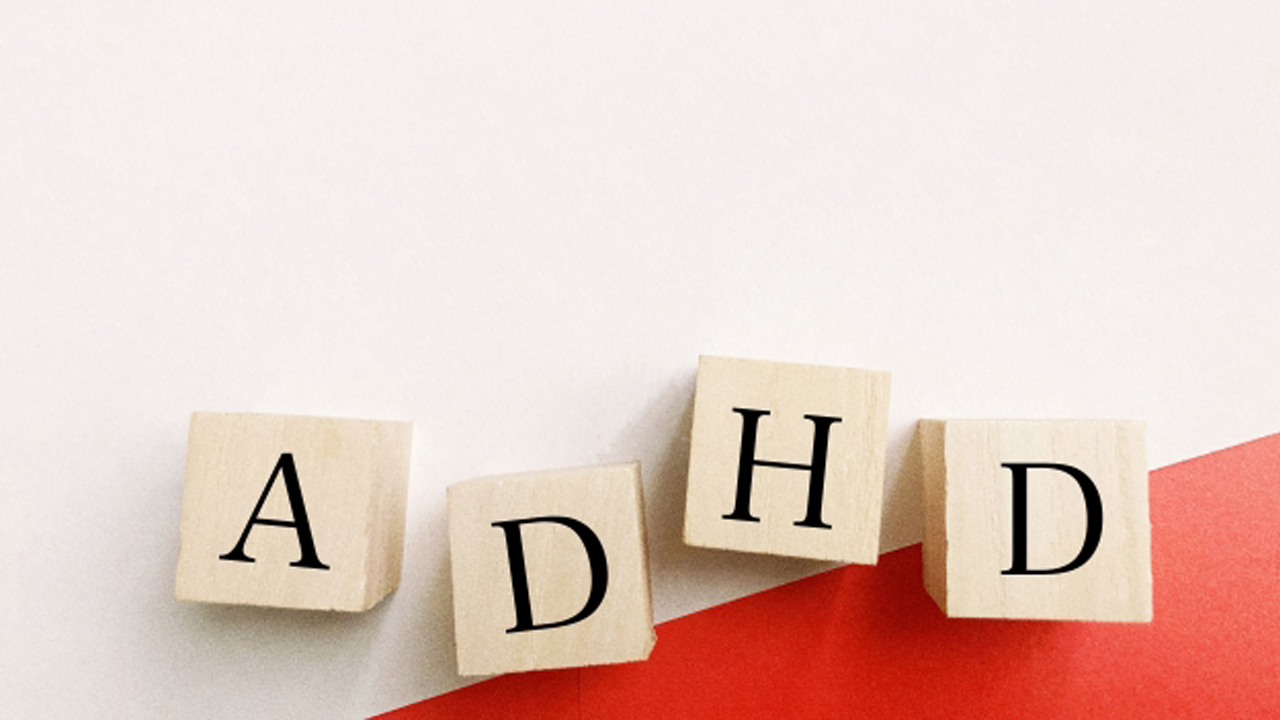
ADHDの子どもが「IQが低めに出やすい」理由
ADHDの子どもは、本来のIQは平均的であっても、IQテストの結果が低めに出ることがあります。これは「IQが低い」という意味ではなく、テストの特性や当日の状況が結果に大きく影響しているのです。
子どもの可能性を正しく見るためには、なぜそうしたことが起きるのかを知っておくことが大切です。
1. IQテストの測定方法と限界
IQテストは「一定のルールを理解し、制限時間内に正しく答える」力を前提に設計されています。つまり、テスト中に注意を持続させる力や、時間内に集中して答える力が求められるのです。
ADHDの子どもは、この「集中を続ける」ことが難しかったり、問題文を読み飛ばしたりするために、実際の力が十分に反映されないことがあります。
また、IQはあくまで知能の1つの側面を数値化したものであり、子どもの創造力やコミュニケーション能力、または興味関心のあることに関する好奇心といった要素は含まれていません。
例えば、絵を描く才能やアイデアを出す力があっても、IQテストの結果には現れないのです。こうしたことを理解しておかないと、単なる数字で子どもの力を判断してしまうことがあります。
2. 注意がそれやすく回答ミスが増えることによる影響
ADHDの子どもは「注意がそれやすい」ため、問題文を最後まで読まずに答え始めてしまうことがあります。
理解自体はできているのに、回答欄を飛ばす、数字を一桁書き間違えるといったケアレスミスが積み重なり、結果として得点が下がるのです。
例えば算数の問題で「36+27」を計算できる力があっても、途中で気が散って「36+2」だけを書いてしまうようなことがあります。本人は正しい答えを出せる力を持っていても、テスト形式だと集中が続かず誤答になってしまう__こうした「もったいないミス」が多いことが、スコアを低く見せる大きな要因になっています。
ADHDと集中力についてもっと知りたい方はこちら
⇒「ADHDと集中力の関係|過集中・不注意に悩む親のための対処ガイド」
3. 複数課題を同時に処理することの難しさ
IQテストには「聞いた情報を覚えて、その場で操作する」といった課題が含まれています。ADHDの子どもはワーキングメモリと呼ばれる「一時的に情報を頭にとどめておく力」が弱いことが多く、このタイプの課題でつまずきやすいのです。
例えば「数字を3つ言われて、それを逆の順番で答える」という課題では、最初の数字を覚えているうちに後の数字を忘れてしまうことがあります。理解はできているのに、同時に処理することが苦手なために点数が下がるのです。
これも「知能が低い」のではなく、情報を処理するスタイルの違いが影響していると捉えるべきです。
ワーキングメモリーについてもっと知りたい方はこちら
⇒「ワーキングメモリーが低い子の特徴とよくある困りごと」
4. 処理速度課題でのつまずきやすさ
IQ検査の一部には「できるだけ早く問題を解く」ことを求められる処理速度に課題があります。
ADHDの子どもは、気が散って手を止めてしまったり、丁寧にやりすぎて時間内に解き終えられなかったりすることが多いです。そのため、処理速度の数値が低めに出やすい傾向があります。
ただし、ここで低い数値が出たからといって「IQが低い」という意味ではありません。むしろ「作業を早く片づけるのは苦手だが、時間をかければ正確にできる」という特性を反映しているにすぎないのです。
このように処理速度は学力の一部に影響しますが、子どもの知能全体を決める要素ではありません。
処理速度(PSI)についてもっと知りたい方はこちら
⇒「WISCで処理速度だけが低いのはなぜ?|子どもの特徴と接し方のヒント」
5. 検査員との相性・環境要因・体調による変動
IQテストは人が実施する検査なので、検査員との相性やその日の体調に大きく左右されます。
緊張して普段のように振る舞えなかったり、部屋の明るさや雑音が気になって集中できなかったりするだけで、点数は変わってしまうのです。
また、寝不足や空腹、体調不良なども影響します。子どもが普段の力を発揮できる状態でなければ、当然スコアは低めに出てしまいます。
つまり「環境によってIQは変動することがある」という前提を知っておくと、結果に振り回されすぎずに済みます。
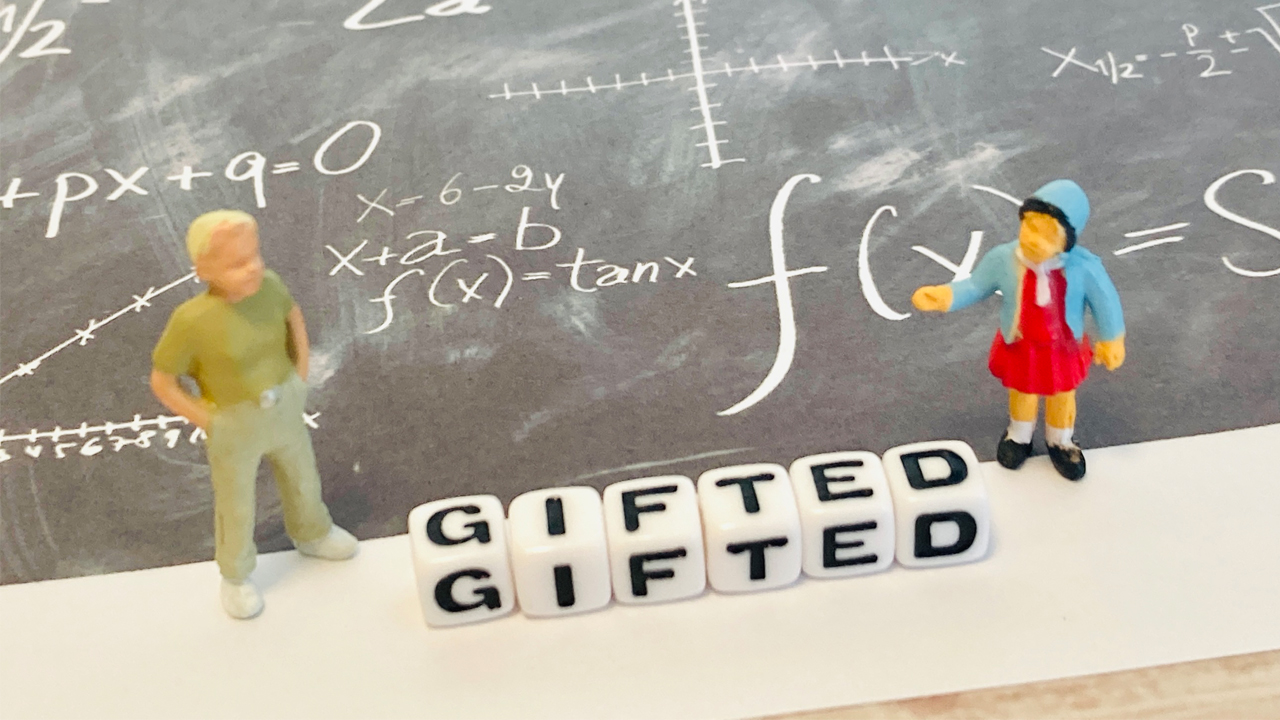
ADHDと「高IQ」|2E(ギフテッド×ADHD)の可能性
ADHDの子どもたちの中には、平均的なIQだけでなく、非常に高いIQを持つケースも存在します。このように「特定分野でずば抜けた力を持ちながら、ADHDの特性によって日常生活や学習で困難を抱える」子どもは、2E(トゥーイー)と呼ばれることがあります。
ここでは、2Eの子どもたちに見られる特徴や背景、そして支援の考え方について解説します。
1. 2Eとは?高いIQとADHD特性が同居する子どもたち
2Eとは「Twice Exceptional」の略で、特別な才能と発達特性が同時に存在する子どもを指します。
ADHDを持ちながらもIQが高い場合、知的には優れていても注意力や衝動性の面で困難を感じることが多いです。周囲からは「頭はいいのに、なぜか課題が進まない」と見られることもあり、理解されにくさから自信を失う子も少なくありません。
参照:国立社会保障・人口問題研究所「日本における2E教育の理念の指導・支援の展望」
2. 発想力や推理力など“光る領域”が見えることもある
2Eの子どもは、発想力や推理力など特定の領域で突出した力を発揮することがあります。
例えば、独創的なアイデアを思いついたり、複雑な問題を直感的に解いたりする場面です。こうした力は、一般的な授業やテストでは測りにくいため、見過ごされやすいのが現実です。
しかし、この「光る部分」を見つけて伸ばすことができれば、子どもの可能性を大きく広げることにつながります。
3. 強みがあっても学校の成績に反映されにくい背景
2Eの子どもは強みを持っていても、学校の成績にそのまま表れないことがよくあります。
これは、授業態度や提出物の管理、集中力の持続といった所でADHDの特性が評価に大きく影響するためです。
例えば、難しい問題はすぐに解けても、宿題を出し忘れる、試験でケアレスミスをするなどで評価が下がることがあります。その結果、実際の知的な力と成績との間に大きなギャップが生まれ、子どもが「自分はできない」と感じてしまうことも少なくありません。
ADHDの子についてもっと知りたい方はこちら
⇒「ADHDの子が宿題に取りかかれない理由と対策法について」
4. 得意を活かす学び方が自信につながる
2Eの子どもにとって大切なのは、苦手を無理に矯正することよりも、得意を活かす学び方を見つけることです。
得意分野で成功体験を積むことで、自信が育ち、他の分野にも前向きに取り組めるようになります。例えば、発想力に優れている子なら、プロジェクト型学習や自由研究の場でその力を発揮できる環境を整えるとよいでしょう。
大人が「この子にはこういう強みがある」と認めることが、子どもの自己肯定感を支える大きな力になります。

IQに振り回されない|ADHDの子どもへの寄り添い方
ADHDの子どもの発達を考える上で、IQは確かに一つの参考情報になります。しかし、数値だけにとらわれてしまうと、子どもの本当の力や可能性を見失う危険があります。
大切なのはIQを「判断のゴール」ではなく、「理解のヒント」として活用することです。ここでは、親が持つべき心構えをまとめます。
1.「IQ=頭の良さ」ではなく理解の手がかりとして捉える
IQはあくまで子どもの特性を知るための一要素にすぎません。
IQが高いからといって万能というわけではなく、逆に低めに出たからといって能力全体が劣っているわけでもありません。
例えば、コミュニケーション能力や創造力はIQスコアでは測れない領域です。親が「IQは頭の良さそのもの」と思い込むのではなく、子どもを理解する手がかりの一つと捉えることが大切です。
2. IQより「何が得意で何が苦手か」を見極める
子どもの成長を支える上で本当に重要なのは、得意分野と苦手分野を具体的に把握することです。
例えば、処理速度が遅くても言語理解が強ければ、本を読んで学ぶことに力を発揮できるかもしれません。逆に言語理解が苦手でも、空間認知や図形の把握が得意なら理科の実験や図工で才能を伸ばせます。
親が数値ではなく「どこで力を出せるか」に注目することで、学びの場を工夫することができます。
3. IQが高くても支援が不要になるわけではない
IQが高くても、ADHD特性による困りごとは残ることがあります。
注意がそれやすい、忘れ物が多い、計画的に課題を進めるのが苦手、といった特徴はIQの高さにかかわらず現れるのです。
そのため、IQが高い子どもでも「支援が必要ない」と判断するのは誤りです。むしろ、学習環境を整えたり声かけを工夫したりすることで、持っている力をさらに活かせるようになります。
4. 苦手克服より「得意を伸ばす」発想が成長を助ける
ADHDの子どもを支える時、どうしても「苦手を直すこと」に注目してしまいがちです。しかし、得意分野を伸ばすことが自信と成長につながるケースは多いのです。
例えば、絵や発想力が得意なら、それを評価される体験が自己肯定感を高めます。その結果、苦手な分野にも前向きに取り組めるようになることがあります。
親は「苦手をゼロにする」より「得意を活かす」方向に意識を向けることが、子どもの力を引き出す大きな支えになります。
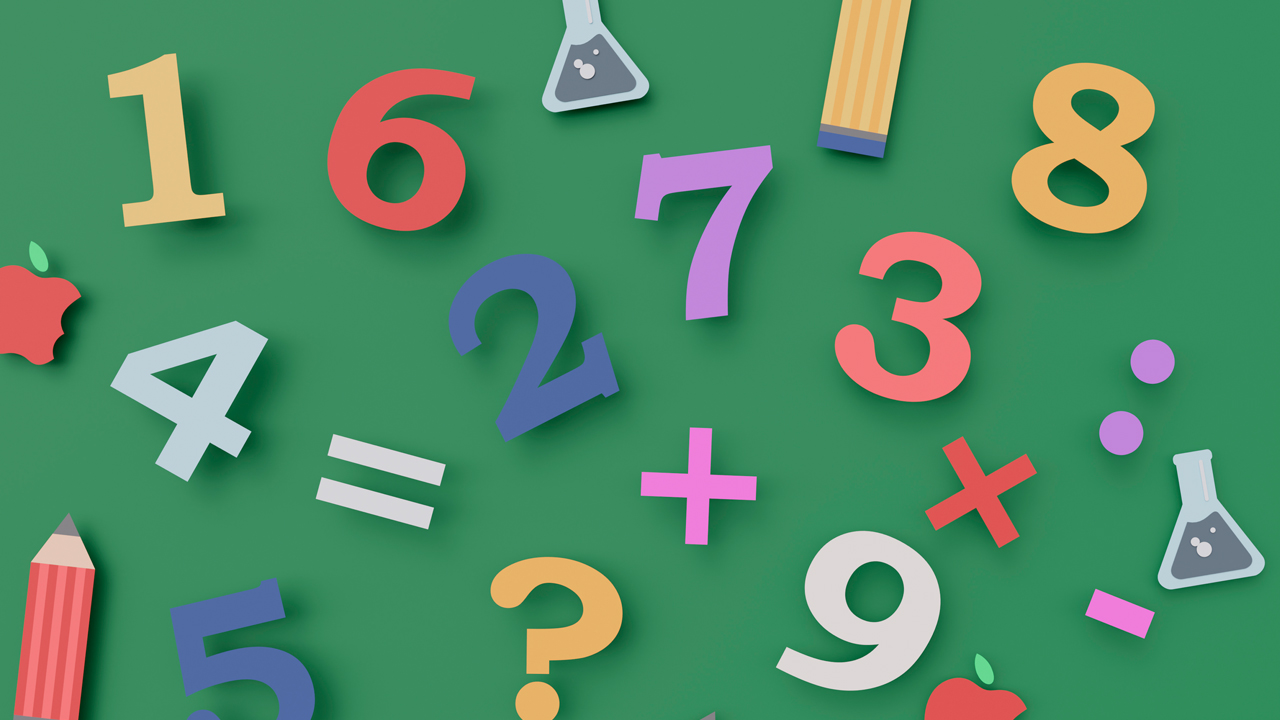
まとめ
ADHDの子どものIQは、平均より低いとは限らず、幅広いばらつきと得意・不得意の差が特徴です。大切なのは数値そのものに振り回されず、子どもの特性を理解し、強みを伸ばす視点を持つことです。
IQは一つの目安にすぎず、子どもの成長を支えるのは日々の関わりと環境づくりにあります。
家庭教師のマスターでは、ADHDのお子さんに向けた学習サポートを行っています。ご興味のある方は気軽にご相談ください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
ADHDの子が宿題に取りかかれない理由と対策法について
-
【高校生向け】ADHDの診断方法とは?
-
ADHDの子が片付けられない理由とは?|6つの改善策もご紹介!
-
ADHDの子どもの忘れ物が減る!親ができる対策&声かけガイド
-
ADHDと集中力の関係|過集中・不注意に悩む親のための対処ガイド
-
学校から帰るとグッタリ…ADHDの子が“疲れやすい”本当の理由とは?
-
「また逃げた…」ADHDの子どもが嫌なことから逃げる本当の理由とは?
-
ADHDの子どもの好きな人への態度とは?
-
勉強ができるADHDの子の“見えにくい困りごと”と、家庭でできる支援のヒント
-
WISC-4の知覚推理(PRI)が低いとどうなる?|子どもの特徴と支援法
-
ワーキングメモリーが低い子の特徴とよくある困りごと
-
落ち着きのない子どもは発達障害?|他の可能性とサポート方法
-
発達障害グレーゾーンの中学生の特徴|判断の仕方やサポート方法について
-
発達障害チェックリスト【中学生のお子さん向け】























