特別支援学級に入る基準とは?|判断の目安と入級までの流れを解説
公開日:2025年11月5日
更新日:2025年11月5日

特別支援学級に入る基準がわからず迷っていませんか?このコラムでは、判断の目安や入級までの流れ、メリット・デメリットをわかりやすく整理しました。
「通常学級か、特別支援学級か」で悩む保護者の方が、判断の目安を整理できる内容です。
特別支援学級とは?|通常学級との違いと対象となる子ども
特別支援学級は、学習や生活において特別な支援が必要な子どもが通うために設けられた学級です。通常学級とは指導体制や学習内容が異なり、子ども一人ひとりの特性に合わせた教育を受けられるのが特徴です。
ここでは、通常学級との違いや対象となる子どものタイプ、受けられる支援について解説します。
1. 特別支援学級と通常学級の違い
通常学級では、1クラスあたり30〜40人程度の生徒が一緒に学びます。カリキュラムは全国共通で、授業の進度も全員に合わせた形で進みます。
これに対して特別支援学級は、少人数制(おおむね6〜8人)で構成されるのが大きな特徴です。
また、担任の先生は特別支援教育に関する専門知識や資格を持っており、子ども一人ひとりに合わせた指導計画を作成します。通常学級では難しい個別対応や、生活面でのサポートも含めてきめ細かく支援が行われます。
多くの学校では交流学習といって、特別支援学級の子どもが通常学級の授業や行事に一部参加する仕組みがあります。これにより、集団生活を経験しながら無理なく成長できる環境が整えられています。
2. 対象になる子どもの特性とタイプ
特別支援学級の対象は、学習や行動に著しい困難があり、通常学級だけでは十分な支援が難しい子どもです。具体的には、次のような特性を持つ子どもが対象になります。
・発達障害の特性が強く表れている場合
例:自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)など
・知的発達の遅れがある場合
例:学年相当の学習内容を理解することが極めて難しい
・身体的な障害や病気によって日常生活に配慮が必要な場合
例:強い聴覚障害があり、集団授業ではなく個別支援を必要とする場合
ただし、これらの特性があっても、通常学級での合理的配慮や支援だけで対応できる場合は、特別支援学級への入級が必須ではありません。
判断の基準は「本人が安心して学べるか」「将来の成長にとってどちらが良いか」という視点が重視されます。
3. 特別支援学級で受けられる主なサポート内容
特別支援学級では、子どもの特性や困りごとに応じてオーダーメイドの支援が行われます。主な支援内容は以下のとおりです。
個別の教育計画に基づく指導
その子に合った目標を設定し、ペースに合わせて学習を進めます。通常学級よりもゆっくりと、理解を確認しながら授業を進めるため、無理なく力を伸ばせます。
生活面でのサポート
集団行動が苦手な子どもには、朝の会や給食、掃除など日常生活の中でも先生が声かけや補助を行い、安心して学校生活を送れるように支えます。
専門職との連携
言語聴覚士、スクールカウンセラー、特別支援コーディネーターなど、専門家との連携を図りながら多角的に支援を行います。
このように、特別支援学級では単に「勉強を教える場」ではなく、子どもの心身の発達を総合的に支える環境が整えられているのが特徴です。

特別支援学級に「入れるかどうか」の基準はどう決まる?
「うちの子は特別支援学級に入るべきなのかな…」と悩む保護者は少なくありません。ここでは、入級を検討する際の判断材料や、決定までの流れをわかりやすく解説します。
1. 判断材料となるチェックポイント
特別支援学級への入級は、医師の診断だけで決まるわけではありません。学校生活の様子や学習の進み具合など、複数の視点から総合的に判断されます。
以下のサインが見られる場合は、早めに学校や専門機関に相談してみましょう。
学習面で見られるサイン
・学年相当の内容を理解するのが難しく、繰り返し練習しても身につきにくい
・文字の読み書きや計算が極端に苦手で、授業のペースについていけない
・テストやプリントでケアレスミスが頻発し、学習意欲が下がってしまう
行動、生活面で見られるサイン
・集団行動が苦手で、授業中に席を立つ、教室を飛び出すなどの行動が多い
・強いこだわりや感覚過敏があり、学校行事や給食、掃除などで大きなストレスを感じる
・友達との関係がうまくいかず、トラブルや孤立が繰り返される
保護者や先生が感じやすい悩みのサイン
・毎朝「学校に行きたくない」と訴え、登校しぶりや不登校が続く
・家庭でも宿題や身支度をめぐって毎日のように親子げんかになる
・先生から「このまま通常学級だけでは難しいかもしれない」と相談を受けている
2. 最終決定者は誰?
特別支援学級に入るかどうかの最終決定権は教育委員会にあります。
しかし、教育委員会が一方的に判断するのではなく、担任や学校長、専門機関の意見を踏まえて協議が行われます。
保護者の意向も重要視されるため、保護者が同意しない限り無理に入級させられることはありません。
そのため、学校との相談や情報共有を丁寧に重ねていくことが必要です。
3. 全国一律の数値基準がない理由
「IQ〇〇以下なら特別支援学級」というような全国一律の基準は存在しません。
その理由は、子どもの困りごとは数値だけでは測れないためです。
同じIQでも、日常生活がスムーズに送れる子もいれば、強い困難を抱える子もいます。そのため、判断は自治体ごとの基準や学校での様子をもとに、多角的な視点で総合的に行われるのが現状です。
発達障害とIQのホントの関係についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「発達障害とIQのホントの関係とは?|子どもの可能性を正しく理解しよう」
4. 入級が決まるまでの流れ5ステップ
STEP1:相談の開始(担任・学校・専門機関)
最初のきっかけは、担任や保護者からの相談です。学校での様子を共有しながら、支援が必要かどうかを話し合います。
STEP2:情報収集と評価(発達検査・観察記録)
心理士による発達検査や、学校での観察記録、保護者の聞き取りなどを通して、子どもの特性を多角的に評価します。
STEP3:就学支援(教育支援)委員会での検討
教育委員会内の専門機関が集まり、支援の方向性を協議します。ここで特別支援学級への入級が適切かどうかを慎重に検討します。
STEP4:保護者との合意形成
検討結果をもとに学校側から保護者に説明があり、同意を得るための話し合いが行われます。保護者が納得することが何よりも重要です。
STEP5:教育委員会による最終決定・通知
最終的に教育委員会が決定し、正式な通知が届きます。
この後、学校と連携して新学期からのサポート準備が始まります。
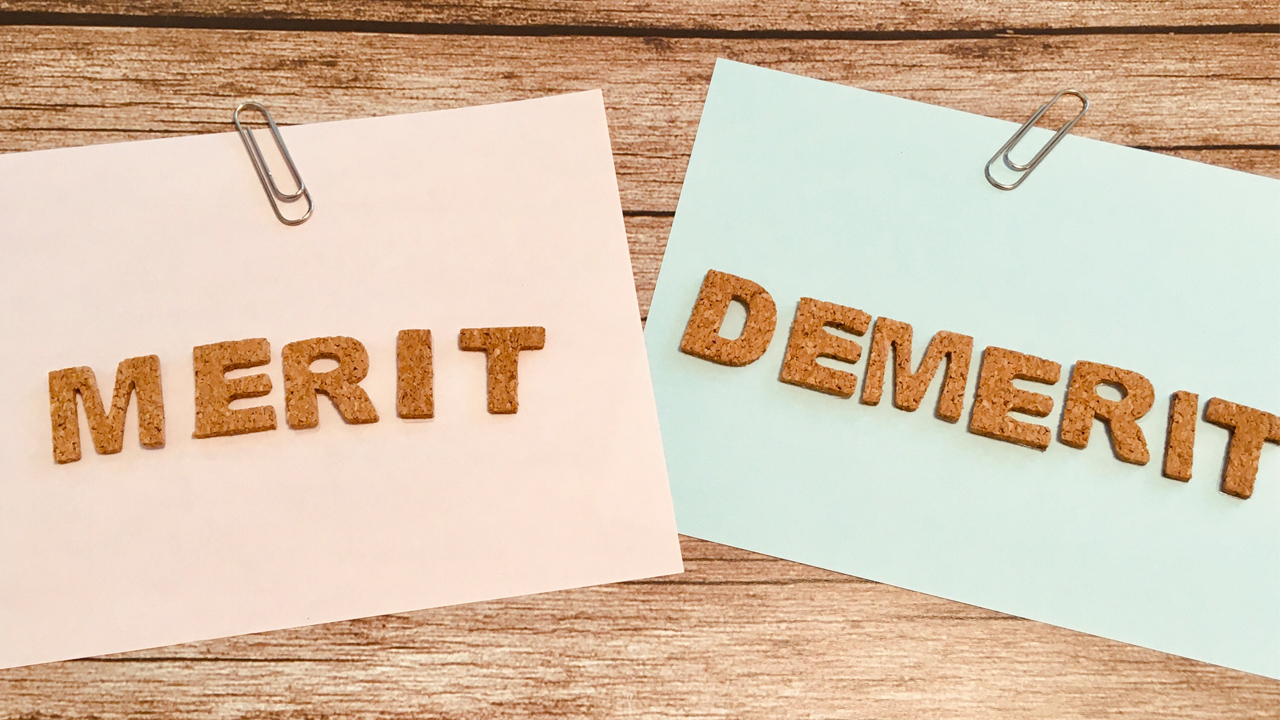
特別支援学級に入るメリットとデメリット
特別支援学級には、子どもの学びやすさをサポートするための工夫がたくさんありますが、一方で通常学級とは異なる点もあります。
入級を検討する際は、子どもの現在と将来の両面を考えながら、保護者・学校・専門機関が一緒に方向性を決めていくことが大切です。
ここでは、実際に通うことで得られるメリットと、注意しておきたいデメリットを整理して解説します。
1. メリット
特性に合わせた環境で学べる
特別支援学級は少人数制(6〜8人程度)で構成されており、先生の目が一人ひとりに行き届きやすい環境です。
学習面だけでなく、生活面での困りごとにも寄り添いながら、安心して学校生活を送ることができるのが大きな強みです。
また、子どもの特性に応じて教材や教え方を柔軟に変えられるため、「わからないまま進んでしまう」という不安を減らせます。
専門的な支援を受けやすい
特別支援学級の先生は、特別支援教育に関する専門知識を持っています。
発達障害や学習障害への理解が深く、子どもが抱える困難に合わせて適切な声かけや支援を行います。さらに、スクールカウンセラーや言語聴覚士など専門職との連携も進めやすく、家庭では対応が難しい部分まで支えてもらえるのも大きなメリットです。
個別支援計画に基づいた学びができる
特別支援学級では、子ども一人ひとりに合わせた個別の教育支援計画が作成されます。
この計画に基づき、学習の目標や支援方法が明確にされるため、成長を長期的な視点で見守ることができます。
「少しずつでも確実に前進している」という実感が得られることで、子どもの自己肯定感の向上にもつながります。
2. デメリット
学習進度が通常学級と異なることがある
特別支援学級では、子どもに合わせたペースで授業を進めるため、教科書の進度が通常学級よりゆっくりになる傾向があります。
このため、中学進学や高校進学を見据えたときに、通常学級との学習のギャップが生じることがあります。
ですので、必要に応じて家庭内での学習フォローや外部サービス(塾など)を利用し補習することも検討が必要です。
同学年の子との関わりが減りやすい
特別支援学級は少人数のため、どうしても同学年の友達との関わりが少なくなることがあります。
学校によっては交流学習の時間を設けていますが、通常学級での人間関係づくりが難しく、孤立感を覚える子もいます。
ですので、保護者や先生が意識的に交流の機会を作ることが大切です。
通常学級への戻りが難しくなるケースもある
一度特別支援学級に入ると、通常学級への復帰が簡単ではない場合があります。これは、特別支援学級での学習進度や授業スタイルが通常学級と大きく異なるためです。
戻る際には、学校や教育委員会とよく相談しながら、段階的に進める必要があります。
発達障害の子に合った高校の選び方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「発達障害の子に合った高校の選び方|進路の選択肢と地域の受け入れ校を紹介」

迷った時に相談できる場所と活用のコツ
「特別支援学級に入るべきかどうか…」と迷った時は、保護者だけで悩まず、信頼できる相談先に話をすることが大切です。
ここでは、相談できる主な場所と、それぞれをうまく活用するコツを解説します。
1. 学校(担任・特別支援コーディネーター)
最初の相談先として一番身近なのが学校です。
まずは担任の先生に、授業中や休み時間の様子を具体的に聞いてみましょう。学校では、子どもの集団での行動や友達との関わりがよくわかるため、家庭では気づきにくい視点からアドバイスがもらえます。
また、多くの学校には「特別支援コーディネーター」という役割の先生がいます。
これは、特別支援教育に関する専門的な知識を持ち、学校内外の支援をつなぐ役割を担う先生です。
迷いが大きい時は、担任だけでなくコーディネーターも交えて相談すると、より具体的な支援策や次のステップが見えてきます。
活用のコツとしては、相談時に、子どもの様子を記録したメモや家庭での困りごとを具体的に伝えることがポイントです。記録があることで、支援の方向性を決めやすくなります。
2. 自治体の教育相談窓口
各市区町村には、保護者や学校からの相談を受け付ける教育相談窓口があります。
ここでは、専門スタッフが子どもの発達や学習に関する悩みを聞き取り、必要に応じて発達検査や面談を行ってくれます。
特に、「学校に相談はしているけれど、第三者の意見も聞きたい」という場合に有効です。
自治体レベルでの支援制度や手続きの流れも案内してもらえるため、特別支援学級への入級を具体的に検討する際に心強い味方になります。
活用のコツとしては、予約が必要なことが多いので、早めに連絡を取り、相談内容を簡単にまとめておくとスムーズです。
3. 児童発達支援センターや専門機関
子どもの発達に関する困りごとが大きい場合は、児童発達支援センターや専門機関に相談することも選択肢の一つです。
ここでは心理士や言語聴覚士などの専門家が、発達検査やトレーニングを通じて子どもの特性を詳しく見極めてくれます。
また、日常生活や学習に活かせる具体的な支援方法や家庭での関わり方を教えてもらえるのも特徴です。
学校や自治体と連携してサポートしてくれることも多く、特別支援学級の検討においても重要な役割を果たします。
活用のコツとしては、初めて利用する場合は、紹介状や学校からの情報提供書類が必要になることもあるため、事前に確認して準備しておくと安心です。

まとめ
特別支援学級への入級は、子どもの特性や将来を考えたうえで、保護者と学校、専門機関が一緒に考えていく大切な選択です。
迷った時は一人で抱え込まず、信頼できる相談先に話すことで、子どもにとって最も安心できる学びの場が見えてきます。
焦らず時間をかけて話し合い、納得できる形で進めていくことが何よりも大切です。
家庭教師のマスターでは、発達障害のお子さんに向けた学習サポートを行っています。ご興味のある方は、気軽にご相談ください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
発達障害の小学生|その特徴や症状の理解、支援方法や接し方を解説
-
発達障害の中学生の特徴と支援法
-
発達障害グレーゾーンの中学生の特徴|判断の仕方やサポート方法について
-
学習障害(LD・SLD)の診断テスト|症状別チェックリストをご紹介
-
勉強をしない中学生|発達障害のタイプ別に対策法をご紹介!
-
発達障害チェックリスト【中学生のお子さん向け】
-
発達障害のある女子中学生の特徴とは?|支援方法も解説します
-
発達障害の子どもを育てるのに疲れた方へ|大切な考え方と具体的な対策とは
-
WISC-IV知能検査(ウィスク-4)の結果の見方と検査内容
-
WISCで処理速度だけが低いのはなぜ?|子どもの特徴と接し方のヒント
-
算数障害の子どもの特徴とサポート方法を解説【簡易チェックリスト付き】























