高校中退する人の特徴とは?|原因と傾向、中退後の進路や対処法まで解説
公開日:2025年8月6日
更新日:2025年8月6日

このコラムでは「高校中退する人の特徴」について詳しく解説します。中退に至る原因や背景、共通する傾向、中退を考えるときの注意点、中退後の進路や支援制度についても紹介します。
自分や身近な人に当てはまるかもしれないと感じた方へ、今できることをわかりやすくまとめています。
なぜ高校を中退するのか?|6つの主な理由と背景
高校を中退する理由は人によってさまざまですが、大きく分けると共通する傾向が見えてきます。
文部科学省の統計による令和5年度の調査では、全国で46,238人が中途退学し、中退率は約1.5%に達しました。中退理由としては、『進路変更』が41.3%で最も多く、『学校生活・学業不適応』も34.2%を占めます。『問題行動等』が原因となるケースは3.3%と少数派ですが、軽視できない実態です。
ここでは、よく見られる中退の理由を6つに分けて、それぞれの背景を詳しく解説します。
1. 不登校や学業不振からの中退
中退理由の中で特に多いのが、「学校に行けなくなった」「勉強についていけなくなった」といった、不登校や学業不振に起因するケースです。
中学校までとは異なり、高校では学習内容が急に高度になり、テストや課題の難易度も上がります。それに加えて、周囲との競争やプレッシャーが強くなり、「自分はダメだ」と感じてしまうことも多くなります。
また、不登校になることで単位が取れず、進級や卒業が難しくなり、やむなく中退を選ぶ生徒も少なくありません。
2. 人間関係・いじめによる離脱
いじめや人間関係のトラブルがきっかけで、学校に居づらくなり中退するケースもあります。
クラス内での孤立、部活動での上下関係、SNSでのトラブルなど、高校生を取り巻く人間関係は複雑です。表面的には目立たないストレスが積み重なり、「学校に行きたくない」「朝がつらい」と感じるようになっていきます。
いじめが表面化しないまま、本人の限界を迎えて中退という形になる場合もあります。
3. 非行・問題行動による離脱
学校のルールを守れなかったり、素行上の問題から中退に至るケースもあります。これは非行・問題行動による中退です。
例えば、無断欠席の常習化、暴力行為、薬物や万引きといった行為が原因で停学・退学処分になることもあります。中退者全体の中では割合は2〜3%程度ですが、学校や保護者との関係が悪化したまま中退に至るという点で、再出発が難しくなるリスクもあります。
非行に走る背景には、家庭環境や過去のトラウマなど、外からは見えにくい事情が隠れていることも多いです。
4. 家庭の事情や経済的な問題
家庭の経済的な事情や家庭環境の変化によって、高校を続けられなくなる生徒もいます。
例えば、「家計を支えるために働かざるを得ない」「親が転職・離婚し、引っ越しを伴う」など、本人の意志とは関係のない事情で通学が困難になる場合があります。
また、親が教育に理解を示さず、「働いた方がマシ」といった価値観を押し付けられて中退を余儀なくされるケースもあります。
このような背景では、学力や人間関係に問題がなかったとしても、「通うこと自体が現実的に難しい」状況に追い込まれてしまうのです。
5. 進路変更や夢のための自主的な中退
近年増えているのが、「進路変更」や「夢を叶えるため」といったポジティブな理由での自主的な中退です。
例えば、プロのスポーツ選手や芸能活動を目指すために専門的な環境に移る、起業や海外留学を目指す、といったケースが該当します。また、「高校が自分に合っていない」「別の通信制やサポート校で学びたい」といった動機も含まれます。
このような中退は決して後ろ向きなものではなく、人生を自分で選び取る前向きなステップとして位置づけられることもあります。ただし、準備や将来の見通しが不十分なまま動くと、途中で壁にぶつかるリスクもあります。
6. 精神的な不調・メンタル面での悩み
見落とされがちですが、うつや不安障害、パニック障害など、メンタル面の不調によって中退を選ぶ生徒も少なくありません。
思春期は心身ともに不安定になりやすく、「理由はわからないけどとにかく学校がつらい」「誰にも話せない」といった状態が続くことがあり、学校生活や人間関係のストレスが蓄積し、心身のバランスを崩してしまうケースもあります。
このような場合、本人に「甘えている」「怠けている」といったレッテルが貼られることもあり、相談や支援につながりにくくなってしまうのが大きな課題です。

高校を中退する人に見られる6つの特徴とは?
高校を中退する理由はさまざまですが、その背景には「中退に至りやすい傾向や特徴」が見え隠れしています。もちろん、すべての人に当てはまるわけではありませんが、共通して見られる性格や環境要因が、中退の決断を後押ししてしまうケースは少なくありません。
ここでは、実際に多く見られる6つの特徴について解説します。
1. 自己肯定感が低くなりやすい傾向
「どうせ自分なんて…」と感じやすいタイプは、失敗や他人との比較から自信を失いやすく、学校生活が苦痛に変わってしまうことがあります。
努力が結果につながらなかった経験や、周囲からの評価が低かったことなどが積み重なると、自分の存在価値そのものに疑問を抱いてしまうこともあります。そうなると、勉強や人間関係に前向きになれず、次第に「学校に行く意味がわからない…」と感じるようになるのです。
子どもの自己肯定感についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「子どもの自己肯定感が低いのは親のせい?|原因と家庭でできるサポート方法」
2. 周囲に相談しにくい環境にある
困っていることがあっても、気軽に相談できる大人や友人がいないという環境も、中退につながりやすい要因のひとつです。
家庭内でのコミュニケーションが少なかったり、学校で孤立していたりすると、自分の悩みを誰にも話せず抱え込んでしまいがちです。中には、「先生に話してもどうせ理解してくれない」「親に言っても怒られるだけ」と感じ、ますます閉じこもってしまう生徒もいます。
孤独や無力感が強くなると、「学校に行かない」という選択が唯一の逃げ道になってしまうこともあります。
3. 反抗的・飽きやすい性格
ルールや上下関係に対して強く反発したり、物事に対してすぐに飽きてしまうタイプの生徒は、学校という集団の枠組みに適応しにくい傾向があります。
授業に集中できない、教師の指示に反発する、やる気が続かない__こうした行動が繰り返されるうちに、周囲との摩擦が増え、本人の居場所がなくなっていくこともあります。特に思春期は、自我が強くなり、「自分の思い通りにいかないなら辞めたい」という思考に至りやすくなる時期です。
反抗期についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「反抗期はいつから始まり、いつ終わるの?|接し方や注意点を徹底解説」
4. こだわりや完璧主義で挫折しやすい
一見すると真面目で頑張り屋に見えるタイプでも、完璧を求めすぎる性格は、中退のきっかけになることがあります。
「100点を取らないと意味がない」「失敗するくらいならやらない方がいい」といった思考に縛られると、小さなミスやつまずきでも大きな挫折感につながってしまいます。
また、周囲と自分を比べて「自分はダメだ」と思い込んでしまい、学校生活に耐えられなくなることも少なくありません。
5. 「ただ面倒くさい」など興味喪失型
特定の大きな原因があるわけではないものの、「なんとなく面倒」「やる意味を感じない」といった無気力・興味喪失型の傾向もあります。
授業がつまらない、校則がうるさい、人間関係が面倒くさい…そんな小さなストレスが積み重なり、次第に「行かなくてもいいかな」という気持ちになっていくのです。
特に目標やモチベーションがはっきりしていない場合、この「なんとなく」の感覚が続き、気づけば中退という選択に流れてしまうケースもあります。
6. 学校に馴染めない“違和感”を抱えている
「ここにいると自分が自分でいられない」__そんな漠然とした違和感や生きづらさを抱えている生徒もいます。
周囲と価値観が合わない、校風が息苦しい、友達づきあいがうまくできないなど、はっきりと言語化はできないけれど「なんとなく合わない…」と感じている状態です。
この“居心地の悪さ”は本人にしかわからないため、周囲からは「普通に見える」のに、本人の内面では強いストレスが蓄積していることもあります。

高校を中退する前に考えるべき3つのこと
「もう学校に行けない」「辞めたい」と思ったとき、つらさのあまり中退という選択が“今すぐの解決策”に見えてしまうことがあります。
しかし、高校を中退するというのは、大きな人生の分岐点です。後から「もう少し考えておけばよかった」と後悔する人も少なくありません。
ここでは、中退を決断する前にぜひ立ち止まって考えてほしい3つのポイントを紹介します。
1. 「本当に他の方法はないのか?」を見直す
「中退しかない」と思い込んでしまう前に、「他に選べる手段がないか?」を一度冷静に見直してみましょう。
例えば、不登校が続いていても、保健室登校や別室登校、スクールカウンセラーのサポートを受けながらの復帰という方法もあります。クラス替えや転校などで環境を変えることで、状況が好転するケースもあります。
また、勉強についていけないと感じている場合は、通信制高校やサポート校への転学も一つの選択肢です。中退=すべてをリセットすることではなく、“柔軟に環境を変える”ことでも改善できる可能性があるという視点を忘れないでください。
2. 「中退後にどうしたいのか?」を考えておく
中退すること自体が目的になってしまうと、その後に何をするべきか分からず、立ち止まってしまう人が多くいます。
「中退したあと、自分はどうしたいのか?」という視点を持つことがとても重要です。
進学を考えているのか、働きたいのか、それとも少し休みたいのか__高卒認定試験を受けて大学や専門学校を目指す道もありますし、通信制高校への再入学という選択肢もあります。
「辞めたあとに何をするか」まで考えておくことが、中退を前向きな選択に変えるカギになります。
3. 「相談できる人はいるか?」を確認する
どんな選択をするにしても、信頼できる人に相談することはとても大切です。
親や先生、スクールカウンセラー、地域の支援機関など、自分の気持ちを受け止めてくれる人が周りにいるはずです。
「他人に迷惑をかけたくない」「どうせ理解してもらえない」と感じてしまうこともあるかもしれませんが、悩みを一人で抱え込むことこそがリスクです。
誰かと話すことで視野が広がり、自分では思いつかなかった選択肢が見えてくることもあります。
もし身近に頼れる人がいないと感じる場合は、若者向けの支援窓口やオンライン相談などを活用するのも一つの方法です。

高校中退後の進路はどうなる?
高校を中退したからといって、人生が終わるわけではありません。今の時代、中退後にも進める道はいくつもあります。
とはいえ、進路によっては社会的なハードルや厳しさも存在します。
ここでは、中退後にどのような進路があるのか、現実的な側面と可能性の両方を踏まえてご紹介します。
1. 就職・アルバイトからの社会参加
高校中退後、すぐに働き始めるという選択肢をとる人もいます。飲食業や工場、配送、介護、接客業など、中卒でも雇ってもらえる職種はあります。
アルバイトから始めて仕事経験を積み、正社員登用を目指す人もいますが、中卒というだけで選考から外れる企業も多く、正社員として安定的に働くのは決して簡単ではありません。
また、キャリアの選択肢が限定されやすく、年齢を重ねるごとに転職や昇進のハードルが高くなる傾向もあります。働く道を選ぶ場合は、職業訓練や資格取得支援などを活用することで、将来の可能性を広げる工夫が必要です。
高校中退後の就職についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高校中退後の就職ガイド|自分に合った進路を見つけ、キャリアアップを目指す方法」
2. 高卒認定試験を取得して進学する道
高校を中退しても、高卒認定試験(旧:大検)に合格すれば、大学・短大・専門学校への進学が可能です。
中退した時点では「高卒」ではありませんが、高卒認定を取得することで、「大学受験資格」を持つことができます。実際に高卒認定を経て大学に進学する人も増えており、中退=学歴を諦める、ということではないということが広く知られるようになっています。
高卒認定試験は、独学でも勉強は可能ですが、通信教育や予備校、オンライン講座を利用して効率的に学ぶ人も多くいます。
高卒認定試験についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「高卒認定試験は簡単すぎ?|難易度や合格率などについて詳しく解説」
3. 通信制・定時制高校への再入学
高校中退後、もう一度高校に入り直すという道もあります。
例えば、通信制高校や定時制高校では、自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムが用意されており、働きながら通うことも可能です。
中退した高校とは別の学校に再入学することで、新たなスタートを切る人もいます。「今の学校が合わなかった」だけであって、「高校という仕組み自体が合わない」とは限りません。
再入学には一定の手続きと条件がありますが、卒業すれば正式な「高校卒業資格」が得られるため、進学や就職の選択肢が大きく広がります。
通信制高校についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「通信制高校とは?気になる仕組みを徹底解説!」
4. 中卒のまま社会に出る厳しさとは?
高校を中退すると、学歴上は「中卒」となります。これは現実問題として、社会に出るうえでの“壁”になることもあります。
例えば、求人情報の多くが「高卒以上」を条件にしており、中卒では応募できない職種や会社も多く存在します。また、正社員になれる確率や初任給、昇進のスピードなどでも差が出やすく、長期的な年収や待遇に影響する可能性があります。
さらに、社会的な偏見や自己肯定感の低下に悩むケースもあります。「もう一度高校に入り直したい」と思っても、20代・30代になってから進学し直すのは簡単ではありません。
中退という選択をするなら、「そのまま中卒でいること」のデメリットも理解しておくことが重要です。
5. 自分らしい生き方に気づくチャンスにもなる
一方で、高校を中退したことがきっかけとなり、「自分にとって本当に大切なもの」や「やりたいこと」に気づく人もいます。
例えば、音楽や芸術、起業、農業、海外での活動など、学校という枠組みでは見つけられなかった世界に踏み出すことで、逆に“自分らしさ”を見つけられる場合もあります。
中退という選択が、すべての可能性を閉ざすわけではありません。大切なのは、「高校を辞めた後をどう過ごすか・どう行動するか」です。
後悔しないためにも、自分の価値観や目標に向き合う時間を大切にしてほしいと思います。
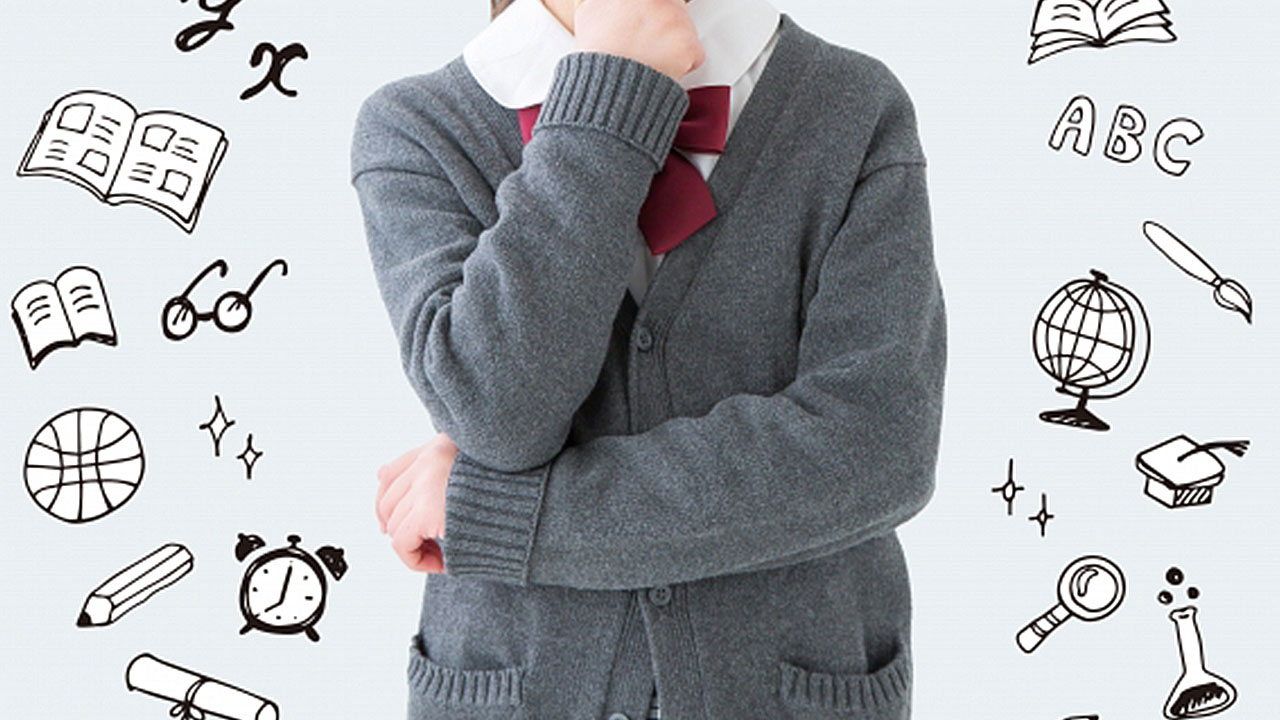
中退後の支援制度や相談先まとめ
高校を中退したあと、多くの人が「どうすればいいかわからない…」と感じます。
進路に悩んだり、働きたいけど何から始めればいいかわからない、心の不調を感じる…そんな時にこそ、外部の支援を上手に活用することが大切です。
ここでは、高校中退後の進路や生活を支える、代表的な支援制度や相談先を4つご紹介します。
1. 若者サポートステーション
「若者サポートステーション(通称:サポステ)」は、厚生労働省の委託事業として全国に設置されている、15〜49歳の若者を対象とした就労支援機関です。
専門のキャリアカウンセラーが在籍しており、以下のようなサポートが受けられます。
・自分に合った働き方や進路の相談
・コミュニケーション講座、職業体験プログラム
・就活書類の書き方、面接練習
高校中退後、進路に迷っている人にとって、「働くこと」や「社会に出ること」への第一歩を踏み出す場所として心強い存在です。相談は無料で、事前予約制のケースが多いです。
2. ハローワーク・ジョブカフェの活用
「ハローワーク(公共職業安定所)」は、仕事を探す人向けの国の機関で、中卒・高校中退者でも利用可能な就職相談・求人紹介を行っています。
また、各都道府県が設置する「ジョブカフェ(若者向け就労支援施設)」では、若者専用の就活支援や、職業適性診断・就活セミナーなどを実施しています。ハローワークよりも雰囲気が柔らかく、若者に寄り添った相談がしやすいのが特徴です。
これらの施設では、高校中退者向けの職業訓練コースや、資格取得を支援する制度も案内してもらえます。
参照:ハローワーク
参照:厚生労働省「ジョブカフェにおける支援」
3. 自立支援や居場所づくりを行うNPO法人
民間のNPO法人でも、高校中退後の若者の自立支援や、安心できる「居場所づくり」を行っている団体があります。
例えば、「育て上げネット」「カタリバ」「認定NPO法人D×P(ディーピー)」などでは、以下のような活動を行っています。
・不登校や中退経験のある若者向けの相談支援
・仕事体験やスキルアップのための講座
・オンラインのコミュニティや学習支援
家庭や学校とは違う「第三の場所」があることで、自分のペースで社会とのつながりを取り戻すことができます。
※団体によって対象年齢やエリアが異なるため、公式サイトでの確認がおすすめです。
参照:育て上げネット
参照:カタリバ
参照:認定NPO法人D×P(ディーピー)
4. 心のケアに役立つ医療機関・カウンセリング
高校中退の背景には、うつや不安障害、対人ストレスなど、心の問題が深く関わっていることも少なくありません。そうした場合は、専門の医療機関やカウンセリングを受けることも大切な選択肢です。
以下のような支援があります。
・スクールカウンセラー(在籍校にまだ在籍している場合)
・地域の精神科・心療内科
・児童・思春期専門の相談機関(例:児童相談所、精神保健福祉センター)
・オンラインカウンセリングサービス
中退という大きな出来事の後は、心が疲れていて当然です。「自分の心がどうなっているのか分からない」と感じたら、一人で抱え込まず、誰かに話してみることから始めましょう。

まとめ
高校中退は人生の“終わり”ではなく、“選び直し”のきっかけになることもあります。大切なのは、中退に至る理由や背景をしっかり見つめた上で、これからの進路を前向きに考えることです。
支えてくれる人や制度もあるので、ひとりで抱え込まず、自分のペースで次の一歩を踏み出していきましょう。
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
























