WISC-IVで言語理解だけが高い子とは?|特徴・注意点・親の支援策を解説
公開日:2025年7月16日
更新日:2025年7月16日

WISC-IVで「言語理解だけが高い」と言われて戸惑っていませんか?
このコラムでは、言語理解が高い子どもに見られる特徴や、他の指標とのギャップの理由、発達の個性としての理解の仕方をわかりやすく解説します。また、親ができるサポートや将来へのヒントも紹介しています。
WISC-IVの「言語理解」とは?|指標の意味と見方を知ろう
WISC-IV(ウィスク・フォー)は、子どもの知的発達のバランスや特徴を詳しく見るための検査です。その中で「言語理解(VCI)だけが高い」という結果を見て、どう受け止めたら良いのか迷う保護者の方も少なくありません。
ここでは、WISC-IVの基本構造や言語理解が指す力、そして結果を見る際の注意点について、わかりやすく解説していきます。
1. WISC-IVの4つの指標と全体像
WISC-IVは、子どもの認知機能を総合的に測る知能検査で、以下の4つの指標から構成されています。
・言語理解(VCI:Verbal Comprehension Index)
・知覚推理(PRI:Perceptual Reasoning Index)
・ワーキングメモリー(WMI:Working Memory Index)
・処理速度(PSI:Processing Speed Index)
それぞれが異なる思考力や認知スキルを反映しており、4つの合計から「全検査IQ(FSIQ)」が算出されます。ただし、指標ごとにばらつきが大きい場合は、FSIQの数値よりも個々の指標の特徴を重視するのが基本です。
2. 言語理解指標(VCI)が測っている力とは
言語理解指標(VCI)は、「言葉に関する理解力・知識・推論力」を測るものです。
具体的には以下のような力が含まれます。
・語彙の理解と使い方(言葉の意味を説明できるか)
・言葉を使った推論力(ことわざの意味を説明するなど)
・常識的な知識(日常生活に関する一般的な理解)
VCIが高い子は、会話の中での表現が豊かであったり、大人の話すことをよく理解できたりする傾向があります。知識を言葉で整理する力にも長けており、「話し上手」「説明上手」と言われることも多いです。
3. 言語理解が高い子どもに見られる特徴
VCIが高い子どもには、以下のような特徴が見られます。
・言葉の使い方が上手で、表現力が豊か
・語彙が年齢相応よりも豊富
・抽象的な概念や比喩も理解して話すことができる
・会話の中で「大人びた発言」をすることがある
・知識を言葉で説明するのが得意
一方で、「話せる=すべてが得意」というわけではなく、実行力や対人スキル、作業のスピードなどに課題を抱えていることもあります。
そのため、言語力の高さだけを見て過剰な期待をかけてしまうと、子どもがプレッシャーを感じてしまう場合もあります。
4. 結果を見るときに注意したいポイント(偏り・平均とのギャップ)
WISC-IVの結果を見るときは、「どの指標が高いか」だけでなく、「他の指標とのバランス」や「全体のばらつき」にも注意が必要です。
例えば、
・言語理解(VCI)だけが極端に高く、処理速度(PSI)が低い
→ 話はよくできるのに、プリントや作業はゆっくりだったり、実行に時間がかかることがある。
・言語理解(VCI)だけが極端に高く、ワーキングメモリー(WMI)が低い
→ 話し言葉の理解はできても、話を記憶して行動につなげるのが苦手なことも。
このように、言語理解だけを見て「頭が良い」と決めつけず、全体のバランスや得意・苦手の凸凹を丁寧に読み取ることが、子どもにとっても保護者にとっても安心につながります。
WISC-IVの結果の見方についてもっと知りたい方はこちら
⇒「WISC-IV知能検査(ウィスク-4)の結果の見方と検査内容」
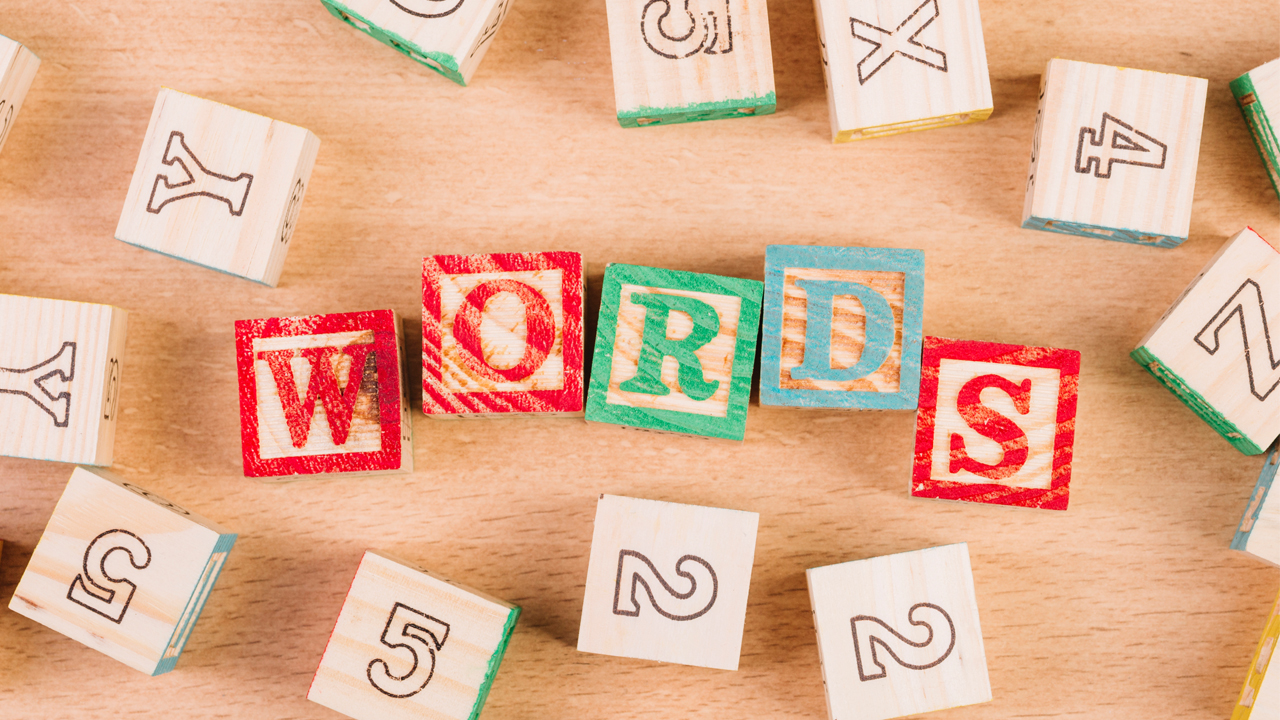
なぜ言語理解だけが高くなるのか?|その背景と理由を解説
WISC-IVの検査結果で「言語理解だけが高い」と示されたとき、多くの保護者が「なぜここだけ高いの?」と疑問に感じます。全体のバランスが整っていれば安心できますが、特定の指標だけが際立って高い場合、背景にはどのような要因があるのでしょうか。
ここでは、言語理解が高くなる理由を、環境的な側面・発達の個性・脳機能の偏りなどの観点から解説します。
1. 家庭環境や育ち方が影響する場合もある
まず考えられるのが、子どもの育ってきた環境の影響です。
例えば、日常的に「会話が多い家庭」「本の読み聞かせが習慣になっている家庭」「大人と接する機会が多い環境」などでは、自然と言葉に触れる量が多くなります。
特に幼児期に、親が子どもの言葉に丁寧に応じたり、語りかけを意識的に行っていた場合、語彙や言語理解が育ちやすくなることが研究でも示されています。
このような環境要因によって、言語理解だけが先行して発達しているというケースもあるのです。
2. 発達の個性として現れる“アンバランス”
子どもの発達は一律ではなく、それぞれに「伸びやすい部分」と「育ちにくい部分」があるのが自然です。
WISCのような検査では、そうした「発達のばらつき」が数値として表れることがあります。
言語理解は高いのに、処理速度やワーキングメモリーは平均〜やや低め、というパターンは珍しいことではありません。これは知的な問題ではなく、「脳の使い方の癖」や「得意不得意の現れ方」といった個性の一部です。
数字に囚われすぎず、その子の「学び方の傾向」や「サポートのヒント」として読み取ることが大切です。
3. 話し言葉は得意でも、実行機能や非言語力に弱さがあることも
「話せる=理解している」ではない、という点にも注意が必要です。
例えば、言語理解が高い子は、話し言葉の面では非常にスムーズでも、実際の行動となると以下のようなつまずきが見られることがあります。
・指示されたことをすぐに行動に移せない
・忘れ物や段取りのミスが多い
・作業に集中し続けるのが難しい
・図や絵など、言語以外の情報処理が苦手
このような傾向の背景には、ワーキングメモリーや実行機能、非言語的な認知力の弱さが関係していることがあります。
つまり、「言葉で表現する力」と「実際にやってみる力」は別物であり、それぞれ別の支援が必要になるのです。
ワーキングメモリーについてもっと知りたい方はこちら
⇒「ワーキングメモリーが低い子の特徴とよくある困りごと」
4. 発達障害やグレーゾーンが関係しているケースもある
言語理解が高く、他の指標にギャップがある場合、発達障害(特にASDやADHD)との関連が示唆されることもあります。
例えば、
・ASD(自閉スペクトラム症)の子どもでは、語彙力や言葉の記憶が非常に高い一方で、社会的なやりとりや非言語的な理解が苦手なことがよくあります。
・ADHD(注意欠如・多動症)の子どもでは、言語理解は高いのに、集中力や実行の持続が難しいため、学習に波が出やすくなります。
ただし、これらの診断が必ずつくわけではありません。
診断名の有無に関わらず、「得意と苦手の差が大きい」子どもには、個性に応じた関わり方が大切になるという考え方が基本です。
ADHDとアスペルガーの違いについてもっと知りたい方はこちら
⇒「ADHDとアスペルガーの違い|困りごとやサポート方法の違いを解説」

言語理解は高いのに…他でつまずく理由とは?|見落とされやすい困りごと
言語理解の高さは、一見すると「優れている」「問題なく育っている」と受け止められがちですが、実際にはその“得意さ”の裏に、見落とされやすい苦手や困りごとが隠れていることもあります。
ここでは、「言葉は通じるのに、なぜかうまくいかない」と感じられる理由や、日常・学校で見られる具体的なつまずきについて紹介します。
1. 「頭が良いはずなのに…」と誤解されやすい苦しさ
「言葉での説明が上手く、難しいことも理解できる」そんな子どもを見ると、まわりは「頭が良い子」と捉えがちです。しかし、実際には学習の定着が遅かったり、指示通りに行動できなかったりすることもあります。
このギャップが大きくなると、「どうしてこんな簡単なこともできないの?」「やればできるはずなのに」といった誤解を受けやすくなり、子ども自身が強いストレスや自己否定を抱えてしまうことがあります。
周囲の期待が高いほど、できなかった時の反動も大きくなり、「できない自分はダメなんだ」と感じてしまうこともあります。
このような周囲とのギャップが、外から見える印象と内面とのズレが生み出す「非常に見えにくい苦しさ」となります。
2. 語彙や表現は得意でも、手先や体の動きが苦手なケース
言語理解が高い子の中には、口では上手に説明できるのに、実際にやってみると不器用だったり、作業が苦手という子もいます。
例えば、
・ハサミや定規をうまく使えない
・絵や図を描くのが苦手
・体育の動作がぎこちない
・字を書くスピードが極端に遅い
こうした子どもたちは、非言語的な動作や空間認知などの面で発達にムラがあることが多く、「頭では分かってるけど体がついてこない」と感じていることがあります。
しかし、言葉がしっかりしているため、「不器用さ」が周囲に理解されにくく、支援が後回しになるケースも少なくありません。
3. 授業中の困りごと
言語理解が高くても、授業の中でつまずくことがあります。
その理由としてよく見られるのが、以下のような点です。
・集中力が続かず、話の途中で気が散ってしまう
・集団のペースに合わせて動くのが苦手
・先生の質問に対して、答えすぎてしまったり、逆に黙ってしまったりする
これは、ワーキングメモリー(作業記憶)や処理速度、社会的スキルの発達具合によって生じる現象です。
特に、「言っていることは分かっているのに、行動がついてこない」タイプの子どもは、教師からは“あえて指示に従わない子・反抗的な子”と誤解されることもあります。
本人に悪気はなくても、「わかること」と「やれること」に差があるため、学校生活でのストレスは大きくなりがちです。
4. 得意が目立つからこそ、苦手が気づかれにくい
言語理解が高い子は、その得意な面がとても目立ちます。語彙も豊富で、よくしゃべり、説明も上手であれば「しっかりしている」「賢い子」と見られることも多いでしょう。
しかし、その得意さが前面に出てしまうことで、周囲が「できて当たり前」と思ってしまうリスクもあります。
例えば、
・本当は聴覚情報の処理が苦手なのに、「ちゃんと聞いている」と思われて見逃される
・集団行動で戸惑っているのに、「しっかりしてるから大丈夫」と思われて声をかけてもらえない
・勉強でミスが多いのに、「うっかりミスじゃない?」と誤解される
このように、得意分野が目立つことによって、苦手な部分が隠れてしまい、適切な支援が受けられないこともあります。
だからこそ、保護者や先生が「得意なことだけで判断しない」視点を持ち、子どもの困りごとに気づく姿勢がとても重要になります。

親ができるサポートとは?|得意を伸ばしつつ、苦手に寄り添う5つのコツ
言語理解が高い子どもは、その力を活かせば大きな可能性を持っていますが、一方で、周囲の期待やギャップによって、苦手なことに対して自信を失いやすい側面もあります。
家庭での関わり方次第で、子どもは「得意」をさらに伸ばし、「苦手」とも前向きに向き合えるようになります。
ここでは、親ができる具体的なサポートのコツを5つ紹介します。
1. 得意なことを伸ばす声かけと関わり方
まず大切なのは、子どもの「得意なこと」をしっかり認めて伸ばすことです。
言語理解が高い子は、説明したり話したりすることに自信を持っている場合が多いため、以下のような関わりが効果的です。
・「その説明、すごく分かりやすかったよ」
・「難しい言葉もちゃんと使えてるね」
・「その考え方、いい視点だね」
このように、“内容”と“理由”をセットで褒めることで、自己肯定感が育ち、さらにチャレンジしようという意欲が高まります。
2. 苦手なことに「手を貸す」ことへの抵抗をなくそう
得意な分野があると、「なんでも自分でできるはず」という期待を持ってしまいがちですが、苦手なことに手を貸すのは“甘やかし”ではなく、発達支援の一環です。
例えば、
・手先が不器用なら作業を一緒にやってみる
・時間管理が苦手ならタイマーを使ってサポートする
・プリント整理が苦手なら親が一緒にチェックする
「やってあげる」のではなく、「できるようになるまで伴走する」姿勢が大切です。
苦手に直面して落ち込みやすい子には、「できなくても大丈夫、やり方を一緒に考えよう」という関わりが安心感につながります。
3. 学校や担任の先生に伝えるときの工夫
学校での理解や配慮があるかどうかは、子どもの安心感や学習環境に大きく関わります。
とはいえ、WISCの検査結果をそのまま伝えても、すぐに理解が得られるとは限りません。ポイントは、「具体的な困りごと」と「家庭での様子」をセットで伝えることです。
例えば、「家では話すのが得意で語彙も豊富なのですが、図を見て理解するのが苦手で…授業中の視覚資料が難しく感じることがあるようです」といった風に、具体的に伝えてみましょう。
先生は一人で多くの生徒を見ているため、気づかれていない困りごとを丁寧に言語化して伝えることが、よりよい支援につながります。
4. 専門機関や相談先の活用
「困っているけれど、どこに相談すればいいのか分からない」という声も多くあります。
そんな時は、自治体や学校、医療機関などの支援窓口を活用してみましょう。
主に、以下のような相談先があります。
・発達相談センターや子育て支援センター
・学校のスクールカウンセラーや特別支援コーディネーター
・臨床心理士によるWISCの結果説明や保護者向けアドバイス
・小児発達外来や地域の療育機関
「相談=診断」ではありません。親が一人で抱え込まず、あくまで客観的な視点でアドバイスをもらう場として利用してみましょう。
5.「うちの子らしさ」を大切にすることの意味
検査の数値やまわりの評価に気を取られてしまうと、つい「できていないところ」に目が行きがちです。
でも本当に大切なのは、「この子はどんなことが好きで、どんなふうに考えるのか」という“その子らしさ”を見つけてあげることです。
例えば、以下のような「その子らしさ」があります。
・言葉で世界を理解するのが得意
・細かい作業は苦手だけど、想像力が豊か
・自分のペースで動くことで安心できる
このように、“評価”ではなく“理解”の視点で関わることが、子どもにとって最も心強い支えになります。子どもに「自分らしくあればいい」と思わせてあげる関わりが、将来への自信と安心につながっていくのです。

WISC-IVの結果をどう活かす?|将来の見通しと学び方のヒント
WISC-IVの結果を手にしたとき、多くの保護者が「この数値は将来にどう影響するの?」「このままで大丈夫なの?」と不安になります。
しかし、知能検査は「進路を決める診断書」ではありません。大切なのは、子どもの特性を知り、それに合った学び方や環境を見つけることです。
ここでは、WISC-IVの結果を将来にどう活かすか、前向きな視点で考えるヒントをお伝えします。
1. 数字にとらわれすぎず、“ヒント”として使おう
WISC-IVの各指標やIQスコアは、「その子の一部の側面」を測っているに過ぎません。
高い・低いという数字に一喜一憂するのではなく、その背景にある認知の特徴や、得意・不得意の傾向を知るための“ヒント”として活用することが大切です。
例えば、「言語理解が高い」という結果は、「言葉で理解・表現することが得意だから、口頭での説明や会話型の学習が合うかもしれない」というヒントになります。
WISC-IVの数字は「判断の材料」であり「評価のラベル」ではない、と捉えることで、子どもに余計なプレッシャーを与えずに済みます。
2. 得意・苦手のバランスを見える化すると関わりやすくなる
WISC-IVの結果をうまく活かすには、得意と苦手のバランスを“見える化”することが役立ちます。
例えば、
・言語理解は高いが、処理速度が低い
→ 作業に時間がかかることを前提に、余裕を持ったスケジュールを組む
・知覚推理が得意だが、ワーキングメモリーが弱い
→ 文章より図やイメージで学ぶ工夫をする
このように、「どこを手助けすればいいのか」「どんな方法が合いそうか」が整理できると、家庭でも学校でも支援の具体性が増し、子どもにとってもストレスが減ります。
3. 学び方や支援の工夫で大きく伸びる可能性がある
苦手があるからといって、そのまま伸びないわけではありません。
子どもに合った学び方やサポート方法を見つけることで、能力は大きく引き出すことができます。
例えば、
・一斉授業ではうまくいかない子が、個別指導やマンツーマンだと理解が進む
・紙と鉛筆では集中できなくても、タブレット学習だと集中して取り組める
・言語優位なので、文章を書くより「話して録音する」ほうが覚えやすい
大切なのは、方法を変えても「学ぶ力」は育てられるという視点です。
どの子も「その子に合ったやり方」であれば、可能性はしっかり広がっていきます。
4. 今できないことも、時間をかけて育てる
発達には「その子なりのタイミング」があります。今は苦手に見えることでも、時間の経過や経験の積み重ねによって、少しずつ育っていくものです。
特に実行機能や非言語的な力は、小学校高学年〜中学生にかけてゆっくり育つ子も多いと言われています。
焦らずに、「今は種まきの時期」と捉え、
・うまくいった経験
・失敗しても受け止められた体験
・自分の力でできた実感
を積み重ねることが、後の自信や成長につながります。
5. 将来を考えるときに大切なのは“今の得意”を信じること
子どもの将来を考えるとき、不安なことばかりに目が行ってしまうのは自然なことです。
子どもの将来を探るうえで最も頼りになるのは、「その子が今、どんなことに喜びや得意を感じているか」ということです。
例えば、以下のような方法で得意を活かすことが可能です。
・話すのが好き
→ プレゼン力、対話力が活きる道へ
・言葉に興味がある
→ 作文、読書、表現の分野で活躍できるかも
・他者への気づきがある
→ 支援者や教育職、カウンセラーなども視野に
WISCの結果は、“可能性を閉ざすもの”ではなく、“選択肢を広げるきっかけ”なのです。
「この子の強みを活かせる場所は、どこにあるだろう?」そんな視点で将来を見つめることが、本人にとって一番の希望になります。

まとめ
WISC-IVで「言語理解だけが高い」という結果は、子どもの得意と苦手のバランスを知るための大切な手がかりです。見落とされがちな困りごとにも目を向けながら、得意を伸ばし、苦手には寄り添う関わりが子どもの安心と成長につながります。
数字に囚われすぎず、その子らしさを信じて支えていくことが、将来への確かな一歩になります。
家庭教師のマスターでは、発達の偏りがある子どもへの学習サポートを行っています。ご興味のある方は、気軽にご相談ください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【発達障害コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
WISCで処理速度だけが低いのはなぜ?|子どもの特徴と接し方のヒント
-
WISC-IV知能検査(ウィスク-4)の結果の見方と検査内容
-
WISC-4の知覚推理(PRI)が低いとどうなる?|子どもの特徴と支援法
-
発達障害とIQのホントの関係とは?|子どもの可能性を正しく理解しよう
-
ワーキングメモリーが低い子の特徴とよくある困りごと
-
漢字が覚えられない発達障害(書字障害・読字障害など)|チェックリスト付き
-
発達障害の子どもを育てるのに疲れた方へ|大切な考え方と具体的な対策とは
-
落ち着きのない子どもは発達障害?|他の可能性とサポート方法
-
算数障害の子どもの特徴とサポート方法を解説【簡易チェックリスト付き】
-
片付けられない発達障害・病気のセルフチェックリスト
























