小学生のための夏休み計画表ガイド|遊びも勉強も両立するコツ
公開日:2025年7月7日
更新日:2025年7月7日

夏休みは遊びや旅行など楽しい予定が盛り沢山です。でも、つい後回しになりがちな宿題や自由研究も計画的に進めたいところ。
このコラムでは、小学生向けの計画表を作るメリットや作成ステップ、無理なく続けるコツまで詳しく紹介します。
夏休みに計画表が役立つ理由とは?
長い夏休みは、小学生にとって楽しいことがたくさんある反面、つい生活が不規則になったり、宿題を後回しにしてしまったりすることも多いです。
そんな中で、計画表をうまく使えば、毎日の行動にメリハリが生まれ、「勉強も遊びも楽しめる夏休み」に近づけます。ここでは、計画表を取り入れることで得られる5つのメリットを紹介します。
1. 学習習慣をキープしやすくなる
学校の授業がない夏休みは、どうしても勉強から遠ざかってしまいがちです。しかし、計画表を使って毎日の学習時間をあらかじめ決めておくことで、「勉強しない日が続く」ことを防げます。
短時間でも「毎日机に向かう」ことが、学習習慣の維持につながり、2学期のスタートでもスムーズに勉強に戻れるようになります。
2. 生活リズムが整いやすくなる
夏休みは夜更かしや朝寝坊が続きやすい時期です。計画表で「何時に起きて、何をするか」を決めておくことで、生活リズムを崩さず過ごすことができます。朝の時間帯に勉強や運動の予定を入れておくと、「起きる理由」ができるため自然と早起きにもつながりやすくなります。
3. やり残しが減り、自由研究も余裕をもって取り組める
夏休みの宿題は量も種類も多く、後回しにしていると終盤で大慌て…というケースも少なくありません。計画表を使えば、「いつ・何を・どのくらいやるか」を見える化できるため、やり残しを防ぐことができます。
特に自由研究のような時間のかかる課題も、計画的に進めれば焦らずじっくり取り組むことができ、完成度も上がります。
4. 自分で計画を立てる力が育つ
小学生のうちから、自分の予定を自分で考える習慣を身につけることはとても大切です。最初は親と一緒に作っていた計画表でも、徐々に「今日はこれをやってみよう」「午後は空いているから宿題をやろう」など、自主的にスケジュールを考えられるようになります。この力は、勉強だけでなく習い事や将来の受験などにも役立つ「自己管理力」の基礎となります。
5. 親子でスケジュールを共有できる
夏休みは家族の予定も多く、子どもの予定と親の都合がぶつかることもあります。計画表を共有しておくと、親も「この日は自由研究をする予定なんだな」「午前中は勉強だから午後に遊びの予定を入れよう」といった調整がしやすくなります。
親子でスケジュールを確認し合うことで、自然とコミュニケーションも増え、夏休みをよりスムーズに過ごせるようになります。

夏休みの計画表はこう作る!親子で取り組む5ステップ
「計画表を作ったけれど、結局うまく使えなかった…」という失敗を防ぐためには、親が一方的に予定を組むのではなく、子ども自身が主体的に関わることが大切です。
ここでは、計画表をゼロから完成させるまでの具体的な5ステップを紹介します。親子で一緒に取り組むことが、成功の鍵です。
1. まずは夏休みの全体像を親子で把握しよう
最初にやるべきことは、「夏休みのスケジュールの全体像をつかむこと」です。学校から配られる「夏のしおり」や「年間予定表」を手元に用意し、以下のポイントを確認してみましょう。
- 夏休みの開始日と終了日(登校日や始業式含む)
- すでに決まっている予定(家族旅行、習い事、イベントなど)
- 地域の行事や夏祭りなど、参加する可能性があるもの
これをカレンダーにざっくり書き込むことで、「自由に使える日数」が明確になります。親子で一緒にスケジュールを見ながら、「この日は旅行だから勉強は休みにしよう」「この週は少しゆっくりめで」と話し合うことで、後の計画が現実的になります。
2. やるべきことを書き出そう
次に、夏休み中に「やるべきこと」をリストアップします。代表的なのは、以下のような項目です。
- 宿題(ドリル・プリント・読書感想文・自由研究など)
- 学校以外の学習(通信教材・家庭学習など)
- 習い事の課題や目標
- お手伝いや生活面の取り組み(早起き、掃除など)
ここでのポイントは、大きなタスクを小分けにすることです。
例えば、「自由研究」だけ書くのではなく、「テーマを決める→調べる→実験→まとめる→清書する」といった工程に分けておくと、1日単位でのスケジューリングがしやすくなります。
親が主導で書き出すのではなく、「○○はどうする?」「これは何日ぐらいかかると思う?」と子どもに問いかけながら進めましょう。「自分で決めた」という実感があると、取り組みの意欲も高まります。
3. 1日のタイムスケジュールを決めよう
続いて、夏休み中の「1日の基本の流れ」を決めていきます。すべての時間を細かく埋める必要はありませんが、起床・食事・勉強・遊び・就寝といった、一日の“型”を決めることで、生活にリズムが生まれます。
例)
| 7:00 | 起床・朝食 |
|---|---|
| 8:00 | 勉強タイム(宿題やドリル) |
| 10:00 | 自由時間(遊び・おでかけ) |
| 12:00 | 昼食 |
| 13:00 | 家族でおでかけ or 自由研究 |
| 16:00 | お手伝い・遊び |
| 18:00 | 夕食 |
| 20:00 | 就寝準備 |
| 21:00 | 就寝 |
重要なのは、「無理のない時間設定」にすることです。
朝からぎっしり詰めすぎたり、集中力が切れやすい午後に長時間の学習を入れたりすると、計画倒れの原因になります。勉強時間は30分〜1時間を目安にし、1日の中に「休憩・遊び・ごほうびタイム」も組み込むと続けやすくなります。
4. 週間・月間単位で見える化しよう
全体と1日の流れが見えてきたら、次はそれを週・月単位でカレンダーに落とし込んでいきます。おすすめは、A3サイズ程度の「月間カレンダー形式」の紙を用意し、親子で書き込んでいく方法です。
やり方のポイントとしては、
- 各週の「テーマ」を決める(例:第1週=自由研究、第2週=工作と読書感想文)
- 「午前は勉強・午後は遊び」など、時間帯ごとの目安を色分け
- 完了したタスクには「○」や「スタンプ」をつける
です。ここで「見える化」することで、子ども自身も「自分の今週の予定」「進み具合」が視覚的に把握でき、達成感や責任感が育ちます。
なお、紙で作るのが難しい場合は、ホワイトボードやスケジュールアプリでもOKです。子どもがアクセスしやすく、更新しやすい方法を選びましょう。
5. 無理のない計画に修正し、親子で確認しよう
計画を立てたら、それで終わりではありません。最後に、親子で「このスケジュールで大丈夫そう?」と再確認し、必要があれば調整しましょう。
特にチェックしたいポイントとしては、
- 予定が詰め込みすぎていないか?
- 連続して同じタスクが続いていないか?
- 疲れていそうな日はちゃんと“ゆとり”があるか?
です。子どもから「ここは多すぎるかも…」「この日は友達と遊びたい」などの声が出てくることもあります。それを頭ごなしに否定せず、「じゃあ、その分この日にやってみようか?」といった“すり合わせ”が信頼感につながります。
また、週に一度「振り返りタイム」を設けて、計画がうまくいっているかチェックし、必要に応じて調整していくと、より実行しやすくなります。

計画倒れを防ぐには?無理なく続ける5つの工夫
どんなに完璧な計画表を作っても、それを最後まで実行できなければ意味がありません。
夏休みはイベントや体調の変化などで、予定通りに進まないこともあるのが普通です。だからこそ、「続ける工夫」「うまくいかなかった時のリカバリー策」をあらかじめ用意しておくことが大切です。
ここでは、計画倒れを防ぐために役立つ5つの工夫を紹介します。
1. 「できた!」を可視化して達成感を積み重ねよう
子どもにとって「やったのに誰も気づいてくれない」「終わった実感がない」というのは、やる気を下げる原因になります。そこでおすすめなのが、「できた!」を目に見える形で残すこと。
たとえば…
- 終わった宿題にシールを貼る
- 1日ごとに○やスタンプをつける
- 完了タスクを「やったリスト」に移動する
といった方法です。
こうした小さな達成感の積み重ねが、自己肯定感ややる気につながります。できれば親が「よく頑張ったね」と声をかけることで、子ども自身も自分を褒めることができるようになります。
2. 毎週末に見直し時間をとる習慣をつけよう
夏休みは思っている以上に予定が変わるものです。遊びの予定が入ったり、体調を崩したりして、最初の計画通りに進まないことも珍しくありません。
そこで大切なのが、「週に一度、計画を見直す時間」を親子で取ることです。
- 毎週末に10〜15分程度、できたこと・できなかったことの確認
- 次週の予定の再調整
- 頑張ったことを親子で振り返る
という時間を設けましょう。
この振り返り習慣があれば、「遅れているからあきらめる」のではなく、「じゃあ、ここで取り戻そう」と前向きに修正できる柔軟さが身につきます。
3. 予定が崩れたときの「予備日」を設けておこう
計画表をつくるとき、多くの家庭が見落としがちなのが「予備日(バッファ)」の存在です。すべてをびっしり詰めてしまうと、少しの遅れでスケジュール全体が崩れてしまいます。
そこで、1週間のうち1日や、月末の数日間を「予備日」として空けておくと安心です。
「自由研究が終わらなかった」「体調が悪くてできなかった」など、予定外の出来事があっても、慌てずリカバーできる仕組みになります。
予備日は「調整のための日」として計画表にも明記しておきましょう。「今日は予備日だから休んでも大丈夫」と思えることで、気持ちにもゆとりが生まれます。
4. 親が干渉しすぎず、でも関心を持つバランスを保とう
計画表の運用でつまずく原因のひとつが、「親の声かけの仕方」です。
つい「まだやってないの?」「今日の分終わったの?」と口うるさくなってしまいがちですが、これでは子どもは「管理されている」と感じてやる気をなくしてしまいます。
理想は、「任せるところは任せる」「でも見てくれている」という“干渉しすぎない見守り”の姿勢です。
たとえば、
- 終わったら「どうだった?」と自然に聞く
- スケジュールの達成具合を一緒に確認する
- 「この前より早く終わったね」と変化に気づく
といった声かけを心がけると、子どもも「ちゃんと見てくれている」と感じて安心します。
親子が伴走するような関わり方が、継続の原動力になります。
5. 小さな目標とごほうびでモチベーション維持をしよう
夏休みは長い分、途中でだれてしまうのは当たり前です。そこで、「1日1つの目標」「今週中にこれだけ終わらせる」など、短期的で達成しやすい目標を設定するのが効果的です。
さらに、ごほうび制度をうまく活用するとモチベーションがぐんと上がります。ごほうびといっても、お金や物ではなく、
- 「全部できたら、アイスを一緒に食べに行こう」
- 「読書感想文が終わったら、映画を見よう」
- 「1週間頑張ったら、1日お休みデーにしよう」
といった“体験”や“リフレッシュの時間”がベストです。
子どもにとって「頑張ったらうれしいことがある」という期待は、日々のやる気を後押ししてくれます。
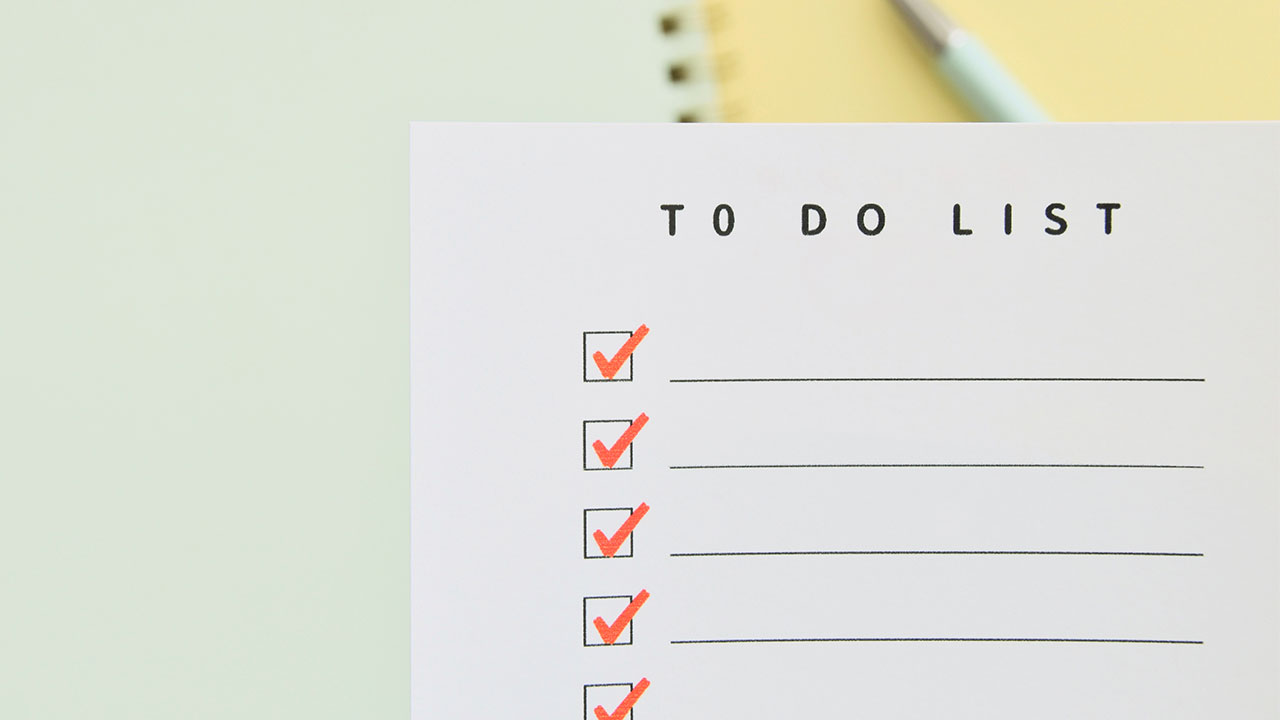
ありがちな失敗はこれ!夏休みの計画作りで気をつけたいポイント
せっかく頑張って作った計画表も、「使いにくい」「途中でやめてしまった」などの理由で活用されなくなってしまうことがあります。
実はそこには、計画作りの段階で陥りがちな「落とし穴」が潜んでいます。このセクションでは、よくある5つの失敗パターンと、その対策を紹介します。
1. 予定を詰め込みすぎて息切れする
「せっかくの夏休みだから、毎日たくさん進めたい」と思うあまり、勉強や課題をぎっしり詰めてしまうのは失敗のもと。最初のうちは頑張れても、途中で疲れて続かなくなるケースが多く見られます。
特に低学年のうちは、「集中できる時間」や「体力」にも限界があります。大人の感覚でスケジュールを立てるのではなく、“ちょっと物足りないくらい”を意識した余白のある計画が、長く続けるためには大切です。
2. 子どもの意見を取り入れずに親だけで作成してしまう
「親が考えたほうが早いから」と、子どもに相談せずにスケジュールを組んでしまうことも、失敗につながりやすいパターンです。
自分で関わっていない計画には、どうしても「やらされている」という気持ちが強くなり、取り組む意欲も続きません。
たとえ親が主導で作るとしても、「これくらいならできそう?」「どの時間にやりたい?」といった形で子どもの意見を取り入れていくことで、自然と主体性が育ちます。「自分で決めた」という感覚があるだけで、子どものやる気は大きく変わってきます。
3. 「作って満足」で実行計画が不明確
計画表を作るだけで満足してしまい、その後どう進めていくかが曖昧なままでは、形だけで終わってしまいます。
例えば、毎日どのタイミングでスケジュールを確認するのか、誰が進み具合を見て声をかけるのか、できたことをどう記録するのかなど、実行の流れまでしっかり決まっていないと、「作ったのに使われない」という事態になりかねません。スケジュール表は作って終わりではなく、毎日使う道具として活用できるように、仕組みや習慣とセットで設計することが大切です。
4. 親の理想と子どもの現実にズレがある
親としては「この夏に○○を身につけてほしい」といった期待があるかもしれません。しかし、こうした親の理想が子どもの実力や性格、生活リズムと合っていないと、現実とのギャップでうまくいかなくなってしまいます。
例えば、「毎朝2時間勉強する」と決めたものの、実際には集中力が続かずに途中で挫折したり、「毎日漢字ドリルを1ページずつやる」と設定したのに、嫌がって全く手がつかないといったこともあります。大切なのは、親の目標に子どもを合わせるのではなく、子どもの今の状態に合わせて現実的な目標やペースを設定することです。無理なく続けられることを積み重ねるほうが、結果的に成果にもつながります。
5. 記録を残していないため、振り返りができない
毎日の取り組みを記録として残していないと、子ども自身も頑張った実感が得られにくく、親としても進捗状況が見えず、適切な声かけやフォローができなくなってしまいます。
また、計画通りに進まなかった時にも、何が原因で遅れたのかを振り返る手がかりがありません。計画表にチェックマークをつけたり、終了した課題に日付を書いたり、スタンプやシールを貼ったりするだけでも、子どもにとっては「ちゃんと進んでいる」という自信になります。
振り返りの記録があれば、次の週や来年の計画にも活かすことができますし、何より「できたこと」を実感できることが、次のやる気につながります。

まとめ
長い夏休みを有意義に過ごすためには、無理のない計画を親子で立て、継続できる工夫を取り入れることが大切です。やるべきことを見える形にし、子どもが自分で動ける環境を整えることで、学びと遊びのバランスが取れた充実した夏になります。
計画表をうまく活用して、家族みんなで気持ちよく夏を乗り切りましょう!
家庭教師のマスターでは、夏休みの宿題に苦戦している小学生をサポート指導しています。
ご興味のある方は、気軽にご相談ください。
もっと知りたい方はこちら
⇒【小学生コース】について
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
























