中間反抗期を見極めるチェックリスト|保護者の接し方のコツやNG行動も紹介
公開日:2025年4月14日
更新日:2025年4月14日

このコラムでは、中間反抗期の子どもの特徴を見極めるチェックリストをご紹介します。
さらに、保護者の方向けに、中間反抗期の子どもへの接し方のコツや避けるべきNG行動についても解説します。
お子さんの反抗期に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
中間反抗期とは何か?
子どもの成長過程において、避けては通れないのが「反抗期」です。
一般的に反抗期というと「イヤイヤ期(第一次反抗期)」や「思春期(第二次反抗期)」が思い浮かぶかもしれません。しかし、実はその中間にも「中間反抗期」と呼ばれる時期があります。
保護者にとっては「まだ早いのに…」と思うような年齢で始まるため、戸惑いを感じやすいのがこの中間反抗期の特徴です。
ここでは、まず中間反抗期の基礎知識から、年齢や特徴、男女差、さらには原因や前兆まで詳しく解説していきます。
1. 中間反抗期の年齢と特徴
中間反抗期とは、一般的に小学校低学年から中学年(6〜9歳ごろ)に訪れることが多い反抗期です。第一次反抗期(2〜3歳ごろ)と、第二次反抗期(思春期前後)との間に現れることから「中間反抗期」と呼ばれています。
特徴としては、親や先生など身近な大人への口答えや反発が目立つようになる点です。また、素直に指示を聞かずにわざと反抗的な態度を取ったり、ルールを破ったりする様子も見られます。ただし、本人の中ではまだ「甘えたい気持ち」と「自立したい気持ち」が混在しており、日によって素直な態度に戻ることもあり、この「甘え」と「反抗」を繰り返すのが中間反抗期の大きな特徴と言えるでしょう。
2. 中間反抗期の男女の違い
中間反抗期は、男女ともに起こる可能性がありますが、その現れ方には違いがあるとされています。
一般的に男の子は、態度や行動が外に向かって表れやすい傾向があります。
たとえば、口調が荒くなったり、すぐにふてくされたりと、周囲から見ても「わかりやすい反抗」として表れるケースが多いです。
一方で、女の子は、比較的内面に反抗心を抱えやすいと言われています。
態度には表れにくいものの、無言で無視したり、反抗的な目つきをしたりすることもあります。
また、女の子は成長が早いこともあり、精神的に「大人びた反発」をする傾向も見られます。
もちろん、反抗期の現れ方は個人差も大きいため「うちの子は男の子だけど…」など違和感があれば個別の性格や環境を考慮して見守ることが大切です。
3. 中間反抗期が起こる原因
中間反抗期は、子どもの「自立心」が芽生えることが主な原因です。
6〜9歳ごろは、学校生活に慣れ始めたり、友達との関わりが広がったりして、少しずつ「自分の考えで行動したい」という気持ちが強くなります。
一方で、まだ十分に物事を判断する力や社会性が備わっていないため、「自分の思い通りにいかない」と感じたときに、親などの身近な大人に対してイライラや怒りをぶつけやすくなるのです。
また、家族関係や学校でのストレスも中間反抗期を引き起こすきっかけとなる場合があります。
たとえば、兄弟姉妹との競争や友達とのトラブルが重なると、その不満が「反抗」という形で表面化するケースも少なくありません。
4. 中間反抗期が始まる前兆
中間反抗期が始まる前には、いくつかのサインが見られることがあります。
たとえば、普段は素直だった子が、急に「うるさい」「わかってる」などの言葉を使うようになったり、何かと親に口答えをするようになった場合は、その前兆かもしれません。
また、「一人でやる!」と自立心が強まる一方で、急に甘えてくる場面が増えることもあります。
さらに、友達との距離感や人間関係が変化してくるタイミングでもあるため、親からの干渉を嫌がったり、学校や友達のことについて話すのを拒む傾向も見られます。
こうした兆候が見えたら、中間反抗期に入る準備段階に入ったと考えてよいでしょう。
5. 中間反抗期とイヤイヤ期・思春期の違い
第一次反抗期(イヤイヤ期)は、2〜3歳ごろに訪れるもので、自我の芽生えが原因です。この時期の子どもは言葉を覚え始めたばかりで、「イヤ」「ダメ」など単純な反発が見られます。
一方、第二次反抗期(思春期)は、12歳ごろからの思春期に現れ、親からの精神的な自立を目指して強い反抗や無関心といった態度が目立つのが特徴です。
その間に訪れる中間反抗期は、ちょうど小学校低〜中学年の時期に起こり、イヤイヤ期ほど単純ではなく、思春期ほど複雑すぎない「中間的な反発」が特徴です。
イヤイヤ期のような単純な否定やかんしゃくとは異なり、中間反抗期は自立心・集団生活の影響・友達関係などが複雑に絡んで起きます。
親としては「この子、もう思春期?」と混乱しやすいですが、年齢や行動パターンを冷静に見ることで、中間反抗期であるかを見極めることができます。
母子分離不安についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「母子分離不安は母親のせい?|原因と対応策について解説」
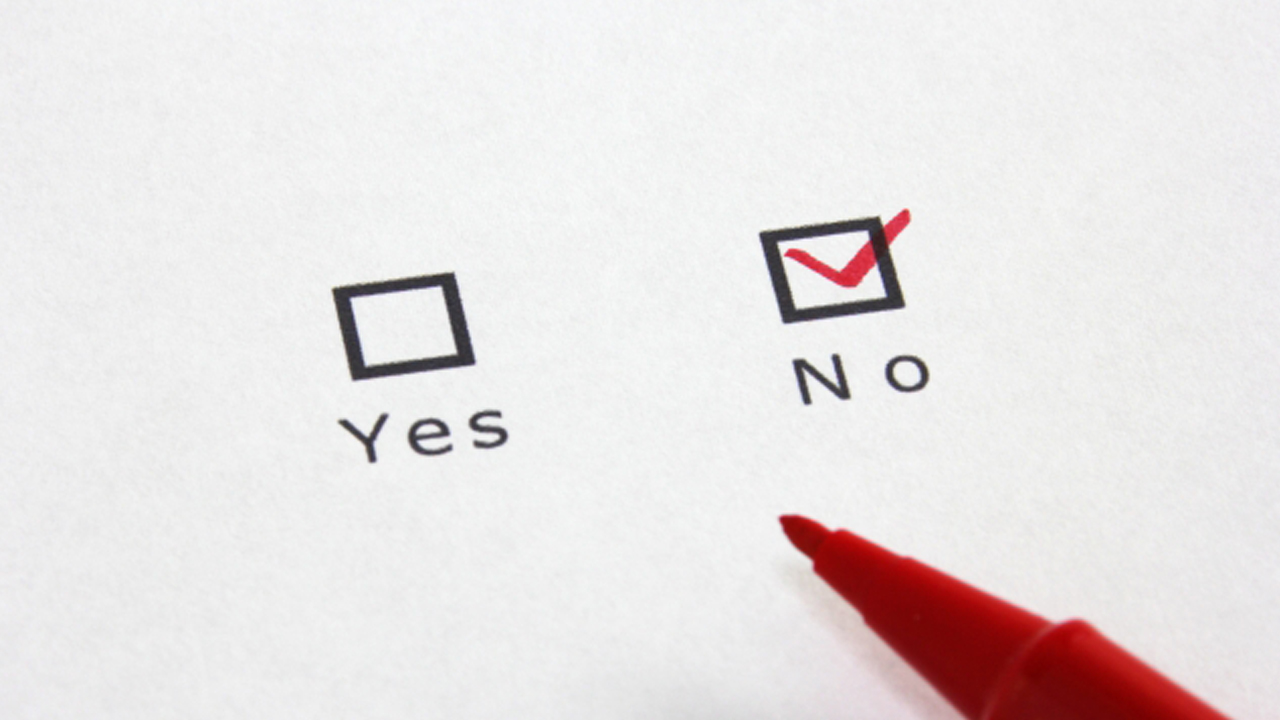
中間反抗期チェックリスト
中間反抗期は、子どもによって現れ方がさまざまです。そのため「これって反抗期なのかな?」と見極めに迷う保護者の方も多いのではないでしょうか?
ここでは、中間反抗期によく見られる9つの行動や態度をチェックリストとしてまとめました。いくつか当てはまる場合は、中間反抗期の可能性が高いと言えるでしょう。
1. 親の言うことにすぐ反発する
たとえば「宿題しなさい」と言うと、「今やろうと思ってたのに!」と怒ったり、反射的に「嫌だ」「うるさいな」と口答えをしたりする場面が増えていませんか?
これは、中間反抗期の典型的なサインのひとつです。親からの指示や声かけに対して、素直に従うことを避け、あえて反発する行動が目立つようになります。
2. 乱暴な言葉づかいをすることが増える
これまで使わなかったような「うざい」「うるさい」「バカ」など、乱暴な言葉を使うようになった場合も要注意です。
親に対して反抗的な気持ちが高まると、日常会話での口調が荒くなりがちです。言葉づかいに加え、態度もぶっきらぼうになりやすくなります。
3. わざとルールを破る
「もう帰る時間だよ」と伝えてもわざと遅く帰ってきたり、約束していたゲームの時間を守らなかったりと、ルール違反を意図的に行うことも中間反抗期の特徴です。
親のルールに反発することで「自分の意思」を強調しようとする心理が背景にあります。
4. 大人の干渉を嫌がる
学校や友達関係のことを聞いても「別に」「言いたくない」と返される場面が増えたら、中間反抗期の始まりかもしれません。
親や先生などの大人の干渉を嫌がり、自分の世界を守ろうとする傾向が強くなります。
5. 親より友達を優先する
これまでは親との時間を楽しんでいたのに、急に「友達と遊ぶから無理」「お母さんと行きたくない」など、友達との予定を優先しはじめるのも中間反抗期によくあるパターンです。
友達とのつながりが大切になり、親との距離を取りたくなる時期に入ったサインとも言えます。
6. 甘えと自立を繰り返す
中間反抗期の子どもは、「甘えたい気持ち」と「自立したい気持ち」が交互に現れることが多いです。
昨日は「ねえねえ!」と甘えてきたのに、今日は「ほっといて」と突き放すなど、日によって態度が揺れ動きます。親としては「どっちなの?」と困惑することもありますが、これも正常な成長過程のひとつです。
7. 親との会話で「何でもいい」など無気力な答えを返す
話しかけても「何でもいい…」「わかんない…」といった無気力な返事が増えた場合も、中間反抗期のサインかもしれません。興味がないわけではなく、あえて「素直に答えたくない」という気持ちから、つっけんどんな対応をする子も多いです。
8. 自分の思い通りにならないと機嫌が悪くなる
中間反抗期の子どもは、些細なことで不機嫌になりやすくなったり、思い通りにいかないとすぐにイライラをぶつけてきたりするケースもあります。
自己主張が強くなり始める一方で、まだ我慢や気持ちのコントロールが未熟なため、感情が表に出やすいのがこの時期の特徴です。
9. 外ではおとなしいが、家ではとても反抗的になる
学校などの外では良い子にしているのに、家では突然反抗的な態度を取るのもよくあるケースです。外で我慢したストレスを家庭内で発散する子も多く、親が「外ではそんな態度しないのに…」と、そのギャップに驚くこともあるでしょう。
反抗期についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「反抗期はいつから始まり、いつ終わるの?|接し方や注意点を徹底解説」
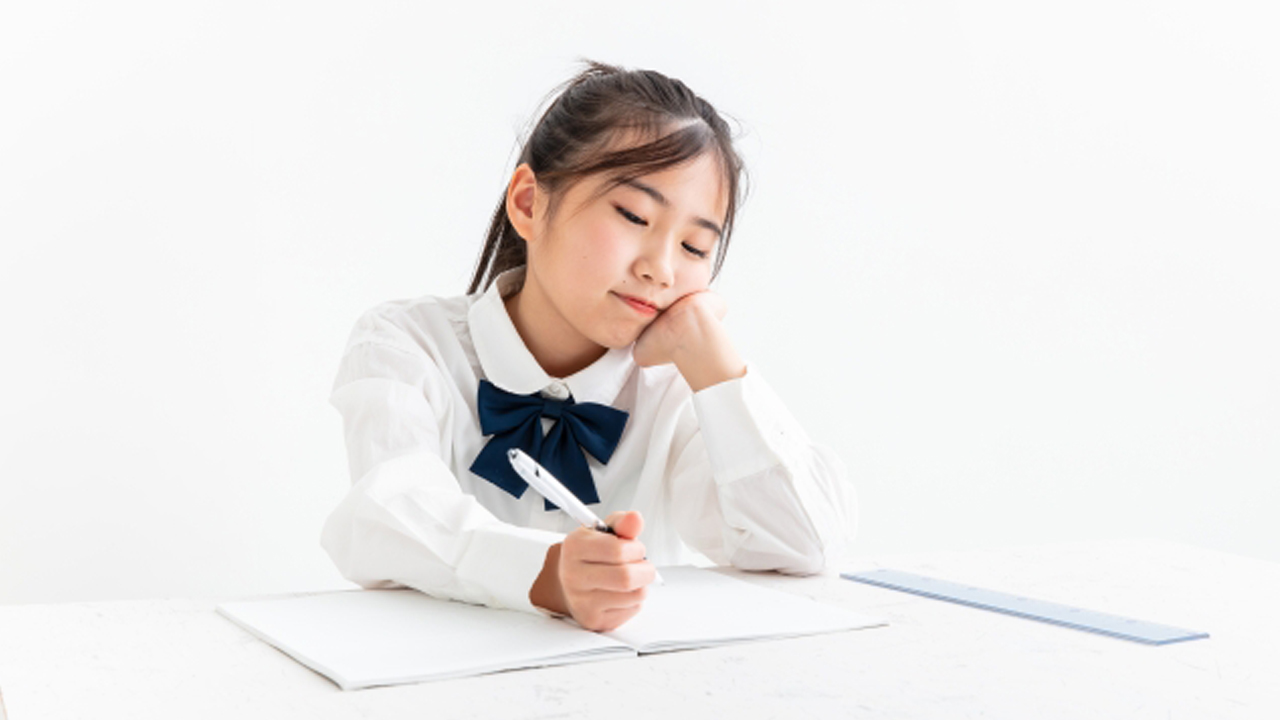
中間反抗期の子どもへの保護者の接し方、5つのポイント
中間反抗期は、子どもの健全な成長過程のひとつですが、反抗的な態度や言葉に悩み、戸惑う保護者の方も多いでしょう。
ここでは、そんな時に心がけたい接し方のポイントを5つご紹介します。日々の関わり方を少し意識するだけでも、子どもとの関係は良い方向に変わっていきます。
1. 頭ごなしに否定しない
子どもが反抗的な態度を取った時に、つい「ダメでしょ!」「何言ってるの!」と強く否定してしまうことはありませんか?
しかし、中間反抗期の子どもは「自分の意見を認めてほしい」という気持ちが強くなっているので、頭ごなしに否定することは、かえって反発心をあおってしまう原因になります。
まずは、子どもの気持ちを受け止める姿勢を持つことで、子どもも少しずつ心を開きやすくなります。
2. 感情的にならないように努力する
反抗的な言動が毎日のように続くと、親もつい感情的になってしまいがちです。
ただ、保護者が感情的になってしまうと、子どもは「親もイライラしている」と受け取り、事態がエスカレートしやすくなります。ですから、深呼吸をする、一度場を離れるなど、感情的なやりとりにならない工夫を心がけましょう。
冷静な対応を重ねることで、子どもも安心し、次第に態度が落ち着いていくことが多いです。
3. 選択肢を与えて自主性を尊重する
「これをしなさい」「今すぐやりなさい」など、一方的な指示は子どもの反発を招きやすくなります。代わりに、「宿題は今やる?それともおやつの後にやる?」など、2択や3択で選ばせる工夫をしてみましょう。
こうすることで、子どもは「自分で決めた」という感覚を持ちやすくなり、素直に行動しやすくなります。
自主性を尊重する姿勢は、子どもの自己肯定感を高めることにもつながります。
4. 適度な距離感を保つ
子どもの行動や態度が気になりすぎて、つい干渉しすぎてしまうケースもあります。しかし、中間反抗期の子どもは「自分の世界」を大切にしたい気持ちが芽生えてきます。
そのため、あえて見守る時間や空間を設けるのも効果的です。
過干渉にならず、必要なときには寄り添える「ちょうど良い距離感」を意識することで、子どもとの関係が穏やかに保てます。
親の過干渉についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「親の過干渉が子どもに与える影響とは?」
5. 子どもの甘えを受け止める
反抗的な態度を取る一方で、時折「甘えたがる」場面が見られるのも中間反抗期の特徴です。急に抱きついてきたり、「一緒に寝よう」と言ったりすることもあるでしょう。そんな時は、「もう大きいのに…」と突き放さず、素直に甘えさせてあげることも必要です。
中間反抗期の裏には、まだまだ親の愛情を求めている感情が隠れています。たっぷりと甘えを受け止めることで、子どもは安心感を得て、心が安定しやすくなります。
6. 自分を責めすぎない・一人で抱えこまない
中間反抗期の子どもに向き合うのは、親にとって心身ともに負担が大きくなることもあります。
「私の育て方が悪かったのかな…」と自分を責めてしまったり、孤独に感じてしまう方もいるでしょう。
しかし、反抗期は成長に必要なプロセスであり、誰しもが通る道です。一人で抱え込まず、周囲の家族や友人、時には学校や専門機関に相談することも大切です。
親自身がリラックスし、安心して子育てに向き合うことが、最終的には子どもとの良好な関係づくりにもつながります。
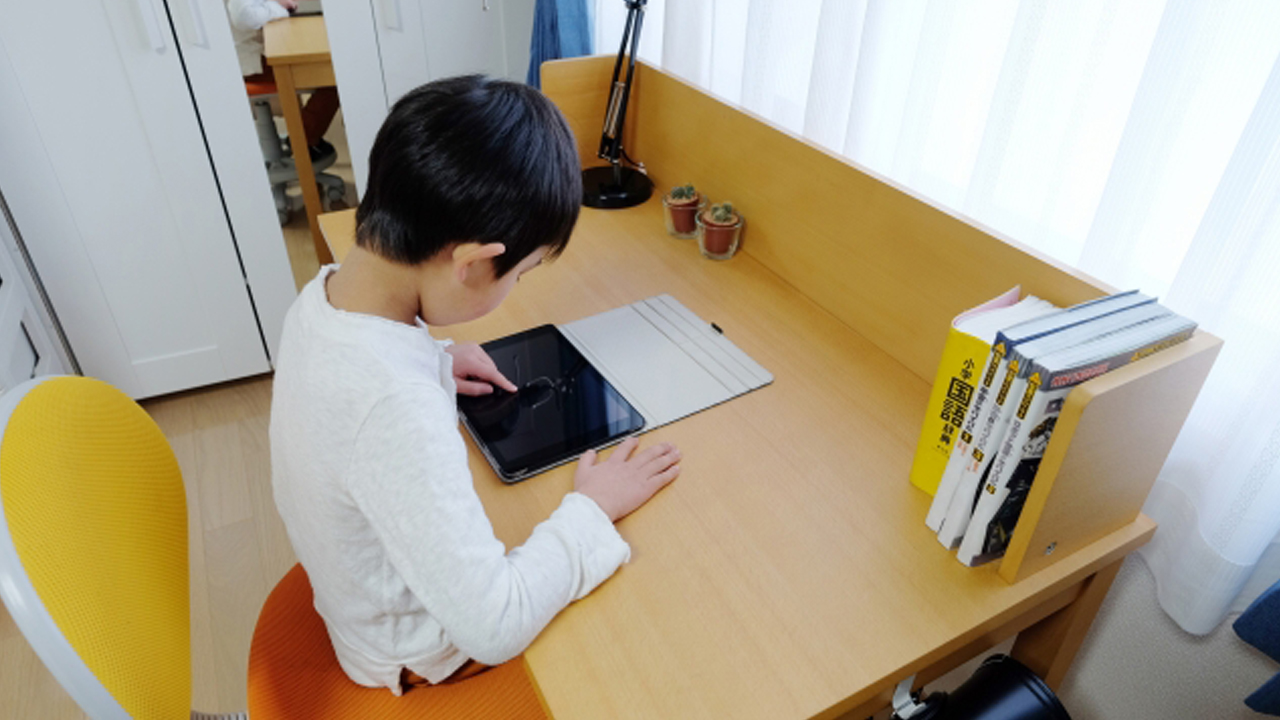
中間反抗期の子どもにしてはいけない5つのNG行動
中間反抗期は、保護者にとって試練の時期とも言えます。ついイライラしてしまったり、対応に悩むことも多いでしょう。しかし、何気ない言動がかえって子どもの反発心を強めてしまうこともあります。
ここでは、反抗期の子どもに「やってはいけない」NG行動を5つご紹介します。避けるべきポイントを知っておくことで、無用な対立を防ぎ、親子関係をスムーズに保ちやすくなります。
1. 子どもの気持ちを無視して正論を話す
子どもの行動に問題を感じたとき、「そんなことしても意味がない」「社会では通用しないよ」などと正論で押さえつけるのはNGです。
大人にとっては当たり前のアドバイスでも、子どもは「気持ちをわかってくれない…」と感じ、次第に聞く耳を持たなくなります。まずは「そういうふうに思ったんだね」と、子どもの感情を受け止めた上で冷静に伝える工夫が大切です。
2. 他の子どもと比較する
「○○ちゃんはちゃんとしてるのに」「お兄ちゃんの時はこんな態度しなかった」など、他の子と比較する発言も避けたいNG行動です。
比較されることで、子どもは「認めてもらえない」と感じ、自己肯定感が低下する可能性があります。また、親への信頼感も損なわれやすくなるため、「その子はその子、自分は自分」という前提を大切にして接しましょう。
3. 子どもを突き放す
「もう勝手にしなさい」「どうでもいい」など、突き放す言葉は、子どもにとって強い不安や孤独感を与えます。
反抗期の子どもは、一見強がった態度を取っていても、心の奥底では「親に見守ってほしい」と感じています。つい距離を取りたくなることもありますが、「困ったときは話していいよ」と安心感を示すことが大切です。
4. 子どもの言動や行動に無関心な態度をとる
忙しさやストレスから、反抗的な態度を見ても「どうでもいい」「知らない」と無関心な態度を取るのも避けたい対応です。
無関心は、子どもにとって「自分は愛されていない」と誤解を与える可能性があります。反抗期の対応は大変ですが、適度に関心を持って見守る姿勢を続けることで、子どもは「本当は気にかけてくれている」と安心できます。
5. 強く否定しすぎない
「何でそんなことするの!」「いい加減にしなさい!」など、強い口調で何度も否定してしまうと、子どもは心を閉ざし、親の話を素直に聞かなくなります。
もちろん危険な行動やルール違反に対しては注意が必要ですが、注意する際は「〇〇するとどうなると思う?」など、問いかけや冷静な説明を心がけると、子どもも話を受け入れやすくなります。
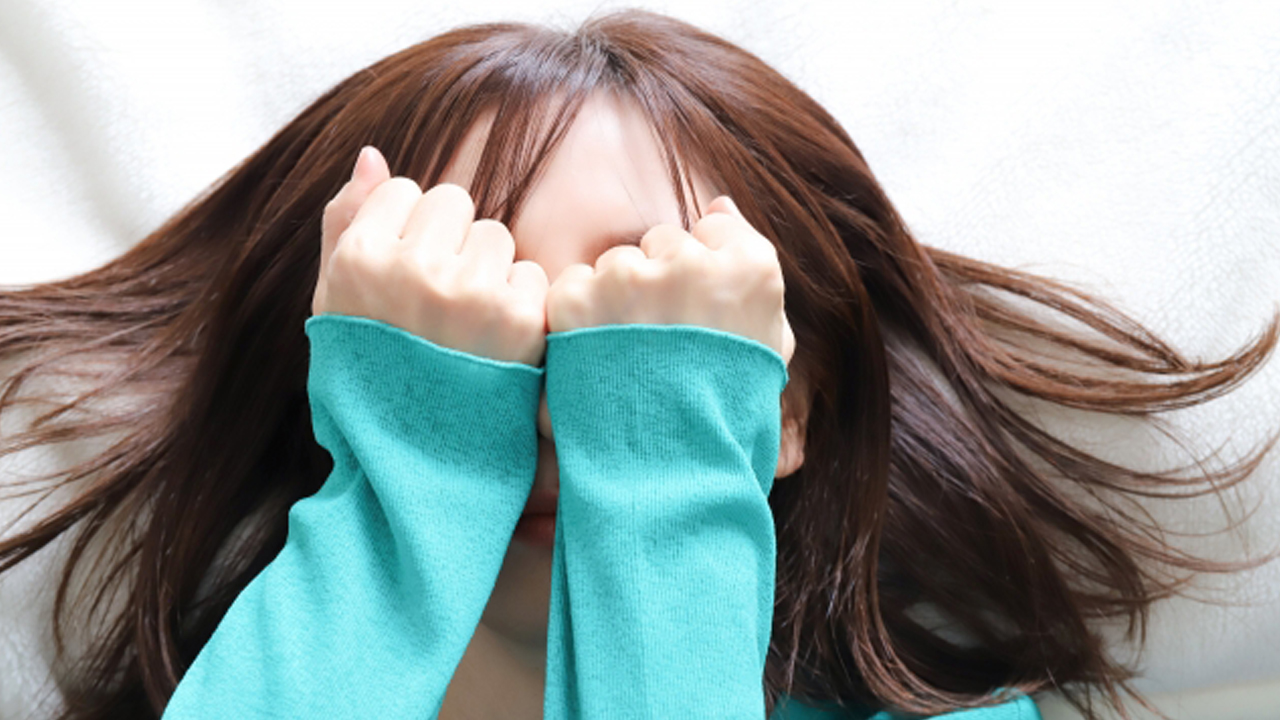
まとめ
中間反抗期は、子どもが心身ともに大きく成長していく過程で誰もが通る大切な時期です。しかし、その過程で親子のコミュニケーションがうまくいかず、戸惑いや悩みを感じることも多いでしょう。
今回ご紹介した「チェックリスト」や「接し方のポイント」「NG行動」を参考に、子どもの心のサインに気づきながら、無理のない範囲で接し方を工夫してみてください。
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
























