愛着障害とは?|症状・原因・タイプ別の特徴と家庭でできる対応策
公開日:2025年11月12日
更新日:2025年11月12日
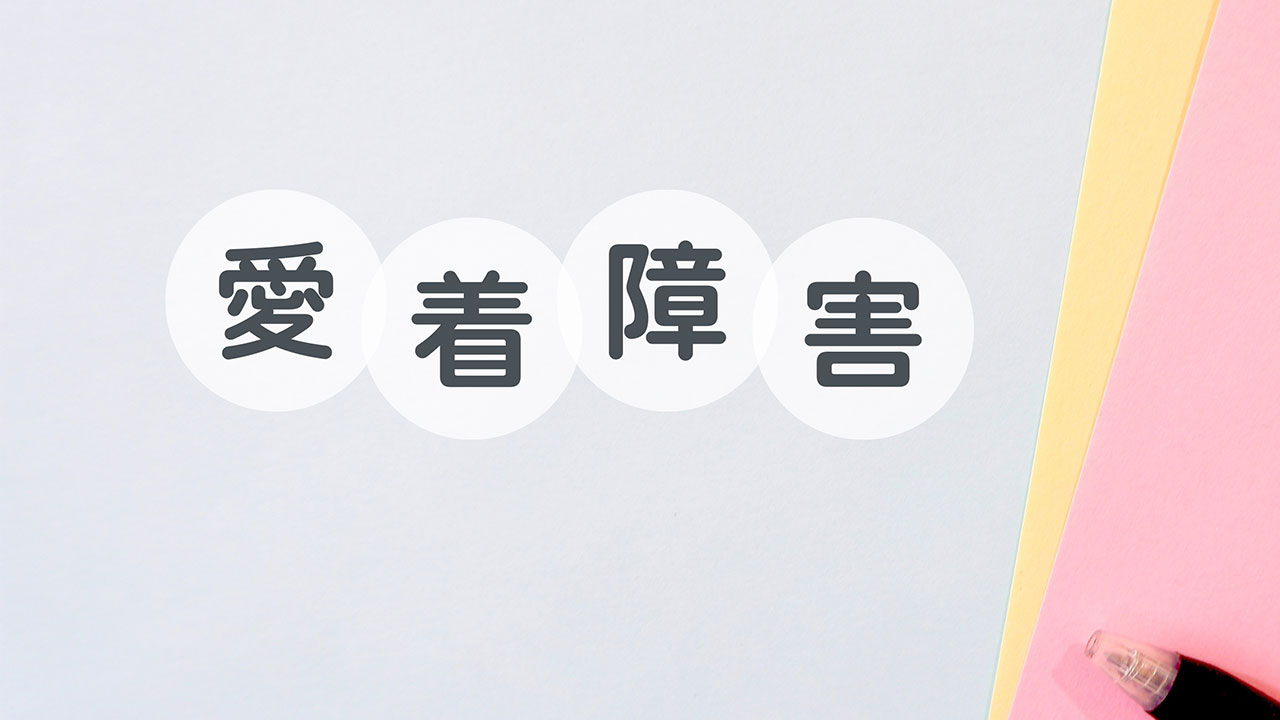
「うちの子、もしかして愛着障害かも…?」
このコラムでは、愛着障害の症状・原因・サイン、4つのタイプ別の特徴、家庭でできる対応策などをわかりやすく解説します。
子どもの行動への理解が深まり、安心できる親子関係を築くヒントが見つかるはずです。
愛着障害とは?|子どもの心と発達への影響
「愛着障害」という言葉は聞いたことがあっても、実際にどのようなものか詳しく知っている方は多くありません。
愛着は子どもの心の成長に大きく関わるもので、親子関係やその子を取り巻く環境によって築かれていきます。
ここではまず、愛着の基本や原因、そして学校や家庭で見られる影響について詳しく解説していきます。
1. 『愛着』とは何か|親子関係で育まれる「心の土台」
「愛着」とは、子どもが特定の人に対して抱く深い安心感や信頼感を指します。
生まれて間もない赤ちゃんは、自分を守ってくれる存在を本能的に求めます。おむつを替えてくれる、泣いたら抱っこしてくれる、こうした日常のやりとりを通じて「この人は自分を守ってくれる」という安全基地が心に育まれます。
この安全基地がしっかりと形成されることで、子どもは安心して周囲の世界に関わり、失敗しても立ち直る力を身につけていきます。
逆に、愛着が十分に育たないと、「どうせ自分なんて…」「誰も自分を分かってくれない」という気持ちが強まり、人間関係や学習への意欲にも影響が及ぶことがあります。
2. 愛着障害が起きる原因と、幼少期の経験が後から影響する理由
愛着障害が生じる原因は一つではありません。
もっとも大きい要因は、幼少期における親子関係や養育環境です。親が忙しくて十分に関わる時間が取れなかったり、過度に厳しい躾や無視が続いたりすると、子どもは「自分は愛されていない」と感じてしまいます。
また、家庭環境以外にも、転園・転校などによる環境の変化や、親以外の養育者との関係性も影響します。
幼い頃は本人が強く意識していなくても、こうした経験は心の奥に蓄積され、小学校・中学校と成長するにつれて問題行動や感情の爆発といった形で表面化することがあります。
つまり、幼少期の経験は「その時限り」ではなく、後からじわじわと影響してくるのです。
3. 「わがまま」「反抗期」との違いを見極めるポイント
愛着障害の特徴は、一見すると「わがまま」や「反抗期」と似ていることがあります。
しかし、本質的な部分で大きく異なるため、見極めが大切です。
「わがまま」は、基本的には親に安心して甘えている状態です。「イヤ!」と言いながらも、内心では親に認めてほしい、わかってほしいという気持ちが根底にあります。「反抗期」も同様で、子どもが自分の世界を広げる過程で自然に起こるものです。
一方、愛着障害の場合は、親や周囲への信頼感そのものが弱くなっているため、怒りや拒絶が深刻で長期化しやすい傾向があります。
「何をしても受け止めてもらえない」「どうせわかってもらえない」という諦めが背景にあり、表面的な言動だけでは見分けにくいことが多いです。そのため、感情の持続時間や、親子関係への不信感の強さなどを手がかりに観察していくことが重要です。
中間反抗期についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「中間反抗期を見極めるチェックリスト|保護者の接し方のコツやNG行動も紹介」
4. 学校と家庭でよく起きる困りごと|勉強・生活・人間関係への影響
愛着障害があると、学校や家庭で様々な困りごとが生じます。
最も分かりやすいのは勉強への集中力が続かないことです。安心感が不足している子どもは、授業中に気持ちが安定せず、先生や友だちとのやり取りにもストレスを感じやすくなります。
結果として、宿題をやらない、テストで実力を発揮できないなどの問題が起こります。
また、友人関係でも影響が見られます。
極端に甘えすぎるか、逆に距離をとりすぎるといった形で、友だちとうまく関わることが難しくなります。先生との関係でも、叱られると過度に落ち込んだり、逆に反発したりと感情が大きく揺れがちです。
家庭では、生活リズムが乱れやすく、朝起きられない、夜遅くまでゲームをしてしまうなどの行動が見られることがあります。これらは単なる反抗や怠けではなく、心の不安定さが表に出ているサインともいえます。親が「困った行動」として叱るだけではなく、背景にある気持ちを理解することが大切です。

愛着障害の4つのタイプと特徴
愛着障害は、大きく4つのタイプに分けられます。
それぞれのタイプには特徴があり、子どもの行動や感情の現れ方にも違いが見られます。
各タイプを理解することで、お子さんの気持ちに寄り添った関わり方を考えるきっかけになるでしょう。
1. 安心感を求めすぎる「不安型」
不安型は、常に誰かにそばにいてほしい気持ちが強いタイプです。
少しでも親や先生の姿が見えなくなると不安になり、「見捨てられるかもしれない」という恐れから過剰に甘える行動が見られます。
例えば、学校へ行く前に何度も「今日怒られないかな?」と確認したり、友だちに対しても「嫌われたらどうしよう」という気持ちから必要以上に気を使ってしまうことがあります。
その結果、精神的に疲れてしまい、勉強や日常生活にも影響が出るケースが少なくありません。
このタイプは、子どもが「自分は大切にされている」という感覚を持てるよう、一貫した対応と安心できる言葉かけが大切です。
2. 人との距離を取りがちな「回避型」
回避型は、表面的には落ち着いて見えても、心の中では人との距離を保とうとするタイプです。
本当は甘えたい気持ちがあるのに、「どうせわかってもらえない」「頼ると裏切られるかもしれない」という思いから、自分の気持ちを表に出すことを避けてしまいます。
学校では「一人でいるほうが楽」と感じて集団活動に参加しなかったり、家庭でも親に本音を話さず「別に」「大丈夫」と短く答えることが多くなります。
このような態度から、一見手がかからない子どもに見えることもありますが、実際は心の中で強い孤独感や不安感を抱えていることが多いです。
このタイプは、無理に距離を縮めようとせず、少しずつ信頼関係を積み重ねることが大切です。
3. 近づきたいけど怖い…「アンビバレント型」
アンビバレント型は、「近づきたい気持ち」と「拒絶したい気持ち」が入り混じるタイプです。
親や先生に甘えたかと思えば、急に怒り出したり拒否したりするなど、感情の起伏が激しく、周囲もどう接してよいか迷うことがあります。
例えば、テストで良い点を取った時は嬉しそうに報告するのに、少し注意されただけで「どうせ自分なんてダメなんだ!」と強く落ち込むといった行動が見られます。
この背景には、「本当は安心したいけれど、傷つくのが怖い」という複雑な気持ちが隠れています。
アンビバレント型の子どもには、感情の揺れを否定せず、「気持ちが揺れても大丈夫だよ」という安心感を伝える関わりが必要です。
4. 関わりが不安定で混乱する「無秩序型」
無秩序型は、4つのタイプの中でも最も不安定で予測が難しいタイプです。
安心したい気持ちが強い一方で、人との関わりに強い恐れや混乱があり、行動が極端にぶれやすい特徴があります。
例えば、ある時は親にべったり甘えたかと思えば、突然激しく怒ったり暴言を吐いたりすることもあります。学校でも友だちとの関係が長続きせず、先生との信頼関係を築くのが難しいケースも少なくありません。
無秩序型の背景には、過去のつらい経験やトラウマが深く関わっていることが多く、専門機関やカウンセラーとの連携が重要です。
家庭ではできるだけ安心できる環境を保ちながら、焦らず一歩ずつ進んでいくことが求められます。

こんなサインは要注意!子どもの行動に隠れる愛着の不安
愛着の不安は、心の内側にあるため直接見ることはできません。しかし、その不安は日常の行動や態度にサインとして表れます。
ここでは、特に注意したい「対人関係」「感情・行動」「学習・生活」といった3つの状況に分けて、具体的な例を解説します。
「少し気になるな」という小さな変化も、早めに気づくことで子どもを支えるきっかけになります。
1. 対人関係に表れるサイン|友だち・先生との関係がうまくいかない
愛着に不安がある子どもは、人との関わり方に偏りが見られます。
友だちと適度な距離感を保てず、極端に甘えすぎたり、逆に距離を取りすぎたりすることが特徴です。
例えば、仲良くなりたい一心で相手にべったり付きまとった後で、「嫌われたらどうしよう」と必要以上に心配になるケースがあります。
反対に、「どうせわかってもらえない」という思いから、教室では一人で過ごし、友だちとの関係をあえて避けることもあります。
先生に対しても同様で、叱られると過度に落ち込むか、強く反発してしまうことがあります。
このような関係の不安定さが続くと、学校生活そのものがつらくなり、不登校や登校渋りにつながることも少なくありません。
友達と遊びたくない症候群についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「友達と遊びたくない症候群」の子どもに親ができる寄り添い方と対処法」
2. 感情や行動に表れるサイン|甘えすぎ・突然の怒り・かんしゃく
愛着の不安が強い子どもは、感情のコントロールが難しくなります。
一見落ち着いているように見えても、心の中では不安や怒りが大きく揺れ動いていることがあります。
例えば、甘えたい気持ちが抑えられず、親から離れられない、何度も同じことを確認するなどの行動が見られることがあります。
一方で、突然怒りが爆発し、大きな声で泣き叫んだり、物を投げたりといった激しい行動をとることもあります。
これらは「わがまま」ではなく、安心感が不足しているサインの一つです。感情が不安定な時期が長引くと、家族との関係がぎくしゃくし、家庭内の雰囲気も不安定になりやすいため、背景にある気持ちを理解する視点が欠かせません。
小学生の癇癪についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「小学生が癇癪を起こす理由と解決策|親ができる対処法についてもご紹介」
3. 学習や生活に表れるサイン|家庭学習が続かない・生活リズムの乱れ
愛着障害は、学校での学びや家庭での生活リズムにも影響を与えます。
例えば、家庭学習に集中できず、すぐに席を立ってしまう、課題をやる前に「できない」「どうせ無理」と諦めてしまうなど、学習習慣が安定しにくくなります。
生活面では、寝る時間が遅くなり朝起きられない、食欲が安定しないといった生活リズムの乱れが見られることもあります。
こうした状況が続くと、学校への遅刻や欠席が増え、さらに自信を失うという悪循環に陥りやすくなります。
これらの問題行動の背景には、「安心したい」「認めてほしい」という子どもの本音が隠れています。単なる怠けや反抗と決めつけず、行動の裏にある気持ちに目を向けることが大切です。
昼夜逆転の治し方についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「昼夜逆転の治し方|不登校、引きこもり、ゲーム・ネットのやり過ぎの子ども」

家庭でできること|親子の安心感を育てる関わり方
愛着の不安は、家庭での小さな積み重ねによって少しずつ和らげることができます。
「うちの子、もしかして…」と感じたときは、まずは親子の関わり方を見直すことが大切です。
ここでは、家庭でできる5つの工夫をご紹介します。日々の接し方を意識するだけでも、子どもの心に「安心の土台」を築く手助けになります。
1. 「聞いてくれている」と感じさせる会話の工夫
子どもが安心感を得るためには、「自分の話をちゃんと聞いてもらえている」という感覚が欠かせません。
忙しいとつい「ながら聞き」になりがちですが、子どもが話しているときは手を止めて目を合わせることがポイントです。
また、子どもの言葉をそのまま繰り返すオウム返しを取り入れると、「ちゃんと理解してくれている」という気持ちが伝わります。
例えば「学校で嫌なことがあったんだ…」という話に対して、「そっか、嫌なことがあったんだね」と返すだけでも、子どもの心は落ち着きます。
否定やアドバイスよりもまずは共感と受け止めを意識しましょう。安心して気持ちを話せる場が、親子の信頼関係を深める第一歩です。
2. スキンシップや習慣で「安心のサイン」を伝える
愛着を安定させるためには、言葉だけでなくスキンシップも大切です。
頭をなでる、ハグをする、背中を軽くたたくなどのスキンシップは、「あなたは大切な存在だよ」というメッセージを直接伝えます。
また、日常の中に安心できる習慣を作るのも効果的です。
たとえば「毎日寝る前に本を一緒に読む」「朝はハイタッチして送り出す」など、決まった行動があることで、子どもは「今日も大丈夫」という安心感を積み重ねていきます。
スキンシップや習慣は短時間でも構いません。続けることが何よりも大切です。
3. 失敗しても大丈夫!を伝える言葉かけ
愛着に不安を抱える子どもは、失敗に対して強い恐怖心を持つことがあります。
「怒られるかも」「見捨てられるかも」という思いが先立ち、挑戦すること自体を避けてしまうことも少なくありません。
そんな時は、失敗しても価値が下がらないことを伝える言葉かけが重要です。
「失敗しても大丈夫」「あなたが挑戦したことが大切なんだよ」というメッセージは、子どもの自己肯定感を育てます。
また、失敗した直後は原因を追及するよりも、「よく頑張ったね」と努力そのものを認めることを意識しましょう。これが次への一歩を踏み出す力になります。
子どもの自己肯定感についてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「子どもの自己肯定感の高め方とは?|7つのNG行動についても解説」
4. 小さな成功体験を一緒に喜ぶ工夫
安心感を育てるためには、子どもが「できた!」と感じる小さな成功体験を積み重ねることが欠かせません。
その際、大きな目標ではなく、達成しやすい小さなステップに分けることがポイントです。
例えば、勉強なら「10分だけ集中する」「1ページだけ解く」から始めてみます。
できたときには一緒に喜びを共有し、「頑張ったね」「できて嬉しいね」と声をかけてください。親が一緒に喜んでくれることで、「自分は認められている」という安心感が育ちます。
成功体験を積むことで、子どもは「次も頑張ってみよう」という前向きな気持ちを少しずつ取り戻していきます。
5. 家庭ルールを「厳しすぎず・ゆるすぎず」に整える
家庭内のルールは、安心感を育てるうえで重要な役割を持ちます。
ただし、ルールが厳しすぎると子どもはプレッシャーを感じ、逆にゆるすぎても、子どもは「自分に興味がないんじゃないか」と考えてしまい、安心できなくなるという問題が起こります。
例えば、勉強時間やスマホの使用時間については、親子で話し合って決めることが大切です。
一方的に押しつけるのではなく、「なぜこのルールが必要なのか」を説明し、子ども自身にも意見を出してもらうことで、納得感が生まれます。
適度なルールは、子どもにとって「ここまで頑張れば安心」という目安になります。家族全員が守れるルールを共有することが、安心感と信頼感を育てる土台になります。
中学生のスマホルールについてもっと知りたい方はこちら
⇒ 「中学生にスマホを持たせる前に知っておきたい!安心して使うためのルールと注意点」

まとめ
愛着障害は、子どもの行動や学習、対人関係にさまざまな影響を与えますが、その根底には「安心したい」という気持ちがあります。子どもの愛着のタイプやサインを理解し、家庭でできる小さな工夫を積み重ねることで、少しずつ親子の信頼関係を築いていくことができます。
焦らず一歩ずつ、子どもの心に寄り添うことが大切です。
家庭教師のマスターについて
家庭教師のマスターの特徴
平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、
- 勉強大嫌いな子
- テストで平均点が取れない子
- 特定の苦手科目がある子
- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子
への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!
家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。
指導料金について
指導料:1コマ(30分)
- 中学生:900円/1コマ
- 小学1年生~4年生:800円/1コマ
- 小学5年生~6年生:850円/1コマ
- 高校生:1000円/1コマ
家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。
2人同時指導の割引き|ペアレッスン
兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!
※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!
教え方について
マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。
「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。
指導科目について
英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。
コースのご紹介
家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。
ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!
無料体験レッスン
私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。
体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。
また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。
他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!
関連する記事
-
集団行動が苦手な子どもについて|心理的背景や効果的な対応方法とは?
-
小学生が癇癪を起こす理由と解決策|親ができる対処法についてもご紹介
-
ゲーム・ネット依存の子どもへの家族の接し方|セルフチェックリスト付き
-
反抗期はいつから始まり、いつ終わるの?|接し方や注意点を徹底解説
-
反抗期がない子どもについて|その理由や将来の影響を徹底解説
-
親の過干渉が子どもに与える影響とは?
-
母子分離不安は母親のせい?|原因と対応策について解説
-
落ち着きのない子どもは発達障害?|他の可能性とサポート方法
-
起立性調節障害なのに、なぜ遊びには行けるのか?|理由や症状を詳しく解説
-
発達障害の子が人間関係を築けないとき|親ができる支援と関わり方のヒント
-
ASDの子どもが苦手としやすいこと|理由とサポート方法を解説
-
「また逃げた…」ADHDの子どもが嫌なことから逃げる本当の理由とは?
-
ADHDの子どもの好きな人への態度とは?
























